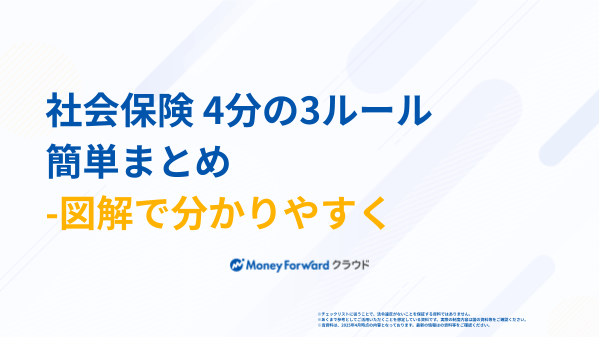- 更新日 : 2025年10月31日
社会保険の4分の3ルールとは?短時間労働者にかかわる制度
社会保険の加入基準の一つとして広く知られている「4分の3ルール」は、正社員と比べた労働時間や労働日数を基に、パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者が社会保険に加入すべきかどうかを判断するために利用されます。
このルールの正確な理解は、法令遵守のみならず従業員の安心や職場環境の整備にも直結します。とりわけ、柔軟な働き方が広がる昨今では、「週30時間以上勤務しているけれども月の勤務日数は少ない」「曜日ごとに勤務時間が異なる」など、従来の一律的な判断だけでは対応しきれないケースも増えています。
本記事では、4分の3ルールの基本的な考え方から、計算方法、よくある疑問について解説します。
目次
社会保険の4分の3ルールとは
社会保険の「4分の3ルール」は、短時間労働者が加入対象となるかを判断する際の基準として広く用いられています。どのようなルールか、詳細を見ていきましょう。
4分の3ルールの基本的な考え方
企業で従業員を雇用した場合、厚生年金保険や健康保険(いわゆる「社会保険」)への加入義務が発生します。もっとも、パートタイマーやアルバイトなど労働時間の短い従業員については、歴史的に「4分の3ルール」と呼ばれる適用基準が設けられてきました。これは、正社員に比べて所定労働時間や日数が少ない短時間労働者をどこまで被保険者として扱うかを定めた基準です。
この基準は1980年6月に国から各機関に示された内部文書(内かん)により提示されたもので、当初は法律に明文化されていない運用上の目安でした。その内容は、「1日または1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、常時雇用される者のおおむね4分の3以上」であることを基準とし、それに満たない場合でも勤務実態をふまえて常用的使用関係が認められれば被保険者とするというものでした。
法改正による明文化と現在の適用状況
短時間労働者の増加や働き方の多様化を受けて、平成28年(2016年)10月の法改正によって4分の3ルールが法的に明確化されました。現在では、健康保険法および厚生年金保険法のもとで、「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一事業所の通常の労働者(正社員)のそれぞれ4分の3以上である従業員」は、パートタイマーであっても社会保険の被保険者となると定められています。
この4分の3という基準は、フルタイム勤務のおおよそ75%にあたる水準です。短時間労働者であっても常勤に近い就労実態がある場合には、社会保険への加入が求められることで、健康保険や年金の保障を受けられるように制度が整えられています。厚生年金保険・健康保険の適用事業所に使用される者であれば、正社員に限らず4分の3以上の勤務条件を満たす従業員も被保険者とする義務が生じます。
この基準は全国共通であり、企業の規模や業種に関係なく適用されます。ただし、適用事業所の範囲については、法人企業はすべて対象ですが、個人事業所では常時5人以上の従業員を使用する特定業種に限られるなど、一定の例外が設けられています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
社会保険の加入条件
社会保険の適用は、事業所の種別や従業員の就業状況に応じて決まります。原則として、一定の条件を満たす事業所に勤務する労働者は自動的に加入対象となります。
適用事業所の条件
社会保険の適用事業所とは、法律によって社会保険の適用が義務づけられている事業所のことを指します。常時従業員を雇用している法人事業所は、たとえ従業員が1名であっても、社会保険の適用事業所とされます。一方、個人事業所の場合は、業種によって条件が異なり、例えばサービス業や商業では5人以上の従業員を使用している場合に適用事業所となります。
加入義務が発生する労働者の条件
社会保険に加入するためには、労働者が一定の条件を満たしている必要があります。原則として、適用事業所で常時使用されている正社員が対象となりますが、4分の3ルールを満たすパートタイム労働者も社会保険に加入します。また、従業員数51人以上の企業に勤めるパートタイム労働者であれば、4分の3ルールを満たさなくても、一定の要件を満たせば加入対象になります。例えば、週の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が88,000円以上であること、勤務期間が2か月を超えて見込まれること、学生でないことなどが挙げられます。
学生の扱いについて
短時間労働者であっても、学生である場合は原則として加入対象外です。ただし、夜間や通信制の学生、定時制の高校生などは例外として加入が必要になる場合もあります。
任意適用事業所
すべての事業所が強制適用というわけではなく、一部には任意で適用が可能なケースも存在します。こうした任意適用の場合には、労働者と使用者の合意が必要となるなど、少し異なる手続きが必要になります。
個人事業所など、法律上は適用事業所に該当しない場合でも、所定の手続きを経て社会保険に加入することができます。このようなケースでは、所轄の年金事務所への申請が必要であり、労働者の2分の1以上の同意が得られていることが前提となります。
社会保険の4分の3ルールの計算方法
4分の3ルールとは、どのように計算するのか解説します。
所定労働時間・労働日数を基準として判断する
4分の3ルールの計算方法は、企業内の正社員(通常の労働者)の労働条件を基準に判定します。該当従業員の1週間あたりの所定労働時間および1か月あたりの所定労働日数を、それぞれ同じ事業所の正社員と比較します。両方の基準でおおむね4分の3(75%)以上に該当する場合、その従業員は社会保険の被保険者となります。
例えば、正社員の所定が「週40時間・月20日勤務」の企業であれば、4分の3の基準は「週30時間・月15日」です。パートタイマーでこの条件を満たす契約であれば、社会保険に加入させなければなりません。
ここでの判断基準は「所定労働時間・所定労働日数」であり、勤務実績ではなく契約上の勤務条件が基準となります。仮に残業や休日出勤で実働が4分の3を超えていても、契約上の所定が満たしていなければ加入義務は生じません。
逆に、契約上の時間が4分の3未満でも、実態として常勤に近い勤務形態が続いている場合には、個別の判断が求められる場合もあります。現在の運用では基本的に契約上の条件に基づく判断が一般的とされています。
計算する際の注意点
週の所定労働時間と月の所定労働日数の双方を確認する必要があり、どちらか一方でも基準を満たしていない場合には、社会保険の適用除外となることが通常です。例えば「週5日勤務だが1日あたりの労働時間が短い」ケースや、「1日の労働時間は正社員と同程度だが、週の勤務日数が少ない」ケースなどが該当します。いずれも一方が75%未満であれば、被保険者には該当しないと判断されることになります。
また、契約における労働時間が月単位などイレギュラーな場合には、週換算が必要です。月間所定労働時間を「12分の52」で乗じて週換算する方法が、厚生年金の実務上でも用いられています。
人事担当者は、各従業員の契約内容を正確に把握し、自社の正社員の所定労働条件に照らして75%を上回っているかを定期的に確認することが重要です。部署によって正社員の条件が異なる場合には、該当する勤務形態ごとに個別に検討する必要も出てきます。わずかに基準を下回る従業員についても、労働時間延長の申し出があった際には将来的な加入義務の可能性があるため、状況の変化にも注意を払う必要があります。
短時間労働者への社会保険適用拡大と2025年度改正の動向
法改正により、社会保険は短時間労働者にもその対象が広がっています。
2025年度の改正を視野に入れた制度の見直しが進められており、企業の規模や賃金要件にとらわれない、包括的な社会保険制度への移行が現実味を帯びています。
企業規模に応じた段階的拡大と法改正の経緯
4分の3ルールに満たないパートタイマーやアルバイトであっても、2016年からは一定の条件下で社会保険の加入義務が生じる制度改正が段階的に行われています。この制度は、週20時間以上の労働、月額賃金8.8万円以上、学生でないこと、2か月を超える雇用見込みという4つの条件を満たす労働者が対象です。もともとは従業員数501人以上の企業に限定された措置でしたが、2022年に101人以上、2024年には51人以上へと適用範囲が広がりました。
また、従業員数50人以下の小規模企業についても、任意特定適用事業所として労使の合意があれば同様の対象とすることが可能で、厚生労働省は積極的な活用を促しています。さらに、従来存在していた「継続して1年以上の雇用見込み」という条件は、2022年10月の法改正で撤廃され、現在では2か月超の雇用見込みがあれば対象となります。
短時間労働者の社会保険加入対象は、制度導入当初よりも広範な範囲へと進展してきました。
2025年度以降の見直しと今後の課題
2025年度の年金制度改正では、この短時間労働者への適用拡大がさらに進められる見通しです。厚生労働省は企業規模要件を将来的に撤廃し、すべての企業規模において週20時間以上働く労働者を社会保険の対象とする方針を示しています。中小企業への負担を考慮し、例えば従業員20人超の企業から段階的に適用範囲を広げる案も検討されています。
あわせて、現在の賃金要件(月額8.8万円以上)についても見直しの議論が進行中です。最低賃金の上昇により、この金額を自然に上回る労働者が増加している現状を受け、就業調整を避けるために賃金要件自体の撤廃が選択肢として挙げられています。ただし、地域差や短時間勤務者への影響に配慮し、拙速な導入ではなく段階的な対応が想定されています。
今後は一部業種への適用拡大も含めて、社会保険制度全体の包括的な見直しが進んでいくと見込まれます。企業の人事担当者は制度改正の最新動向を注視し、短時間労働者への適切な対応準備を進めることが求められます。
社会保険の4分の3ルールについてよくある疑問
4分の3ルールに関して寄せられることの多い疑問と、その回答について解説します。
4分の3ルールの「正社員との比較」は、会社全体で統一的に見る?
4分の3ルールにおける「正社員との比較」は、企業全体で一律に判断するのではなく、実務上は「同一事業所内の通常の労働者」との比較が原則です。比較対象となるのは、あくまで同じ場所・組織で通常勤務している正社員の労働条件です。例えば、シフト制を採用している会社で正社員の所定労働時間が部署ごとに異なる場合、短時間労働者がどの勤務体系に属しているかをふまえて、対応する正社員の条件と個別に比較することになります。
また、全国に複数の事業所を持つ企業であっても、比較基準は事業所単位で判断されるため、本社と支店で労働時間が異なる場合には、それぞれの正社員に合わせて判断する必要があります。この点を見落として全社平均で一律に判断してしまうと、制度上の誤適用や未加入者の発生につながる恐れがあります。
4分の3ルールを適用する際は、勤務先の正社員の就業規則や雇用契約を個別に確認することが欠かせません。
社会保険の4分の3ルールおよびその適用拡大により、企業の人事・労務管理にはいくつかの実務的な影響と留意点が生じます。
祝日の労働は4分の3ルールの労働時間・日数に含まれる?
4分の3ルールにおける判定基準は、実際の勤務実績ではなく、雇用契約や就業規則で定められた「所定の」労働時間・労働日数に基づきます。したがって、祝日が労働義務のある日として設定されている場合には、その日も「所定労働日数」に含まれます。一方で、会社が就業規則で祝日を「休日」と定めており、労働義務のない日と扱っている場合には、たとえ実際に勤務していたとしてもその祝日は所定労働日数には含まれません。
同様に、祝日に労働した時間についても、所定労働時間に含めるかどうかは、契約上その日が勤務日として扱われているかに左右されます。祝日勤務の有無ではなく、祝日が所定の勤務日に該当するかどうかが判断のポイントです。就業規則や雇用契約書に基づいて、祝日が所定労働にあたるのかを確認しましょう。
有給休暇は4分の3ルールの労働時間・日数に含まれる?
有給休暇は労働者にとって「労働義務のある日」として扱われるため、原則として所定労働日数・時間に含まれます。これは、有給休暇が労働契約上の勤務日に取得されるものであり、その日が本来労働する日であったという前提があるからです。したがって、労働者が有給休暇を取得した日も、その日数分を含めて所定労働日数をカウントし、労働時間についても通常その日に予定されていた労働時間分が所定労働時間として算定されます。
ただし、あくまで契約上の所定労働日・時間を基に判断するため、イレギュラーな休暇や特別休暇は含まれないケースもあります。4分の3ルールの判定に際しては、実際に出勤したかどうかではなく、契約上の勤務条件を基に算定することが大前提です。そのため、有給休暇を取得している日でも、労働義務のある日であれば正社員との比較に含めて問題ありません。
4分の3ルールを正しく理解し、実務に活かそう
4分の3ルールは、社会保険の加入対象を判断するうえで重要になる基準です。特にパートタイマーやアルバイトなど多様な雇用形態を持つ企業では、ルールを正しく理解し、日々の労務管理に反映させることが欠かせません。実務においては、単に労働時間や日数を比較するだけでなく、雇用契約や就業規則に定められた「所定労働時間・日数」に基づいて適切に判定することが求められます。
また、近年は法改正により、4分の3未満の労働者にも社会保険の加入義務が生じるケースが増えており、従来の判断基準にとどまらない柔軟な対応が必要です。
4分の3ルールを制度上の知識として押さえるだけでなく、自社の実態に即して運用できるよう、定期的な見直しと社内ルールの整備を進めていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の資格喪失届とは
社会保険の資格喪失届とは、従業員が退職や解雇、死亡などにより社会保険のうちの健康保険・厚生年金保険の資格を喪失する場合に提出する書類です。なお、被保険者本人が資格喪失届を提出する必…
詳しくみる退職時の社会保険資格喪失日はいつ?社会保険喪失届の書き方も解説!【資格喪失証明書のテンプレート付き】
従業員の退職にあたっては、社会保険資格喪失の手続きをしなければなりません。5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。退職日の属する月の社会保険…
詳しくみる厚生年金の加入条件とは?加入義務のある対象企業や加入手続きを解説
法人ならびに常時5人以上の従業員がいる個人事業主は、厚生年金保険に加入する義務があります。また個人事業主は、適用業種で常時5人未満の場合および適用業種以外の場合は、任意適用事業とい…
詳しくみる労災の休業補償の振込が遅い!時期の目安や遅れる理由、対応方法を解説
労災によるケガや病気で働けなくなったとき、頼りになるのが「労災保険の休業補償」です。しかし、いざ申請しても「なかなか振り込まれない」「どのくらいで支給されるのか分からない」と不安に…
詳しくみる【記入例付き】就業促進定着手当支給申請書の書き方は?ダウンロードから提出方法まで解説
再就職後の収入が離職前より下がってしまった方を支援する「就業促進定着手当」を受け取るには「就業促進定着手当支給申請書」の提出が必須です。 この記事では、就業促進定着手当支給申請書の…
詳しくみる雇用保険における再就職手当とは
失業や休業の場合にはもちろん、労働者が能力開発のため教育を受ける場合にも利用できる雇用保険。一般的には失業保険と言われる、自己による都合や会社側の都合によって離職した際に支給される…
詳しくみる