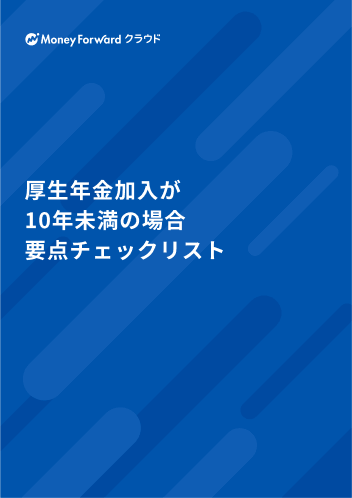- 更新日 : 2025年12月11日
厚生年金の資格期間が10年未満の場合 – 受給できるのかを解説
日本の年金制度では、国民年金、厚生年金への加入期間が10年以上でなければ受給資格がないとされています。では、これらの年金に加入していた期間が10年未満の場合には、もう受給する方法はないのでしょうか。この記事では、年金受給の資格期間についてご説明します。
資格期間が10年未満の場合は年金を受給できない
現在、自営業などで仕事をする方は国民年金に、会社員など事業所に雇われて仕事をしている方は国民年金と厚生年金に加入しています。そして、65歳になった時点で国民年金に加入している方は老齢基礎年金を、厚生年金に加入している方は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます(60~64歳に繰上げ、または66~75歳に繰下げ受給も可)。
ただし、国民年金または厚生年金に加入していた期間が10年未満の場合には、年金を受給できません。
例えば、65歳の時点で加入期間(保険料を納めた期間)が10年未満の場合、65歳を過ぎてからも保険料を納め、10年という条件を満たせば、そのときから受給資格が発生します。
参考:年金を受けとるために必要な期間が10年になりました|厚生労働省
参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
資格期間とは
上記のように、年金を受給するためには、一定の期間保険料を納付していた、または加入していたという条件が決まっています。この条件となる期間が「受給資格期間(資格期間)」です。2022年現在、受給資格期間は10年と決まっています。従って、65歳になったときに加入期間が10年未満の方は年金を受給できません。
なお、受給資格期間は厚生年金の加入期間ではなく国民年金だけに加入していた期間も合わせて計算されます。また、保険料の免除期間や一部免除期間も計算に含まれます。
つまり、何らかの理由で保険料を納められない場合でも、きちんと免除や一部免除の手続きを行っていれば、加入期間としてカウントされるということです。払えないから、とそのままにするのではなく、手続きを行うようにしましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
厚生年金とは
厚生年金とは、基本的には「常時5人以上を雇用している事業所」に強制的に適用され、適用された事業所の70歳未満の従業員全員を被保険者とする年金です。なお、アルバイトやパートでも、1週間または1ヶ月の労働時間が同様の仕事をしている従業員の3/4以上の場合、被保険者となります。
よく日本の年金は「2階建て」などと例えられますが、1階部分は20歳~60歳までの国民全員が加入する国民年金、2階部分が会社などに所属して働く方が加入する厚生年金となっています。すなわち、厚生年金加入者は、国民年金と厚生年金両方に加入していることになり、保険料もその分上がります。その代わり、受給額も「2階建て」で、国民年金のみ加入する方より多くなるのです。
厚生年金の計算方法
日本の年金制度は基本的に国民年金と厚生年金の2階建てだとご説明しました。
適用事業所に勤務していない方は、国民年金のみの受給となります。それでは、厚生年金を受給する場合の金額は、どのようにして計算されるのでしょうか。
年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類がありますが、ここでは最も受給者の多い老齢厚生年金の計算式を紹介します。
「報酬比例分」とは
年金の加入期間や過去の報酬等(収入)により決まるもので、年金受給額計算の基礎となるものです。以下の式で計算されます。
- A. 平成15年(2003年)3月以前の加入期間について
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数 - B. 平成15年(2003年)4月以降の加入期間について
平均標準報酬額(賞与を含む) × 5.481/1000 × 加入月数
「経過的加算」とは
昭和60年(1985年)の法改正により、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。これに影響を受ける方のために、移行措置として60歳から65歳になるまで受けられる「特別支給」の制度が設けられました。「特別支給」は定額部分と報酬比例部分に分けられ、65歳になると定額部分は老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金となります。
ただ、当分の間は老齢基礎年金が定額部分より少なくなってしまうため、その差額が老齢厚生年金に加算して支払われます。これを「経過的加算」といいます。
「加給年金額」とは
厚生年金に加入していた(被保険者であった)期間が20年以上の方が65歳になったとき、生計を共にしている配偶者や18歳以下の子がいる場合、家族構成や人数に応じて受給額が加算されます。これを「加給年金額」といいます。
参考:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
参考:報酬比例部分|日本年金機構
参考:経過的加算|日本年金機構
参考:老齢年金ガイド令和4年度版|日本年金機構
受給資格期間の短縮について
以前は、老齢厚生年金を受給するには資格期間が25年以上必要でした。それが、平成29年(2017年)8月1日からは資格期間が10年(120ヶ月)以上に短縮されています。
上でも述べたように、資格期間とは厚生年金に加入していた期間だけではありません。国民年金だけに加入していた期間や、保険料納付の免除や一部免除を受けていた期間、また、「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間も含まれます。
合算対象期間とは、制度の変わり目など、保険料を納付できなかった期間があっても資格期間に加算される期間のことをいいます。具体的には以下のような例があります。
- 昭和61年(1986年)3月以前に、会社員の配偶者だった期間
- 平成3年(1991年)3月以前に、学生だった期間
- 海外に住んでいた期間
- 脱退手当金の支給対象となった期間など
なお、合算対象期間は資格期間には影響しますが、年金の受給額の計算には算入されません。受給資格期間が10年未満の場合も、上記のような条件によっては10年を超える場合があります。可能性があると思う方は、年金事務所に相談してみましょう。
また、年金の受給は自分から請求しなければなりません。受給資格期間が10年未満の方も、10年以上25年未満の方も、年金事務所から年金請求書や受給資格期間の案内が送られてきます。必ず目を通しましょう。
さて、厚生年金には、これまでご説明してきた老齢年金のほかに、遺族年金と障害年金があります。簡単に言うと遺族年金は家族が亡くなったときに受けられるもの、障害年金は自身が障害のある状態になったときに受けられるものです。どちらも老齢年金と同様にそれぞれ資格期間が設けられています。
遺族年金の受給資格期間は亡くなった本人の加入状況などにより異なりますが、老齢年金の受給資格がある方の場合、受給資格期間は25年以上となります。すなわち、老齢年金の受給資格期間が10年以上あっても、25年未満ならば遺族年金を遺族が受給することはできないのです。
25年から10年に短縮されたのは老齢年金の受給資格期間だけであるため、注意しましょう。
参考:必要な資格期間が25年から10年に短縮されました|日本年金機構
参考:年金ニュース第2号(平成29年2月)|厚生労働省
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
自分の受給資格期間を把握しておきましょう
本記事では、厚生年金の受給資格期間についてご説明しました。
国民年金または厚生年金に加入していた期間が10年未満だと、将来厚生年金を受給することはできません。1ヶ月でも足りなければ受給できないのです。
転職をされた方や、厚生年金適用でない事業所に勤めていたなど、保険料の納付状況や厚生年金への加入状況について不安がある方は、日本年金機構の「ねんきんネット」や毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」などで年金履歴を確認してみましょう。
65歳までの長い長い期間の記録を自分ですべて管理するのは大変です。日本年金機構からの通知や案内にはしっかり目を通して、将来の受給の際にあわてないように、自分の年金の状況を把握しておくことが大切です。
そして、資格期間が足りないと感じたら、早めに対策を行いましょう。
- ねんきんネット https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/Z01/W_Z0101SCR
- ねんきんダイヤル 0570-05-1165
参考:私の履歴整理表 ~ 年金記録確認をスムーズに行うために~|日本年金機構
参考:大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています|日本年金機構
参考:年金ニュース第2号(平成29年2月)|厚生労働省
よくある質問
厚生年金の加入期間が10年未満でも年金を受給できますか?
国民年金または厚生年金に加入している期間が10年未満の方は、受給できません。詳しくはこちらをご覧ください。
資格期間とは何ですか?
年金を受給するために国民年金または厚生年金に加入していなければならない期間をいいます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
健康保険の傷病手当金とは
健康保険に加入していれば、被保険者や家族がケガをしたり病気になったりしたとき、一部の負担で治療を受けることができます。お医者さんが処方してくれた薬も同様です。 これを「病養の給付」…
詳しくみる適応障害の労災認定は難しい?手続きや証拠の重要性、デメリットなども解説
適応障害は、強いストレスが原因となって心や体の調子を崩し、仕事や日常生活に支障をきたす精神疾患の一つです。現代の職場では、長時間労働や人間関係のトラブル、業務上のプレッシャーが大き…
詳しくみる雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)の記入例とポイント解説
従業員が育児休業を取得する際、初回申請書(育児休業給付受給資格確認票)とあわせて提出が必要になるのが「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」です。 この書類の作成は担当者の方に…
詳しくみる社会保険料変更のお知らせの作り方や記載項目・テンプレートを紹介
2024年10月より、パート・アルバイトも含め従業員数が51名以上の企業では、全社員を社会保険に加入させる義務が生まれました。 社会保険料が変わったときは、従業員に変更内容を通知す…
詳しくみる社会保険の任意加入とは?メリットや任意適用事業所の申請手続きを解説!
厚生年金と健康保険からなる社会保険は、適用事業所に所属し、条件を満たした全従業員が加入しなければならない強制保険制度です。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。…
詳しくみる傷病手当はいつ振り込まれる?遅れる理由や申請から受給までの流れなど解説
病手当金は、業務外の病気やケガで療養するために仕事を休み、給与が支払われない期間の生活を保障する公的な制度です。申請から実際の支給までには審査等の手続きを要するため、「いつ振り込ま…
詳しくみる