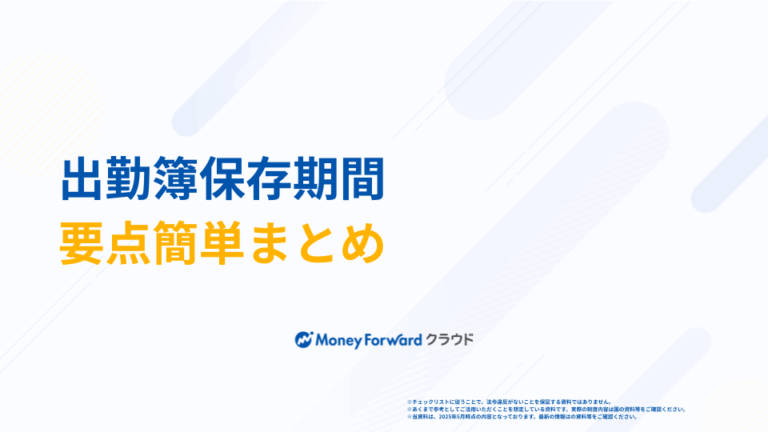- 更新日 : 2025年12月24日
【テンプレ付】出勤簿とは?記載項目や書き方、注意点など網羅的に解説
出勤簿とは、従業員の出勤時刻や退勤時刻などの記録です。給料計算の基礎になるため、会社は出勤簿をきちんと作成・管理しなければなりません。労働基準法でも労働者名簿や賃金台帳と並び、保存期間が定められています。タイムカードも出勤簿と同じように「その他労働関係に関する重要な書類」として、一定期間の保存が義務づけられています。
目次
出勤簿とは?
出勤簿とは、従業員の出勤日や労働日数、出勤・退勤時刻などを記した文書です。労働基準法によって定められた法定帳簿の一つで、従業員を雇用する事業者に作成が義務付けられています。
労働基準法が定める出勤簿の性格・位置づけをみていきましょう。
出勤簿は法定三帳簿の一つ
労働基準法は、労働者保護を目的としている法律です。立場の弱い従業員を守るため、会社・事業主にさまざまな義務を課しています。労働者名簿や賃金台帳の備え付けも、以下のように労働基準法に規定されています。
使用者は、事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。第108条(賃金台帳)
使用者は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
また労働基準法は、第109条において労働者名簿と賃金台帳、およびこの2つ以外の帳簿などについて保存期間を定めています。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
出勤簿は「その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。そのことから会社・事業主は労働者名簿や賃金台帳と同じように、出勤簿を作成しなければなりません。労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、会社・事業主が従業員について必ず作成、管理、保存しておかなければならない書類や資料であり、3つはセットで「法定三帳簿」と呼ばれます。
出勤簿とタイムカードの違い
出勤や退勤の記録にタイムカードを利用している会社もありますが、出勤簿とタイムカードは明確に異なります。
出勤簿は労働者の出勤日や時間などを正確に記録し、証拠書類として使える書類です。
これに対し、タイムカードは従業員が各自で出勤・退勤の際に使用するものであり、正確な出勤・退勤時間を反映しているとは限りません。タイムカードを出勤簿として扱う場合には、その時間が適正かどうかを判断するため、作業日報や残業許可証といった補足資料が必要です。
出勤簿と賃金台帳の違い
賃金台帳とは、労働基準法第108条の規定により、会社・事業主に作成が義務づけられている帳票です。労働基準法施行規則第54条の規定に基づき、賃金台帳には次の内容の記載が求められます。
- 労働者氏名
- 性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や手当等の種類とその金額
- 控除項目とその金額
賃金台帳には、様式第20号(常用)・様式第21号(日雇)が定められていて、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができます。しかし、記載しなければならない内容に漏れがなければ、異なる様式を使っても問題ありません。
出勤簿には賃金台帳と違い、定められた様式はありません。しかし、前述のように記載しなければならない項目は定められているので注意が必要です。
出勤簿の目的
出勤簿をつける目的は、従業員の労働日や労働時間を正確に把握し、労働基準法や就業規則に違反しないよう管理することです。
労働基準法では、労働時間について原則として1日8時間、または週に40時間までと定めています。この労働時間を超過する場合、割増賃金の支払いが必要です。出勤簿を適切に管理することで、法に沿った賃金の支払いができます。
出勤簿の保存は義務?
出勤簿は、労働基準法第109条において記録の保存が義務づけられている「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。出勤簿の保存が行われていないと労働基準法違反となり、第120条の規定により30万円以下の罰金が科せられます。
出勤簿に記載すべき項目と書き方
出勤簿には、必ず記載すべき項目があります。
ここでは、記載項目と書き方を解説します。
出勤日・労働日数
出勤簿は、従業員が出勤した日と労働日数の記載が必要です。労働時間にかかわらず、出勤したときは出勤日として扱います。リモートワーク、在宅勤務などで労働している日も、同じく出勤日として記載してください。
ただし、リモートワークなどタイムカードによる出退勤の記録ができない場合は、出勤状況を把握するための方法を考える必要があります。
出勤(始業)・退勤(終業)の時刻
出勤日ごとに、出勤(始業)と退勤(終業)の時間も記載が必要です。また、労働時間を正確に計算するために、休憩時間も記載しなければなりません。休憩時間は、1日のうちで6時間以上働く場合、以下のように付与することが義務付けられています。
- 6時間超8時間以内:45分
- 8時間超:1時間
出退勤の時刻は正確に記録することが必要であり、タイムカードやICカードなど、ツールの活用が必要になるでしょう。
日ごとの労働時間数
日ごとの労働時間数は、出勤と退勤の時間、および休憩時間によって算出しましょう。出勤から退勤までの勤務時間を計算し、休憩時間を差し引けば労働時間がわかります。
たとえば、始業時刻が8時30分、終業時刻が17時30分、休憩時間が12時〜13時の1時間というケースでは、労働時間は「9時間-1時間=8時間」になります。
時間外労働を行った日付・時刻・時間数
労働基準法で定められた労働者の法定労働時間は、原則として1日8時間、週に40時間です。この時間を超えて労働を行った場合は時間外労働に該当するため、日付・時刻・時間数を正確に記載する必要があります。
変形労働時間制を採用している場合は、注意が必要です。日や週ごとなどで所定労働時間が変わるため、その都度時間外労働時間を正確に算出しなければなりません。
休日労働(休日出勤)を行った日付・時刻・時間数
労働基準法で定められた法定休日に出勤した場合は休日労働に該当するため、日付や時刻、時間数の記載が必要です。
法定休日は、毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日と定められています。曜日の限定はありません。
週休2日制で土日を休日にしている会社であれば、土日のどちらかが法定休日となります。どちらが法定休日かは、就業規則で定められているのが一般的です。
日曜日が法定休日であれば、土曜日は法定外休日になり、出勤しても休日労働にはなりません。出勤簿には、あくまで法定休日に出勤した休日労働のみを記載します。
深夜労働を行った日付・時刻・時間数
労働基準法では、事業者が労働者を深夜時間に労働させた場合、割増賃金を支払うことを義務付けています。
この場合の深夜時間とは22時〜翌5時までの時間帯と規定されており、これらの時間帯に労働させた場合は出勤簿へ日付と時刻、時間数を記載しなければなりません。給与計算では記載された内容で算出し、割増賃金の支払いが必要です。
休暇・欠勤・遅刻・早退の書き方と注意点
出勤簿は出退勤の時間を記録するだけでなく、休暇・欠勤・遅刻・早退といった勤務外の情報を正確に反映させる必要があります。不適切な記録は給与計算ミスや法令違反につながるため、明確なルールに基づいて記載しましょう。
各勤務状況を区別して記録する
休暇・欠勤・遅刻・早退は、すべて勤務時間の計算や賃金の支払いに影響を与える要素です。それぞれの区分を曖昧にせず、「有給休暇」や「病欠」、「私用欠勤」など、理由と区分を明示して記録することが重要です。遅刻や早退についても、開始・終了時刻とあわせて、遅れや早退した理由を記録しておくとトラブル防止に役立ちます。
給与・社保・法定帳簿と整合させる
こうした勤務記録は、給与計算や社会保険の手続き、さらには賃金台帳など他の法定帳簿の整備義務にも直結します。休暇や欠勤が適切に反映されていないと、賃金計算の誤りだけでなく、未払い賃金・過剰支給の原因になります。従業員にもルールを明示し、統一された記録方法を採用することが重要です。
出勤簿(エクセル)のひな形・テンプレート
出勤簿の作成は、テンプレートがあると便利です。以下のURLからエクセルですぐに使えるテンプレートを無料でダウンロードできるため、ぜひご活用ください。
在宅勤務中のルール周知文(ワード)のテンプレート
業種別に見る出勤簿の書き方のポイント
出勤簿はすべての業種に共通して必要な法定帳簿ですが、実際の勤務形態やシフト体制、法令上のルールは業種ごとに異なります。業種特有の事情に即した記録方法を採用することが、労働時間の適正な把握と法令遵守につながります。以下に代表的な業種ごとの記載ポイントを解説します。
建設業:日毎の現場ごとの記録が必須
建設業では、勤務場所が日ごとに変わることが多く、作業日報的な役割も果たす出勤簿が求められます。特に「出面管理(でづらかんり)」と呼ばれる、誰がどの現場に何時間勤務したかの記録が重要です。これにより、元請企業や建設業許可の帳簿としても活用されることがあります。
- 勤務日・開始時刻・終了時刻に加えて、現場名・作業内容を記載
- 雨天中止や半日勤務などの記録も詳細に残す
- 複数現場を掛け持ちする場合は、時間帯別に分けて記録
医療・介護業:夜勤・シフト勤務の詳細な記録が必要
医療・介護業界では、24時間体制の勤務が多く、日をまたぐ夜勤や交代制勤務の管理が求められます。そのため、単なる「出勤・退勤」だけでなく、「夜勤」「早番」「遅番」といった勤務区分の明示が必要です。
- 日付の切り替わりに注意し、夜勤明けの扱いなどのルール設定
- 勤務区分(例:日勤・夜勤・明けなど)を記載
- 休憩・仮眠時間も明確に記録して実働時間を正確に把握
小売・飲食業:シフト変更の都度の更新と反映が肝心
小売業や飲食業では、学生アルバイトやパートの多い「シフト制勤務」が主流です。そのため、事前シフトと実際の勤務の差異が発生しやすく、出勤簿には事実ベースでの記録が求められます。
- シフト変更があった場合は、出勤簿も即時に修正する
- 「無断欠勤」や「早退」「残業」も正確に反映
- 勤務時間が日によって異なる場合、シフト表との整合性もチェック
IT・事務系業種:フレックスタイム・在宅勤務の対応
フレックスタイム制やテレワークを導入しているIT・事務職では、勤務開始・終了時刻を柔軟に設定できることが特徴です。ただし、労働時間の記録自体は義務であり、裁量労働制であっても同様に勤怠管理が必要です。
- 始業・終業時刻を記録しつつ、コアタイムの有無も明記
- テレワーク中の勤務は、「在宅」などの勤務形態表示を併記
- 休憩時間を取っていない場合など、労基法違反につながる恐れもあるため注意
製造業:交代制・残業・休憩の正確な記録が重要
工場勤務のある製造業では、日勤・夜勤の交代制勤務や、残業時間の管理が法令遵守に直結します。また、作業中の休憩や中抜け時間なども明確に記録しなければ、36協定違反や過重労働とみなされる恐れがあります。
- 所定勤務時間に加え、残業・早出の記録欄を設ける
- 休憩時間や中抜けは別欄で時間帯を記載し、実働時間と区別
- 労働時間の通算が容易になるように、日ごとの合計時間を自動計算する工夫も有効
出勤簿は手書きでも良い?
手書きや自己申告の出勤簿は違法ではありませんが、推奨される方法とはいえません。厚生労働省は労働時間を把握するための方法として、「客観的な記録」によることを定めているためです。
手書きの記録は従業員が自由に改ざんできるため、会社は正確な労働時間を把握できない可能性があります。
営業など外勤の仕事では、労働時間を客観的に把握する方法がないため、手書き・自己申告でもやむを得ないといえるでしょう。しかし、客観的に労働時間を把握する手段があるにもかかわらず手書きや自己申告による出勤簿により勤怠管理をすることは、違法になる可能性があります。
やむを得ない場合以外、出勤簿は手書きではなく、タイムカードやICカードによる打刻など、客観的に把握できる方法で記録することをおすすめします。
出勤簿の保存期間は?民法改正や賃金台帳との違いなど
出勤簿は労働基準法第109条に規定されている「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、労働者名簿や賃金台帳と合わせて「法定三帳簿」と呼ばれる帳簿です。定められている内容を記載しなければならず、不備があれば労働基準法違反として罰則が科せられます。保存も定められた期間、行わなければなりません。
出勤簿の保存期間は、民法改正により3年から5年に変更
民法改正に伴い、労働基準法の賃金が請求できる期間も変更になりました。賃金請求権が時効によって消滅するまでの期間が2年間から5年間に延長されています。これに伴って出勤簿の保存期間も3年間から5年間に変更されました(経過措置として当分の間は3年間)。
労働基準法は第115条において賃金請求権の定めをしています。今回の民法改正では、この定めの根拠となった民法の使用人の給料などに関する短期消滅時効が廃止になり、また一般債権に係る消滅時効についても見直しが行われました。
このことを踏まえて労働基準法も改正になり、賃金請求権が時効によって消滅するまでの期間が2年から5年に延長となっています。出勤簿の保存期間が3年間から5年間に変更になったのも、民法改正があったことによるものです。
賃金台帳の保存期間は7年
賃金台帳の保存期間は、労働基準法では5年(当面の間は3年)と規定されています。保存期間は、原則として労働者の最後の賃金について記入を行った日から数えます。ただし、記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、 当該支払期日が記録の保存期間の起算日となります。
しかし、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は、7年間の保管が必要になります。源泉徴収簿とは、従業員から申告された扶養家族の状況や、毎月の給与の金額、その給与における源泉徴収額などを記録する帳簿です。
源泉徴収簿の作成は、法律で義務づけられてはいませんが、毎月の給与に対する源泉徴収や年末調整などを正確かつ効率的に行うために、国税庁から様式が配布されています。また定められた内容が記載していれば、賃金台帳と源泉徴収簿を兼用とすることが認められています。しかし、源泉徴収簿を兼ねた賃金台帳を年末調整の根拠として用いる場合は、保存期間を7年間としなければなりません。
タイムカードの保存期間は5年
タイムカードは出勤簿と同じ、労働基準法第109条に規定されている「その他労働関係に関する重要な書類」の一つです。そのため保管も出勤簿と同じく5年間、行わなければなりません。
しかし、前述の通り賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は、タイムカードも7年間が保存期間となります。
アルバイトやパートの方の出勤簿も保存が必要?
出勤簿は雇用形態にかかわらず作成、保存が求められます。アルバイトやパートといった非正規雇用についても出勤簿が必要です。
アルバイト・パート向け出勤簿の書き方のポイント
アルバイトやパートタイマーは、シフト制や不定期勤務が多く、正社員とは異なる働き方をしています。そのため、出勤簿もその実態に即した形式で作成し、正確な勤怠管理を行うことが重要です。ここでは、出勤簿作成時に押さえるべきポイントを解説します。
実際の勤務実績を正確に記録する
アルバイトやパートは、あらかじめ決められたシフトに沿って勤務するケースが大半です。しかし、実際の勤務内容は突発的な欠勤、早退、残業、またはシフトの入れ替えなどが日常的に発生します。そのため、出勤簿には予定されたシフトとは別に、実際に出勤・退勤した時刻を正確に記載することが求められます。単に出勤・退勤時間を記録するだけでなく、予定との差異が生じた場合の理由を明記しておくことで、後からの確認作業や給与計算時のトラブルを防ぐことができます。
実働時間を明確に算出できるようにする
アルバイトやパートの多くは時給制であるため、実際に働いた時間に応じて給与が決まります。このため、出勤簿には単なる出退勤の時刻だけでなく、休憩時間や中抜け時間も正確に記載する必要があります。たとえば、午前と午後で分けて勤務した場合は、それぞれの開始・終了時間を分けて記録する必要があり、1行にまとめると実働時間の集計に誤差が出る可能性があります。また、休憩時間についても「1時間休憩」とするのではなく、13:00〜14:00のように時間帯を記録することで、法定労働時間の遵守状況を確認しやすくなります。
雇用契約の内容と整合させる
出勤簿は、勤怠管理の資料としてだけでなく、労働契約の実態を示す証拠資料としての役割も持ちます。たとえば、雇用契約では週3日勤務とされているのに、出勤簿上では週5日勤務していることが常態化している場合、契約内容と実態に齟齬があるとみなされることがあります。このような齟齬は、労基署の調査時に是正を求められる要因にもなり得ます。さらに、週20時間を超える勤務が続く場合には、社会保険の加入要件に該当する可能性もある
学生アルバイトや外国人の記録に配慮する
学生アルバイトや外国人労働者を雇用している場合は、出勤簿への記載内容にも特別な配慮が求められます。たとえば、18歳未満の高校生が深夜時間帯(22時から翌5時)に勤務していた場合、それは労基法違反となります。また、資格外活動許可を得た外国人留学生は、週28時間以内という制限があるため、出勤簿で超過労働が明確に記録されていれば、雇用主にも責任が問われる可能性があります。こうした特殊ケースでは、シンプルな勤務記録だけでなく、年齢や在留資格に応じた管理ルールを設け、明確に運用することが重要です。
出勤簿の不備が招く労務リスク
出勤簿の記録ミスや記載漏れは、企業にとって大きな労務リスクを伴います。給与トラブルや法令違反、行政指導の原因にもなり得るため、日々の勤怠記録を正確に管理することが不可欠です。ここでは、主なリスクと背景を解説します。
未払い残業の発生
出退勤時刻が不正確に記録されていると、実際に働いた時間よりも短く処理され、残業代が支払われないケースが生じます。こうした未払い残業は、労働者からの訴えや監督署への通報によって発覚し、企業に遡及支払いが求められる可能性があります。記録が曖昧であるほど、企業側が不利になる傾向にあります。
労働基準監督署からの是正勧告
出勤簿に不備があると、労働時間の適正な管理ができていないと判断され、監督署から是正勧告を受ける場合があります。特に、タイムカードや打刻データと出勤簿の内容に不整合がある場合、企業は勤怠管理体制の見直しを求められることになり、信頼性の低下や社内調査の負担が生じます。
出勤簿を効率よく管理するには?
出勤簿への記載項目は多く、給与に反映されるためには正確な記載が欠かせません。シフト制や裁量労働制・フレックスタイム制など、さまざまな雇用形態がある場合、管理には時間と手間がかかります。
効率的に管理するためには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
勤怠管理システム「マネーフォワード クラウド勤怠」であれば、出勤簿の管理を大幅に効率化できます。パソコンやスマホから出退勤の打刻ができ、打刻機を使ったICカード打刻も可能です。出退勤打刻の漏れを防ぎ、タイムカードでの収集・集計作業といった手間を省きます。
基本勤務制だけでなく、シフト制や裁量労働制・フレックスタイム制など、さまざまな就業ルールにも対応できます。また、勤務予定(シフト)を入力することで予定を確認することができ、所定時間と時間外の自動集計も可能です。
出勤簿やタイムカードは保存期間に注意して適切に取り扱おう
出勤簿は、労働者名簿や賃金台帳と合わせて「法定三帳簿」と呼ばれています。労働基準法第109条に規定されている「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、会社には作成、保存が義務づけられています。労働者の氏名や労働日数、労働時間数などの定められた内容を記載しなければならず、不備があれば労働基準法違反となります。
保管期間も定められていて、5年間の保存が必要です。労働基準法ではタイムカードも保存期間は5年間とされていますが、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は7年間の保存が必要です。必要な保管期間の違いに注意して、適切に取り扱いましょう。
よくある質問
出勤簿とはなんですか?
出勤日・労働日数、出勤・退勤時刻、日ごとの労働時間数、時間外労働を行った日付・時刻・時間数、休日労働(休日出勤)を行った日付・時刻・時間数、深夜労働を行った日付・時刻・時間数を記した帳簿です。詳しくはこちらをご覧ください。
出勤簿の保存期間について教えてください。
労働基準法第109条に規定されている「その他労働関係に関する重要な書類」として、5年間の保存が必要です(経過措置として当分の間は3年間)。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
時間外労働の上限規制とは?2024年の変更点を厚生労働省の指針をもとにわかりやすく解説
2019年4月から施行されている改正労働基準法により、労働時間に関するルールが大きく変わりました。その中でも特に重要なのが、時間外労働(残業)の上限規制です。 これまで法律上は残業時間の上限が明確でなく、過労死や長時間労働が社会問題となって…
詳しくみる1年単位の変形労働時間制とは?違いやメリット・デメリット、残業代の計算方法を解説
1年単位の変形労働時間制には、1ヶ月単位や1週間単位のものと異なる特徴や利点があります。 本記事では、変形労働時間制のメリット・デメリットや残業代の計算方法、シフト制との違いなどを解説します。ぜひ参考にしてください。 1年単位の変形労働時間…
詳しくみる【申請書テンプレ付】テレワーク導入に必要な準備 – 企業が行うこと
近年、導入が進んでいるテレワークは、通勤時間の軽減など従業員にメリットがある一方で、スムーズなテレワークの実施には事前準備が重要です。ここでは、企業がテレワークを導入する上で必要となる環境整備や制度について解説します。セキュリティ対策や勤怠…
詳しくみる有給休暇義務化に罰則はある?取れなかった場合
2019年4月1日以降、企業は対象となる従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。義務に違反した場合、30万円の罰金が科される可能性もあります。ここでは年次有給休暇の取得義務の対象者や罰則規定について解説するとと…
詳しくみる終業時間とは?始業時間との関係やどこまで含まれるか解説
終業時間を守ることは働き方を見直す第一歩です。 本記事では、終業時間の定義や始業時間との関係性、労働時間に含まれる範囲を解説します。 終業時間を守るためのポイントも紹介するので、働きやすい環境を整えたい方は参考にしてみてください。 終業時間…
詳しくみる労働時間管理のガイドラインを徹底解説!厚生労働省が示す具体的な措置の内容とは?
2019年の働き方改革関連法の施行によって労働安全衛生法が改正され、すべての企業に客観的な方法で労働時間を把握する義務が課せられました。しかし、厚生労働省が示すガイドラインの意図を正確に理解し、自社の労務管理に落とし込むのは容易ではありませ…
詳しくみる