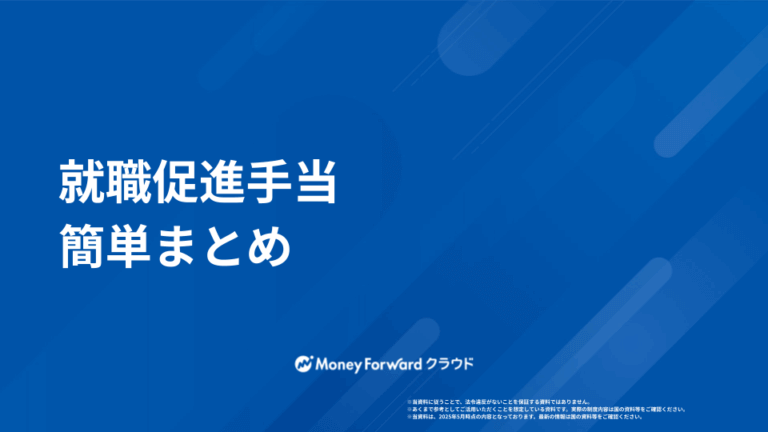- 更新日 : 2025年11月19日
就職促進給付とは?再就職するなら覚えておくべき手当について解説!
雇用保険制度には、さまざまな保険給付が設けられています。失業時の生活保障として基本手当などの求職者給付が大きな柱となっていますが、失業者が失業状態を脱して早く就職できるように促す就職促進給付も重要な役割を担っています。就職促進給付にも、さらに複数の給付があり、内容は複雑です。今回はその中の就業促進手当について詳しく解説していきます。
目次
就職促進給付(就業促進手当など)とは?
就職促進給付とは、失業中の労働者に対して雇用保険から支払われる給付金の一つです。雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定のために設けられている社会保険制度です。求職者給付のうちの基本手当は失業保険の呼ばれ方でよく知られている、雇用保険の行う代表的な給付です。
失業者に対して労働者が安定した生活をしながら、就職に向けた活動を行えるようにと支給されます。また雇用保険は、育児休業や介護休業で給料が支払われない労働者に対しても育児休業給付・介護休業給付を行っています。
失業した労働者が安定した職業に就くことを支援するための給付が就職促進給付です。就職促進給付には就業促進手当・移転費・求職活動支援費があり、就業促進手当には受け取れる失業保険を多く残して再就職した場合に支給の対象になる再就職手当などの4種類の手当があります。
| 就職促進給付 | 就業促進手当 | 再就職手当 |
| 就業促進定着手当 | ||
| 就業手当 | ||
| 常用就職支度手当 | ||
| 移転費 | ||
| 求職活動支援費 | 広域求職活動費 | |
| 短期訓練受講費 | ||
| 求職活動関係役務利用費 | ||
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
就業促進手当には4つの種類がある
雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を図る目的で設けられている保険制度です。失業者に対しては求職者給付や就職促進給付を行い、生活を安定したものとしたり早期に安定した職に就いたりすることの支援としています。就職促進給付のうちの一つである就業促進手当には、次の4種類の手当があります。
再就職すると受給できる「再就職手当」
早期に再就職した場合に受給対象となるのが、再就職手当です。失業者は求職者給付の基本手当(いわゆる失業保険)を受けながら再就職に向けた求職活動を行います。基本手当の給付日数は、年齢や雇用保険であった期間、離職理由などによって決定されますが、再就職すると受け取れなくなります。
失業者が多くの給付日数を残すという不利益を被らないための制度が再就職手当です。給付率は2つあり、早く就職を決めた失業者に対しては高い給付率を用いて再就職手当給付額が計算されます。
前職より賃金減少したら「就業促進定着手当」
再就職はしたものの、前職より賃金が下がってしまった場合に受け取れるのが就業促進定着手当です。離職前の賃金の1日分の額に比べて低下している場合、給付を受けることができます。ただし就業促進定着手当支給額には、上限がある点に注意が必要です。
再就職手当支給外への就職は「就業手当」
再就職手当が安定した職業に就いた場合に対象になるのに対し、就業手当は常用雇用等以外の形態で就業した場合に受け取れる給付です。
就職困難者に支給される「常用就職支度手当」
障害があるなど、就職が困難である人を対象に給付されるのが常用就職支度手当です。基本手当受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者のいずれかであり、就職困難者が安定した職業に就いた場合、要件に該当すると受け取ることができます。
就業促進定着手当を受け取れる3つの条件
就業促進手当のうち、就業促進定着手当は再就職によって給料が低下した場合に受け取ることができる給付です。以下で説明する条件に当てはまる場合に受給できます。3つの条件は全てに該当することが必要です。
再就職手当の支給をすでに受けている
就業促進定着手当を受けるためには、まず再就職手当の支給を受けていることが必要です。再就職手当とは先に触れた通り、求職者給付である基本手当について支給残日数がある場合に受け取れる手当です。決定された基本手当を1/3以上残して安定した職業に就いた場合に受け取ることができます。
就業促進定着手当は、再就職手当を受け取っている場合に支給対象となる給付で、再就職手当を受け取っていなければ就業促進定着手当も受け取ることはできません。
特定の条件で6カ月以上雇用されている
継続雇用されていることが、就業促進定着手当を受け取る、2つ目の条件です。就業促進定着手当を受け取る1つ目の条件は再就職手当を受け取っていることですが、再就職手当は「1年を超えて勤務することが確実であること」が支給要件とされています。就業促進定着手当を受け取るにあたっても継続して雇用されていることが求められ、6カ月以上雇用されていることが必要です。
同じ事業主に、雇用保険の被保険者として雇用されていなければ、就業促進定着手当の給付対象にはなりません。再就職手当は雇用される以外に自分自身が事業を開始する場合も支給対象になりますが、就業促進定着手当では起業は支給対象外になっています。
前職の賃金を下回っている
就業促進定着手当を受け取る条件の3つ目は、前職の賃金を下回っていることです。再就職によって賃金の低下が起こる場合に、就業促進定着手当の給付は行われます。前職の賃金よりも再就職先で支払われる賃金のほうが低い場合でなければ、就業促進定着手当は給付されません。
再就職先による6カ月間の賃金の1日分の金額が、離職前の賃金の1日分の金額に比べて低いことが必要です。
就業促進定着手当支給額の正しい計算方法
就業促進定着手当支給額の計算は以下のようにして求めます。
1.賃金の低下額を求める
以下の計算により賃金低下額を求めます。
2.再就職後6カ月間の賃金の支払い日数となった日数をかける
原則として月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数となります。
また、就業促進定着手当には上限額が定められています。上限額は、次の計算式で算出されます。
就業促進定着手当の申請方法
就業促進定着手当の受給には申請手続きが必要です。以下に説明する方法で手続きします。
必要書類を用意する
就業促進定着手当の受給該当者には、ハローワークより申請書類が届きます。申請書や案内が郵送されるので、受け取ったら確認して準備を開始しましょう。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 再就職した日から6カ月間の出勤簿の写し
- 再就職した日から6カ月間の給与明細、または賃金台帳の写し
「4.再就職した日から6カ月間の給与明細、または賃金台帳の写し」について、再就職した日が賃金締切日の翌日でない場合には、再就職後最初の賃金締切後の6カ月分が必要です。
また「3.再就職した日から6カ月間の出勤簿の写し」「4.再就職した日から6カ月間の給与明細、または賃金台帳の写し」について、出勤簿の写し・賃金台帳の写しは事業主から原本証明を受けたものが必要になります。
必要事項を記入する
以下が就業促進定着手当支給申請書です。

引用:ハローワーク インターネットサービス|就業促進定着手当支給申請書
赤枠は本人が記入する部分ですが、青枠部分は事業主に記入してもらう必要があります。
書類をハローワークへ持参するか郵送する
就業促進定着手当受給に必要な書類が準備できたら、ハローワークに以下の方法で提出して申請します。
申請先:再就職手当の支給申請を行ったハローワーク
申請方法:窓口への持参、あるいは郵送
申請期間:再就職した日から6カ月を経過した日の翌日から2カ月間
就職促進給付を活用して有利に再就職しよう
転職のために会社を辞めると雇用保険から失業保険が受給できます。雇用保険は労働者の生活と雇用の安定のために、失業保険のほかにもさまざまな手当の給付を行っています。
早期に再就職した場合には再就職手当、再就職手当の対象外の就業をした場合には就業手当、就職困難者が安定した職業に就いた場合には常用就職支度手当の受給対象となります。
就業促進定着手当もこれらと同じ就職促進給付の一つで、再就職で賃金が低下した場合に受給できる手当です。再就職手当をすでに受けている・特定の条件で6カ月以上雇用されている、あるいは前職の賃金を下回っていることを条件に支給されます。
該当する場合は忘れずに申請して給付金を受給し、再就職に活用しましょう。
よくある質問
就職促進手当はどんな制度?
失業者が早期に安定した職業に就くことを促進する目的で設けられている制度で、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当の4種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。
就職促進手当を受け取る条件は?
就職促進給付のうちの就業促進定着手当は、「再就職手当の支給をすでに受けている」「一定の条件で6カ月以上雇用されている」「前職の賃金を下回っている」という3つの条件に全て当てはまる場合に受け取れます。詳しくはこちらをご覧ください。
就業促進定着手当支給額の計算方法は?
離職前の賃金日額と、再就職後6カ月間の賃金の1日分の金額との差に、再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数をかけて就業促進定着手当支給額は計算されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
勤怠管理とは?仕事内容や活用できるツールの比較
勤怠管理は、会社で人事総務関係や給与関係の担当者が必ずといっていいほど関わることになる業務の一つです。 今回は、勤怠とは、勤怠管理とは、といった基礎的な知識から勤怠管理の仕事内容や…
詳しくみる時短勤務における給与計算のやり方は?給与は減るの?
働き方改革が叫ばれるなか、法律も整備され、多くの企業で働き方の多様化が進められています。時短勤務もそのひとつです。育児時短勤務、介護時短勤務は育児・介護休業法で義務づけられましたが…
詳しくみる時間外労働が360時間を超えたらどうなる?36協定のルールや時間外労働の上限について解説
長時間労働の是正が社会的な課題となる中、「36協定の360時間」を超える時間外労働が発生した場合に企業が直面するリスクは極めて深刻です。企業の人事担当者や労務担当者にとって、労働時…
詳しくみる15連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
15連勤は、働く人にとって非常に過酷な状況です。身体的な疲労と精神的なストレスが限界まで積み重なり、心身ともに追い詰められてしまいます。働き続けることが当たり前になってしまう前に、…
詳しくみる【テンプレ付】出張旅費規程とは?相場や作り方をわかりやすく解説
出張旅費規定とは、出張に関わる経費を精算する際に基準となる規定です。 出張には宿泊費や交通費などの経費がかかります。加えて、出張中の食費や通信費を補助するための日当も支給しなければ…
詳しくみる就業規則の閲覧を求められたときの対処法を解説
就業規則はあるものの、従業員の多くが入社以来内容を把握していない、ということはありませんか。就業規則は作成・変更したら従業員に周知し、従業員が随時閲覧できるようにしておかなければな…
詳しくみる