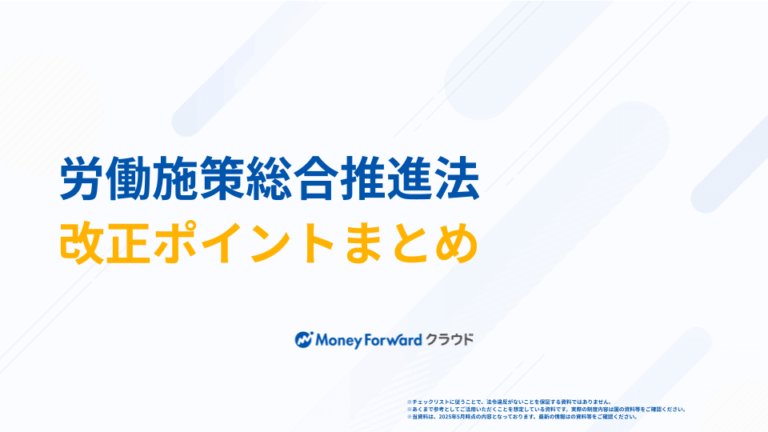- 更新日 : 2025年12月24日
労働施策総合推進法とは?概要と2022年施行のポイントを解説!
労働施策総合推進法は別名「パワハラ防止法」と呼ばれ、働く人にとって身近な法律です。2022年4月1日からは中小企業もこの法律の対象となるため、内容を把握しておきましょう。ここでは改正の背景や目的、企業が取るべき対応、気になる罰則について解説します。
※ 中小企業の定義は中小企業庁のHPをご参照ください
目次
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)とは?
労働施策総合推進法は、1966年に制定された「雇用対策法」を改正し、労働者が生きがいをもって働ける社会の実現を目的として成立しました。正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。2019年5月の改正により、大企業に2020年6月から職場におけるパワーハラスメントの防止が義務づけされ、パワーハラスメント対策の強化が図られたことにより「パワハラ防止法」とも呼ばれるようになりました。
パワハラ防止法にいう「パワハラ」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素をすべて満たすものをいいます。ただし、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントに該当しません。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)改正の背景と目的
2016年度に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した人は32.5%に上りました。このような背景の下、職場のパワーハラスメントの予防・解決を目的として、労働施策総合推進法が改正されました。
参考:厚生労働省|平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書 厚生労働省
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。
本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド
雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。
本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。
2022年施行のポイント
改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では「第30条の2(雇用管理上の措置等)」「第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)」の条文が新設されました。これまで規定のなかった職場におけるパワーハラスメントを初めて定義した点や、企業にパワーハラスメント防止のため、社内のルールや相談体制の整備など、雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけた点が改正ポイントです。すでに大企業では法令が適用されていますが、中小企業にとって2022年は、努力義務とされていた期間が終わり、義務化が適用される節目の年となります。
2022年4月から中小企業も法令の対象となる
2020年6月から大企業で適用されているパワーハラスメントの防止義務が、2022年4月から中小企業にも適用されます。そのため、労働施策総合推進法の改正の理解と、パワーハラスメント対策の基本的な枠組みを早急に構築することが求められています。
この法令の対象となるのはすべての労働者とされており、正社員に限らず、パートや契約社員などの非正規労働者や、派遣労働者も含まれるため注意しましょう。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)について企業が取るべき対応
労働施策総合推進法は、職場のパワーハラスメントに対して、企業にどのような対応を義務づけたのでしょうか。ここでは具体的な対策方法を挙げながら説明します。
パワーハラスメントが生じないための環境整備
厚生労働省が定めた「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワハラ指針)」の項目を確認し、就業規則に関係規定を設けることや、労使協定を締結するなど、まずは社内ルールを明確化し、周知・啓発することが重要です。この周知は電子メールやポスター等で伝えるだけでなく、会社が本気でパワハラ防止に取り組んでいることを理解してもらえるようにしましょう。また、相談窓口をあらかじめ定め、迅速に適切な対応ができるよう、解決に向けたガイドラインも作成しましょう。これらの活動の継続には、効果把握の調査や、取り組みの修正を含め、年間スケジュールを立てて計画的に進めることが大切です。
パワーハラスメントを相談した者に対する不利益の排除
パワーハラスメントの相談者や、事実確認するための第三者、行為者などの個人情報が職場に広まり、不利益な扱いを受けることや、企業の不都合を隠すために相談者を解雇することは、法律上禁止されています。パワーハラスメントの相談者は、行為者からの報復を恐れながら過ごしていることを心に留め、秘密が守られ、安心して相談できる窓口をつくりましょう。できるだけ初期の段階で気軽に相談できるような環境を提供する方法のひとつとして、外部相談窓口の活用も有効です。また、相談内容や状況に応じて適切に対応できるよう、フォロー体制を整えましょう。
社内研修ほかパワーハラスメントに関する従業員への周知
パワーハラスメントの防止には、会社の方針やルール、相談窓口や取り組みを積極的に周知して、会社が真剣に取り組んでいることを従業員に実感してもらうことが大切です。社内研修などの教育は、周知を確実なものにするために効果的な方法といえます。
また、パワハラ防止法では、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントに該当しないとされていますが、「適正な指示」であったとしても、時として感情がこもってしまったりすることは人間である以上、避けられない側面があります。パワハラの図式は、必ずしも上司から部下に対する態様のものばかりとは限りませんが、一般的には上司との関係において問題となることが多いと想像されます。せっかくの熱のこもった指導が、従業員にとってはパワハラであるとも受け止められかねません。
従って、従業員へパワハラに関する研修を実施することは、多少の感情がこもってしまったとしても、上司からの「適正な指示」であるか否かを彼らに適切に判断してもらうための一助にもなるかもしれません。
もっとも、パワハラとなり得る態様を押さえておくことは、これからマネジメントを担う立場として必須のスキルだといえるでしょう。
事業主自らのパワーハラスメント防止への理解と徹底
職場のパワーハラスメントは、業務上の教育指導や注意との見分けがつきにくいという難点があるため、まず事業主自らが「パワーハラスメントとは何か」を理解することが必要です。職場のパワーハラスメントは、受ける人だけの問題ではありません。パワーハラスメントの放置は、貴重な人材の損失や、裁判沙汰による会社名の公表、被害者によるSNSを使った拡散など、使用者としての責任を問われ、イメージダウンにつながりかねません。パワーハラスメントを見過ごさないためにも、対策を徹底しましょう。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)を遵守できなかった場合の罰則
労働施策総合推進法には、違反した場合の罰則がありません。しかし、厚生労働大臣が必要と判断する場合は、企業に対して助言や指導、勧告するとされています。従わない場合は内容が公表され、企業の社会的信用が失われることにもつながりかねません。
2022年の施行に合わせてパワハラへの理解と防止策を徹底しよう
労働施策総合推進法は、パワーハラスメントの防止に関する規定が盛り込まれた身近な法律であることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。2022年4月から中小企業も法令の対象となることに合わせ、まずは企業の方針を明確にすることや、相談など適切に対応するための体制を整え、教育や周知することをおすすめします。職
場のパワーハラスメントは、誰もが被害者にも行為者にもなる可能性があります。この法律の施行をきっかけに、パワーハラスメントのない職場を目指してみてはいかがでしょうか。
よくある質問
労働施策総合推進法とは何ですか?
これまで法的規定のなかったパワーハラスメントについて定義し、防止措置を事業主に義務づけた法律で「パワハラ防止法」とも呼ばれています。 詳しくはこちらをご覧ください。
労働施策総合推進法について2022年4月施行のポイントは何ですか?
2022年4月1日から、労働施策総合推進法の適用が大企業から中小企業まで拡大されます。そのため中小企業にも、パワーハラスメント対策の基本的な枠組みを早急に構築することが求められています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
勤怠控除(欠勤控除)とは?計算方法を分かりやすく解説!
勤怠控除とは、給与から差し引かれる項目のひとつです。端的にいうと、働かなかった時間分の賃金を給与から差し引くことで、「欠勤控除」と呼ばれることもあります。この記事では、勤怠控除の考え方や計算方法などを解説します。 勤怠控除(欠勤控除)とは?…
詳しくみる一年変形労働時間制とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
一年変形労働時間制は、年間を通じて労働時間を調整する働き方です。とくに業務の繁忙期と閑散期が明確な業種に最適です。労働時間に関する制度は、ほかにもいくつかの種類があり、それぞれのメリット・デメリットも存在します。 本記事では、一年変形労働時…
詳しくみるパートの勤務時間を変更するには?会社都合や自己都合のルールや手続きを解説
パートの勤務時間を会社の判断だけで勝手に変更することは、原則として認められていません。会社とパート本人の話し合いで決める必要があります。この記事では、会社から変更を伝える場合と、本人から希望がある場合の勤務時間変更のルールや手続き、トラブル…
詳しくみる夜勤の仮眠時間の理想は?16時間夜勤で仮眠なしは違法?
深夜に及ぶ夜勤で労働時間が長時間になる場合、仮眠時間が問題となることがあります。例えば、16時間に及ぶ夜勤で仮眠時間が与えられない場合、法律上違法なるのでしょうか。今回は、仮眠時間の付与について、労働基準上の扱いについて解説していきます。 …
詳しくみる労働基準法第68条とは?生理休暇の取得方法や企業が配慮すべきポイントを解説
労働基準法第68条は、女性労働者が生理による体調不良で働くことが著しく困難な場合に取得できる「生理休暇」について定めた規定です。本記事では、労働基準法第68条の基本概要や適用範囲、最新の判例や厚生労働省のガイドラインの情報を解説します。人事…
詳しくみる休憩時間が取れなかった場合どうすればよい?対処法や違法性について解説!
休憩時間は、労働基準法に定められた事業主が労働者に与えなければならない義務です。しかし、仕事の事情などで、労働者が休憩時間を取得できないケースもあるでしょう。本記事では、休憩時間が取れなかった場合の対処法や違法性について解説します。 この記…
詳しくみる