- 更新日 : 2025年12月24日
コアタイムとフレキシブルタイムとは?フレックスタイム制の基本を解説
子育てをしながら働く社員や、仕事をしながら親の介護をしている社員など、生活環境が多様化するなか、現在政府は「フレックスタイム制」を促進しています。
この制度は「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を労使間で決定し、それに基づいて運用されなければなりません。ここではスムーズにこの制度を導入するためのコアタイムやフレキシブルタイムの考え方、導入に必要な要件について解説します。
目次
フレックスタイム制におけるコアタイムの決め方
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は労働基準法第32条の3に基づいた労働時間の管理方法です。一般的に企業では「午前8時から午後5時まで」「午前9時から午後6時まで」というように労働者が勤務する時間を定め、労働者はそれに従って働きます。
これに対してフレックスタイム制では1日当たりの労働時間を固定しません。一定期間の総労働時間だけを決めておき、労働者はその労働時間の範囲内でいつ働くかを自分の裁量で決めます。そのため労働時間を固定する場合よりも、各労働者の事情に応じた働き方がしやすくなります。
フレックスタイム制促進の背景
フレックスタイム制は厚生労働省によって、促進されています。グローバリゼーションの進展により経済状況はめまぐるしく変化するようになりました。
これに日本がついていくためには、これまで以上に各労働者の個性・能力を活用する必要があります。また労働者自身の生活も以前とは大きく変わり、親の介護が必要な場合や、共働き家庭で子どもの送迎が必要な場合など、様々な生活パターンが増えてきています。
このような状況に対応するためには固定的な労働時間管理ではなく、各労働者の裁量に任せるフレックスタイム制の導入が必要になるのです。
フレキシブルタイムとコアタイム
フレックスタイム制には2種類の労働時間があります。それがフレキシブルタイムとコアタイムです。
フレキシブルタイムとは労働者が自身の裁量で決められる時間帯のことです。労働者は定められたフレキシブルタイムの中から、自分が働きたい(あるいは働くべき)時間を決定します。裁量で決められる時間が短いと、フレックスタイム制とはみなされなくなるため、フレキシブルタイムをどの程度認めるかがフレックスタイム制のポイントとなります。
これに対してコアタイムとは労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯のことです。フレックスタイム制においてもこのコアタイムには必ず勤務していなければなりません。定例会議など固定的な業務がある場合はコアタイムを設定することで対応できます。

(出典:フレックスタイム制の適正な導入のために|東京労働局労働基準部・労働基準監督署)
こちらは東京労働局が提示するフレックスタイム制の基本モデルです。間に休憩時間を挟みながら10時から15時をコアタイムとし、6時から10時までと15時から19時までをフレキシブルタイムとしています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
就業規則の作成・変更マニュアル
就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。
本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。
労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。
本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。
就業規則(ワード)
こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
就業規則変更届 記入例
こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。
実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。
フレックスタイム制採用に必要な2つの要件
フレキシブルタイムとコアタイムの設定をしただけではフレックスタイム制を導入したことにはなりません。「就業規則への明記」と「労使協定の締結」という2つの要件を満たす必要があります。
就業規則への明記
フレックスタイム制を導入するには就業規則にその旨を明記しなければなりません。具体的には次のような内容です。

(出典: フレックスタイム制の適正な導入のために|東京労働局労働基準部・労働基準監督署)
ここで明記する内容はそれぞれ労使協定であらかじめ定めておく必要があります。
労使協定で定めるべき6項目
労使協定で定めておかなければならない項目は以下の6つです。
1.対象となる労働者の範囲
→各人、各課、各グループなどで定めます。「全従業員」としても構いませんし、フレックスタイム制が求められる部署が営業部だけなら「全営業部職員」としても構いません。
2.清算期間
→フレックスタイム制において労働者が勤務するべき時間を定める期間を、清算期間と呼びます。賃金の計算に合わせて1ヶ月に設定するのが一般的です。なお清算期間は最長1ヶ月となっています。
3.清算期間における起算日
→清算期間がどの期間かを明確にするために「毎月○日」というように起算日を具体的に定めておく必要があります。
4.清算期間における総労働時間
→清算期間における総労働時間とはいわゆる所定労働時間を指します。清算期間を平均した時に1週間の労働時間が40時間以内になるよう定めなければなりません。具体的な総労働時間を定めるためには以下の条件式を使います。
清算期間における総労働時間≦清算期間の暦日数/7日×1週間の法定労働時間
5.標準となる1日の労働時間
→標準となる1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に1日を何時間労働として賃金計算するかを決めるためのものです。
6.フレキシブルタイムとコアタイム
→1~5を踏まえたうえで、フレキシブルタイムとコアタイムを設定します。
のちのち余計なトラブルを招かないよう、労使協定の段階でしっかりと話し合い、決定するようにしましょう。
まとめ
フレックスタイム制は各労働者の生活環境等に応じた働き方を実現するための労働時間の管理制度です。
しかし労働時間の管理は賃金計算に直結するため、適切な運用には事前にしっかりと労使間でルールを決めておく必要があります。安易に導入せず、導入前には自社の状況に本当に必要な制度かどうかを吟味するようにしましょう。
関連記事
・残業代計算、正しくできていますか?基本的な考え方を解説
・みなし残業は本当に従業員にとってメリットなのか?残業代を支給給与に含む意味とは
・雇用契約書は必要か不要か?事業者が知っておくべき基礎知識
よくある質問
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は労働基準法第32条の3に基づいた労働時間の管理方法で、1日当たりの労働時間を固定しない制度です。 詳しくはこちらをご覧ください。
フレックスタイム制採用に必要な要件は?
フレックスタイム制を導入するには「就業規則への明記」と「労使協定の締結」という2つの要件を満たす必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
終業時間とは?始業時間との関係やどこまで含まれるか解説
終業時間を守ることは働き方を見直す第一歩です。 本記事では、終業時間の定義や始業時間との関係性、労働時間に含まれる範囲を解説します。 終業時間を守るためのポイントも紹介するので、働…
詳しくみる台風で有給取得させるのはおかしい?強制取得の禁止や無給のルールなどを解説
台風などの悪天候で出社が困難な場合、企業が従業員に有給を取得させる対応は適切なのでしょうか。本記事では、台風時の有給休暇取得に関する法律的な側面について詳しく解説します。安全確保と…
詳しくみる雇用契約とは?労働契約との違いや雇用契約書・労働条件通知書の必要性も解説!
会社と雇用契約を結んで仕事に従事する人は、労働者として定義されています。そして、労働者はパート・アルバイトなどの雇用形態に依らず、労使間で雇用契約を結ぶことが法律で義務付けられてい…
詳しくみる25連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
25連勤ともなると、身体の疲労と精神的なストレスの負担は非常に深刻なものになります。 本記事では 「25連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりやすく解説します…
詳しくみる年次有給休暇が20日以上になる条件とは? 申請を拒否できるケースも紹介
有給休暇は、労働者に与えられた重要な権利のひとつです。企業は要件を満たした従業員に対して、適当な日数の有給休暇を付与しなければいけません。 しかし、「各従業員に何日の有給休暇を付与…
詳しくみるみなし残業に上限はある?45時間・60時間では?目安や違法な場合を解説
みなし残業の上限は、労働基準法で明確に定められているわけではありません。しかし、36協定の上限規制に合わせて、一般的には月45時間以内に設定されています。 みなし残業とは、事前に一…
詳しくみる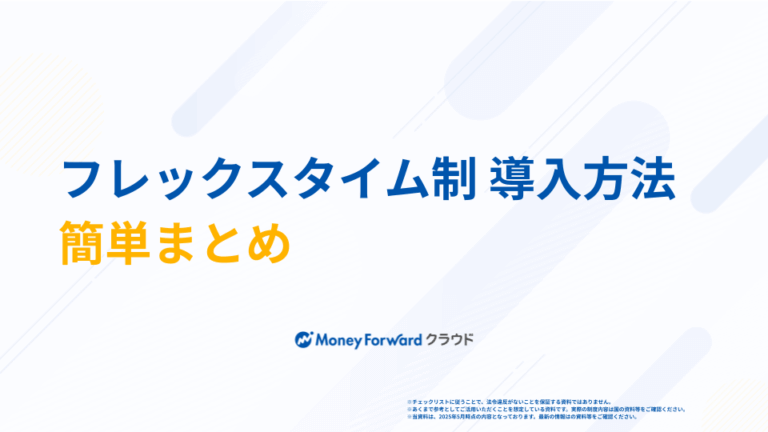


-e1762754602937.png)
