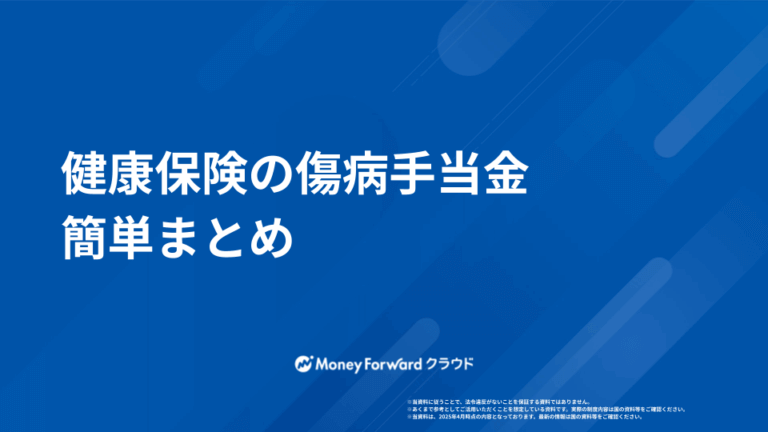- 更新日 : 2025年11月11日
健康保険の傷病手当金とは
健康保険に加入していれば、被保険者や家族がケガをしたり病気になったりしたとき、一部の負担で治療を受けることができます。お医者さんが処方してくれた薬も同様です。
これを「病養の給付」といい、名称を知らない人であっても、病院に行った際、健康保険証を提出しさえすれば、一部の負担金で治療を受けることができるということを知らない人は少ないでしょう。
病院にかかったときに70歳未満の被保険者の場合は3割負担で医療を受けられるのはこの制度があるためです。そのほかにも、健康保険にはさまざまな制度があります。医療費が高額になりそうなときの「限度額適用認定」や高額な医療費を払ったときの「高額療養費」、病気やケガにより会社を休んだ場合の「傷病手当金」などがあります。
このうち今回は「傷病手当金」について解説します。
傷病手当金のあらまし
傷病手当金とは、病気やケガで出勤できず給料をもらえない場合に、被保険者とその扶養家族の生活を保障するために扶養家族の生活を保障するために設けられた制度で、健康保険から支払われるお金のことを指します。
傷病手当金は非課税で、社会保険料控除の対象です。なお、傷病手当金を受給中であっても社会保険料は請求されます。
ただし、任意継続被保険者の方は傷病手当金支給の対象外であり、傷病手当金は支給されませんので注意しましょう。なお、任意継続被保険者とは、会社を辞めて社会保険の資格を喪失した後も、一定条件を満たすことにより社会保険を継続している方です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
受けとるための要件は?
傷病手当金は、会社を休まざるを得なかったときに健康保険から支給されるものですが、例えば1日休んだだけでは適用されません。
被保険者が病気やケガで出勤できず、欠勤日が連続して3日間あった場合の4日目過ぎてから休んだ日に対して支給されるものです。
会社を休んでいても、病院へ行かずに自宅で休養した場合などには適用されません。保険診療でも自由診療でもかまいませんが、診療した事実があることが支給の要件に掲げられています。
受給期間について
4日以降から最長1年6カ月間まで支給されます。ただし、会社から傷病手当金の金額よりも多い給料が支給された場合、傷病手当金は支給されないため注意が必要です。
支給される金額について
支給額は、原則として、病気やケガで欠勤した日1日にごとに、標準報酬日額の3分の2が支払われます。ただし、以下の場合は支給額が調整されます。
・事業主から給料を受けとっている場合
・同一の傷病により障害厚生年金を受給している場合(国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
・退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを受給している場合 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
以上の支給日額が、傷病手当金の金額を上回る場合は、傷病手当金は支給されません。一方で、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
退職後の支給条件について
傷病手当金を受けとっている途中に退職することになった場合、あるいは退職日に傷病手当金を受けとるための要件を満たしている場合、社会保険資格喪失の前日(つまり退職日)まで社会保険の被保険者期間が継続して1年以上あれば、傷病手当金を継続して受けとることができます。
在職中の手続きは事業主が行いますが、退職後は自分で社会保険事務所か健康保険組合に直接出向き、手続きを行います。
まとめ
以上、見てきたように、健康保険に加入していれば、病気やケガなどの治療、療養が必要になり、仕事復帰がすぐにかなわない場合に給料が支払われなくても被保険者と家族の生活の保障のために設けられているのが傷病手当金です。
支給の適用となるためには、健康保険組合のHPなどで、一定の条件があることを確認しておき、必要な状況になったときでも慌てずに利用できるようにしておきましょう。
また、この制度は、退職後の方でも条件によっては利用可能です。社会保険事務所あるいは健康保険組合に相談することになりますが、自分でも制度のあらましを知っておくと、相談しやすいでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
育児休業給付金の80%引き上げはいつから?人事労務担当者が注意するポイントも解説
2025年4月1日より、育児休業給付金の実質給付率が80%(手取り10割相当)へ引き上げられました。これは新設された「出生後休業支援給付金」によるものですが、「夫婦ともに通算14日…
詳しくみる厚生年金の事業所番号とは?わからない時の確認方法は?
従業員を雇用すると、事業主は健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関するさまざまな手続きを行う必要があります。 所定の書類を年金事務所などに提出することになりますが、その際は事業所…
詳しくみる確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表とは?記入例を解説
労働保険の年度更新の時期(毎年6月1日~7月10日) になると、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(様式第6号)の作成が必要になります。しかし、その申告書に正しい金額を記…
詳しくみる健康保険とは?被用者保険と国民健康保険の違い
健康保険は、日本の医療制度を支える重要な保険制度です。会社員や公務員が加入する政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合のほかに、個人事業主や自営業者が加入する国民健康保険があります…
詳しくみる算定基礎届と月額変更届との違いは?対象者や提出方法を詳しく解説
算定基礎届と月額変更届は、企業の社会保険手続きにおいて重要な書類です。従業員の標準報酬月額を決定するために提出が必要な手続きであり、提出方法や提出先に関して注意すべきポイントがあり…
詳しくみる雇用保険被保険者離職証明書の離職理由|自己都合・会社都合の書き方やコードを解説
雇用保険被保険者離職証明書および離職票に記載される離職理由は、退職後の失業保険(基本手当)の受給内容を左右する重要な項目です。離職理由の書き方や、ハローワークが判断する離職区分コー…
詳しくみる