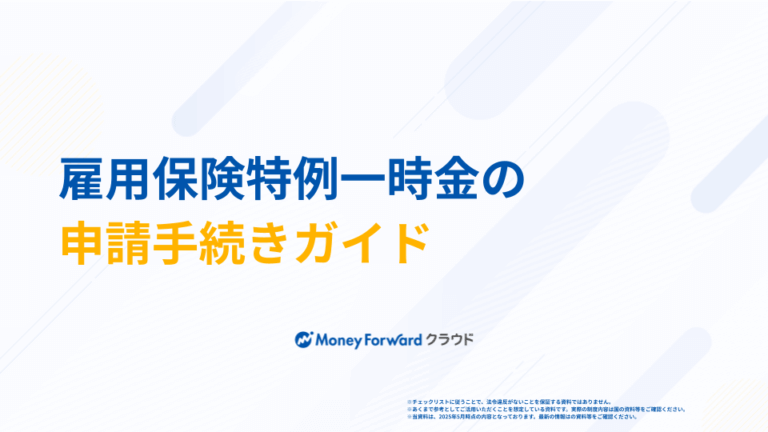- 更新日 : 2025年11月18日
雇用保険における特例一時金とは
雇用の形態には職種や業態によってさまざまなものがあります。一年を通して平均して仕事がある会社と雇用契約を結んで勤め続けるのが一般的ですが、一定の期間のみ仕事があってその都度雇用をする形態の会社も少なくありません。
雇用保険では、このような就職と離職をある期間で繰り返している被保険者に対して、一時金を支給する制度を設けています。この制度で給付されるものを特例一時金と言います。
雇用保険の特例一時金の受給資格
雇用保険の特例一時金の給付を受ける対象となるのは、短期雇用特例被保険者と呼ばれる雇用保険の被保険者です。短期雇用特例被保険者とは季節的な雇用をされる者を指します。
季節的な雇用とは、天候に左右される仕事で季節を限定して行われる雇用をいい、具体的な例としては、農閑期となる冬に農業従事者が行う他業種への就業や、夏の海の家や冬のスキー場での就業などがあげられます。(なお、短期雇用特例被保険者となる条件は、「4ヶ月以上の期間を定めて雇用される」、「週所定労働時間30時間以上」となります。)
短期雇用特例被保険者に対して雇用保険の特例一時金が支給されるためには、ハローワーク(住所地を管轄する職業安定所)に本人が出向き、求職の申し込みをし、特例受給資格の決定を経なければなりません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
雇用保険の特例一時金の受給資格要件
雇用保険の特例一時金を受給するために必要な特例受給資格を得るには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
1.離職して雇用保険の被保険者ではないことをハローワークが確認していること。
2.求職の申し込みをすることによって、就職していない状況であること、および就職口を探す意思や能力があることを示し、受給資格決定日・認定日においても就職していないこと。
3.離職日直前の1年間で雇用保険に通算で6ヶ月以上加入していたこと。ただし、この場合の被保険者期間は、賃金の支払い対象となった日を基準として、1ヶ月のうちに11日以上あればそれを1ヶ月として計算したもの。
前記要件を満たしても、自分で事業を始めていたり、家業に従事したり、家事の手伝いをして実際に就職ができない状態であれば、特例一時金は受給できません。パートタイム労働やアルバイト、日雇い、報酬のあるなしに関わらず会社役員に就任した場合なども同様です。
雇用保険の特例一時金を受給する手順
雇用保険の特例一時金を受給するまでの手順は次のとおりです。
1.住所地を管轄しているハローワークに、離職票、本人確認書類、本人名義の通帳や印鑑などを用意して行き、求職の申し込みを行います。短期雇用特例被保険者の場合は2枚以上の離職票がある場合もあります。特例受給資格に関係するので、離職票はすべて提出してください。(実際の持ち物については、管轄にご確認ください。)
2.ハローワークが提出者の状況と要件を照らし合わせ、受給資格があるかどうかを判断します。資格があると判断されれば、特例受給資格の決定が下されます。
3.特例受給資格の決定に従って、特例受給資格者証が交付されます。また、失業認定に関する手続きに必要な特例受給資格者失業認定申告書を渡されますので、失業の認定日までに必要事項を記入しておきます。
4.後日指定された失業の認定日にハローワークへ出向きます。そこで失業の認定に関する手続きを行います。
失業の認定に関する手続きとは、記入しておいた特例受給資格者失業認定申告書を窓口に提出することです。ハローワークが失業の認定を行った時点で、雇用保険の特例一時金の支払いが行われます。
受給期間と給付制限
雇用保険の特例一時金の場合、その受給できる期間は、離職した日の翌日を起算日として、6ヶ月までとなります。一般の雇用保険(失業給付)と同様に、特例受給者資格についても離職日から7日間の待機期間が定められています。つまり、申請をして特例受給資格者であるとハローワークが確認しても、待機期間を過ぎてからでなければ雇用保険の特例一時金は受給できません。
また、場合によっては待機期間が3か月になる(自己都合退職や職務上の責任を取って解雇された場合など)というもの、一般の雇用保険(基本手当)と同様です。
雇用保険の特例一時金の支給額
ハローワークが特例受給資格者と確認し、待機期間を過ぎた時点で、ハローワークが算出した基本手当日額の30日分(現在のところ暫定措置として40日分)が支給されます。
なお、ハローワークが失業を認定した日と受給期限日(離職から6ヶ月目)が30日(暫定40日)に満たない場合は、雇用保険の特例一時金の算定は残っている日数分に減じられます。
まとめ
雇用保険の特例一時金は、基本手当を受けることのできない短期雇用特例被保険者を保護するための給付制度です。
名称のとおり失業の認定を受けた時点で1回しか支給されませんが、受給要件や期間が基本手当を受給する場合とは異なるため、きちんと確認し、漏れのないよう受給手続きを行う必要があります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の健康保険料はどのくらい?計算方法や標準報酬月額の仕組みを解説
健康保険料や厚生年金保険料がどのように計算されるかは、実務に携わる者として当然備えておくべき基礎知識です。社会保険に関する知識が不足したまま給与計算を行うと、従業員から徴収すべき保…
詳しくみる健康保険の被扶養者の要件について
日本に在住する人であれば、短期滞在者を除いて国籍にも性別にも年齢にも関係なく、どの人に対しても加入が義務付けられているのが健康保険です。 この健康保険により、病気や負傷、出産や亡く…
詳しくみる社会保険の手続き・届出一覧 – 被保険者と事業所に分けて解説
社会保険には、健康保険や雇用保険、厚生年金保険など、労働者の生活の安定や雇用の維持・促進をサポートするためのさまざまな制度が含まれます。労働者を雇用する企業(事業主)は、法令に従い…
詳しくみる社会保険の加入義務とは?対象者の条件やパート・アルバイトの適用範囲拡大についても解説!
社会保険は、けがや病気、出産、老後、障害、死亡といった生活に支障をきたすさまざまなリスクに備え、生活の安定を図ることを目的とした公的な保険制度です。ただし、その仕組みは複雑であり、…
詳しくみる労災で骨折した際に休業補償給付を受給できる期間は?支給額や労災申請の流れも解説
労災で骨折して働けなくなると、多くの場合は休業補償給付の支給対象になります。休業補償給付は、仕事中のケガで休業する時に働けない日の収入を補償する、労災保険の制度です。 労災で骨折し…
詳しくみる子供を扶養に入れる条件は?共働き・大学生の年収基準や手続き方法を解説
子供を親の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入れると、子供自身の社会保険料の負担がなくなります。共働きのご家庭や、アルバイトをする大学生の子供を持つご家庭にとって、「子供が扶養…
詳しくみる