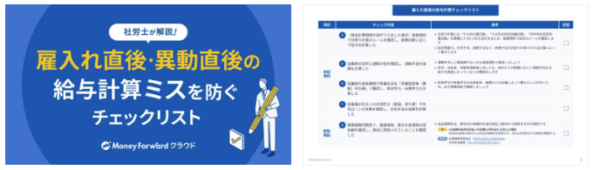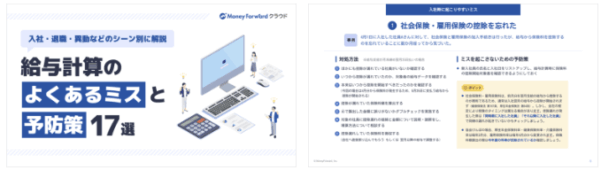- 更新日 : 2025年11月21日
その異動命令、権利濫用かも?経営者が知るべき法的リスクと対策
企業の成長戦略において、人事異動は不可欠な打ち手です。しかし、その命令の出し方を一歩間違えれば「権利濫用」と見なされ、思わぬ法的リスクを抱えることになります。異動命令が無効になるだけでなく、従業員との信頼関係が崩れ、最悪の場合、訴訟に発展することも。この記事では、どのような異動が権利濫用にあたるのか、企業が直面するリスクと具体的な対策について、経営者や人事担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
異動命令が「権利濫用」になる3つのケース
企業は労働契約に基づき、従業員に対して配置転換や転勤を命じる「人事権」を持っています。しかし、この権利は無制限ではありません。労働契約法では、権利の行使が客観的に見て合理性を欠き、社会通念上許されない場合は、その権利を濫用したものとして無効になると定められています。これを「権利濫用の禁止」と呼び、人事異動においては、主に以下の3つのケースで権利濫用が問われます。
業務上の必要性がない
異動命令を出すには、その背景に合理的な理由が必要です。「人員の適正配置」「業務効率の向上」「従業員の能力開発」といった、企業の円滑な運営に資する目的があれば、通常は業務上の必要性が認められます。しかし、特定の従業員を隔離するためだけ、あるいは人員が充足している部署へあえて異動させるなど、経営上の合理的な理由が見いだせない命令は、権利濫用と判断される可能性が高まります。
不当な動機・目的がある
業務上の必要性があったとしても、その裏に不当な動機や目的が隠されている場合、その異動命令は権利濫用と見なされます。例えば、労働組合の活動を妨害する目的や、内部告発者に対する報復、あるいは自主的な退職に追い込むための嫌がらせとして異動を命じるケースがこれにあたります。このような社会通念上許されない目的による人事権の行使は、たとえ形式を整えていても無効と判断されます。
労働者の不利益が著しく大きい
異動によって労働者が受ける不利益が、企業側が主張する業務上の必要性と比較して、あまりにも大きい場合も権利濫用にあたります。転勤による単身赴任や、子の育児、家族の介護が困難になるなど、家庭生活への影響は避けられません。こうした不利益が、社会通念上「通常甘受すべき程度(受け入れるべき範囲)」を著しく超えると判断された場合、異動命令は違法・無効となる可能性があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
異動の権利濫用で企業が負う法的リスク
権利濫用と判断された場合、企業は単に「異動が認められなかった」だけでは済みません。そこから派生する様々な法的リスクに直面することになり、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。
関連記事|人事異動は拒否できる?拒否された場合の対応やスムーズな異動のポイントを解説
異動命令が無効になる
裁判所などによって異動命令が権利濫用と判断された場合、その命令は法的に効力を失います。つまり、従業員はその異動に従う義務がなくなり、元の部署や役職で働き続ける権利が認められます。もし企業がこれを無視して異動先での勤務を強要したり、拒否したことを理由に不利益な扱いをしたりすれば、さらなる法的トラブルへと発展する火種になりかねません。
損害賠償を請求される
不当な異動命令によって精神的な苦痛を受けたとして、従業員から慰謝料を請求される可能性があります。また、異動に伴って役職が下がり賃金が減額された場合には、その差額分の支払いを求められることもあります。権利濫用の態様が悪質であると判断されれば、賠償額が高額になるケースも少なくありません。法的リスクは、企業の財務にも直接的な影響を及ぼすのです。
企業の評判や従業員の士気が低下する
訴訟トラブルは、企業の社会的な評判を大きく損なう可能性があります。特に近年はSNSなどで情報が瞬時に拡散するため、「ブラック企業」との評判が広まれば、採用活動や取引関係にも悪影響が及びます。また、社内においても「次は自分が不当な異動をさせられるかもしれない」という不安が広がり、従業員のエンゲージメントや生産性の低下、さらには有能な人材の離職につながる恐れもあります。
関連記事|配置転換はパワハラになる?該当するケースや拒否された場合の対応を解説
権利濫用トラブルを防ぐための企業の対策
人事異動をめぐるトラブルは、その多くが事前の対策によって防ぐことが可能です。日頃から適切な労務管理を徹底し、権利濫用と指摘される隙を作らないことが、経営者や人事担当者に求められます。
関連記事|転勤命令の拒否は原則不可?トラブルを防ぐために企業が知るべき対応方法
就業規則に根拠規定を整備する
企業が人事異動を命じるための大前提として、就業規則や労働協約にその根拠となる規定があることが不可欠です。「会社は業務上の必要がある場合、従業員に対して配置転換、転勤を命じることがある」といった包括的な条文を明記しておくことで、人事権の正当な根拠となります。この規定がなければ、原則として従業員の個別的な同意なしに異動を命じることはできません。
採用時に勤務地や職種の範囲を明確にする
採用時に「勤務地は本社限定」「職種は経理のみ」といった限定的な合意(職種限定・勤務地限定合意)を結んでいる場合、その範囲を超える異動命令は原則として従業員の同意がない限り無効となります。トラブルを避けるためにも、採用時の労働契約書において、将来的に配置転換や転勤の可能性があることを明確に伝え、双方の認識を合わせておくことが極めて重要です。
対象者へ丁寧に説明し、手続きの透明性を保つ
異動を命じる際は、一方的な「命令」ではなく、丁寧な「説明」を尽くすことがトラブル回避の鍵です。なぜその従業員が異動の対象となったのか、異動先でどのような役割を期待しているのか、といった業務上の必要性を具体的に説明することで、本人の納得感を得やすくなります。内示から発令までの期間に十分な余裕を持たせるなど、手続きの透明性を確保することも信頼関係の構築につながります。
従業員の個人的な事情に配慮する
異動を打診する際には、従業員が抱える個人的な事情にも耳を傾ける姿勢が求められます。特に、育児や家族の介護、本人の持病といった重要な問題については、可能な限りの配慮を検討することが不可欠です。代替案(例:異動時期の延期、一時的な単身赴任手当の増額など)を示すなど、真摯に対応することで、権利濫用との指摘を受けるリスクを大幅に低減できます。
【判例解説】権利濫用の判断ポイント
人事異動の権利濫用が争われた過去の裁判例は、現在においても重要な判断基準となっています。特に以下の2つの事件は、企業の担当者として必ず押さえておくべきリーディングケースです。
東亜ペイント事件:権利濫用と認められた代表例
この事件は、転勤命令の権利濫用に関する最高裁判所の基本的な判断枠組みを示したことで有名です。判決では、企業に広範な人事権を認めつつも、①業務上の必要性がない場合、②不当な動機・目的がある場合、③労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負う場合には、権利濫用として無効になるとしました。この3つの判断基準は、その後の多くの裁判で引用される基本的な考え方となっています。
ケンウッド事件:労働者の不利益が限度を超えないとした例
この事件では、育児中の女性従業員に対する遠隔地への転勤命令および懲戒解雇処分の相当性が争われました。裁判所は、企業の業務上の必要性を認め、転勤によって従業員が負うことになる不利益(幼い子供の保育が困難になるなど)は、業務上の必要性と比較して「通常甘受すべき程度を著しく超えるものではない」と判断し、転勤命令および懲戒解雇を有効としました。不利益は必ずしも小さくないが、転居が可能であり、転居を行えば不利益を軽減できたことが指摘されています。
増加するメンタルヘルスと異動命令の問題
現代の職場において、従業員のメンタルヘルスは避けて通れない重要な課題です。特に、環境の変化を伴う人事異動は、従業員にとって大きなストレス要因となり得ます。
うつ病など健康問題を理由に異動は拒否できるか
従業員がうつ病などの診断を受け、主治医から「現在の環境での就労が望ましい」といった意見書(診断書)が提出されている場合、それを無視して異動を強行することは極めてリスクが高い行為です。本人の症状を悪化させる可能性があり、権利濫用と判断されるだけでなく、次に述べる「安全配慮義務」に違反する可能性も出てきます。健康問題を理由とした異動拒否には、企業として慎重な対応が必要です。
関連記事|うつ病になった従業員を部署異動させるのは義務?配置転換のポイントもあわせて解説
企業に求められる安全配慮義務
企業は、労働契約法第5条により、企業は従業員が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮を行う義務(安全配慮義務)を負っています。メンタルヘルスの不調を抱える従業員に対して、その状態を悪化させるような異動を命じることは、この安全配慮義務に違反すると判断される恐れがあります。産業医や専門家と連携し、従業員の健康状態を最優先に考えた配置を行うことが、法的なリスクを回避する上で不可欠です。
関連記事|安全配慮義務とは?範囲や違反した場合の罰則、注意点を解説!
適切な人事権の行使が異動の権利濫用リスクを回避する
人事異動は企業の正当な権利ですが、その行使には常に合理性が求められます。権利濫用と判断されるリスクを避けるためには、異動の「業務上の必要性」を明確にし、従業員が被る不利益に十分配慮した上で、丁寧な手続きを踏むことが不可欠です。就業規則の整備はもちろん、日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、個々の事情を把握しておくことが、健全な労使関係を築き、不要なトラブルを事前に防ぐための最も効果的な手段と言えるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
パワハラで労災申請するコツは?認定の基準や認められた事例を解説
パワハラが原因で精神障害になった場合は、労災申請の対象になることも考えられます。労災申請の条件は、業務中のパワハラであり、個人間のトラブルではないことです。 本記事では、パワハラ行…
詳しくみる外国人雇用で利用できる助成金とは?2026年最新情報を徹底解説
近年では事業における人材不足が進んでおり、グローバル化に伴い外国人雇用をご検討の方もいらっしゃるでしょう。事業者向けの各種助成金制度を活用すれば、採用負担を軽減できるチャンスも広が…
詳しくみる安全衛生委員会の設置基準は?50人未満の場合やメンバー構成、進め方まで解説
労働安全衛生法では、一定規模以上の事業場に対して、安全衛生委員会の設置を義務付けています。しかし、「どんな場合に設置が必要なの?」「メンバーはどうやって選べばいいの?」「委員会では…
詳しくみる労働協約とは?労使協定との違いや締結プロセスを解説
会社で働くうえでは、給与や休暇をはじめとする様々な取り決めがなされます。労働条件などをあらかじめ当事者間で定めることによって、後のトラブル発生を防止しています。 当記事では、労働協…
詳しくみる就業規則の効力がおよぶのはどこまで?発生要件や周知の重要性を解説
就業規則は、会社に勤める人全員に適用されるルールです。しかし、適切に運用されておらず効力がないままだと、従業員とトラブルになった際に規則が有効だと認められず、損害を被る可能性があり…
詳しくみるバーチャルオフィスとは?費用の目安や選び方、開業・法人登記時の注意点
バーチャルオフィスとは、住所を借りて郵便物の受け取りを代行してもらうような、会社運営に必要なオフィス機能を利用できるサービスをいいます。法人登記や法人口座開設の際に住所を利用できる…
詳しくみる