- 更新日 : 2025年11月4日
基本給と職務手当を分ける理由は?含めた場合の年収の違いや違法性を解説
基本給と職務手当を分けるのは、能力・貢献を正しく反映し、制度を柔軟に運用するためです。賞与・退職金の基礎は会社の規程、残業代の基礎は法令(職務手当は原則算入/固定残業代は除外)で決まります。
人事や会計の担当者としては、日々の給与計算において「基本給が低く手当が多いこの給与体系は問題ないのか?」といった疑問や、従業員への説明責任に悩む場面も少なくないでしょう。
本記事では、基本給と職務手当を分ける理由から、法的な注意点、双方のメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
目次
基本給と職務手当とは何が違うのか?
基本給と職務手当は、どちらも給与の一部ですが、その性質と決定基準が根本的に異なります。給与明細を見る際は、これらの違いを理解しておくことが不可欠です。
基本給は給与の土台
基本給は、年齢、学歴、勤続年数といった属人的な要素に基づいて決定される、給与のベースとなる部分です。各種手当や賞与(ボーナス)などを除いた、毎月固定で支払われる賃金を指します。
景気の変動や個人の業績によって大きく変動することが少なく、従業員の生活を支える安定した基盤としての役割を担います。
職務手当は職務に応じて変動
職務手当は、従業員が担当する職務の内容、責任の度合い、求められるスキルや難易度など、「仕事」そのものに対して支払われる手当です。例えば、特別なスキルを要する専門職や、管理責任が重い役職者に対して支給されます。成果や職務内容に応じて変動する可能性があるため、貢献度を給与に反映させやすい特徴があります。
基本給と職務手当の比較表
基本給と職務手当の違いを明確にするために、以下の表にまとめました。
| 項目 | 基本給 | 職務手当 |
|---|---|---|
| 決定基準 | 年齢、勤続年数、学歴など(属人的要素) | 職務内容、責任、難易度など(仕事的要素) |
| 安定性 | 高い(変動しにくい) | 変動の可能性あり(職務変更や評価による) |
| 主な役割 | 生活の基盤となる安定した賃金 | 職務の価値や貢献度を反映させる報酬 |
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
従業員の賃上げに潜むリスクと、企業が打つべき対策
人手不足や物価上昇などを背景に、賃上げが企業経営の重要テーマとなっています。しかし、賃上げには様々なリスクを伴います。
本資料では、企業が賃上げを進める際に注意すべきリスクと対策について解説します。
住宅手当申請書(ワード)
住宅手当の申請にご利用いただけるテンプレートです。 Wordファイル形式のため、直接入力や編集が可能です。
ダウンロード後、必要事項をご記入の上、申請手続きにお役立てください。
休業手当の計算シート(エクセル)
休業手当の計算にご利用いただける、Excel形式の計算シートです。
Excelファイル形式のため、ダウンロード後自由にご使用いただけます。 業務での休業手当の計算を行う際にお役立てください。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
なぜ基本給と職務手当を分けるのか?
企業が給与体系において基本給と職務手当を区別するのは、主に従業員を公正に評価し、柔軟な経営をすることが理由として挙げられます。
貢献度や職務内容を給与に正しく反映させるため
従業員の貢献度を評価し、給与に反映させることが、分ける最大の理由の一つです。基本給だけでは、勤続年数が長いという理由だけで、職務の責任が軽い従業員の給与が高くなる逆転現象も起こりかねません。
職務手当を導入することで、担当する仕事の難易度や責任の重さ、必要な専門性といった「職務の価値」を評価し、それに見合った報酬を支払うことが可能になります。これは、従業員の不公平感を解消し、公正な賃金設計を実現することにつながります。
柔軟な賃金制度を運用するため
企業の業績や事業戦略の変化に合わせ、柔軟に人件費を調整できる点も大きな理由です。一度定めた基本給を引き下げることは、労働条件の不利益変更にあたり、従業員の同意なく行うことは原則としてできません。
しかし、職務手当であれば、職務内容の変更や役職の変更に伴い、合理的な範囲で見直し(増額・減額)が可能です。これにより、企業は経営状況に応じた柔軟な賃金体系を構築できます。
残業代や賞与の算出基礎額を調整するため
賞与や退職金は、基本給を算定基礎とする企業が多い一方、残業代(割増賃金)は法令のルールに基づき、職務手当など“労働の対価”の手当を基礎として算定されます。(固定残業代は要件を満たす場合に限り例外)。
そのため、基本給を低めに設定しその分を手当で補っても、名称の付け替えで残業単価を下げることはできません。一方で賞与や退職金については、自社の規程により基本給ベース等で金額が変動し得ます。
例のように、同じ月給30万円であっても
- A社:基本給30万円、手当なし
- B社:基本給22万円、職務手当8万円
賞与や退職金の計算基礎となる1時間あたりの賃金はA社の方が高くなりますが、残業単価はA社、B社とも「30万円」をベースで算定するため、同じ単価となります。企業側から見れば人件費管理の一環ですが、従業員側にとっては重要なポイントとなるでしょう。
基本給に職務手当を含める、分ける場合の年収の違い
給与の総支給額が同じでも、基本給と職務手当の内訳によって、残業代や賞与、そして最終的な手取り年収がどのように変化するか見てみましょう。
ここでは、月給30万円の独身・扶養家族なしの社員(東京都在住・40歳未満)を例に、「職務手当を基本給に含めるケース」と「分けるケース」を比較してみましょう。
- 月給(基本給+手当): 300,000円
- 労働時間: 1日8時間・月160時間
- 残業時間: 月20時間
- 賞与(ボーナス): 年2回(合計で基本給の4ヶ月分)
- その他: 社会保険料・税金は2025年9月時点の東京都の料率で計算
ケース1:基本給に職務手当を含む場合(基本給30万円)
このケースは、給与の全額が各種計算の基礎となるため、手当で分ける場合よりも年収が高くなるのが特徴です。
- 残業代の計算
- 時間単価:300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
- 残業代(20時間分):1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円
- 月収(総支給): 300,000円 + 46,875円 = 346,875円
- 賞与(年間): 300,000円 × 4ヶ月分 = 1,200,000円
- 想定年収(総支給): (346,875円 × 12ヶ月) + 1,200,000円 = 5,362,500円
ケース2:基本給と職務手当を分ける場合(基本給22万円+手当8万円)
同じ月給30万円でも、基本給が低いと、それを基に計算される賞与が少なくなる分、結果として年収に差が生まれます。
- 残業代の計算
- 時間単価:300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
- 残業代(20時間分):1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円
- 月収(総支給): 300,000円 + 34,375円 = 334,375円
- 賞与(年間): 220,000円 × 4ヶ月分 = 880,000円
- 想定年収(総支給): (346,875円 × 12ヶ月) + 880,000円 = 5,042,500円
同じ月給でも年収に約32万円の差が生まれる
| 項目 | ケース1(基本給に含む) | ケース2(基本給と分ける) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 月間の残業代 | 46,875円 | 46,875円 | 0円 |
| 年間の賞与額 | 1,200,000円 | 880,000円 | -320,000円 |
| 想定年収 | 5,362,500円 | 5,042,500円 | -320,000円 |
このシミュレーションからわかるように、毎月の給与総額が同じ30万円でも、基本給と手当の内訳によって最終的な年収に約32万円の違いが生じました。
給与から天引きされる社会保険料や税金も年収に応じて変動しますが、それを考慮しても大きな差です。求人票を見たり雇用契約を結んだりする際には、月給の総額だけでなく、賞与や残業代の計算基礎となる「基本給」がいくらなのかを確認することが、ご自身の収入を正確に把握する上で重要になります。
職務手当の種類や、相場はいくらか?
職務手当は、その目的や性質に応じて様々な名称で設定されます。ここでは代表的な例と、その相場観について解説します。
職務手当の具体例
職務手当は、広義には以下のような手当が含まれることがあります。これらは、特定の職務遂行に伴う付加的な価値や負担に対して支払われるものです。
- 役職手当:部長、課長、リーダーといった役職の責任の重さに応じて支給される手当。
- 資格手当:業務に直接関連する特定の資格(例:弁護士、公認会計士、一級建築士など)の保有者に対して支給される手当。
- 特殊勤務手当:危険な作業や不規則なシフト勤務など、心身に通常以上の負担がかかる業務に対して支給される手当。
- 専門職手当・技能手当:高度な専門知識や特殊な技能が求められる職務に対して支給される手当。
職務手当の相場
職務手当の金額に法的な決まりはなく、企業の規模や業種、地域によって大きく異なります。一般的な相場としては、役職手当を例に挙げると以下のようになります。
| 役職 | 支給額の目安(月額) |
|---|---|
| 係長・主任クラス | 1万円~3万円 |
| 課長クラス | 5万円~8万円 |
| 部長クラス | 8万円~15万円 |
これはあくまでも目安であり、企業の給与水準や評価制度によって金額は変動します。自社の賃金水準や同業他社の動向をふまえ、適切な金額を設定することが求められます。
「基本給が低く手当が多い」給与体系は違法になるのか?
「基本給が低く、手当の割合が高い」という給与体系が、直ちに違法となるわけではありません。しかし、特定の法律に抵触するケースがあり、注意が必要です。
最低賃金法との関連
まず確認すべきは、最低賃金法です。最低賃金は、時給換算した賃金額が、都道府県ごとに定められた最低賃金額を上回っているかで判断されます。この計算には、基本給と一部の手当(職務手当など)が含まれます。
- 最低賃金の計算に含める賃金: 基本給、職務手当、役職手当など
- 最低賃金の計算から除外する賃金: 通勤手当、家族手当、時間外労働手当、賞与など
したがって、基本給が低くても、「基本給+職務手当など」の合計額を時給換算した際に最低賃金を下回っていなければ、最低賃金法違反にはなりません。
割増賃金(残業代)計算への影響
問題になりやすいのが、割増賃金(残業代)の支払いです。職務手当を「固定残業代(みなし残業代)」として運用している企業は少なくありません。この制度自体は合法ですが、適切に運用するには以下の要件を満たす必要があります。
- 明確な区分:
通常の労働時間に対する対価(基本給など)と、固定残業代部分(職務手当など)が明確に区別されていること。 - 対価性:
固定残業代が何時間分の時間外労働に対する対価であるかが、雇用契約書や就業規則で明記されていること。 - 差額の支払い:
実際の残業時間が、固定残業代に含まれる時間を超えた場合、その超過分の割増賃金を追加で支払うこと。
これらの要件が満たされていない場合や、実質的に残業代の支払いを免れる目的で職務手当の名称を使っていると判断された場合は、違法とされ、未払い残業代の請求を受けるリスクがあります。
従業員から見て基本給と職務手当はどちらが高い方が得か?
従業員の視点では、基本給と手当のどちらを重視すべきか、一概に「こちらが得」とは言えません。自身のキャリアプランや働き方の価値観によって、メリット・デメリットの捉え方が変わるからです。
基本給が高い場合のメリット・デメリット
- 賞与・退職金の額が多くなる傾向: 多くの企業では賞与や退職金を「基本給の〇か月分」という形で算定するため、基本給が高い方が有利になります。
- 給与の安定性が高い: 会社の業績や個人の評価に左右されにくく、毎月の収入が安定します。
- 社会的な信用度: 住宅ローンなどの審査において、変動の少ない基本給が高い方が有利に見られることがあります。
- 成果が給与に反映されにくい: 年功序列的な要素が強くなり、個人の成果や貢献が給与にすぐに結びつきにくい場合があります。
手当が多い場合のメリット・デメリット
- 成果が給与に反映されやすい: 担当する職務や出した成果が手当として直接評価されるため、モチベーションの向上につながりやすいでしょう。
- 専門性を高める意欲につながる: 資格手当や専門職手当があれば、スキルアップが収入増に直結します。
- 賞与・退職金が少なくなる可能性: 基本給が低いと、賞与などの算定基礎額も低くなる可能性があります。
- 収入が不安定になるリスク: 会社の業績悪化や組織変更に伴う職務内容の変更で、手当が減額・廃止されるリスクがあります。
求人票を確認する際は、月給の総額だけでなく、その内訳、特に基本給と各種手当の金額をしっかりと確認することが重要です。
職務手当の導入と管理における実務上の注意点
職務手当は有効な人事施策ですが、その導入と運用には細心の注意が求められます。トラブルを未然に防ぎ、制度を円滑に機能させるための実務ポイントを解説します。
STEP1:支給基準と金額の客観的な策定
職務手当を導入するには、全社的に公平で透明性のある基準を設けることです。「なぜこの職務に、この金額の手当がつくのか」を誰にでも説明できるようにしなければなりません。
- 職務分析・職務評価の実施: 各職務の責任の重さ、難易度、必要なスキルなどを客観的に分析・評価し、等級付けを行います。
- 基準の明確化: 等級ごとに、どのような基準で手当額を決定するのかを明確に定義します。あいまいな基準は、従業員の不満やトラブルの原因となります。
STEP2:就業規則・給与規程への明記
策定した基準は、必ず就業規則や給与規程に明記し、全従業員に周知する必要があります。記載すべき項目は以下のとおりです。
- 支給対象者: どのような職務、役職、資格を持つ従業員が対象か。
- 支給条件: 手当が支給されるための具体的な条件。
- 手当の金額と計算方法: 金額そのもの、または等級に応じた金額テーブル。
- 改定・廃止に関するルール: どのような場合に手当額が変更、または廃止されるのか。
STEP3:従業員への丁寧な説明と同意
特に、既存の給与体系を変更して新たに職務手当を導入する場合や、手当額を見直す場合は、従業員への丁寧な説明が不可欠です。
- 不利益変更への配慮: 変更によって一部の従業員の給与が実質的に下がる場合、それは労働条件の不利益変更にあたります。原則として、対象となる従業員から個別の同意を得る必要があります。
- 説明会の実施: 制度変更の背景、目的、新しい基準の内容、給与シミュレーションなどを提示し、従業員の理解を求める場を設けましょう。
STEP4:会計処理と給与計算のポイント
会計上、職務手当は給与手当として費用計上されます。給与計算においては、社会保険料と所得税の計算に正しく反映させる必要があります。
基本給と職務手当を分けるのは、公正な評価と柔軟な経営のため
基本給と職務手当を分けることは、従業員の職務価値を公正に評価し、貢献意欲を高めると同時に、企業にとっては経営環境の変化に対応しやすい柔軟な賃金体系を構築するという重要な意味を持ちます。この仕組みは、残業代や賞与の額にも影響を与えるため、企業は最低賃金法や割増賃金のルールを遵守し、透明性の高い制度を設計・運用することが不可欠です。
従業員側も、給与の総額だけでなく、その内訳である基本給と各種手当のバランスを理解し、自身のキャリアプランと照らし合わせることが求められるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
定額減税において従業員への案内は必要?テンプレートも紹介
定額減税は、従業員の税負担を軽減するための重要な制度です。しかし、従業員がこの制度を正しく理解し、適切に利用するためには、企業の人事担当者による案内・周知が不可欠です。 本記事では…
詳しくみる伊丹市の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
伊丹市は、大阪府の北部に位置し、交通の便が非常に良い都市として知られています。商業施設や工業団地が充実しており、多くの企業が拠点を構えています。 こうした多様なビジネス環境では、給…
詳しくみる有給休暇の買取は原則違法!認められる3つのパターンやデメリットを解説
有給休暇の買取は、労働基準法39条に反するものであり原則としては違法です。 しかし、退職時など特定の3つの条件下では買取が認められる場合もあります。 この記事では買取が可能なケース…
詳しくみる福利厚生費として社宅の費用を計上する条件とは
社宅制度に興味がある方のなかには、社宅費用を福利厚生費として計上するための条件が気になっている人も多いでしょう。 本記事では、福利厚生費の基礎知識のほか、法定外福利費の実態調査、社…
詳しくみる給与計算システムのメリット・デメリットとは?導入で注意すべき点も解説
本記事では、給与計算システムについて、メリットとデメリット、導入で失敗しないための注意点などを解説します。 給与計算は、従業員の生活を支える非常に重要かつ複雑な業務です。給与計算シ…
詳しくみる定額減税について子供がいる場合どうする?具体例をもとに対象者を解説
定額減税は、令和6年度の税制改正により、所得税と住民税から一定の額を控除する制度です。今回の定額減税では、1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円が控除されますが、子供がいる場…
詳しくみる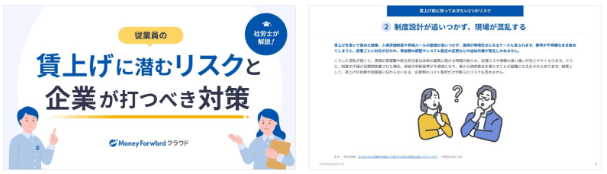
-e1763436002347.jpg)
-e1763436316712.jpg)
.png)