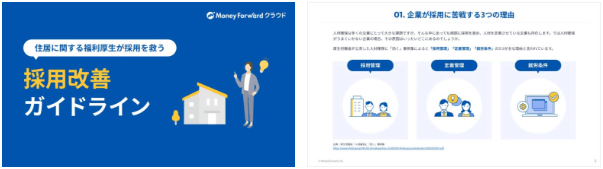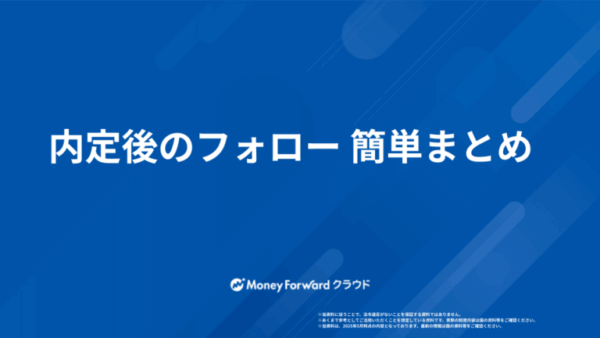- 更新日 : 2025年11月5日
試用期間中の社員が能力不足の場合、延長は可能?手続きや注意点を徹底解説
試用期間中の社員のパフォーマンスが期待に満たない場合「能力不足」を理由に期間の延長を検討する人事担当者も多いでしょう。この延長は法的に可能ですが、企業が自由に行えるものではなく、適切な手続きと客観的な理由が不可欠です。
本記事では、能力不足の社員に対して、試用期間の延長を適法に行うための具体的な条件や手続き、注意すべきポイントを網羅的に解説します。安易な判断が労務トラブルに発展しないよう、正しい知識を身につけましょう。
目次
そもそも試用期間の延長は法的に認められる?
試用期間の延長は可能です。ただし、延長が有効と判断されるためには、原則として「就業規則などに延長の根拠がある、または本人の個別合意がある」ことに加え「延長する客観的・合理的な理由があり、その期間が必要最小限である」ことが求められます。
試用期間の法的な性質
試用期間は、過去の判例などにより法的には「解約権留保付労働契約」と解釈されています。これは、企業側が本採用に適さないと判断した場合に、通常の解雇よりも広い範囲で契約を解約する権利(解約権)を留保している状態を指します。
試用期間は、過去の判例などにより法的には「解約権留保付労働契約」と解釈されています。これは、企業側が本採用に適さないと判断した場合に、通常の解雇よりも広い範囲で契約を解約する権利(解約権)を留保している状態を指します。
延長の有効性を判断する際の考慮点
企業が一方的に、いつでも自由に試用期間を延長できるわけではありません。延長の有効性は、法令に定型の「三要件」があるわけではなく、主に以下の点を個別の事情に応じて総合的に考慮して判断されます。
- 就業規則や雇用契約書への明記:延長の可能性があること、その場合の事由、期間などについて、あらかじめ就業規則や個別の雇用契約書に記載しておく必要があります。
- 客観的・合理的な理由の存在:なぜ延長が必要なのか、具体的な事実に基づいた客観的かつ合理的な理由が求められます。「なんとなく不安だから」といった主観的な理由では認められません。
- 社会通念上の相当性:延長する期間が不当に長くないか、延長の理由が社会の常識に照らして妥当か、といった点も考慮されます。
無効となるリスクが高いケース
これらの要件を満たさずに期間を延長した場合、その延長は無効と判断され、後のトラブルに発展するリスクがあります。特に、以下のようなケースは違法性が高いと判断されるため注意が必要です。
- 雇用契約書や就業規則に延長に関する記載が一切ない
- 延長理由が主観的で、客観的・合理的な事実が存在しない
- 延長期間が不当に長い(期間の上限を定めた法律はありませんが、適性判断に必要最小限の範囲を著しく超える長期の試用期間は、公序良俗に反し無効と判断される可能性があります)
- 明確な改善計画がないまま、試用期間が何度も繰り返されている
延長の合理性の判断に迷う場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間が延長されるのはどのようなケース?主な3つの理由
試用期間の延長には「客観的で合理的な理由」が必要ですが、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。主に以下の3つのパターンが挙げられます。
ケース1. 能力・適性の見極めにもう少し時間が必要な場合
採用時に期待された能力の発揮に時間がかかっているなど、本人の適性を判断するには当初の期間では短かった、というケースです。新しい環境に慣れるのに時間がかかっていたり、業務の習熟に一定期間を要したりする場合、もう少し時間をかけて本来の能力を見極めるために延長が認められることがあります。
ケース2. 病気や怪我による欠勤で、判断材料が不足している場合
試用期間中に、本人の病気や怪我による欠勤が多かったケースです。これは本人の能力や勤務態度に問題があるわけではなく、会社として「適性を判断するために必要な勤務日数」が確保できなかったという理由です。この場合、不足した日数分などを考慮して延長し、改めて適性を見極めることは合理的と判断されます。
ケース3. 別部署での適性など、配置転換の可能性を探る場合
現在の配属部署では期待されたパフォーマンスに至らないものの、本人の性格やスキルから、別の部署であれば活躍できる可能性があると考えられるケースです。本採用拒否(解雇)を猶予し、他部署での適性を試すために期間を延長することは、従業員の雇用機会を守る観点からも合理的な理由と判断され得ます。
ただし、その配置転換自体にも業務上の必要性があり、本人の不利益が大きすぎないかといった合理性が別途求められるため、常に延長が認められるわけではありません。
能力不足を理由に試用期間を延長する場合の注意点とは?
延長理由の客観性、本人への具体的なフィードバック、そして延長期間中の改善計画が不可欠です。主観的な判断や不十分な説明による延長は、社員の不信感を招き、不当解雇などの労務トラブルに発展するリスクを高めます。
また、もし本人が延長に納得できない場合、自身の評価に不満を感じて会社に反感を抱いたり、継続雇用への不安から仕事へのモチベーションが低下したりする原因となり、結果的に早期離職につながる可能性もあります。そのため、丁寧な説明を通じて本人の納得感を得ることが極めて重要です。
客観的で合理的な理由を明確にする
「能力不足」という理由は、非常に主観的になりがちです。そのため、誰が見ても納得できるような客観的な事実に基づいて説明できなければなりません。
- 業務マニュアルで定められた手順を、3回指導しても習得できていない。
- 作成を指示した報告書において、誤字脱字や数値の間違いが指摘事項の8割を超えており、修正指示後も改善が見られない。
- 営業目標に対し、達成率が著しく低い状態が続いている(あくまで目安であり、指導内容や改善の機会があったかなども含めて総合的に判断される)。
- やる気が感じられない。
- 期待していたほどの活躍ではない。
- 他の社員と比べて成長が遅い。
具体的なエピソードや数値を記録として残しておくことが、客観性を担保する上で極めて重要です。
就業規則や雇用契約書に根拠規定を設ける
前述の通り、試用期間を延長する可能性があるのであれば、その旨を事前に就業規則や雇用契約書に明記しておく必要があります。これは、労働者に対して「こういう状況になった場合は、期間が延長されることがある」という予測可能性を与えるためです。
- 新たに採用した者については、採用の日から〇か月間を試用期間とする。
- 前項の試用期間中または期間満了時において、勤務状況、能力、適性などが本採用に適さないと会社が判断した場合、会社は、合理的理由がある場合に、必要最小限の範囲で試用期間を延長することがある。その際は本人に理由を十分に説明し、書面で通知するものとする。
試用期間の延長が認められるには、原則として就業規則などに延長の根拠規定があるか、従業員の個別の同意が必要です。規定がないからといって、一律に延長が認められないわけではありませんが、トラブルを避けるためにも規定を設けておくことが極めて重要です。
社員本人から個別の同意を得る
就業規則に規定があったとしても、実際に延長する際には、対象となる社員本人から個別の同意を得ることが強く推奨されます。同意なく一方的に延長を通知した場合、社員がそれに納得せず、後の紛争の原因となる可能性があります。
後述する「試用期間延長通知書兼同意書」などの書面を取り交わし、本人が延長の理由と条件を理解し、納得した上で合意したという証拠を残しておくことが、トラブル防止の観点から非常に重要です。
延長期間と目的を具体的に設定する
延長する期間は、いたずらに長く設定すべきではありません。どのスキルや業務遂行能力が不足しているのかを具体的に特定し、その改善や見極めに合理的に必要な期間」を設定します。
延長期間に法的な定めはありませんが、実務上は1か月から3か月程度とされるのが一般的です。あくまで現在の課題や適性を評価するために、客観的に見て必要最小限の期間を設定することが求められます。
また、延長期間中に「何を」「どのレベルまで」達成すれば本採用に至るのか、具体的な目標(ゴール)を本人と共有することが不可欠です。これにより、社員は目標達成に向けて努力しやすくなり、会社側も期間満了時の判断がしやすくなります。
指導や教育の記録を残す
試用期間およびその延長期間は、単に社員の能力を見極めるだけでなく、会社が指導・教育を尽くす期間でもあります。万が一、最終的に本採用拒否(解雇)という判断に至った場合、「会社として必要な指導・教育を十分に行ったか」が争点となることがあります。
- いつ、誰が、誰に、どのような指導を行ったか
- 指導に対して、本人はどのように反応し、改善が見られたか(または見られなかったか)
- 定期的な面談の内容(フィードバック、本人の課題認識など)
これらの記録を日報や面談記録シートなどに具体的に残しておくことで、会社が責務を果たしたことの証明となります。
試用期間の延長を決定した場合、手続きはどのように進める?
事実の記録、面談の実施、通知書の交付、そして合意の取り付けという手順で進めるのが一般的です。適正な手続きを踏むことで、労務トラブルを未然に防ぎ、社員の納得感を得た上で延長期間へと移行することができます。
ステップ1. 能力不足の具体的な事実を記録する
まず、延長の根拠となる「能力不足」を裏付ける客観的な事実を収集・整理します。
- 業務上のミスやトラブルの具体的な内容、日時
- 指導記録、面談記録
- 業務の成果物(例:作成した資料、営業成績データ)
- 周囲の同僚や上司からのヒアリング内容(客観的な事実に限る)
これらの情報は、次のステップである本人との面談において、具体的な説明を行うための重要な材料となります。
ステップ2. 本人と面談を実施し、現状と課題を伝える
収集した事実に基づき、対象社員と面談を行います。この面談は、一方的な通告の場ではなく、対話を通じて相互理解を図る場とすることが重要です。
- 肯定的な側面から入る:まずは、できていることや評価している点を伝え、相手が心を開きやすい雰囲気を作ります。
- 客観的な事実を伝える:感情的な表現は避け、「〇月〇日の報告書で、こういうミスがあった」というように、ステップ1で整理した事実を具体的に伝えます。
- 期待する水準とのギャップを説明する:会社として期待している役割やパフォーマンスレベルを明確にし、現状との間にどのようなギャップがあるのかを丁寧に説明します。
- 本人の意見を傾聴する:なぜそうなってしまうのか、本人なりの理由や考え、課題認識を聞きます。
- 試用期間の延長を提案する:上記を踏まえ、「この課題を克服し、本採用の基準に達するかをもう一度見極めるため」として、試用期間の延長を提案します。
ステップ3. 「試用期間延長通知書兼同意書」を作成・交付する
面談で延長の方向性について大筋の理解が得られたら、正式な書面を作成し、本人に交付します。この書面は、後の「言った・言わない」のトラブルを防ぐための重要な証拠となります。
- 宛名(社員氏名)
- 通知日、会社名、代表者名
- 当初の試用期間満了日
- 延長後の試用期間満了日
- 延長の理由(能力不足の具体的な内容)
- 延長期間中の課題・目標(例:〇〇業務をミスなく一人で完遂できるレベルになること)
- 会社のサポート体制(OJT担当者、面談の頻度など)
- 延長に同意する旨の署名・捺印欄
ステップ4. 本人から署名・捺印済みの同意書を回収する
本人に書面の内容を十分に確認・理解する時間を与え、質問があれば誠実に対応します。内容に納得してもらえたら、署名・捺印の上で提出してもらいます。会社と本人の双方が1部ずつ保管するようにしましょう。
万が一、本人が同意を拒否した場合でも、就業規則に延長の根拠が明確にあり、かつ延長理由も客観的・合理的である場合は、延長が有効と判断される可能性があります。ただし、一方的な延長は後の紛争リスクを高めるため、あくまで丁寧な説明と合意形成に努めるべきです。
ステップ5. 延長期間中の具体的な指導・教育計画を立て、実行する
同意が得られたら、通知書に記載した課題・目標を達成するための具体的な指導・教育計画(アクションプラン)を策定し、実行に移します。
- OJT担当者を明確にする
- 週次での進捗確認面談(1on1ミーティング)を設定する
- 必要な研修や学習機会を提供する
- フィードバックは具体的かつタイムリーに行う
延長期間中は、これまで以上に密なコミュニケーションと手厚いサポートを行い、本人の成長を支援する姿勢を示すことが重要です。もちろん、その過程もしっかりと記録に残します。
試用期間を延長しても改善が見られない場合の対処法は?
最終的な手段として、本採用の拒否(解雇)を検討することになります。試用期間の目的は、あくまで本採用の可否を判断することにあり、指導や教育を尽くしてもなお改善が見込めず、社員としての適格性が欠けていると判断される場合には、契約を終了させるという選択肢も含まれます。
本採用拒否(解雇)が認められるための要件
試用期間中の解雇(本採用拒否)は、三菱樹脂事件などの最高裁判所の判例により、通常の解雇よりは広い範囲での解約が認められていますが、それでも無制限に許されるわけではありません。客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があります。
具体的には、以下のような点が総合的に判断されます。
- 採用時に期待された能力・適性と、実際のパフォーマンスとの間に著しい乖離があること
- 会社が具体的な指導や教育、改善の機会を十分に与えたこと
- 本人に改善の意欲や見込みが全く見られないこと
- これらの事実を客観的な証拠(指導記録、面談記録など)で証明できること
「試用期間の延長」というプロセスを経ていることは、「会社が改善の機会を十分に与えた」という事実を補強する有力な材料となります。
解雇予告または解雇予告手当の必要性
試用期間中であっても、採用から14日を超えて雇用している労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。なお、採用から14日以内であれば、この解雇予告制度は適用されません。
試用期間を延長した後に本採用を拒否する場合、原則として勤務期間は14日を超えているため、この解雇予告制度の対象となります。ただし、天災事変などやむを得ない事由や、従業員本人に解雇の原因がある場合で、労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けた場合は例外です。
トラブルを避けるための最終面談のポイント
本採用拒否を伝える最終面談では、これまでの経緯を客観的な事実に基づいて丁寧に説明し、会社として最大限の努力をしたが、残念ながら本採用の基準には至らなかったという結論を冷静に伝えます。相手を非難したり、感情的になったりすることは避け、あくまで契約上の手続きとして粛々と進めることが、無用なトラブルを回避する上で重要です。
試用期間に関するよくある質問
ここでは、試用期間の延長や期間設定に関して、人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめます。
Q1. 採用しても早期退職が多いため、試用期間を最初から長めに設定したいのですが、デメリットはありますか?
A. はい、従業員側・企業側双方にデメリットが生じる可能性があります。
従業員にとって、試用期間は雇用が不安定な状況に置かれることを意味します。この期間が不当に長いと、従業員は「いつ解雇されるかわからない」という不安を抱えながら働くことになり、エンゲージメントの低下につながります。結果として、より安定した雇用を求めて他社へ転職してしまったり、業務に集中できず本来のパフォーマンスを発揮できなかったりする可能性があり、これは企業にとっても大きな損失です。
労働基準法で期間の上限は定められていませんが、過去の調査では3か月前後とする企業が多い傾向にあります。ただし、これもあくまで実態であり、自社の業務内容や教育計画に照らして、適性判断に必要最小限の期間を超えて設定することは、公序良俗に反し無効と判断されるリスクがあります。
Q2. 試用期間が延長されると、勤続年数や社会保険の扱いで従業員が不利になることはありますか?
A.いいえ、原則として不利になることはありません。
能力不足による試用期間の延長を円滑に進めるために
本記事では、試用期間中の社員に能力不足が見られた場合の期間延長について解説しました。試用期間の延長は、就業規則などの根拠規定と客観的で合理的な理由があれば可能ですが、その運用は慎重に行わなければなりません。
重要なのは、客観的な事実に基づき、本人と真摯に向き合い、適切な手続きを踏むことです。面談を通じて課題を共有し、書面で合意を取り付け、延長期間中は具体的な指導計画に沿って改善をサポートする姿勢が求められます。こうした丁寧な対応が、社員の成長を促すとともに、万が一の労務トラブルを防ぐための最良の策となるのです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
異動挨拶のメールやお礼のスピーチの内容は?社内外の例文をもとに解説
異動の挨拶は、社内の立ち位置を明確にし、スムーズな人間関係を築いていくために重要なステップです。この記事では、異動の挨拶の目的や基本的なマナー、メールやお礼のスピーチの例文などを解…
詳しくみる【日報テンプレ付】建設業で使う作業日報とは?エクセルで作成する方法を解説
建設業では、現場の管理者は日々の業務の進捗状況や課題を把握する必要があります。作業日報は、そのために不可欠な記録です。 かつて作業日報は、紙の用紙に手書きで作成するのが一般的でした…
詳しくみる就業管理とは?勤怠管理との違いやシステム導入時の注意点を解説
就業管理は、従業員を雇用する企業において欠かせない業務です。法律に則った管理を求められますが、目的や業務内容を詳しく把握できていないまま、業務に携わっているケースもあるようです。近…
詳しくみる外国人雇用における人事管理とは?労務管理との違いや必要な手続きを解説
日本における外国人労働者の数は年々増加しています。外国人労働者を受け入れる際は、日本人労働者とは異なる法的手続きや労務管理が必要です。 適切な人事管理を行わなければ、企業が法的リス…
詳しくみる再雇用がみじめすぎる…。理由や後悔しないための対策、転職・独立などの選択肢も解説
定年後の再雇用制度を利用して働き続ける方が増えていますが、再雇用後に予想外のみじめさを感じて後悔するケースも少なくありません。収入が激減し、後輩の下で働く立場になったり、職場での人…
詳しくみる育休は何ヶ月取れる?制度ごとに何日取得できるかを解説
育児休業は、子育てと仕事の両立を支援し、労働者が安心して育児に取り組めるようにするための重要な制度です。 この記事では、「育休は何ヶ月取れるのか」という基本的な疑問から、育児休業の…
詳しくみる