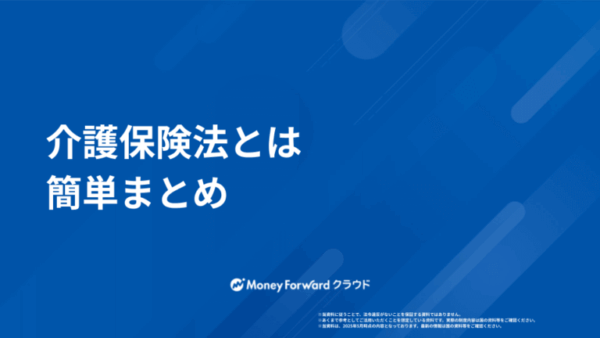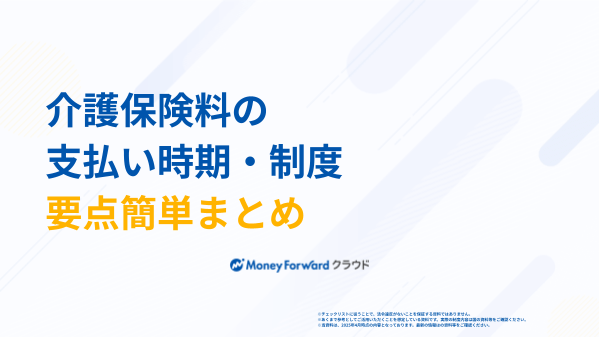- 更新日 : 2025年11月6日
介護休暇は年5日まで?給与は無給?条件や対象家族、介護休業との違いも解説
家族の介護が必要になったとき、仕事を休んで対応するための制度が「介護休暇」です。この制度では年に5日まで取得できますが、「給与は無給?」「対象家族に制限は?」「介護休業とは何が違うのか?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
この記事では、介護休暇の年5日制度の概要、取得条件、給与の扱い、手続きの進め方、実務での活用方法までをわかりやすく解説します。
目次
介護休暇は年5日まで?
介護休暇は、家族の介護や通院の付き添いなどに対応するために取得できる制度で、法律により年間最大5日まで取得できます。従業員から申し出があった場合、企業は原則として拒否できません。
介護休暇とは
介護休暇は、要介護状態にある家族の介護や世話をするために取得できる、年次有給休暇とは別の休暇制度です。通院の付き添いや介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの面談といった、短期的・一時的な介護を理由に取得できる休暇制度です。
法律上、休暇中の給与支払い義務はなく、多くの企業では無給として扱われますが、就業規則により有給としている場合もあります。
対象は厚生労働省の「育児・介護休業法」に基づいており、雇用形態に関係なく原則すべての労働者です。ただし、日々雇用以外の労働者や、会社が労使協定を締結している場合は、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者も対象外です。
年に何日まで取得できるのか
介護休暇を取得できる日数は、介護の対象となる家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで取得できます。年度は、事業主が就業規則などで特に定めをしない場合、毎年4月1日から翌年3月31日となります。
介護休暇の分割取得はできるのか
介護休暇は1日単位だけでなく半日単位でも取得可能です。また、2021年の法改正により、時間単位での柔軟な取得も認められています。
たとえば、午前中だけ介護対応が必要な日には、午後から出社するといった柔軟な働き方も認められています。
【調査データ】介護休暇と介護離職の実態
2025年4月の東京商工リサーチが実施した「介護離職に関するアンケート調査」(有効回答:5,570社)によると、介護休暇が発生した企業は全体の4.3%、介護離職が発生した企業は7.3%でした。
介護離職者のうち、介護休業や介護休暇などの制度を利用していなかった人は54.7%にのぼり、制度の活用が進んでいないことが確認されました。
「仕事と介護の両立支援が十分だと思う」と回答した企業は19.8%にとどまり、企業規模によって認識に差も見られました。
中小企業では特に整備状況が不十分とする回答が多く、制度の周知や社内フローの明確化などが課題となっています。介護休暇制度があっても、実際に活用されるには一定の仕組みと運用の工夫が必要です。
出典:介護離職者 休業や休暇制度の未利用54.7% 規模で格差、「改正育児・介護休業法」の周知と理解が重要|東京商工リサーチ
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
介護保険法とは かんたん解説ガイド
介護保険法の概要や仕組みについて、わかりやすく解説したガイド資料です。
制度への理解を深めるための学習用資料や、社内研修の参考情報としてご活用ください。
介護保険料の支払い時期・制度 要点簡単まとめ
介護保険料の支払い時期や制度の仕組みについて、要点を簡潔にまとめた資料です。
実務における確認用や、制度理解を深めるための参考資料としてご活用ください。
介護休暇と介護休業との違い
介護休暇と介護休業は、いずれも家族の介護を支援する制度ですが、その性質や目的が大きく異なります。
介護休暇は「通院の付き添い」や「一時的な介護対応」に使われ、短期的・断続的な支援を前提としています。
一方で、介護休業は「長期にわたり日常的な介護が必要」な場合に取得できる制度です。また、介護休業には雇用保険による給付金制度があり、生活への経済的負担を軽減することができます。
どちらを使うべきかは、家族の介護状態や支援の頻度・内容に応じて使い分けることが重要です。
介護休暇と介護休業の違い一覧
| 比較項目 | 介護休暇 | 介護休業 |
|---|---|---|
| 目的 | 通院の付き添い、役所の手続きなど短期・単発の世話 | 家族の集中的な介護、介護体制の構築など長期的な対応 |
| 取得可能日数 | 介護が必要な対象家族1人につき年5日 (2人以上で年10日) | 対象家族1人につき通算93日まで |
| 取得単位 | 1日または時間単位 | 原則として1日単位 |
| 分割取得 | 可能(回数制限なし) | 3回まで分割可 |
| 申請期限 | 期限は会社の規定による。口頭申請も可能 | 休業開始の2週間前までに書面で申請 |
| 給与の扱い | 法的な支払義務はなし | 法的な支払義務はなし |
| 公的な給付金 | なし | 介護休業給付金 |
| 対象となる労働者 | 原則すべての労働者(正社員・パート等含む) | 雇用保険の被保険者であること |
介護休暇を年5日取得できる条件とは?
介護休暇を取得するには、従業員本人の雇用条件や、介護対象となる家族の状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。以下に主な判断ポイントを示します。
要介護認定がなくても取得できる
法律上の「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。
介護休暇の取得には、公的な「要介護認定」や「要支援認定」がなくても問題ありません。法律上は「2週間以上にわたり常時介護が必要な状態」であることが判断基準です。
この状態にあることを労働者が申し出れば、原則として企業は休暇を認めなければならず、医師の診断書等も必須ではありません。
同居していなくても家族も対象になる
介護休暇は、同居していない家族の介護でも取得可能です。
対象家族は義父母も含まれる
介護休暇の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫です。これに加えて、配偶者の父母(義父母)も対象に含まれます。
パートや契約社員でも取得できる
介護休暇は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など雇用形態に関係なく、すべての労働者が対象です。ただし、日々雇用される方は除きます。
また、労使協定を締結している場合に限り、以下の労働者を対象から除外することが認められています。
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象家族が2人以上なら10日まで取得できる
介護が必要となる対象の家族が2人以上いる場合は、年間最大10日まで取得することができます。
家族1人ごとに5日ずつではなく、「全体で10日まで」という扱いになる点には注意が必要です。
たとえば、両親それぞれの介護で5日ずつ取得することは可能ですが、それを超える取得には別の制度(介護休業など)との併用を検討する必要があります。
介護休暇の年5日は無給?給与の扱い
介護休暇は、法律で取得が認められている制度ですが、給与が支払われるかどうかは企業ごとに異なります。また、介護休業とは異なり、国からの給付金の支給はありません。
介護休暇は「無給」としても問題ない
育児・介護休業法では、介護休暇を取得した日の給与支払いについて、特に定めを置いていません。したがって、企業が介護休暇を無給としても、法的に問題はありません。
就業規則で「介護休暇中の賃金は支給しない」と定めている企業も多いです。あくまで「休暇を取得できる権利」がある制度です。
ただし、企業によっては福利厚生の一環として有給扱いにしているケースもあり、制度の運用は各社の就業規則や労使協定に委ねられます。
実際に給与が出るかどうかは、社内規定の確認が必要です。
介護休業給付金は介護休暇には適用されない
介護休業を取得した場合には、雇用保険から「介護休業給付金」が支給される制度があります(原則、休業前賃金の67%)。
しかし、介護休暇にはこの給付金は適用されません。あくまで長期の介護休業のみが給付金の対象です。短期的な対応であっても給与補償が必要であれば、有給休暇の利用などを検討することになります。
有給休暇との併用を検討する
たとえ介護休暇が無給であっても、有給休暇を活用することで給与の確保ができます。
介護休暇制度とは別に、年次有給休暇の取得理由に制限はないため、介護を理由とすることも当然認められます。
介護休暇の年5日は出勤日数に含まれる?
介護休暇を取得した日が「出勤日」として扱われるかどうかは、年次有給休暇の付与、賞与や人事評価、給与計算により異なります。
年次有給休暇の付与計算
年次有給休暇(有給)の付与日数を決めるための出勤率の計算において、介護休暇を取得した日は「出勤した日」として扱います。
これは育児・介護休業法で定められており、労働者が法律に基づいた休暇を取得したことで、有給休暇をもらうという別の権利において不利益を受けないようにするためです。
したがって、介護休暇を年5日取得しても、それが原因で出勤率が下がり、翌年の有給休暇が減ったり付与されなくなったりすることはありません。
賞与(ボーナス)や人事評価の算定
賞与(ボーナス)や人事評価の算定においては、介護休暇を取得した日を「欠勤」として扱い、算定の基礎となる出勤日数から除くことが、必ずしも違法とはなりません。
賞与には「働いたことへの対価」という側面があり、実際に勤務しなかった日数分を支給額から控除する「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されるためです。
ただし、「不利益取扱いの禁止」には注意すべきです。介護休暇の取得を理由に査定を不当に下げたり、賞与を大幅にカットしたりすることは法律(育児・介護休業法第10条)で禁じられています。
給与計算
給与処理においては、介護休暇が有給か無給かによって対応が分かれます。介護休暇は、法律で有給とすることが義務付けられていませんが、企業独自の福利厚生として有給扱いとしている場合もあるため、就業規則を確認することが重要です。
- 無給の場合:欠勤控除の対象となり、日割りまたは時間割で減額処理
- 有給として認めている場合:通常通りの給与が支払われ、控除なし
給与計算時は介護休暇の種別(有給/無給)を明確にし、勤怠システムや給与ソフト上で正しく区分して処理する必要があります。
介護休暇の社内フローや手続き
介護休暇は、従業員が必要なときに安心して取得できるよう、社内の申請フローや書式、確認方法を整備しておくことが重要です。申請の拒否は原則できないため、スムーズに対応できるよう、具体的な流れを整備しておきましょう。
従業員からの申し出を受け付ける
介護休暇の申し出は、原則として拒否できません。まずは従業員の状況をヒアリングし、休暇の取得日時や理由を確認します。
口頭での申し出でも法律上は有効ですが、記録を残すためにも、簡易的な申請書を提出してもらうことが望ましいとされます。事後提出でも問題ありません。
申請書で必要な情報を取得する
トラブルを避けるためにも、社内で統一された申請書フォーマットを準備しておくと便利です。記載項目としては、以下のようなものが考えられます。
- 申請者の氏名・所属
- 休暇取得希望日時
- 対象家族の氏名と申請者との続柄
- 休暇取得の理由(例:通院の付き添いのため)
証明書類は柔軟に対応する
企業は、介護の事実確認のために証明書類の提出を求めることができますが、あまりに厳格な書類要求は従業員の負担となり、制度利用を妨げるおそれがあります。
たとえば、毎回医師の診断書を求めるのではなく、介護保険被保険者証の写しを初回に提出してもらう、または「通院予定日のメモ」など、現実的な範囲での確認方法を導入するとよいでしょう。
なお、厚生労働省の通達により、労働者が証明書類を提出しないことのみを理由に、企業は休暇の申し出を拒否できないとされています。
社内周知とフローの整備を進める
介護休暇は急な対応が多いため、申請方法・手順・担当窓口などをあらかじめ社内に周知しておくことが重要です。就業規則への記載、社内ポータルへの掲載、管理職向けのマニュアル化などを通じて、迷わずに申請できる仕組みを構築しておきましょう。
介護休暇は1人なら年5日まで、仕事との両立を支援する職場づくりを進めよう
介護休暇は、対象家族が1人の場合は年5日、2人以上であれば年10日まで取得できる制度です。法律上は給与の支払い義務がないため、多くの企業が無給としていますが、通院の付き添いや急な対応など、介護と仕事を両立させるために欠かせない制度のひとつです。
介護休暇制度の正しい理解と、取得しやすい社内フローの整備は、従業員の安心と介護離職の防止につながります。
介護は誰にとっても起こりうるライフイベントです。柔軟な働き方と制度活用の支援を通じて、企業と従業員がともに持続可能な働き方を築いていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
建設業における労災保険の特徴は?単独有期と一括有期の違いなど
事業主は、労働者を雇用すれば原則として労働保険(労災保険、雇用保険)の適用事業所として加入義務が生じ、所定の手続きを行う必要があります。 一般的な業種の手続きは共通していますが、建…
詳しくみる育休中は社会保険料が免除に?手続きの流れや計算方法を解説
社会保険は毎月の給与から保険料が控除されますが、育児休業期間中は免除されます。育児休業とは、育児・介護休業法に定められた1歳に満たない子を養育するための休業期間です。 育休中は事業…
詳しくみる厚生年金保険料の計算方法 – 標準報酬月額・標準賞与額など保険料額表をもとに解説!
厚生年金とは、会社員などが加入する公的年金制度のことです。厚生年金の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に決められた保険料率を掛けて計算します。保険料率は平成29年9月から18.30…
詳しくみる【2025年4月】育児時短就業給付金はいくらもらえる?計算方法や申請手続きも紹介
育児と仕事の両立を支援するため、2025年4月から育児時短就業給付金が新設されました。この制度は、時短勤務による給料の減少を補う仕組みで、安心して働き続けられるよう支援するものです…
詳しくみる雇用保険被保険者証とは?紛失したときの再発行なども解説!
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを示す証明書のことです。雇用保険に加入できる条件を満たしている従業員について会社からハローワークに加入の申請を行います。紛失した場…
詳しくみる介護保険被保険者証とはいつ使う?申請手続きや有効期限について解説
介護保険被保険者証とは、介護保険の被保険者資格を証明するものです。65歳以上の第1号被保険者には全員に送付されますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者には、一定の条件のもとで発…
詳しくみる