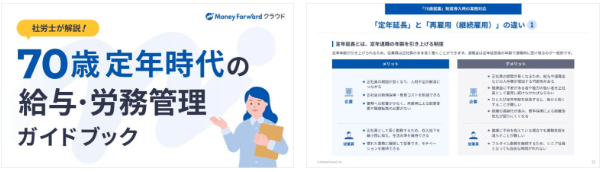- 更新日 : 2025年11月13日
高年齢雇用継続基本給付金は65歳以上になるとどうなる?代わりの給付金はある?
少子高齢化が進む中、企業にとって高齢者の活用は重要な課題となっています。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も引き続き働く意欲のある60歳から65歳未満の雇用保険被保険者を対象です。60歳以降に賃金が下がった場合に、一定の給付金を支給する制度となっています。それでは、65歳以上になるとどうなるのか、代わりの支援策はあるのかが気になるところです。この記事では、2025年の制度改正を踏まえつつ、65歳以上の高齢者が活用できる給付金や助成金、企業の支援策についてわかりやすく解説します。
目次
【2025年4月改正】高年齢雇用継続基本給付金の縮小
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も働く意欲のある60歳から65歳未満の方を対象に、再雇用などで賃金が下がった場合、その一部を補填する給付金制度です。雇用保険に加入していることが前提で、賃金の低下によって収入が減っても働き続けやすくすることで、高齢者の就労を支援することが目的です。
2025年4月1日から、高年齢雇用継続基本給付金には変更が加えられました。主なポイントは以下の通りです。
- 支給率の上限が引き下げ:従来の最大15%から、10%に変更されました。
- 改正の適用対象:2025年4月1日以降に60歳を迎える方が対象となり、それ以前に60歳になっていた方は従来の条件(最大15%)が引き続き適用されます。
- 最大支給率の条件変更:これまで最大の支給率(15%)は、賃金が60歳到達時の61%以下に下がった場合に適用されていましたが、改正後は、64%以下に下がった場合に最大支給率(10%)が適用されるようになりました。
新旧支給率の比較
| 賃金低下率(60歳時賃金比) | 支給率(2025年3月31日まで) | 支給率(2025年4月1日から) |
|---|---|---|
| 75%以上 | 支給対象外 | 支給対象外 |
| 61%超~75%未満 | 0%~15%未満 | 0%~10%未満 |
| 61%以下 | 15.00% | 10.00% |
| 64%以下 | – | 10.00% |
改正前後での支給額の違いと給付金の計算方法
高年齢雇用継続基本給付金の金額は、「60歳到達時の賃金」と「現在の賃金」の比率(賃金低下率)に応じて決まり、最大で賃金の10%(改正前は15%)が支給されます。
例えば、60歳到達時の賃金が月額30万円で、再雇用後の賃金が月額18万円(60%に低下)になった場合、給付金は賃金低下率に応じて、以下のように算出されます。
- 改正前の給付金額(2025年3月までに60歳になった方)
⇒ 30万円 × 15% = 月額4万5,000円 - 改正後の給付金額(2025年4月以降に60歳になった方)
⇒ 30万円 × 10% = 月額3万円
給付額は2か月ごとに申請し、過去2か月間に支払われた賃金の実績に基づいて算出されます。したがって、勤務状況や労働時間の変動によっても、給付額が変動することがあります。
高年齢雇用継続基本給付金と年金制度との関連性
高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、年金制度との関連で注意点があります。特に、65歳になるまでの間に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取っている方が、高年齢雇用継続基本給付金も受給すると、老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があります。
年金の支給停止額は、高年齢雇用継続基本給付金の額や、その方の標準報酬月額などによって異なります。したがって、特別支給の老齢厚生年金を受給している方が高年齢雇用継続基本給付金の受給を検討する際には、年金事務所などに問い合わせて、支給停止となる金額を確認することが重要です。
高年齢雇用継続基本給付金の仕組み
高年齢雇用継続基本給付金は、主に2つの種類に分けられます。
- 高年齢雇用継続基本給付金:60歳以降も同じ企業に継続して雇用されているか、または失業給付を受けずに再就職した方
- 高年齢再就職給付金:60歳以降に失業給付を受給した後、再就職した方
いずれの場合も、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あり、かつ60歳以降の賃金が、60歳到達時と比べて75%未満に減少していることが支給要件です。給付金の支給額は、賃金の低下率に応じて段階的に決まっており、下がった割合が大きいほど支給率も高くなります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
65歳以上の高年齢雇用継続基本給付金の取り扱い
受給者が65歳の誕生月に到達した時点で、高年齢雇用継続基本給付金の支給は自動的に終了します。たとえ65歳以降も雇用が継続されており、60歳時点と比べて賃金が75%未満の状態が続いていたとしても、それ以降はこの給付金を受け取ることはできません。
高年齢雇用継続基本給付金が、60歳から65歳までの、いわば現役世代から年金受給世代への移行期における雇用を支援するための制度として設計されているためと考えられます。65歳以降は、年金制度が主な所得保障の役割を担うことになります。
65歳到達時の給付終了の手続き方法
高年齢雇用継続基本給付金は、65歳に到達すると自動的に支給が終了するため、特別な終了手続きは不要です。しかし、65歳に達する月の給付申請を行う際には、事業主からハローワークへの提出書類に、受給者が65歳に到達したことが確認できる書類(例:生年月日が確認できる住民票の写しや身分証明書のコピーなど)を添付すると、手続きが円滑に進みます。
また、65歳を迎えた後に誤って支給申請を継続してしまうケースもあるため、企業側でも従業員の年齢管理や申請時期の確認をしっかり行うことが大切です。本人にとっても、「65歳以降はこの給付金が受け取れない」という点をあらかじめ理解しておくことで、誤解や手続きのトラブルを避けることができます。
65歳以上の雇用継続に関する給付金・助成金
65歳に到達すると高年齢雇用継続基本給付金は終了しますが、65歳以上の高齢者の雇用を促進し、就労を支援するための代替的な給付金や助成金制度を紹介します。
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上の高年齢者の雇用を促進するため、企業が定年の引き上げや66歳以上への継続雇用制度の導入などに取り組む事業主に対して支給されます 。この助成金には、さらに以下のコースがあります。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入などを行った事業主に対して、措置の内容や引き上げた年齢に応じて一定額が助成されます。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの評価制度、賃金・人事制度、労働時間制度等の導入・改善を実施した事業主に対して、雇用管理整備に要した費用の一部が助成されます。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主を対象に、転換した労働者一人につき一定額の助成金が支給されます。
申請方法
申請は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にて受け付けています。詳細な手続きや申請書類については、同機構の公式ウェブサイトをご確認ください 。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金は、60歳以上の高年齢者で、就職が特に困難な求職者をハローワークなどの紹介により雇用した場合に、事業主に対して支給されます。
支給額
中小企業:最大60万円(短時間労働者は最大40万円)
中小企業以外:最大50万円(短時間労働者は最大30万円)
対象者一人につき一定額の助成金が支給されます。支給額は、雇用形態や労働時間などにより異なります。
申請方法
申請は、雇用保険適用事業所の事業主が、所定の申請書類を提出することで行います。詳細は、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください 。
参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
高年齢再就職給付金(個人向け)
高年齢再就職給付金は主に60歳から65歳未満の方を対象とした制度ですが、失業保険を受給後に再就職した場合に支給されるもので、再就職支援という観点からは、65歳以上の方が再就職を目指す際の参考となる可能性があります。
年金生活者支援給付金(個人向け)
この給付金は、低所得の年金受給者を支援するための制度です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税の対象であること。
- 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金等の非課税収入は対象外せん)と、その他の所得の合計額が1956年4月2日以降に生まれの方は889,300円以下、1956年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下。
- 老齢基礎年金受給者の場合、2025年度の年金生活者支援給付金は月額5,450円×12か月=65,400円です。
申請方法
65歳の誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。必要事項を記入し、ポストへ投函することで申請が完了します 。
65歳以上の雇用継続を支援する企業の取り組み
高齢者の雇用安定を図るため、「高年齢者雇用安定法」では、企業に対して70歳までの就業機会を確保する努力義務が課されています。
この就業機会の確保は、以下のような措置を通じて行うことが求められています。
- 定年年齢の引き上げ(例:65歳→70歳)
- 定年の廃止
- 希望者全員を対象とする再雇用制度の導入
- 勤務延長制度の導入(柔軟な就業継続への対応)
企業がこれらの取り組みを実行することで、高齢者が意欲と能力に応じて長く働ける職場環境が整備され、「生涯現役社会」の実現に近づくことが期待されています。
JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)によるサポート
高年齢者雇用の実現を企業と高齢者の両面から支援しているのが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、JEED)です。JEEDは、以下のような多様な支援策を提供しています。
1. 無料の相談・助言サービス
企業が高齢者の雇用環境を整備する際、次のような支援を専門家(70歳雇用推進プランナー、高年齢者雇用アドバイザー)から受けることができます。
これらはすべて無料で対応してもらえるため、制度導入を検討する企業にとって心強い存在です。
2. 高齢者雇用に関する情報提供
厚生労働省は「高齢者雇用対策ラボ」という特設ウェブサイトを運営しており、以下のような情報が掲載されています。
- 他社の先進的な取り組み事例
- 業種別の雇用動向
- 雇用管理マニュアルや制度設計のヒント
企業の実務担当者が活用しやすい資料が豊富にそろっており、政策と実務の橋渡し役を担っています。
3. 研修プログラムの提供
企業の要望に応じて、中高齢社員向けの研修を企画・実施しています。たとえば以下のような研修があります。
- モチベーション維持・自己肯定感の向上
- 新たなスキル習得や役割の見直し
- ライフプラン設計やセカンドキャリア支援
研修の多くは個社対応型で、柔軟にプランニング可能です。
4. 企業診断システムの提供
高齢者雇用に関する社内の状況を診断できる、パソコンを使った簡易診断システムを無料で利用可能です。企業規模や業種に応じた結果が得られ、今後の改善の方向性を確認できます。
5. 生涯現役支援窓口(ハローワーク内)
全国のハローワークに設置されている「生涯現役支援窓口」では、高齢者向けの再就職支援を専門的に実施しています。
- 高年齢者を積極採用している企業の求人紹介
- 就職活動に関する個別相談・ガイダンス
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接対策や応募書類の書き方講座
これにより、高齢者本人も安心して就業継続や転職に取り組むことができます。
高齢者の雇用を継続していくためには、単なる制度の整備だけでなく、企業文化の醸成や実務面での仕組み作りが不可欠です。国の支援制度を上手に活用しながら、高齢者一人ひとりが意欲と能力に応じて活躍できる職場環境を整えていくことが、今後ますます重要になっていくでしょう。
65歳以上も給付金や支援を活用し働ける環境を整えよう
高年齢雇用継続基本給付金は65歳の誕生月で支給が終了しますが、働き続けたい高齢者のために、企業向けの助成金や個人向けの給付制度が用意されています。「65歳超雇用推進助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」など、就労継続を支援する制度は多岐にわたります。企業と個人が制度を正しく活用し、高齢者が安心して働ける環境を整えることが今後ますます求められます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
中小企業の人手不足にどう対応する?経営者が知っておくべき3つの道
景気回復に伴って浮き彫りになってきた中小企業の人手不足問題。 ここではその現状を解説するとともに、企業が取るべき3つの対応策、すなわち「攻め」の採用活動、女性雇用促進、外国人雇用促…
詳しくみる外国人労働者の受け入れに必要な教育とは?日本語教育の現状や7つの解決策を紹介
外国人労働者を雇用するにあたり、大きな課題となるのが教育です。低い日本語レベルによって伝達ミスが起きてしまったり、安全教育の不足によって労働災害が起きてしまったりするリスクが想定さ…
詳しくみる【記入例付き】育児休業期間変更申出書の書き方は?延長・短縮・開始日変更の具体例を解説
育児休業の期間は、「保育園に入れない」「予定より早く復職したい」「家庭の事情で開始日をずらしたい」など、さまざまな理由で当初の予定から変更が必要になることがあります。 このような場…
詳しくみる労働基準法第16条とは?違約金・罰金の禁止をわかりやすく解説!
労働基準法第16条は、労働契約の不履行に対する違約金・損害賠償の予定を禁止する規定です。簡単に言えば、従業員が会社を辞める際などにあらかじめ罰金や賠償金の支払いを約束させる契約は違…
詳しくみる経歴詐称とは?具体例や罰則、企業の対応方法を解説
経歴詐称とは、学歴、職歴、犯罪歴などの経歴を隠したり、虚偽の申告をしたりする行為のことです。経歴詐称が発覚すると企業にとっては大きなリスクになるため、企業の対応が重要になります。本…
詳しくみる産休・育休中にふるさと納税できる?損しない年収や上限額を解説
産休・育休中でもふるさと納税はできます。ただし、控除上限額は寄付を行う年の所得にもとづいて決まるため、収入が変動する産休・育休中は注意が必要です。 本記事では、産休・育休中のふるさ…
詳しくみる