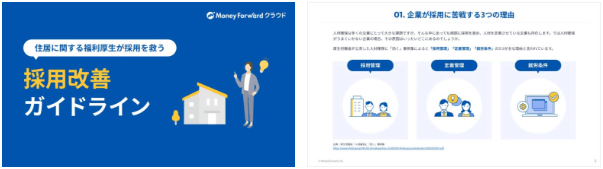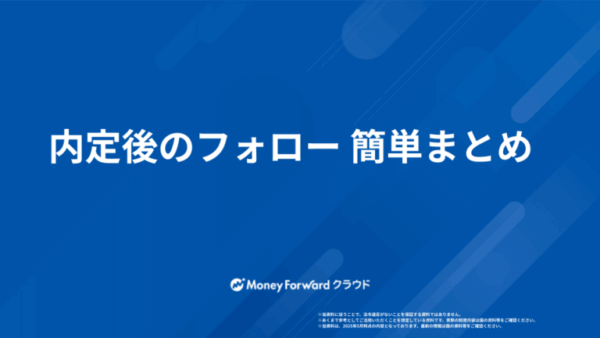- 更新日 : 2025年6月13日
離職状況証明書とは?正式な名称と取得方法をわかりやすく解説
退職後の手続きで「離職状況証明書」を求められて、どうすればよいかお困りではありませんか? 実は、公的な書類として「離職状況証明書」という名称のものは存在しません。
この言葉は、ご自身の退職状況を証明する複数の書類を総称している場合がほとんどです。
この記事では、「離職状況証明書」という言葉で検索された方が本当に必要としているであろう書類の正式名称、その取得方法、そしてそれぞれの主な用途を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
目次
「離職状況証明書」の正式名称
多くの方が「離職状況証明書」として探している書類は、主に以下のいずれかを指していると考えられます。
それぞれの書類には、異なる目的と役割があります。
- 雇用保険被保険者離職証明書
- 会社がハローワークへ提出する、失業給付の申請に必要な元の書類。
- 雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2)
- 上記「離職証明書」に基づきハローワークが発行し、退職者自身が失業給付を申請する際にハローワークへ提出する書類。
- 退職証明書
- 会社が退職の事実を証明するために発行する、私的な証明書。
これらの書類は似ているようで、用途や取得方法が異なりますので、一つずつ詳しく見ていきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
「雇用保険被保険者離職証明書」とは?
雇用保険被保険者離職証明書は、失業給付(基本手当)を受給する際に使用します。
提出者
退職した会社(事業主)が作成し、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。退職者自身が作成・提出する書類ではありません。
提出期限
原則として、退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出する義務が会社に課せられています。
様式
厚生労働省が定めた複写式の3枚つづりの専用様式です。この書類の記載内容が、後に退職者に交付される「雇用保険被保険者離職票(離職票-2)」に反映されます。
この「雇用保険被保険者離職証明書」に記載される「離職理由」や「賃金支払状況」は、失業給付が支給されるか否か、支給開始時期、そして支給額を決定する上で極めて重要な情報となります。特に「離職理由」は、自己都合退職か会社都合退職かによって、給付の開始時期や期間に大きな影響が出ます。
会社がこの書類をハローワークへ提出し、ハローワークで内容の確認作業が行われた後、約1週間から2週間程度で、退職者の方のご自宅へ後述する「雇用保険被保険者離職票」が郵送されます。ただし、地域や時期によるハローワークの混雑状況によって、多少変動することがあります。
「雇用保険被保険者離職票」の用途と取得方法
前述の「雇用保険被保険者離職証明書」を基にハローワークが発行し、退職者本人に交付されるのが「雇用保険被保険者離職票」です。これは「離職票-1」と「離職票-2」の2枚組で構成されています。
用途
この「離職票」は、退職後に失業給付(基本手当)を受け取るためにハローワークへ提出する、最も重要な書類です。離職票がなければ失業給付の申請手続きはできません。
取得方法
会社がハローワークへ「離職証明書」を提出した後、ハローワークから直接、退職者の住所へ郵送されます。会社から手渡しされるものではありません。
届かない場合
退職後2週間以上経過しても離職票が届かない場合は、まずは退職した会社の人事担当者へ、離職証明書をハローワークへ提出したか確認してみましょう。それでも解決しない場合は、ご自身の住所を管轄するハローワークに直接問い合わせてみてください。
「退職証明書」とは?
「退職証明書」は、上記2つの公的な書類とは異なり、会社が退職の事実を証明するために発行する私的な書類です。
発行義務
労働基準法第22条に基づき、退職者から請求があれば、会社には発行する義務があります。ただし、請求がない限り自動的に発行されるものではありません。
用途
転職先から前職の在籍期間や業務内容の確認のために提出を求められることがあります。
また、国民健康保険や国民年金への切り替え手続き、扶養家族の追加、あるいは保育園や学童保育の入所申請などで、退職の事実を証明する書類として利用できる場合があります。
様式
公的な書式は定められていないため、会社ごとに書式や記載される項目が異なります。一般的には、氏名、退職日、勤務期間、業務内容、退職理由などが記載されます。
「離職状況証明書」が必要な場合の対応方法
ご自身の状況と目的に合わせて、適切な書類を確実に取得しましょう。
失業給付の受給を希望する場合
会社がハローワークに「雇用保険被保険者離職証明書」を提出することで、ハローワークからご自宅へ「雇用保険被保険者離職票」が郵送されます。まずは会社に手続き状況を確認しましょう。
転職活動やその他の公的手続きで退職を証明する必要がある場合
会社に「退職証明書」の発行を請求してください。会社によっては、「雇用証明書」や「在籍証明書」など、異なる名称で発行される場合もあります。
退職後の手続きは多岐にわたりますが、適切な書類を理解し、準備することでスムーズに進めることができます。ご不明な点があれば、遠慮なく退職した会社の人事担当者や、お近くのハローワークに問い合わせてみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働組合への対応方法は?団体交渉の進め方から不当な要求への法的対処まで解説
労働組合から団体交渉の申し入れがあり、対応方法にお悩みの人事担当者や経営者の方もいるでしょう。労働組合への対応を誤ると、不当労働行為と見なされ、企業にとって大きな不利益を生む可能性…
詳しくみる退職者への源泉徴収票の発行はどうする?再発行の対応や注意点を解説
退職者への源泉徴収票の発行は、企業が必ず対応すべき重要な法定業務のひとつです。これは退職者が確定申告や転職先での年末調整を行う際に必要不可欠な書類であり、正確かつ期限内に交付しなけ…
詳しくみる非財務情報とは?開示すべき理由や具体例をわかりやすく解説
企業が持続的に成長するためには、「非財務情報」の開示が欠かせません。環境対策や人的資本、知的財産など、数値では表しにくい要素が投資判断や企業評価に大きく影響するためです。 本記事で…
詳しくみる介護離職とは?後悔しない両立方法、企業の取り組み事例、助成金
介護離職とは、家族の介護を理由に仕事を辞めることです。介護離職を防ぐためには、介護休業や介護休暇の制度、勤務先の支援、介護サービスの利用が欠かせません。政府や企業も助成金や柔軟な働…
詳しくみる雇用契約書がないとどうなる?トラブル例と作成方法を解説
労働契約は雇用契約書がなくても成立します。しかし、書面で労働条件を明確にしない場合、認識のずれや法的なトラブルが生じやすくなります。 契約内容に関する争いが生じると、双方に不利な結…
詳しくみる中小企業の人手不足にどう対応する?経営者が知っておくべき3つの道
景気回復に伴って浮き彫りになってきた中小企業の人手不足問題。 ここではその現状を解説するとともに、企業が取るべき3つの対応策、すなわち「攻め」の採用活動、女性雇用促進、外国人雇用促…
詳しくみる