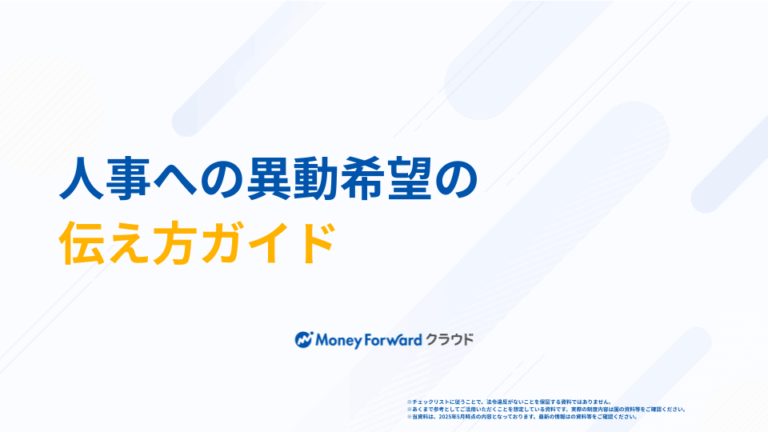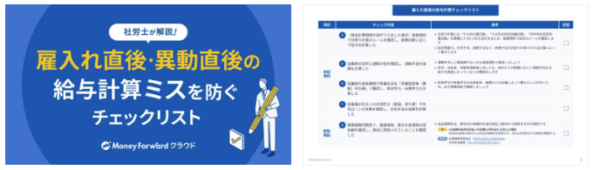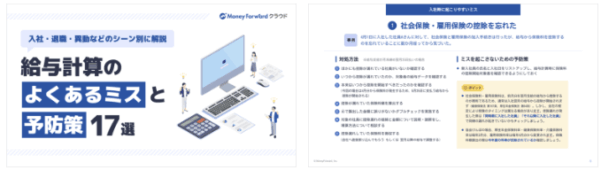- 更新日 : 2025年10月31日
ストレスで異動したい場合の伝え方は?部署異動できない場合の対応も解説
職場でのストレスで部署異動したいと感じる人は少なくありません。しかし、部署異動したいという希望をどのように伝えればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、ストレスで部署異動するメリット・デメリットから、異動希望の正しい伝え方、異動希望が通らなかった場合の対応までわかりやすく解説します。
目次
ストレスで部署異動したいと感じる原因
職場のストレスで部署異動したいと感じる原因はさまざまですが、多くの場合、働く環境や人間関係、業務内容が大きく関係しています。ここでは、ストレスで部署異動したいと感じる主な原因について解説します。
人間関係のトラブル
職場の人間関係が原因でストレスを感じるケースは非常に多くあります。例えば、一緒に働く上司や同僚との相性が悪いと、日々の業務が精神的に負担になるでしょう。また、パワハラやいじめが原因で、働き続けるのが困難になる場合もあります。大きなトラブルはなくても、チームの中で自分の意見が通らず、孤立感によってストレスが蓄積されるでしょう。
業務内容のミスマッチ
業務内容が自分に合わない場合も、大きなストレスとなります。例えば、得意なスキルが活かせない業務や、難易度が高すぎる仕事を任されると、やりがいや達成感を得ることができません。また、仕事量が多すぎると、体力的な負担だけでなく、精神的なストレスも限界に達する場合があります。一方、業務内容に興味が持てず、モチベーションが低い状態で仕事を続けると、ストレスを感じて生産性も下がってしまいます。
職場環境の問題
職場環境そのものがストレスの原因となることもあります。例えば、長時間労働や低賃金など、劣悪な労働条件がストレスを引き起こします。自分の価値観やライフスタイルと職場の文化が合わない場合は、居心地の悪さを感じるでしょう。職場環境が整備されていない場合も、業務効率を低下させ、ストレスを感じやすくなります。
その他にも、家庭との両立が難しいなど、個人的な事情がストレスの原因となる場合があります。ストレスが蓄積すると、心身に悪影響を及ぼすため、放置せず適切な対応を取ることが重要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
ストレスで部署異動したい場合の伝え方
職場のストレスが原因で部署異動したい場合は、上司や人事に希望を伝えることが重要です。ただし、伝え方を間違えると、希望が通りにくくなったり、職場での関係性が悪化したりする可能性があります。ここでは、部署異動を希望する場合の効果的な伝え方について解説します。
部署異動を希望する理由を明確にする
まずは、部署異動を希望する理由を明確に言語化しましょう。「ストレスが限界だから」という漠然とした理由ではなく、「業務量が過多で体調を崩している」や「現部署の業務がスキルに合わない」といった具体的な理由を用意します。その際、ストレスの原因や状況を記録しておくことで、説得力が増します。日常的なストレスの具体例や、体調への影響があれば記録しておくとよいでしょう。
そして、異動後に希望する部署や業務も具体的に示すことが大切です。自分のスキルやキャリアプランをもとに、新しい部署でどのような貢献ができるかを考えましょう。
伝えるタイミングや話し方に注意する
上司や人事担当者に異動希望を伝える場合は、繁忙期を避け、落ち着いて話ができるタイミングを選びましょう。その際、否定的な理由ばかりを並べるのではなく、「新しいスキルを活かしたい」などポジティブな表現を心がけることで、上司や人事が前向きに検討しやすくなります。人間関係が原因であっても、個人を直接批判する表現は避けるべきです。また、理由を詳しく話しすぎると、話が逸れる可能性があります。具体的かつ簡潔に理由を述べることを心がけましょう。
上司と話しづらい場合は第三者に相談する
上司に直接伝えることが難しい場合、人事部に相談するのも一つの手段です。また、社内のメンター制度や労働組合、外部の労働相談窓口を利用することも視野に入れましょう。ストレスが体調不良につながっている場合は、医師の診断書を活用することで、異動希望の説得力を高めることができます。
ストレスで部署異動するメリット
部署異動は、職場のストレスを軽減し、新たな環境で自分の能力を活かすチャンスにもなります。ここでは、部署異動によって得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。
ストレスが軽減される
部署異動の最も大きなメリットは、現在抱えているストレスから解放されることです。上司や同僚との相性が悪い場合も、人間関係をリセットできるため、精神的な負担が軽減されます。また、職場の文化や雰囲気が変わるため、自分に合った環境で働ける可能性が高まります。過度な業務量やパワハラなど、現在の部署でのストレス要因から距離を取ることで、冷静に状況を見直す時間も確保できるでしょう。
心身の不調が改善される
ストレスの軽減により、心身の健康状態も向上する可能性があります。特に、ストレスが原因で頭痛や胃痛、不眠といった体調不良に陥っている場合は、部署異動によって不調が改善されるかもしれません。また、新しい環境で前向きな気持ちで仕事に取り組むことで、メンタルヘルスも向上します。
自分のスキルや経験を活かせる
異動先の部署では、自分のスキルや経験がより活かされる場面があるかもしれません。自分の得意分野や適性のある業務を担当することで、仕事への意欲が高まり、生産性も向上します。また、異動先でこれまでとは異なる業務を担当することで、新たなスキルを身につける機会が得られます。
キャリアの可能性が広がる
部署異動は、キャリア形成においても有効です。別の部署で働くことで、会社全体の業務や流れについてより深く理解できるようになります。これにより、自分の役割を広い視野で捉えることが可能です。また、複数の部署での経験は、昇進や評価にプラスとなる可能性があります。特に、リーダーシップや適応力が求められるポジションへの昇進に有利になるでしょう。
ストレスで部署異動するデメリット
部署異動はストレスの軽減に有効な手段ですが、デメリットがないわけではありません。ここでは、ストレスで部署異動するデメリットについて解説します。
新しい環境への適応が必要
部署異動によって、慣れ親しんだ環境から離れることになります。新しい上司や同僚との人間関係を構築する必要があるため、内向的な人や社交的でない人にとっては負担になるかもしれません。また、異動先での業務内容がこれまでと大きく異なる場合、新しいスキルや知識を習得するために努力が必要です。この期間中はストレスを感じることもあるでしょう。
ストレスが解消されない可能性がある
異動したにもかかわらず、ストレスが解消されないことがあります。例えば、異動先でもストレスの根本原因が解決しなかったり、新たなストレス要因が生じたりするケースです。また、「期待していた環境と違った」と異動後のギャップに悩むことがストレスの要因になることもあります。
キャリアにマイナスな影響を与える
部署異動がキャリアにマイナスな影響を与える場合もあります。新しい部署では、これまでの実績や評価が引き継がれない可能性があるからです。また、異動先での業務が自分のキャリア目標に合わない場合もあります。特に希望部署が選べない場合には、このリスクが高まります。
経済的・生活的な負担がかかる
部署異動に伴い経済的や生活面での負担が発生することもあります。例えば、異動先の部署によっては、給与体系や待遇が変わる場合があります。また、異動に伴い勤務地が変わる場合、通勤時間が増えたり引っ越しが必要になる場合があります。
ストレスで部署異動するときの注意点
部署異動は職場のストレスを解消するのための一つの手段ですが、慎重に進めないと新たな問題を引き起こす可能性もあります。ここでは、部署異動を希望する際の注意点について解説します。
自分の健康状態を優先する
ストレスが原因で体調不良に陥っている場合は、自分の健康状態を第一に考えた行動が求められます。異動先でさらに大きなストレスを抱え込むことがないよう、自分の体調やメンタルヘルスに合った選択を心がけましょう。医師の診断書を用意すれば、上司や人事担当者に現状を正しく伝えられます。
社内規則や相談窓口を確認する
社内規則や相談窓口を確認することは、自分を守るためにも役立ちます。社内規則では、異動の申請手続きやフローについて確認しましょう。不備のない手続きがスムーズな異動につながります。また、社内にメンタルヘルスの相談窓口や外部カウンセリング制度がある場合、それらを利用して専門家の意見を聞くのも効果的です。
異動先の情報収集を行う
異動先の部署について十分に情報収集しておくことが、理想とのギャップを減らす上で大切です。異動先での具体的な仕事内容や期待される役割を事前に把握しましょう。また。異動先の職場の雰囲気についても可能な範囲で確認しておきましょう。同僚や先輩からの情報が参考になります。
現部署の人間関係に配慮する
現在の部署の人間関係を悪化させないための配慮も必要です。異動の相談する際は、現部署のメンバーや上司を批判するような言動を避けましょう。感謝の気持ちを伝えることで、円満な関係を保てます。また、異動を決めた後でも、現在の業務をきちんとこなす姿勢を見せることが重要です。引き継ぎも含め、最後まで責任を持つことで、信頼関係を保てます。
ストレスによる部署異動が認められない場合の対応
ストレスによる部署異動を希望したものの、会社から認められない場合もあります。このような場合でも落胆せず、冷静に次の行動を考えることが重要です。
自分でストレスを軽減する方法を考える
異動が認められなかった場合、まずは自分でストレスを軽減する方法を考えることが重要です。業務内容を見直し、効率化できる部分を探してみましょう。無駄な負担を減らすことでストレスが軽減されることがあります。また、仕事外の時間をリフレッシュに充てることは、ストレスを軽減する有効な手段です。適度な運動や趣味の時間を確保しましょう。
異動以外の選択肢を模索する
部署異動が難しい場合、他の解決策を模索することも一つの方法です。在宅勤務や時短勤務、フレックスタイム制度などが利用できる場合、それらを活用することでストレスを減らせる可能性があります。また、他部署と関わるプロジェクトに参加することで、新たなスキルや人間関係を築くきっかけが得られるかもしれません。
もう一度異動の希望を伝える
現段階では異動の希望が認められなくても、状況が変われば再度検討される場合もあります。適切なタイミングで希望を伝える準備をしましょう。異動が行われやすいタイミングで再度希望を伝えることで、希望が通る可能性が高まります。また、現在の部署で引き続き業務をこなし、成果を上げることで信頼を築くことができます。この信頼が異動希望の再検討にプラスに働く場合があります。
最終手段として転職を検討する
どうしても現在の職場ではストレスが改善されない場合、転職も選択肢の一つです。冷静に今後のキャリアを見直し、転職が本当に必要かを慎重に検討しましょう。転職活動に取り組む場合は、キャリアコンサルタントに相談すると、自分のスキルや経験をもとに、適切な転職先を探すためのアドバイスを受けることができます。
ストレスによる部署異動に職場が配慮すべきポイント
ストレスで部署異動する従業員に対しては、職場の配慮が重要です。ここでは、職場が配慮すべき具体的なポイントについて解説します。
従業員の声に耳を傾ける
従業員の悩みや異動希望の理由を正確に理解することが、適切な配慮への第一歩です。上司や人事担当者がヒアリングの場を設け、従業員の声をしっかりと聞きましょう。否定的な態度を避け、話しやすい雰囲気で従業員の気持ちを受け止めることが大切です。また、デリケートな内容を話す場合もあるため、相談内容が他の従業員に漏れないよう、プライバシーを厳守しましょう。
個別の事情を考慮して柔軟に対応する
部署異動をスムーズに進めるには、個別の状況に応じた柔軟な対応が必要です。ストレスの原因が人間関係、業務量、職場環境などさまざまであることを理解し、それに応じた異動先の選定を行いましょう。また、異動先での業務内容や人間関係にスムーズに適応できるよう、研修やオリエンテーションを行うことも大切です。
異動先の部署を正しく選定する
異動先の選定は、従業員が新しい環境でストレスなく働けるかどうかを大きく左右します。異動先の業務が従業員のスキルやキャリア目標に合致しているかを慎重に検討しましょう。適性を無視した配置は、さらなるストレスを引き起こす可能性があります。異動先での業務量や職場の雰囲気、人間関係について事前に把握し、ストレスを引き起こす要因が少ない環境を選びます。
異動による負担をサポートする
異動による従業員の負担を最小限にするためにサポートすることも大切です。現在の部署での業務引き継ぎを円滑に進めるために、チーム全体で協力する体制を整えましょう。異動に伴う通勤時間や生活環境の変化に対して、在宅勤務やフレックスタイム制度の活用を検討することも効果的です。ストレスが異動の理由となっている場は、定期的なフォローアップや相談窓口の設置により、異動後も従業員のメンタルヘルスに注意を払うことが重要です。
ストレスを解消する手段は部署異動だけではない
部署異動は、ストレスを解消し新しい環境で再スタートを切るための有効な手段ですが、それが唯一の解決策ではありません。異動が認められなかった場合の対応策や、他の選択肢も視野に入れて柔軟に考えることが大切です。
また、異動希望を実現するためには、自分自身の希望や状況を冷静に見つめ直し、周囲とコミュニケーションを図ることが欠かせません。適切な準備と行動が、より良い職場環境と働き方を手に入れるための鍵となるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
異動時に労働条件通知書は必要?再交付のルールや確認すべきポイントを解説
企業から人事異動の辞令を受けると、「給与や勤務地、仕事内容は具体的にどう変わるのだろうか」「そもそもこの異動は法的に問題ないのか」といった不安や疑問を感じる方は多いでしょう。異動は…
詳しくみる移民と外国人労働者の違いは?定義や問題点を徹底解説
移民と外国人労働者は、法律上の定義や目的が異なります。違いを理解することは、適切な雇用管理の第一歩です。 本記事では、移民と外国人労働者の違いを明確にし、日本における受け入れ状況や…
詳しくみる介護事故報告書とは?書き方やポイントを解説【無料テンプレートつき】
介護事故報告書は、介護サービスの提供に伴う事故が発生した場合に市町村などの行政機関に報告するものです。介護保険法や各自治体が定める指針では、介護事業者は事故の状況および事故に際して…
詳しくみる労働者名簿は一覧形式でも問題ない?無料テンプレートも
労働者名簿は、一覧形式で作成しても問題ありません。労働基準法には労働者名簿の様式についての具体的な指定がないため、必要な情報がすべて記載されていれば、1人1枚の形式でも一覧形式でも…
詳しくみる離職票とは?退職証明書との違いや発行手続きについて解説!
離職票とは、雇用保険に加入している退職者が失業手当を受け取るための必要書類です。退職者から依頼を受けた会社は、退職日から一定の期間内にハローワークへの手続きをしなければなりません。…
詳しくみる就職氷河期とは?いつのこと?現在の年齢や支援プログラムについて解説!
就職氷河期とは、バブル崩壊後の、新卒採用が特に厳しかった1993年〜2005年頃のことで、当時大学などを卒業した世代を就職氷河期世代と呼びます。本記事では、就職氷河期世代の年齢や特…
詳しくみる