- 更新日 : 2025年11月19日
すぐパワハラと騒ぐ人にはどう対処する?指導のポイントやトラブル防止策を解説
近年、パワハラへの関心が高まる一方で、些細なことでもパワハラと騒ぐ従業員が増えています。このような状況を放置すると、職場環境の悪化やモチベーションの低下、エンゲージメントの喪失、業務効率の低下などの良からぬ事態になる恐れが出てくるでしょう。本記事では、すぐにパワハラと騒ぐ従業員への対処の仕方を解説します。
目次
すぐパワハラと騒ぐ人の特徴は?
すぐにパワハラと騒ぐ理由には、その人の心理的な傾向による場合もあれば、仕事や職場に対する何らかの意図を含んだ場合もあります。前者の場合は、他人の注目を集めたがるタイプと、想定外の事態にうまく対応できないタイプに分けられます。そして、後者の場合は、職場管理・業務管理の根幹にかかわる問題をはらんでいます。ここでは、すぐパワハラと騒ぐ従業員の特徴を紹介します。
権利意識が高い
権利意識の強い従業員の特徴として、何かにつけてパワハラだとすぐ騒ぎ、自己中心的な態度が見られます。このタイプの従業員の場合、通常の業務量でも「過剰な業務量のせいで時間外勤務を強いられる」と騒ぐケースがあります。他にも、さまざまな理屈を申し立てて業務を避けようとするケースがあるでしょう。
パワハラを口実に仕事をサボることが多い
「こんな仕事をさせるのはパワハラだ」「上司に厳しく言われた言葉が気にかかって仕事ができなかった」などと申し立ての中には、面倒な仕事からの逃避、いわゆるサボりといったケースも含まれています。この場合、仕事に対する姿勢が消極的で、業務に関する知識や能力が不足などの課題を抱えた従業員が、それを隠すための対策として、パワハラを訴えることがあるのです。
業務指示に従わない
業務に関する正当な指示を受けても反省する姿勢を見せず、「パワハラ」と騒ぐ従業員がいることがあります。このような従業員には、権利意識が強い、仕事をおろそかにするなどの傾向が見られると言われています。しかし、最も大きい問題として挙げられるのが、法律上の労働契約の内容について十分に理解していない点です。労働契約においては、雇用主の指示に従って仕事をすることが労働者の義務であり、その対価として賃金が支払われる仕組みになっています。
他責思考が強い
他責思考とは、問題が発生した際に、その原因を自分以外のもの(他人、アクシデントなど)に押しつけることです。他責思考の従業員は、当事者意識が低く、責任感や積極性が希薄という傾向があるため、仕事では同じミスの繰り返しや、常に指示待ち状態も珍しくありません。周りからミスや態度を指摘された場合などに、自分に責任がないことの言い訳としてパワハラを申し立てるケースがあるとされています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
パワハラの判断基準と実務対応
従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。
本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。
ハラスメント調査報告書(ワード)
本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。
ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。
パワハラのNGワード&言い換えまとめ
職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。
すぐパワハラと騒ぐ人を放置するリスク
職場のパワハラ問題は、それが事実であっても単なる噂であっても、従業員に対して何らかの悪影響を及ぼし、結果的に企業風土の低下や業績の低迷などにつながります。ここでは、職場でパワハラとすぐ騒ぐ人を放置するリスクについて詳しく解説します。
職場環境の悪化
ハラスメント問題が発生すると、それが事実でなかったとしても、従業員は自分も同じような問題に巻き込まれるのではないかという不安を抱くことでしょう。特に注意したいのは、単なる噂だからといって対処が遅れた場合、上司の問題解決能力や会社の姿勢に対する不信にもつながる恐れがあります。さらに、これを機に過去の上司の言動に対する不満などが表面化し、職場環境がさらに悪化する可能性が高くなるでしょう。
業務効率の低下
ハラスメント問題が発生すると、現場の管理者は、事実関係の確認や対処方針の検討などに追われ、通常のマネジメント業務に割くべき時間が損なわれることになります。
また、ハラスメント問題の噂が広まることによって従業員の集中力が低下したり、モチベーションが落ちたりするという良からぬ事態も生じます。その結果、業務を推進する活力が衰え、業務の効率が下がるといったリスクが高くなるでしょう。
他の従業員の離職
パワハラ騒ぎが長引いた場合、それに巻き込まれた従業員のエンゲージメントが下がり、離職してしまうことが考えられます。その従業員が職場内で一定の存在感を持った人物であった場合、その人物を慕う従業員も相次いで離職するといった事態も起こるでしょう。
パワハラと言われた時の適切な対応手順
パワハラ発生時の基本的な対応の流れは以下の通りです。当事者のプライバシーには十分配慮することも忘れてはなりません。

すぐパワハラと騒ぐ人が部下になったら、どう指導する?
職場でパワハラ騒ぎが起こったら、まずは話を聞き、次に事実関係を確認しましょう。事実関係が整理できたタイミングで、パワハラの基準に該当するかどうかを判断し、従業員に説明します。
しかし、パワハラ騒ぎをする人の中には、「自分がパワハラと感じたら、その行動はパワハラだ」と解釈し、誤解するケースが多く見られます。パワハラ認定には基準があること、騒ぎ立てた事態は適正な指導・監督の範囲内であることなどを明確に伝えましょう。また、パワハラと騒ぐ従業員に課題があることが明らかになった場合には、改善に向けた具体的なプログラムを本人に提示し、実行をサポートします。
厚生労働省が示すパワハラの3要素・6類型についてはこちらをご覧ください。
パワハラトラブルを防止する対策
パワハラの防止には、管理職も含めた従業員の意識啓発と発生したトラブルに迅速かつ適正に対処できる制度構築が必要です。
パワハラの認定基準と処分を周知徹底
パワハラと騒ぎ立てる従業員がいるということは、職場におけるパワハラ対処方針が周知・徹底されていないことが原因だと考えられます。職場内でパワハラの認定基準を明確に示し、被害の状況に応じて懲戒解雇も含めた厳正な処分を行うという方針を全社的に周知・徹底しましょう。その際に就業規則などの文書の整備も必要です。
パワハラ対処体制を周知
パワハラ問題が発生した場合の対処体制を整備しておくことも、パワハラ防止につながります。パワハラ問題が会社にもたらす損失の大きさを考えると、パワハラ問題に遭遇した従業員が、最初にアプローチする相談窓口の存在感を整備することは大切なポイントです。
また、パワハラの加害者に対して厳正な処分を下すことも抑止力となります。この場合、根拠のない噂に対して、より厳しい対応をすることも必要です。
被害者の保護を徹底する
パワハラ対処制度を活用してもらうためには、被害者に関するプライバシーを徹底的に保護することが必要です。パワハラの相談をしたために不利益を受けるようなことが一度でもあれば、パワハラ相談窓口の存在価値は失われてしまいます。被害者の保護を徹底することは、制度を機能させるための重要なポイントです。
社員の意識向上が最善の対策~研修を繰り返す~
パワハラに対処する制度の構築と併行して、従業員全員のパワハラに対する理解の促すことも必要です。身近な事例で、どこがパワハラに該当するのか、そのパワハラ行為によって加害者はどのような処分を受けることになったのかといったことを、繰り返し伝えることで、理解を深めるきっかけになるでしょう。職場内で発生した問題を事例にする場合には、プライバシーへの配慮も行うことも忘れてはなりません。
肝心なのはパワハラに対してぶれない姿勢
すぐにパワハラと騒ぐ従業員に振り回されないようにするためには、管理者自身がパワハラの認定基準を正しく理解し、この基準をもとに事案の解決を行う姿勢を堅持することが重要です。
また、根拠のない騒ぎは職場の秩序を乱す可能性があります。一方で、労働施策総合推進法では、パワハラ相談を理由とした不利益な取扱いを厳しく禁じています。会社として公正な調査と適切な対応をすることを従業員に周知・啓発することが必要となります。
参考
厚生労働省|労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職理由の伝え方は?理由の書き方や注意点を解説【ワード・エクセル別テンプレ付き】
介護、引越し、転職のためなど、従業員が退職する際の理由はさまざまです。しかし、退職届にネガティブな理由が書かれていたら気になるのではないでしょうか。 従業員が会社を辞めるには理由が…
詳しくみる【テンプレート付】ビジネスで使えるお見舞いの手紙例文や書き方を解説
お見舞いの手紙を送る機会は、ビジネス・プライベートを問わず多くあります。書き方や文例を解説するので、ぜひ参考にしてください。また、無料でダウンロードできるテンプレートや、一筆箋で気…
詳しくみる退職勧奨される人の特徴とは?拒否する場合と応じる場合の対処法や注意点
退職勧奨は従業員に自発的な退職を勧める制度であり、解雇のように一方的に辞めさせられることはありません。しかし「自分が対象になるのでは」と不安に感じる人も少なくないでしょう。この記事…
詳しくみる行動指針とは?企業事例や作り方・社内への浸透方法をわかりやすく解説
企業の成功と持続可能な成長は、明確な行動指針によって大きく左右されます。行動指針は、従業員が日々の業務を遂行する際の道しるべとなり、組織の価値観や目指すべき方向性を示します。本記事…
詳しくみる高年齢雇用継続基本給付金のデメリットとは?2025年改正や年金併用、企業の対応を解説
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の再雇用や再就職時に賃金が減少した場合、その差額を補填する制度です。しかし、制度の複雑さや年金との関係、2025年の支給率変更など、注意すべき…
詳しくみるジョブコーチ(職場適応援助者)とは?支援内容や種類、助成金制度など解説!
障害のある従業員を雇用する際、企業は適切な支援体制を整備することが重要です。そこで注目されているのが、ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援です。ジョブコーチは、障害者の職場適応…
詳しくみる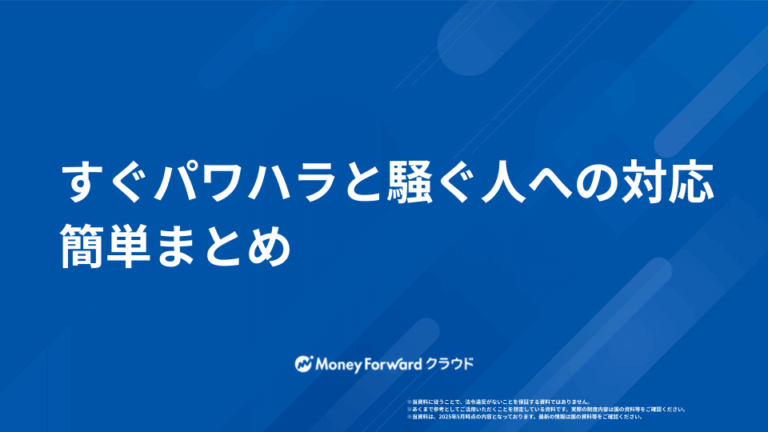


-e1762259162141.png)
