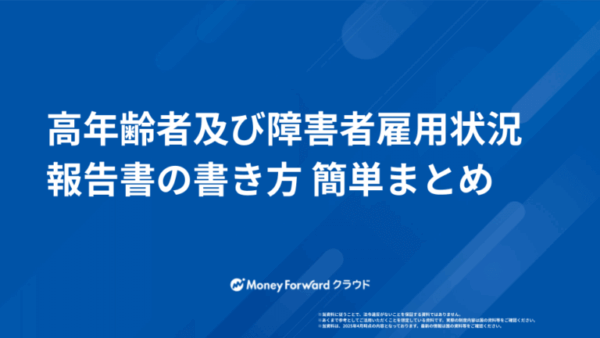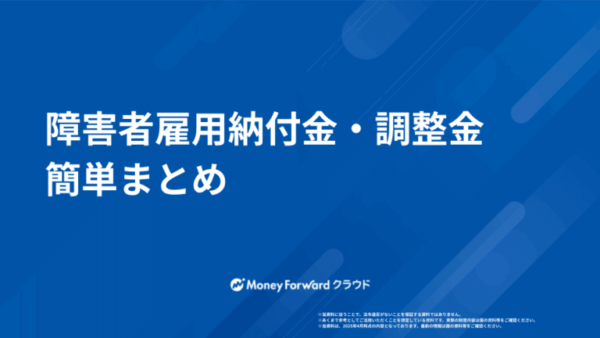- 更新日 : 2024年12月24日
ジョブコーチ(職場適応援助者)とは?支援内容や種類、助成金制度など解説!
障害のある従業員を雇用する際、企業は適切な支援体制を整備することが重要です。そこで注目されているのが、ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援です。ジョブコーチは、障害者の職場適応を専門的に支援する役割を担っています。本記事では、ジョブコーチの支援内容や種類、利用方法、助成金制度などを詳しく解説します。
目次
ジョブコーチ(職場適応援助者)とは?
ジョブコーチ(Job Coach)とは、障害者の就職や職場適応を支援する専門家のことを指します。障害者一人ひとりの特性に応じて、職場での課題解決や業務遂行のサポートを行います。
具体的には、障害者が職場に適応できるよう、作業手順の指導や環境調整、コミュニケーション支援などを行います。障害特性を踏まえた合理的配慮の提案や、障害者と職場の相互理解を促進することも重要な役割です。
ジョブコーチは、障害者が自立して働くことができるよう、一時的な支援を行います。徐々に支援を減らしながら、最終的には障害者が職場に完全に馴染めるよう寄り添い、企業と障害者の架け橋となり、障害者の職場定着と自立を目指します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の書き方 簡単まとめ
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の作成準備で、お困りごとはございませんか?
本資料は、報告書の書き方を分かりやすくまとめた資料です。ぜひダウンロードいただき、報告書作成にご活用ください。
障害者雇用納付金・調整金 簡単まとめ
障害者雇用納付金・調整金の申告準備はお済みでしょうか?
本資料は、障害者雇用納付金・調整金の制度について分かりやすくまとめた資料です。ぜひダウンロードいただき、制度の理解や実務にお役立てください。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
ジョブコーチ(職場適応援助者)の支援内容は?
ジョブコーチの具体的な支援内容は、企業に対するものと障害者に対するものがあります。それぞれについて解説します。
企業に対する支援内容
ジョブコーチは、障害者の受け入れ企業に対しても重要な支援を提供するのです。
まず、障害者の特性や配慮点について企業に説明し、障害理解の促進や作業環境の改善提案、障害者に適した業務内容の検討など、受け入れ体制の整備を支援します。
また、障害者の強みや可能性を企業に伝えることで、プラスの期待を醸成し、障害者の個別指導を通じて得られた気づきを企業にフィードバックすることで、効果的な対応方法を示唆します。
さらに、障害者の同僚や上司に対しても、障害特性に応じたコミュニケーション方法や支援の仕方を助言し、チームで障害者を受け入れる雰囲気づくりを後押しします。
このように、ジョブコーチは企業と障害者の架け橋となり、お互いの理解を深め、障害者が職場に馴染めるよう環境を整備する重要な役割を担っているのです。
障害者に対する支援内容
ジョブコーチは、障害者一人ひとりの特性に合わせたきめ細かい支援を行います。
就職前から障害者のアセスメントを行い、適性や強み、支援ニーズを把握し、適切な職場環境や業務内容を見極めたうえで、マッチングを支援するのです。
就職後は、作業手順の指導や記憶の補助、コミュニケーション支援などを行い、課題が発生した際には、障害特性に応じた対処方法を一緒に考え、実践を促します。
また、障害特性に起因する課題に対し、合理的配慮の提案や環境調整の働きかけを行い、障害者のストレス軽減にも注力し、メンタル面での寄り添いも大切にしています。
このほか、障害者の成長を見守りながら、自立に向けた支援を徐々に減らしていき、最終的には、障害者自身が職場に溶け込み、自立して活躍できるよう尽力するのです。
ジョブコーチ(職場適応援助者)の種類は?
ジョブコーチは、支援形態によって配置型ジョブコーチ、訪問型ジョブコーチ、企業在籍型ジョブコーチの3種類に分けることができます。
配置型ジョブコーチ
配置型ジョブコーチは、障害者が就職する企業内に常駐し、日常的に障害者の職場定着を支援する形態です。企業からの雇用ではなく、専門機関から派遣される形が一般的です。
配置型の最大のメリットは、障害者の状況に密着して支援できることです。企業内の環境や人間関係を熟知しているため、障害者に合った適切な対応が可能となります。業務指導はもちろん、障害特性への配慮や同僚とのコミュニケーション支援など、細かい部分までサポートできます。
また、企業内での障害者受け入れ体制の整備にも貢献できます。障害理解の促進や合理的配慮の提案、環境調整の働きかけなどを通じて、障害者が活躍しやすい職場づくりを後押しします。企業と障害者の橋渡し役として機能するのが配置型の大きな役割です。
訪問型ジョブコーチ
訪問型ジョブコーチは、障害者が就職した企業を定期的に訪問し、支援を行う形態です。複数の企業を巡回しながら、障害者の状況に応じて柔軟に対応します。
訪問型の利点は、専門性の高い支援を提供できることです。ジョブコーチ自身が特定の障害特性に精通しており、的確なアドバイスや指導が可能です。また、企業外部の視点から客観的に障害者の状況を捉えられるのも強みです。
一方で、企業にジョブコーチが常駐しないため、障害者の日常的な様子を継続的に把握するのが難しいという課題もあります。そのため、障害者や企業との緊密なコミュニケーションが不可欠となります。
企業在籍型ジョブコーチ
企業在籍型ジョブコーチは、企業に雇用されたスタッフが障害者の職場支援を担う形態です。企業内の人材を活用するため、企業文化や業務内容を熟知していることが最大の強みとなります。
障害者の業務指導はもちろん、障害特性に合わせた職場環境の整備や合理的配慮の検討など、企業内での調整がスムーズに行えます。また、障害者と同僚との間に入り、お互いの理解を深めることもできます。
ただし、ジョブコーチとしての専門性を備えていないケースもあり、障害特性への対応力に課題があるかもしれません。そのため、外部の専門家によるバックアップやスキルアップの機会が重要となってきます。
ジョブコーチ(職場適応援助者)を利用する方法は?
では、ジョブコーチを利用するにはどのようにすればよいのでしょうか。利用方法について説明します。
障害者が利用する場合
障害者がジョブコーチを利用する場合は、主に障害者就労支援機関を通じて手続きを行います。ハローワークや障害者就業・生活支援センター、障害者職業紹介機関など、支援機関へ相談し利用を申込みます。
支援機関では、障害者一人ひとりの特性やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、適切なジョブコーチを選定、マッチングします。障害特性に応じた専門性の高いジョブコーチを派遣してもらえるのがメリットです。
企業が利用する場合
企業が障害者の職場定着を目的にジョブコーチを利用する場合は、人材紹介会社や専門機関へ直接依頼することになります。自社で障害者受け入れを検討している際に、ジョブコーチの派遣を申込みます。
企業内での障害者の受け入れ体制整備や、職場環境の改善提案などの支援を受けられます。障害者の適性把握や業務マッチングの助言も得られるため、円滑な障害者雇用に役立ちます。
助成金制度の活用
ジョブコーチの利用にあたっては、後述するように国や自治体の助成金制度を活用することができます。障害者の雇用に係る各種助成金のほか、ジョブコーチ利用に特化した助成金制度も存在します。
ジョブコーチ(職場適応援助者)の利用にかかる費用は?
ジョブコーチを利用するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。
ジョブコーチ支援の基本的な費用負担
ジョブコーチ制度は厚生労働省が推進する支援事業の一つで、基本的には無料でサポートを受けることができます。ジョブコーチ支援の運用は国の助成金で賄われているためです。
訪問型ジョブコーチの費用
訪問型ジョブコーチによる援助を提供する社会福祉法人等に対しては、助成金が支給されます。ただし、助成金の対象となる訪問型ジョブコーチは、国や地方公共団体等の委託事業費で人件費の一部または全部が支払われているものではないことが必要です。
企業在籍型ジョブコーチの費用
自社で雇用する対象労働者の職場適応のために企業在籍型ジョブコーチによる支援を行う事業主に対しても、助成金が支給されます。厚生労働省は、企業在籍型ジョブコーチによる支援を行う事業主に「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」を支給しています。
ジョブコーチになるための研修費用
ジョブコーチになるには、厚生労働大臣が指定する民間の養成機関で研修を受講する必要があります。研修費用は5万円前後ですが、旅費が別途必要となります
ジョブコーチ(職場適応援助者)に関する助成金制度とは?
ジョブコーチ(職場適応援助者)に関する主な助成金制度は、以下の2つです。
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
この助成金は、障害者の職場適応のために職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して支給されます。
支給要件
対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)地域障害者職業センター(以下、地域センター)が作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせることが必要です。
対象労働者
次のいずれかに該当する者です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 難治性疾患のある方
- 高次脳機能障害のある方
- 上記以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
支給額
例えば、訪問型ジョブコーチの場合は、次の①と②の合計額が支給されます。
①支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円)
b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日 8,000円)
②訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6ヵ月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
この助成金は、障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直し、柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して支給されます。
支給要件
次の7つのいずれかの措置を講じる場合に受給することができます。
- 柔軟な時間管理・休暇取得
- 短時間労働者の勤務時間延長
- 正規・無期転換
- 職場支援員の配置
- 職場復帰支援
- 中高年障害者の雇用継続支援
- 社内理解の促進
対象労働者
基本的に「障害者職場適応援助コース」の対象労働者と同じですが、措置内容によって若干、異なっています。
支給額
7つの措置ごとに異なります。例えば、①柔軟な時間管理・休暇取得の場合は、対象労働者1人当たり6万円(中小企業は8万円)、支給対象期間1年が2期に分けて支給されます。
障害者雇用の課題解決に、ジョブコーチ支援を活用しよう!
ジョブコーチは、障害者の職場定着と事業主の障害者雇用を効果的に支援する重要な制度です。障害者一人ひとりの特性に合わせた具体的な支援計画のもと、本人への業務遂行支援、事業主への障害理解促進、家族への助言など、多角的なアプローチで障害者の職場適応を図ります。
利用する際の費用は基本的に無料で、助成金制度も整備されています。障害者雇用で課題を抱える企業は、ジョブコーチ支援を積極的に活用することで、障害者が長期的に活躍できる職場環境の実現が期待できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【申請書ひな形付き】産休とは?取得条件や給付金、会社の手続きまとめ
Point産前産後休業(産休)とは産休とは、労働基準法で定められた出産前後の母体保護のための休業制度で、雇用形態を問わず全ての女性労働者が取得できる権利です。 全女性が対象: 正社…
詳しくみる産休退職で後悔しないために!手当金の条件、退職の伝え方を解説
産休後の退職を検討している方も多いのではないでしょうか? 産休前に退職すると、出産手当金・育児休業給付金のいずれももらえなくなるなど、さまざまな影響があります。 しかし、一定の条件…
詳しくみる退職証明書の発行ルールやもらい方、離職票との違い【テンプレ付】
退職証明書は、その会社を退職したことを証明するための書類で、法律にもとづいて請求できる書類です。転職先への提出や、国民健康保険への切り替え手続きなどで必要になります。しかし、「離職…
詳しくみる労働契約法第10条とは?就業規則や不利益変更、違反例をわかりやすく解説
就業規則の変更を考えているものの、労働者の同意が得られない、または労働者に不利益になる内容を盛り込みたいといった悩みは、多くの人事・労務担当者や経営者が抱える問題です。 労働契約法…
詳しくみる正社員とは?メリット・デメリットや種類について解説!
正社員とは、労働契約の定めがなく企業に直接雇用される従業員のことです。一般的な正社員は、これらの要件に加えフルタイムで働くケースが多いでしょう。今回は、正社員のメリット・デメリット…
詳しくみる社宅の退去費用を負担するのは企業?入居者?相場やトラブルの対応策を解説
社宅は従業員の住環境を支援する制度です。しかし、退去時の費用負担をめぐってトラブルが起こるケースも少なくありません。 本記事では、社宅退去時にかかる費用の種類や相場、企業と入居者の…
詳しくみる