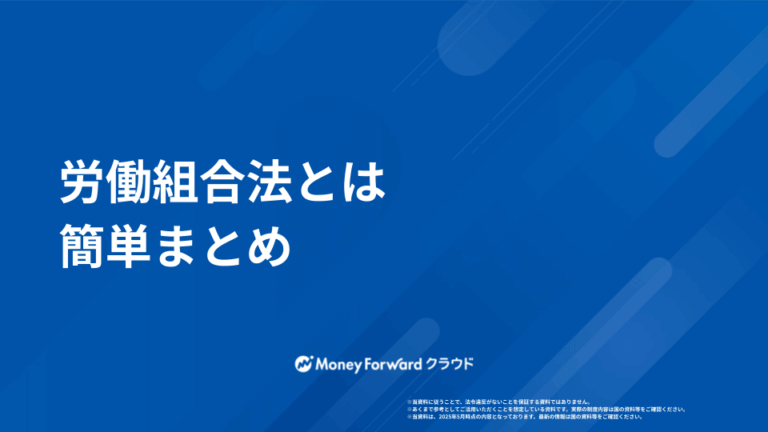- 更新日 : 2025年12月24日
労働組合法とは?労働三法の違いやメリット、違反した場合の罰則を解説!
労働者は、雇用する使用者に対して弱い立場に置かれがちです。そのため、労働者を保護するために、労働基準法などの法律が定められています。
当記事では、労働三法のひとつである労働組合法について解説します。労働三法それぞれの特徴や労働組合加入のメリット・デメリットなどについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
労働組合法とは?
「労働組合法」は、労働者が団結することによって労働組合を結成し、使用者と団体交渉を行い、ストライキなどの団体行動をする権利を定めた法律です。労働者と使用者が労働条件の維持改善のために行う交渉において対等な立場に立つことを促進し、労働者の経済的地位を向上させることを目的としています。
労働組合法と「労働基準法」「労働関係調整法」の3つを合わせて「労働三法」と総称します。労働基準法と労働関係調整法の内容については後述しますが、労働三法はそのいずれも労働者を守るための法律です。
現行の労働組合法は、1949年に制定・施行されています。現行法に通じる旧労働組合法は戦後間もない1945年に制定されており、労働組合法は労働三法の中でも最も古い歴史を持つ法律です。
労働組合とは
労働組合法は、労働条件の維持改善を図るために労働者が自主的に組織する団体である「労働組合」について定めています。労働組合法で定義される労働組合とは、次のような条件を満たす団体または連合団体を指します。
- 労働者が主体となって自主的に組織されている
- 労働条件の維持改善そのほか、労働者の経済的地位の向上を目的としている
- 監督的立場にある労働者や使用者の利益を代表する者の参加を許していない
- 団体運営のために必要な経費について、使用者からの経理上の援助を受けていない
- 共済事業や福利事業のみを目的としていない
- 政治運動または社会運動を行うことを主たる目的としていない
労働組合の代表者または労働組合から委任された者が、労働組合または組合員のために使用者と労働協約の締結などをはじめとする交渉を行うことを「団体交渉」と呼びます。例年春に各企業の労働組合が行う賃上げ交渉である「春闘」などが代表的な団体交渉の例となるでしょう。
労働組合の団体交渉そのほかの行為は、労働組合法の目的を達成するための正当なものであれば、刑事免責を受けるとされています。刑法第35条においては、「法令または正当な業務による行為は罰しない」と定められているためです。ただし、いかなる理由であっても暴力の行使は、正当な行為と解釈されることはありません。また、労働組合法第8条により、民事免責も受けるため民事による賠償を請求することもできません。
参考:刑法|e-Gov法令検索
労働組合法|e-Gov法令検索
争議行為とは
労働組合は、使用者との交渉において、その目的を達成するために「争議行為」を行います。争議行為には複数の種類がありますが、代表的な3つを以下で紹介します。
- 同盟罷業(ストライキ)
労働条件などの維持改善を目的として、労働者が一斉に休業を行います。集団的な労務提供の拒否により、使用者に圧力を掛ける争議行為です。ノーワークノーペイの原則から、使用者はストライキ中の労働者に賃金を支払う必要はありません。ただし、ストライキ参加者に対して、解雇などの不利益処分を科すことは「不当労働行為」として禁止されています。
- 怠業(サボタージュ)
サボタージュは、ストライキと異なり労務自体の提供は継続されますが、その質や量を意図的に低下させていることが特徴です。商品の生産量などを低下させることを通して、事業の運営を妨げ、使用者に圧力を掛けます。不利益処分を科すことが禁止されることは、ストライキの場合と同様です。ただし、サボタージュ中は、労務の不完全履行にあたるため、その分に応じた賃金カットは可能となります。
- 不買運動(ボイコット)
ボイコットでは、労働者が自社の商品やサービスに対して、組織的な購入拒否を行います。商品やサービスの購入拒否によって、使用者に直接経済的な圧力を掛けることが特徴です。なお、自社と取引関係にある第三者に自社商品の不買を働きかけることは認められません。
上記のような労働組合の争議行為に対して、使用者は作業所閉鎖(ロックアウト)を行うことで対抗します。工場などから労働者を排除し、就労させないことで賃金の支払い義務を免れます。ロックアウトによって、労働者に経済的な圧力を掛けるわけです。労働組合の争議行為同様に、使用者によるロックアウトも正当なものであれば、違法とはなりません。
労働基準法との違いは?
労働基準法は、1947年に施行された労働者の労働条件における「最低の基準」を定めた法律です。また、労使双方が対等な立場で労働条件を決定することも、法の基本理念としています。賃金や労働時間、年次有給休暇などについて、その基準を定めることで労働者の適正な労働条件の決定を図っています。
労働基準法に定められた労働条件は、あくまで最低の基準となります。そのため、労働関係の当事者は、労働基準法を下回る労働条件を設定できないことはもちろん、その向上を図るように努めなくてはなりません。たとえば、週に1日または4週4日が求められる法定休日を、週に2日または4週8日にすることは認められます。しかし、これを2週に1日や4週2日にするような休日設定は、労働基準法違反になるということです。仮に労使双方の合意があっても、このような休日設定は違法となります。
労働基準法も労働組合法も労働三法のひとつであり、労働者の権利を守るための法律であるという点も同様です。しかし、労働基準法は労働条件を定めた法であり、労働条件の交渉方法などについて定めた労働組合とは異なった法律となります。
労働関係調整法との違いは?
労働関係調整法は、1946年に施行された労働関係の公正な調整を図ることを目的とする法律です。また、労働争議(争議行為が発生または発生する恐れのある状態)の予防や解決を図ることにより、産業の平和を維持し、経済の興隆への寄与することも法の目的としています。
労働関係調整法は、労働争議により生じた紛争の調整方法や争議行為の届出義務、争議行為の制限などについて定めています。この法律により、当事者は争議行為が発生した際には、速やかに労働委員会または都道府県知事に届け出る義務を負っています。
また、労働関係調整法において定められた労働委員会による労働争議の調整には、以下のようなものが挙げられます。
- 斡旋
斡旋員が当事者の中間に立つ媒介役となって、紛争の解決を図ります。
- 調停
調停委員会が当事者の意見を聞いたうえで、調停案を作成し、双方に受諾を勧告します。
- 仲裁
仲裁委員会が労働争議の実情を調査し、裁定を行います。仲裁裁定は労働協約と同様の効力を持ちます。
労働組合法が正当な争議行為の免責などを定めているのに対して、労働関係調整法は争議行為発生の予防や発生した場合の調整方法などについて定めています。両者は非常に近しい法律ですが、労働関係調整法は具体的な制限や調整方法を定めている点で労働組合法とは異なる法律といえるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。
本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド
雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。
本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。
労働組合に入るメリットは?
労働組合は、労働者の経済的地位向上を図るための重要な団体です。厚生労働省の「令和4年労働組合基礎調査の概況」によると2022年6月における単一労働組合数は23,046組合、組合員数は999万2千人、推定組織率は16.5%となっています。
いずれの数字も前年比で減少しているとはいえ、未だに1,000万人近い組合員が存在します。では、労働組合への加入には、どういったメリットがあるのでしょうか。
団体として労働条件が交渉可能となる
労働者の立場は、どうしても雇用する側の使用者より弱くなりがちです。組織と個人では、どうしても組織の方が強い立場になってしまうでしょう。また、労働条件の改善を望んでも、ひとりではそもそもの交渉すらできない場合もあります。しかし、労働組合という団体を組織することで、企業という組織に対する対等な立場での交渉が可能となります。
不当な処分や不合理なハラスメントに対抗できる
正当な理由のない減給や解雇といった企業による不当な処分が下されることも珍しくありません。また、職場においてパワハラやセクハラが横行している場合もあるでしょう。これらの不当処分やハラスメントがあった場合に、被害者個人が訴え出てもトラブルを嫌う企業から黙殺される恐れがあります。しかし、労働組合を通して訴え出れば、企業は対応せざるを得なくなります。
従業員のモチベーションアップや人材確保につながる
労働組合への加入は、労働者だけにメリットがあるわけではありません。労働組合の活動により、労働条件や職場環境の改善が図られれば、従業員の業務への意欲も高まります。また、ハラスメントのない健全な職場であれば、求職者にも魅力的に映り、人材確保の効果も期待できるでしょう。
労働組合に入るデメリットは?
労働組合への加入は、メリットだけではありません。いくつかのデメリットも存在するため紹介します。
組合費が徴収される
労働組合に加入する場合には、組合費を支払わなければなりません。日本労働組合総連合会が公表した「第20回 労働組合費に関する調査報告」によると、正規雇用組合員の月額組合費の平均は、5,066円です。月に5,000円以上徴収されるため、年間では6万円以上の負担となります。2018年調査より100円程度低下しているとはいえ、無視できる負担額ではありません。
参考:第 20 回 労働組合費に関する調査報告|日本労働組合総連合会
組合活動に時間を割く必要がある
労働組合に加入した場合には、組合の活動に参加する必要が出てきます。通常の業務に加えて、組合活動に参加しなければならないことは大きな時間的負担となるでしょう。日々の業務に忙しく、他の活動に割く時間がないという場合には、加入を見送る必要もあるかも知れません。
脱退しづらいことがある
労働組合は、原則として任意加入の団体です。そのため、脱退も任意であることが基本となります。しかし、組合活動を通して人間関係が構築されている場合には、なかなか脱退を言い出しにくいでしょう。また、そのような例は少ないでしょうが、脱退希望者に対して度を超えた引き留めが行われる可能性もあります。
労働組合法に違反した場合の罰則は?
労働組合法においては、正当な理由なく団体交渉を拒否する「団交拒否」のような行為を不当労働行為として禁止しています。不当労働行為は、団交拒否のほかにも労働組合に加入しないこと、脱退することを雇用の条件とする「黄犬契約」などが挙げられます。
団交拒否などの不当労働行為を行ったとしても、それ自体によって、企業が直接的な罰則を科されることはありません。ただし、不当労働行為の中止を求める救済申し立てに基づいて救済命令が出される場合があり、命令に違反した場合には労働組合法第32条により50万円以下の過料が科されます。
救済命令に対しては取消訴訟を提起可能です。しかし、裁判所が救済命令を正当と認め、取消しを認めない場合もあります。そのような場合には、救済命令の内容が確定し、違反した場合には、労働組合法第28条により1年以下の禁固または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。不当労働行為による直接的な罰則がないからといって、団交拒否などを行わないようにしましょう。
労働組合法を理解し円滑な労使関係の構築を
組織率が低下の傾向にあるとはいえ、まだまだ労働組合の組合員は数多く存在します。現在労働組合が組織されていない企業でも、今後組織される可能性もあるでしょう。労働組合との交渉において、不当労働行為とされないためにも、当記事を参考にして正しい理解に努めてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働三法とは?労働三権との違いや覚え方をわかりやすく解説
労働三法は、労働者の権利を守るために制定された「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の3つの法律です。企業の人事・労務担当者にとって、これらの法律を理解し適切に運用すること…
詳しくみる【申請書ひな形付き】産休とは?取得条件や給付金、会社の手続きまとめ
Point産前産後休業(産休)とは産休とは、労働基準法で定められた出産前後の母体保護のための休業制度で、雇用形態を問わず全ての女性労働者が取得できる権利です。 全女性が対象: 正社…
詳しくみるパワハラをする人の特徴は?パワハラ防止の対策も解説
パワハラは、職場の相手に威圧感や恐怖を与える行為です。では、どのような特徴の人がパワハラ行為をするのでしょうか。パワハラ行為に及ぶ人には、いくつかの特徴があります。 本記事では、パ…
詳しくみる労働保険の保険関係成立届とは?書き方・記入例や提出方法などを解説
労働者を雇用した場合には、原則として雇用保険や労災保険といった労働保険に加入しなければなりません。その際に必要となる届出が「労働保険の保険関係成立届」です。当記事では、労働保険の保…
詳しくみる退職手続きの効率化でミス削減!具体的な方法からメリット、注意点まで徹底解説
退職手続きの煩雑さや、ミスの許されないプレッシャーに、頭を悩ませていませんか?一つひとつの手続きは単純でも、重なると大きな負担となり、対応を誤れば法的なリスクや退職者とのトラブルに…
詳しくみる退職勧奨を受けた際の退職届の書き方ガイド【例文・テンプレート付】
突然の退職勧奨に「どうしたらいいのかわからない」と困惑しているなか、さらに退職届の提出を求められ、不安や焦りを感じていませんか? 言われるがままに退職届を出してしまうと、思わぬ不利…
詳しくみる