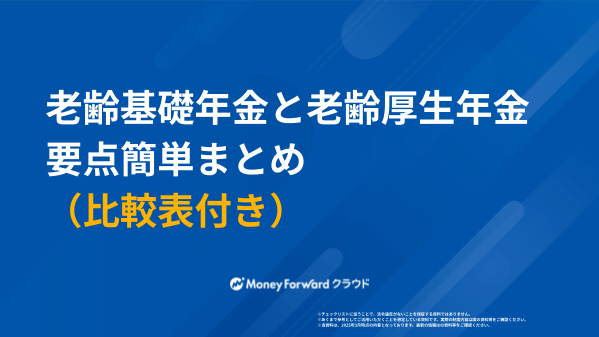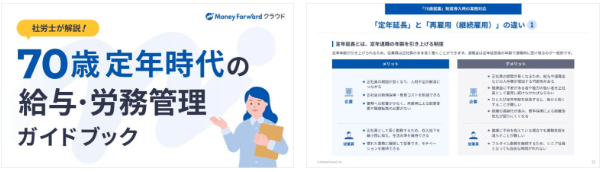- 更新日 : 2025年11月5日
老齢基礎年金・老齢厚生年金とは?受給要件・支給開始年齢・年金額の違いを解説!
老齢年金には国民年金から支払われる老齢基礎年金と、厚生年金から支払われる老齢厚生年金があります。法改正によって老齢厚生年金の支給開始年齢は引き上げられましたが、大きな影響を受ける受給者には経過的加算などの措置があります。国民年金基金や確定拠出年金などを利用することで、年金額を増額することができます。
目次
老齢基礎年金とは?
老齢基礎年金とは、国民年金による老齢年金のことです。公的年金制度には国民年金と厚生年金があり、国民年金を1階、厚生年金を2階とする2階建て構造になっています。
- 国民年金:国民全員が加入する
- 厚生年金:会社員や公務員などが加入する
老齢年金も、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされる形で支給されます。
受給要件
老齢基礎年金は以下の要件を満たす人が受給できます。
- 受給資格期間が10年以上あること
受給資格期間とは年金受給資格の判定に用いられる、保険料を納めた期間や加入者であった期間のことです。保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合計して10年以上あることが、老齢基礎年金の受給要件になっています。
- 65歳以上であること
老齢基礎年金の受給は65歳からです。ただし、65歳到達時に受給資格期間が10年以上ない場合は、その後に要件を満たした時から老齢基礎年金を受け取ることができます。また、希望した場合は60歳から65歳までの間に繰り上げ受給、66歳から75歳までの間に繰り下げ受給が可能です。
支給開始年齢の推移
老齢基礎年金支給開始年齢は65歳です。国民年金法第26条「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 」という規定によるもので、制度が発足した時から変わっていません。
年金額の計算方法
老齢基礎年金額は、定められた一律の金額です。20歳から60歳までの国民年金加入期間に未納期間がない人には、満額が支払われます。未納期間がある場合は、納付済期間に対して老齢基礎年金が支払われます。計算式は以下のとおりです。
保険料免除期間の計算方法
国民年金に加入している間に保険料の免除を受けた場合は、期間や免除された率に応じて老齢基礎年金は計算され、減額されます。老齢基礎年金の受給額の計算における保険料免除期間は、以下の表のとおりです。
| 全額免除 | 1/2ヵ月 |
| 3/4免除 | 5/8ヵ月 |
| 半額免除 | 6/8ヵ月 |
| 1/4免除 | 7/8ヵ月 |
平成21年3月分までは以下の表のとおりです。
| 全額免除 | 1/3ヵ月 |
| 3/4免除 | 1/2ヵ月 |
| 半額免除 | 2/3ヵ月 |
| 1/4免除 | 5/6ヵ月 |
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
老齢厚生年金とは?
老齢厚生年金とは、厚生年金から支給される老齢年金のことです。会社員や公務員など、厚生年金に加入していたことのある人に支給されます。
受給要件
老齢厚生年金は、以下の要件を満たす人が受給できます。
- 老齢基礎年金を受け取れること
受給資格期間とは年金受給資格の判定に用いられる、保険料を納めた期間や加入者であった期間のことです。保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合計して10年以上あることが、老齢基礎年金の受給要件となっています。 - 65歳以上であること
老齢基礎年金の受給は65歳からですが、老齢基礎年金と同じように繰上げ支給や繰下げ支給ができます。特別支給の老齢厚生年金の支給対象者には、60歳から64歳までの間に支給が開始されます。
支給開始年齢の推移
現在の老齢厚生年金の支給開始年齢は男子、女子ともに65歳です。厚生年金保険法は、労働者年金保険法として制定・施行された後、下記のように数度の改正を経て現在に至っています。
- 昭和17年
男子55歳・女子は適用外(労働者年金保険法制定) - 昭和19年
男子、女子ともに55歳(厚生年金保険法に改称) - 昭和29年
男子60歳に引き上げ(昭和32年度から16年をかけ4年に1歳ずつ引き上げ)
女子は55歳のまま - 昭和60年
男子65歳に引き上げ(60~65歳まで特別支給の老齢厚生年金を支給)
女子60歳に引き上げ(昭和62年度から12年をかけ3年に1歳ずつ引き上げ) - 平成6年
定額部分について男子、女子ともに65歳に引き上げ
男子は平成13年度、女子は平成18年度から12年をかけ3年に1歳ずつ、男子65歳に引き上げ
- 平成12年
報酬比例部分について男子、女子ともに65歳に引き上げ
男子は平成25年度、女子は平成30年度から12年をかけ3年に1歳ずつ、男子65歳に引き上げ
年金額の計算方法
老齢厚生年金は、報酬比例年金額・経過的加算・加給年金の合計額が支給されます。
報酬比例年金額
老齢厚生年金の報酬比例年金額は厚生年金の加入期間や報酬によって求められる、年金額計算の基礎となる金額です。
平成15年3月以前と平成15年4月以降に分けて、以下のように計算します。
▼ 平成15年3月以前
※平均標準報酬月額:各月の標準報酬月額の総額/平成15年3月以前の加入期間の月数
▼ 平成15年4月以降
※平均標準報酬額:各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額/平成15年4月以降の加入期間の月数
報酬比例部分の給付乗率※は昭和21年4月1日以前に生まれた方は異なります。
経過的加算
65歳以降に受け取る老齢基礎年金額が特別支給の老齢厚生年金の定額部分より少ない場合に、経過的加算が老齢厚生年金に加算されます。経過的加算の金額は、以下の計算式で算出します。
加給年金
厚生年金に20年以上加入していた人が老齢厚生年金を受けられるようになった時に、配偶者や子どもを扶養している場合は加給年金が加算されます。加給年金の対象者と金額は以下のとおりです。
- 加給年金の対象者
- 65歳未満の配偶者
- 18歳に到達する年度末(障害等級1級・2級の場合は20歳)までの子ども
- 加給年金の金額
対象者が配偶者である加給年金には、特別加算も上乗せされます。特別加算は、老齢厚生年金受給者の生年月日によって以下のように変わります。配偶者につき 22万3,800円 2人目までの子ども1人につき 22万3,800円 3人目以降の子ども1人につき 7万4,600円 - 特別加算額
受給者の生年月日 特別加算額 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日まで 3万3,100円 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで 6万6,000円 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日まで 9万9,100円 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日まで 13万2,100円 昭和18年4月2日以後 16万5,100円
老後にもらえる公的年金の受給額は増額できる?
老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給額は計算で求められる金額と定められていますが、増額できる方法がいくつかあります。自営業者などの国民年金第1号被保険者が老齢基礎年金を増やすために利用できるのが、付加年金と国民年金基金です。会社員や公務員などの厚生年金加入者(国民年金第3号被保険者)は、以下の方法で公的年金を増やすことができます。
平均標準報酬額を上げる
平成15年4月以降、老齢厚生年金は前述のとおり以下の式で受給額が計算されます。
※平均標準報酬額:各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額/平成15年4月以降の加入期間の月数
厚生年金加入者は、報酬比例部分を増やすことによって老齢厚生年金の受給額を増やすことができます。報酬比例部分を増やすには、平均標準報酬額を上げる必要があります。具体的な方法としては、「昇給する」「長く勤務する」の2つが考えられます。
繰り下げ受給をする
繰り下げ受給をすると老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに年金受給額が割り増しになります。割増率は0.7%です。ひと月繰り下げるごとに0.7%ずつ割り増しになり、認められている繰り下げ受給で最も遅い75歳からの受給とすると、84%の割り増しになります。
公的年金の上乗せとして企業年金制度も!
企業年金制度は、年金額を増やす方法の一つです。厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の3種類がありますが、厚生年金基金は平成25年の法改正により新規設立ができなくなりました。
企業年金について以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。
厚生年金基金
従業員に手厚い老後保障を行うため、大企業によって設立されるのが厚生年金基金です。国に代わって老齢厚生年金の一部を支給するほか、さらに独自で上乗せして給付します。年金制度の健全性や信頼性確保のため、平成26年4月1日以降は新規設立ができなくなりました。
確定給付企業年金
確定給付型企業年金は、あらかじめ給付額が定められている年金制度です。労使の合意による柔軟な制度設計が可能、給付額が決まっているため将来設計がしやすい、といったメリットがあります。労使合意による規約に基づいて年金資金の管理・運用を行う「規約型」と、母体企業とは別の法人格を持った基金において年金資金の管理・運用を行う「基金型」があります。
確定拠出年金
確定拠出年金は加入者ごとに区分される拠出掛金と、自らの指図によって生じた運用益との合計額から給付される年金額が計算される年金制度です。拠出を企業が行う「企業型確定拠出年金」と、個人が行う「個人型確定拠出年金」があります。
将来への備えとして、公的年金制度や企業年金制度の仕組みをよく理解しよう
老齢になった際に受け取る公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢基礎年金は国民年金から、老齢厚生年金は厚生年金保険から支払われます。老齢基礎年金額は保険料納付済期間などで定額ですが、老齢厚生年金額は加入していた期間や報酬を用いて計算されるため、人によって支給額が異なります。老齢厚生年金額を増やす方法としては、昇給や長く勤務することで平均標準報酬額を上げる、繰り下げ受給で割り増しを受ける、といったものが考えられます。
将来の年金額は、企業年金制度を活用することでも増やせます。公的年金制度や企業年金制度の仕組みを正しく理解して、将来に備えましょう。
よくある質問
老齢基礎年金とは?
老後に受け取る老齢年金のうち、国民年金から支払われる年金です。詳しくはこちらをご覧ください。
老齢厚生年金とは?
厚生年金保険に加入していた人が老齢基礎年金を受け取れるようになった場合に、厚生年金保険から支払われる年金です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
配偶者の扶養に入ったまま社会保険には加入できる?外れる条件や手続き
会社員の配偶者(妻や夫)がパートタイマーで働いている場合、収入によっては扶養から外れて所得税の控除を受けられなくなったり、配偶者自身に社会保険の加入義務が生じて新たに保険料負担をし…
詳しくみるうつ病の休職期間の目安は?過ごし方や退職・復職のポイントも解説!
うつ病による休職は、企業の人事担当者にとって慎重な対応が求められる課題です。労働者の健康と職場の生産性のバランスを取りながら、適切な休職期間の設定や復職支援を行うことが重要となりま…
詳しくみる社会保険料について本人は何割負担?負担割合を解説!
社会保険の保険料は毎月給与から天引きで徴収されるため、本人は何割負担か意識したことがないかもしれません。健康保険と厚生年金保険の保険料は労使折半となっています。医療費の自己負担割合…
詳しくみる産休の社会保険料免除はいつから?免除の仕組みは?【産休申請書のテンプレ付き】
産休を取得している間、申請することにより会社と従業員双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが一定期間免除されます。これは従業員と企業の負担を軽減するためで、免除された期間も…
詳しくみる労災保険の休業補償とは?支給要件や申請手続きの流れをまとめて解説
企業において、労働者が業務中の事故や業務に起因する病気によって休業を余儀なくされた場合、労災保険の休業補償給付が適用になります。 この制度は、労働者が業務上の理由で働けなくなった際…
詳しくみる令和7年度の労災保険料率は?金額の計算方法もシミュレーションつきで解説
労災保険料率は、労災保険料の計算に用いられる料率です。 労災事故が起こりやすい危険な業種ほど労災保険料率が高く設定され、危険が少ない安全な業種には低い労災保険料率が設定されています…
詳しくみる