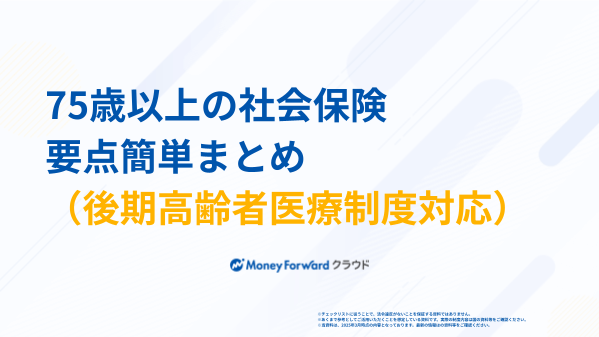- 更新日 : 2025年10月31日
75歳以上の社会保険手続きは?後期高齢者医療制度や被扶養者についても解説!
定年年齢の引き上げの流れが象徴するように、生活費の確保や社会とのつながりなど、定年年齢を超えても働き続ける方が増えています。
高齢の従業員を雇用する場合には、職場環境の配慮はもちろんのこと、通常の社会保険加入とは手続きが異なることに注意しなければいけません。ここでは、75歳以上の方の社会保険の手続きについて解説します。
目次
75歳以上の社会保険手続きは?
会社に雇用される従業員が加入する健康保険は、原則として75歳までの方を対象としています。75歳以上の社会保険(健康保険)については、以下の3点を押さえておく必要があります。
健康保険の被保険者資格を失う
75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格を失います。退職後、健康保険の任意継続被保険者であった方も同様に被保険者資格を失います。
もし、75歳になる前から雇用されている場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出し、健康保険に加入していたときの健康保険被保険者証および高齢受給者証を事業者が回収し、保険者に返却する必要があります。
提出の期限は、資格喪失の日である75歳の誕生日から5日以内です。また、被保険者が資格を喪失した場合には、75歳未満の扶養されている方も同時に被扶養者でなくなるため、従業員が住んでいる市区町村で国民健康保険に加入する手続きが必要となるため注意が必要です。
後期高齢者医療制度に自動加入
75歳以上の方は、健康保険の被保険者資格を喪失した後、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者へと移行します。加入は自動的に行われるため、手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方々を国全体で支える制度です。保険制度の運営で必要となる財源の半分を公費で負担し、4割を健康保険に加入している現役世代からの支援金で負担、残りの1割を被保険者が保険料として納めています。後期高齢者医療制度は、各都道府県の区域ごとにある広域連合によって運営されており、すべての市区町村がその都道府県ごとに設置された広域連合に加入しています。
後期高齢者医療制度の被保険証は、誕生月の前月頃、運営元となる市町村より本人に送付されます。
退職後、健康保険の任意継続被保険者だった場合も同様
退職後、健康保険の任意継続被保険者だった方も、同様に健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行することとなります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
75歳以上の被扶養者の社会保険手続きは?
健康保険に加入している被保険者に被扶養者の要件を満たす家族がいれば、被扶養者として健康保険の給付を受けることが可能です。しかし、被保険者自身が75歳になると健康保険の資格を失い、後期高齢者医療制度に移行するため、たとえ被扶養者が75歳未満だったとしても健康保険の被扶養者の資格を喪失します。
健康保険の被扶養者資格を失う
75歳未満であるにもかかわらず、健康保険の被扶養者資格を喪失するのは、その方を扶養していた被保険者が資格を喪失するためです。被扶養者資格を喪失した家族は、なんらかの健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入
被扶養者である方が、どこからも雇用されていない場合、選択肢としては国民健康保険の加入が考えられます。また、被扶養者自身が企業に雇用されることで、勤務先の健康保険や健康保険組合に加入することも可能です。この場合、75歳以上の家族は後期高齢者医療制度に加入しているため、被扶養者にすることができないことに注意しましょう。
国民健康保険の加入手続きは、住んでいる市区町村の役所で被扶養者ではなくなった日から14日以内に行います。手続きにあたっては、健康保険の資格喪失証明書など健康保険の資格を喪失した日がわかる書類が必要です。世帯主と本人のマイナンバーが確認できるものや本人確認書類も必要となりますので、あらかじめ必要書類を確認してから手続きをしましょう。
75歳以上の被扶養者は社会保険料を軽減できる?
健康保険に加入していた被保険者が75歳以上となり、後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合、被扶養者が65歳以上75歳未満の場合は、保険料の軽減措置が受けられます。
この保険料の軽減措置は、75歳になるまでです。被扶養者であった方が75歳以上となった場合には、後期高齢者医療制度に移行しますので軽減措置はなくなります。
75歳となった人の被扶養者の社会保険手続きに注意する
健康保険の被保険者が75歳以上になり後期高齢者医療制度に移行すると、その方の被扶養者は、同時に健康保険の被扶養者資格を喪失するため、なんらかの健康保険に加入しなければいけません。
被扶養者本人が働いている場合には、勤務時間を長くしてもらうなどして、勤め先の健康保険に加入するのも1つの方法です。無職や自営業であれば、国民健康保険に加入します。被扶養者だった方が60歳未満の場合には、国民健康保険だけではなく、国民年金に加入しなければいけないことも覚えておきましょう。
被扶養者の方が65歳以上75歳未満のあいだは、保険料の軽減措置が受けられるため、お住まいの市区町村で事前に確認してから手続きをしましょう。
よくある質問
75歳以上の社会保険手続きは?
75歳の誕生日に健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度に移行するため、会社を通じて「被保険者資格喪失届」を提出し、それまでの被保険者証を返納する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
被扶養者は社会保険料を軽減できる?
健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した場合、それまで被扶養者だった方も被扶養者ではなくなるため、国民健康保険等に加入します。被扶養者が65歳以上75歳未満であれば保険料の軽減措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
従業員の結婚に関する社会保険・雇用保険の変更手続きは?
従業員から結婚の報告があった場合に人事担当者がまず行うのが結婚に伴う各種手続きになります。手続きを行うためには、従業員に確認すべき項目や変更に伴い必要な手続きについて理解する必要が…
詳しくみる社会保険診療報酬支払基金とは? 保険医療機関との関わり
社会保険支払基金(社会保険診療報酬支払基金)は、病院などの保険医療機関で働いている人にとって目にする機会の多い名称ではないでしょうか。診療費の請求やレセプトの送付など、日々の業務で…
詳しくみる標準報酬月額とは?決め方や計算方法、間違えた場合をわかりやすく解説!
毎月の給料から、標準報酬月額をもとにした社会保険料が控除されています。この標準報酬月額は、1年に1度の定時決定や、報酬額が大きく変わった場合に行われる随時改定などで決定されます。こ…
詳しくみる退職後も出産手当金がもらえる?要件と手続きについて解説!
出産手当金は被保険者が出産のために休職し、その間に給与を得られなかった場合に支給される給付金です。 このお金は、在職中の休業であれば受け取ることができますが、受け取る前後において退…
詳しくみる健康保険の切り替えの手続き
会社員の場合、事業主の手続きにより健康保険に加入していますが、退職した場合の健康保険はどうなるのかご存知でしょうか。 退職した場合は社会保険資格を喪失してしまうため、国民健康保険に…
詳しくみる扶養に入る条件とは?税法上・社会保険上の違いや対象となる親族範囲など詳しく解説
従業員の家族を扶養に入れる際、もっとも重要なのは税法上と社会保険上で条件が異なる点を正しく理解することです。これらを混同すると、給与計算のミスや保険証の未交付、最悪の場合は遡及して…
詳しくみる