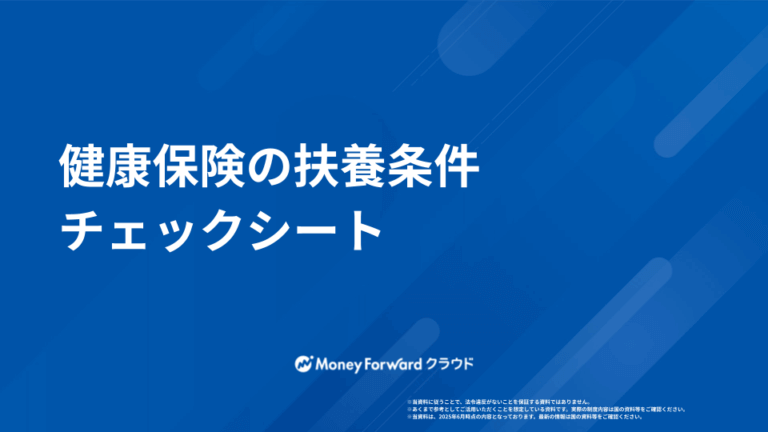- 更新日 : 2025年7月30日
健康保険の扶養条件 所得税法などとの違いを比較
従業員の給与計算をしたり、社会保険の手続きを取ろうとして混乱したりすることが多いのは「扶養家族はどの範囲までなのか」という扶養基準です。これは、健康保険での扶養基準と、ほかの扶養基準が異なることに関係しているようです。
ここでは健康保険での扶養基準を軸にして、ほかの扶養基準とはどのように違うのかを見ていきます。
健康保険での扶養基準
まず、健康保険における扶養条件には複数のとポイントがあります。
まず、「同居しているかいないか」が前提となる重要なポイントです。そしてその次に、扶養基準の範囲と年収など収入要件を満たすかどうかで扶養基準は異なります。
それぞれのポイントから扶養基準を確認してみましょう。
扶養基準における被扶養者の範囲
別居の場合の扶養基準
健康保険での別居の場合の扶養基準において、被扶養者として認められるのは、父母や配偶者、兄弟姉妹、子、祖父母、孫です。
同居の場合の扶養基準
健康保険での同居の場合の扶養基準において、扶養者と同居している事実があれば、親族でも認められます。ただし、3親等内の親族に限られます。3親等とは、父母の兄弟姉妹、甥姪です。3親等の配偶者も認められます。
なお、配偶者が内縁関係であってもかまいません。その配偶者の父母や、配偶者の子供も配偶者生存中はもちろん、配偶者が死亡した後に引き続いて同居している場合も認められます。
被扶養者の収入要件
健康保険での年間収入による扶養基準において、大前提となるのが年間収入額です。その額が130万円未満でなければ扶養とは認められません。
年間収入とは、給与によるもの(賞与や手当などを含む)のほか、事業所得、傷病手当や出産手当金などの手当金、公的年金、給付金(雇用保険の失業給付など)を合わせたものになります。
別居の場合の扶養基準
年間収入が130万円未満で別居している場合は、この年間収入額が被保険者から援助される額に満たななければに、扶養家族として認められます。被保険者からの援助とは、仕送りなどによる受け渡しがあった年間合計額です。
年間収入の130万円未満という扶養基準は、60歳以上が対象となる場合には180万円未満となります。障害のある人(障害厚生年金該当者)の場合も同様です。
同居の場合の扶養基準
年間収入が130万円未満で同居している場合は、家族の年間収入が被保険者の2分の1未満である場合に被扶養者として認められます。
また、世帯の状況によっては、年間収入が被保険者の年間収入の半分を上回っても、全額を上回らなければ、被扶養者として認められる場合があります。
なお、この場合の同居は、住民票に記載された住所を同じくする同一世帯であることが求められます。
※平成28年10月より、年間収入が130万円以下未満であっても一定の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は健康保険の被保険者として加入対象になり被扶養者から除かれることになります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
厚生年金保険と健康保険での扶養基準の違い
厚生年金の場合、被扶養者として認められるのは配偶者のみで、健康保険の被扶養者の範囲と大きく違っています。しかも、年齢が20歳以上60歳未満と限定されています。
収入に関しての制限については健康保険と同様です。この被扶養者は国民年金の第3号被保険者と呼ばれ、保険料は加入する組織(厚生年金または共済組合)の負担となります。
所得税法上と健康保険での扶養基準の違い
会社の経理では、扶養控除や配偶者控除として所得税の計算をする際にも扶養基準を確認する必要があります。
扶養控除と配偶者控除という2つの控除における扶養基準から、所得税法上と健康保険との違いを見てみましょう。
扶養控除での扶養基準
所得税法上の扶養控除における被扶養者の要件は、以下のとおりです。
1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この4つに当てはまれば、所得税申告の際に扶養控除(扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)を受けることができます。健康保険では年間収入が130万円未満を前提としている部分が違います。
所得税に関わる扶養控除について詳しくはこちらのページをご参照ください。
配偶者控除での扶養基準
所得税法では、配偶者に対して扶養控除とは別に、配偶者控除という制度を設けています。健康保険では被扶養者の範囲を配偶者に限定していないので、まずこの点が違います。
所得税法では、原則として配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下の場合に配偶者控除が適用されます(控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません)。
しかし、合計所得金額の計算は、所得の種類によって異なります。
所得が給与によるものだけである場合、その年間合計額から給与所得控除額を引いた額が38万円以下であれば配偶者控除が適用となります。(2020年分以降、配偶者の年間所得が48万円以下の場合に対象 )給与のほかにも不動産や譲渡、一時所得などがあれば、給与所得控除後の金額にその他の所得の金額を足して38万円以下となる場合に適用されます。
また、令和2年から配偶者控除・配偶者特別控除の改正がおこなわれ配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合で、控除をうける納税者本人の合計所得金額が900万円超え1000万円以下の場合には一定(最大38万円)の配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除の要件について、より詳しい解説は「年末調整における配偶者控除」のページよりご確認ください。
まとめ
健康保険での扶養基準はとても広い範囲に及んでいます。この基準で所得税の処理をしてしまうと、税務署の指摘を受けて申告をし直さなければならなくなったりします。また、延滞税や加算税などが発生することもありますので、これらを混同しないように注意が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金の受給に必要な加入期間 – 10年未満の場合はどうなる?
日本の公的年金制度は2段階です。会社勤めで厚生年金保険に加入していた方は、国民年金の制度で受け取れる老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金が上乗せされます。 国民年金の支給額が年間約78…
詳しくみる社会保険の種類について解説!一覧表付き
社会保障制度のなかでも最も身近に感じるのが社会保険制度といえるでしょう。病気やケガの際には医療保険や労災保険、老後の生活には公的年金、会社退職時には雇用保険と、誰にとっても頼りにな…
詳しくみる社会保険の休業補償とは?金額や手続きについて解説
休業補償給付とは、業務災害にあった従業員の生活の保護を目的とする社会保険(労働保険)の1つ、労災保険の制度です。企業として労働災害は軽視できない問題であり、労災事故を発生させない仕…
詳しくみる育児休業給付金の80%引き上げはいつから?人事労務担当者が注意するポイントも解説
2025年4月1日より、育児休業給付金の実質給付率が80%(手取り10割相当)へ引き上げられました。これは新設された「出生後休業支援給付金」によるものですが、「夫婦ともに通算14日…
詳しくみるマイナ保険証とマイナンバーカードの違いは?マイナ保険証のメリットや従来の健康保険証との違いも解説
「マイナ保険証」は、身近なマイナンバーカードと深く関係する新しい仕組みですが、両者の違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 2024年12月2日から健康保険証はマ…
詳しくみる年金受給者の方必見!所得税がかかる場合とかからない場合
年金は税法上の雑所得にあたるため、所得税がかかります。しかし、中には所得税が免除される場合もあります。所得税が免除される場合、所得税がかかる場合の源泉徴収のプロセス、また、確定申告…
詳しくみる