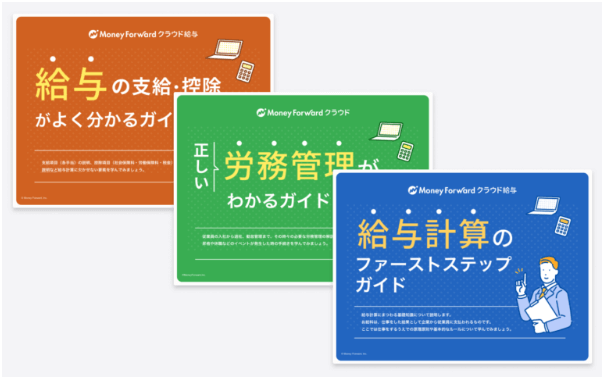- 更新日 : 2025年2月21日
賞与の控除額の計算・シミュレーション例!手取り額を増やす方法は?
会社員にとって、賞与(ボーナス)の支給は楽しみなイベントのひとつです。
しかし、明細を見ると各種社会保険料や所得税が控除の対象として引かれており、実際に手にする金額が減ってガッカリしてしまうことがありますよね。
この記事では、賞与の各種控除の計算方法やシミュレーション、そして控除額を増やすための節税方法を解説します。
目次
賞与の控除とは?計算方法と合わせて解説
賞与の控除とは、賞与から社会保険料などの税金が差し引かれることです。
賞与からは毎月の給与と同様に社会保険料と所得税が控除され、実際の支給額(手取り)は控除後の金額になります。
しかし、住民税の計算については、賞与と毎月の給与は計算方法が異なります。
住民税は前年の総所得から計算し、毎月の給与から定額で控除されているため、賞与からは控除されていません。
賞与の手取り金額の計算式は、下記のようになります。
社会保険料の種類 所得税の種類
|
年収やその他条件で変動しますが、一般的に賞与からの控除額は総支給額の10%代後半から30%程度と考えてよいでしょう。
賞与と住民税の関係について、より詳しくは下記記事をご確認ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
賞与計算規程(エクセル)
賞与計算に関する取り決めを整備するための、エクセル形式の規程テンプレートです。貴社の規定や運用に合わせて手軽に内容を修正・カスタマイズいただけます。
スムーズな運用開始をサポートする実用的な資料としてご活用ください。
賞与計算(社会保険料計算)シート
賞与支給額の算出および、社会保険料の計算に対応した実務用シートです。
計算業務の効率化と円滑な事務処理をサポートする資料として、ぜひダウンロードしてご活用ください。
給与計算ミスを防ぐ60のチェックリスト<完全版>
給与計算ミスの発生を防ぐため、雇入れ直後・異動直後などのシーン別に確認すべきポイントを完全保存版・チェックリストとしてまとめました。
起こりやすいミスの傾向についても解説していますので、ぜひ業務にお役立てください。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
賞与の各控除の種類について
この章では、賞与にかかる控除の種類について解説していきます。
社会保険料は4種類
4種類ある社会保険料の仕組みや計算式を、それぞれ解説します。なお、労災保険料も社会保険料に含まれますが、こちらは事業主のみが負担し、従業員の負担はありません。
健康保険料
健康保険料は医療費の負担軽減や死亡時の保障などを目的とした、医療保険制度に使われています。
健康保険料の控除額はまず賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てて「標準賞与額」を算出し、そこに健康保険料率を掛けて計算します。
保険料は事業主と従業員がそれぞれ半分ずつを負担する、労使折半の形です。
計算式
健康保険料=標準賞与額(1,000円未満切り捨て)× 健康保険料率÷2
※2で割るのは労使折半のため。
健康保険料率は全国一律ではなく、加入している健康保険組合や事業所が所在する都道府県によって異なります。
例として、協会けんぽ(全国保険協会)の場合はおおむね10%前後です。
また、標準賞与額には上限が設けられており、4月1日から翌年3月31日までの1年間で累計573万円が上限になります。
参考:都道府県ごとの保険料額表│全国健康保険協会(協会けんぽ)
介護保険料(40歳から適用)
介護保険料は介護保険制度を支えるために使われており、40歳から64歳までの従業員にのみ適用されます。
介護保険料も健康保険料と同様に標準賞与額を基準に計算され、労使折半となります。
計算式
介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率(1.6%)÷2
※介護保険料率は協会けんぽの令和6年3月分を採用。
介護保険料率の保険料率も組合によって異なりますが、協会けんぽの場合は全国一律となっています。
また、標準賞与額の上限は健康保険料と同じ年額573万円となります。
参考:協会けんぽの介護保険料率について│全国健康保険協会(協会けんぽ)
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、老後の年金受給や障害年金などを支えるために使われています。
こちらも「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算し、労使折半である点も健康保険料・介護保険料と同様です。
2025年2月時点の保険料率は都道府県や保険組合に関わらず一律18.3%です。
この料率は2017年以降、変更されていません。
計算式
厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 18.3% ÷ 2
標準賞与額の上限は、1ヶ月につき150万円です。
また、何らかの理由で1ヶ月に複数の賞与が支給された場合は、賞与の総支給額を合わせて計算します。
厚生年金保険料の上限は長らく変更がありませんでしたが、2027年9月から賞与を含まない年間の給与が798万円以上の会社員を対象に、増額する方向で調整されています。
現時点では確定というわけではありませんが、気になる方は今後の発表を注視していきましょう。
参考:年収798万円以上の厚生年金保険料、月額9000円増額へ…通常国会に関連法案を提出予定│ 読売新聞
雇用保険料
雇用保険料は、失業給付や育児休業給付金などの社会保障のために使われています。
これまで説明した他の社会保険料とは異なり、総支給額の全額に保険料率を掛けて計算し、
1,000円未満の切り捨ても行いません。
そして、労使間で保険料を折半するのではなく、業種によって負担率が異なります。
計算式
雇用保険料 = 賞与支給額 × 雇用保険料率
※1円未満の端数について:50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ
▼業種による負担率の違い
| 雇用保険料率 | ||
|---|---|---|
| 従業員負担分 | 会社負担分 | |
| 一般の事業 | 0.60% | 0.95% |
| 1.55% | ||
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.70% | 1.05% |
| 1.75% | ||
| 建設の事業 | 0.70% | 1.15% |
| 1.85% | ||
雇用保険料率について、令和6年度は5年度と同じ保険料率になっていますが、毎年見直される可能性があります。
その都度、最新の保険料率を確認しましょう。
所得税
所得税は、道路や橋の整備、国防関連など国の根幹を支えるために使われています。
賞与にかかる所得税は、社会保険料と比べると少し複雑になります。
計算式
所得税={賞与支給額-社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)}×賞与に対する源泉徴収税率
※1円未満の端数は切り捨て
この「賞与に対する源泉徴収税率」は、前月の給与から社会保険料を控除した金額と、扶養親族の数に基づいて決定されます。
また、所得税の税率は0%から45.945%まで、所得に応じて段階的に設定されています。
この仕組みは累進課税制度と呼ばれ、所得が多いほど高い税率が適用されます。
所得税に関して、その他の注意点を下記にまとめました。
より詳しくは関連記事をご確認ください。
関連記事:「賞与・ボーナスの所得税・社会保険料が高いと感じるのはなぜ?税金の計算方法を解説」
3パターンで計算!賞与控除後の手取り額シミュレーション例
上記の計算式を参考に、この章では3つのモデルケースで賞与の手取り額を計算しました。
| 条件 | ケース1(若手単身) | ケース2(子育て世代) | ケース3(ベテラン社員) | |
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 年齢 | 26歳 | 31歳 | 45歳 |
| 会社所在地 | 東京都 | 愛知県 | 大阪府 | |
| 前月給与 | ¥250,000 | ¥280,000 | ¥380,000 | |
| 業種 | 一般 | 建設 | 一般 | |
| 扶養家族 | なし | 2人 | 3人 | |
| 控除項目 | 健康保険料 | ¥9,980 | ¥20,040 | ¥33,605 |
| 介護保険料 | – | – | ¥5,200 | |
| 厚生年金保険料 | ¥18,300 | ¥36,600 | ¥59,475 | |
| 雇用保険料 | ¥1,200 | ¥2,800 | ¥3,900 | |
| 所得税 | ¥6,964 | ¥13,908 | ¥33,559 | |
| 最終支給額 | 支給総額 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥650,000 |
| 控除合計 | ¥36,444 | ¥73,348 | ¥135,739 | |
| 控除割合 | 18.22% | 18.34% | 20.88% | |
| 手取り額 | ¥163,556 | ¥326,652 | ¥514,261 |
※協会けんぽへの加入を想定しています。
3パターンのシミュレーション結果を参考に、実際の手取り額の目安にしてみてください。
そもそもなぜ賞与からの控除がある?
「そもそもなぜ控除があるの?」「税金で引かれすぎでは?」と思われる方もいるかもしれません。
各種税金は、社会を維持するための財源として使われています。
賞与から控除された税金が何に使われているのかを、下記へ簡単にまとめました。
| 項目 | 使い道 |
|---|---|
| 健康保険料 |
|
| 介護保険料 |
|
| 雇用保険料 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
| 所得税 |
|
このように、控除された税金は公共施設の整備や医療介護など、生活の基盤を支える財源として活用されています。
いつから控除は始まった?
賞与から現在のように社会保険料が控除されるようになったのは、2003年4月からです。
2003年3月までは「特別保険料」という名前で賞与には1%の保険料率が適用されており、労使(労働者と会社)が0.5%ずつ保険料を負担していました。
しかし、企業が月給を減らし賞与の割合を多くすることで、社会保険料の負担を軽減するケースも見られました。
こうした不公平を改善するため、賞与にも社会保険料を適用する「総報酬制」が2003年4月に導入されたのです。
また、所得税の成り立ちは古く、歴史を遡れば導入は明治20年(1887年)になります。
参考:所得税の歴史|平成18年度特別展示|税務大学校|国税庁
手取り収入をアップ!賞与の控除額を増やす8つの方法
最後に賞与の控除額を増やし手取り収入をアップするための、8つの節税方法を紹介します。
①扶養控除
扶養控除は、16歳以上の子どもや親を養っている場合に所得控除が受けられる制度です。
控除額は扶養親族の年齢や同居しているかどうかで変わります。
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
また、扶養控除には下記のような適用条件があります。
条件の一例
|
控除額は大きいため、適用できるのであれば家計の大きな味方になるでしょう。
より詳しい適用条件は、下記の関連記事をご確認ください。
関連記事:「扶養控除とは?年収の壁や控除金額を分かりやすく解説!」
②医療費控除
医療費控除は、年間で支払った医療費が一定額を超える場合、所得控除を受けられる制度です。
自分だけではなく、家族の医療費も対象となり、病院以外にも薬局や通院のための交通費なども含まれます。
限度額は200万円までとなりますが、健康保険で補填された金額は除外されるため注意しましょう。
控除額の計算式
控除額 = 実際に支払った医療費 - 保険金などで補填された金額 - 10万円
※ 所得が200万円未満の場合は「所得金額の5%」
医療費控除の仕組みについてより詳しく知りたい方は、関連記事も参考にしてみてください。
関連記事:「医療費控除とは?確定申告・計算方法や明細書の書き方を解説!」
③セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、対象となる市販薬の購入費用が1万2,000円を超えた場合に適用されます。
健康診断や予防接種を受けていることが条件であり、限度額は最大8万8,000円となります。
控除額の計算式
控除額 = 対象となる医薬品の購入費用 - 1万2,000円
対象の市販薬は下記サイトの「セルフメディケーション税制対象品目一覧」から確認できます。
適用の範囲が広く2025年2月時点で対象となる市販薬は2800品目を超えているので、現在使っている市販薬があればぜひリストから探してみてください。
参考:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について│厚生労働省
④ふるさと納税
ふるさと納税は自分が選んだ自治体に寄付すると、寄付金額のうち2,000円を超えた部分が所得税や住民税から控除される制度です。
また、返礼品を用意している自治体へ寄付した場合は、寄付金のおよそ30%相当の返礼品が受け取れます。
控除の上限額については年収や家族構成で異なるため、寄付の金額に注意しましょう。
控除額の計算式
控除額 = 寄付金 - 2,000円
返礼品は地産のお米や牛肉、イチゴやシャインマスカット、または地域の伝統工芸品などバラエティ豊かで、自分の好みに合わせて選ぶ楽しさがあります。
関連記事:「確定申告不要!ワンストップ特例制度を使ったふるさと納税の方法について解説!」
⑤生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険や個人年金保険、介護医療保険などに支払った保険料が所得税と住民税から控除される制度です。
それぞれ控除額は最大4万円(合計最大12万円)になりますが、適用条件は異なります。
適用できる可能性がある方は、下記の国税庁の公式サイトで確認してみてください。
⑥地震保険料控除
地震保険料控除は、契約している地震保険の保険料に応じて、所得税の控除を受けられる制度です。
また、地震保険への加入は基本的に単独ではできず、火災保険の契約がセットになります。
控除限度額
5万円以下の場合:全額
5万円を超える場合:一律で5万円
関連記事:「火災保険・地震保険は年末調整や確定申告で控除できる?」
⑦住宅ローン控除
住宅ローン控除は、マイホームの購入やリフォームで住宅ローンを利用した場合に使える制度で、「住宅ローン減税」とも呼ばれます。
住宅ローン控除を使うと新築では13年、中古住宅では10年、年末時の住宅ローン残高から0.7%の所得税控除を受けられます。
控除額の計算式
控除額 = 年末のローン残高 × 0.7%(控除率)
また、控除の適用を受けるためには、1年目のみ確定申告が必要になります。
年末調整では対応できないため、会社に勤めている方は注意しましょう。
関連記事:「住宅ローン控除とは?確定申告の必要書類、ふるさと納税の併用方法も解説」
⑧iDeCo(個人型確定拠出年金)
最後にご紹介するiDeCoは、個人で掛金を拠出し投資商品を積立運用することで、所得税の控除を受けられるようになる制度です。
通常、投資で得た運用益には20.315%の譲渡益課税がかかりますが、iDeCoにはかかりません。
毎月の積立金額は5,000円からとなり、掛金の上限は自営業者や会社員など職業によって異なります、
所得税の控除は大きなメリットになりますが、原則として60歳まで引き出せない点には気をつけましょう。
関連記事:「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の特徴と年末調整・確定申告」
賞与控除の仕組みを理解して上手く節税しよう
賞与からは各種社会保険料や所得税が控除され、省庁や地方自治体の運営費用、出産育児一時金や防衛費に使われています。
とはいえ、あまりにも賞与から引かれる税金が多いと生活も大変です。
節税の仕組みを活用して、少しでも手取りを増やすために、医療費控除やふるさと納税などの制度を上手に使っていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
休業手当の計算方法をケースごとに紹介!
会社都合での休業は、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければいけません。しかし休業には自然災害や経営悪化など様々な事情があります。雇用形態により計算方法は異なり、細かい判…
詳しくみる基本給の決め方と低い場合のデメリットとは?
基本給は給与の基本になる重要な賃金ですが、手取り額は気にしても基本給の額はあまり気にしない人が多いのではないでしょうか。 基本給は賞与や退職金、残業代などに影響する重要な金額ですか…
詳しくみる転勤の引っ越し費用は給与課税?非課税の範囲と支度金の扱いを解説
従業員の転勤。新たな門出は応援したいけれど、税務上の判断はあいまいで不安…。このような悩みを抱えていませんか? この記事では、転勤の引っ越し費用に関する給与課税のルールを分かりやす…
詳しくみる福利厚生賃貸とは?住宅系福利厚生制度と他の福利厚生制度を比較しながら解説
採用や人材定着、ブランディングなど、さまざまな部分に影響を与える福利厚生。 今回は福利厚生の基礎知識に加え、住宅系福利厚生制度(住宅手当/社宅制度)と他の福利厚生の比較、福利厚生賃…
詳しくみる有給を入社後すぐに付与したい場合はどうする?要件や注意点を解説
有給休暇を入社後すぐに付与することは可能です。本来は入社から6ヶ月後に付与することが原則ですが、前倒しの付与は労働者に不利益を与えるものではなく、かえって「ゆとりある生活を保障する…
詳しくみる役員報酬の決め方ガイド!具体的な流れや注意点、金額の相場・変更ルールまで徹底解説
会社経営において、役員報酬の決め方は、手元に残るキャッシュと納税額を左右する最も重要な経営判断の一つです。社長や取締役の給与額を適切に設定することで、法人税と個人の所得税・住民税・…
詳しくみる-e1763462562443.jpg)
シート-1.png)