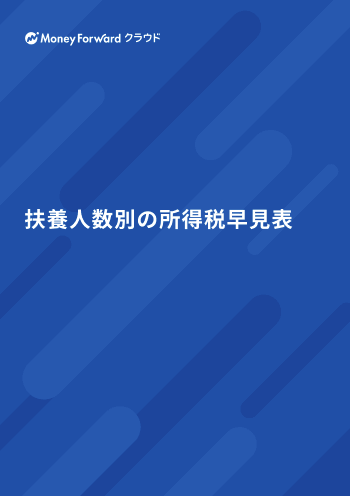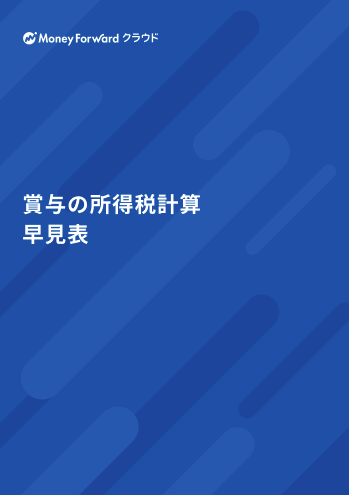- 更新日 : 2025年11月20日
所得税が非課税になるケース – 非課税所得も解説
所得税は、納税義務のある人のすべての所得に対して課税されます。しかし、所得の中には、所得税を課さないとする「非課税所得」と定められているものもあります。
ここでは、非課税所得とはどのようなものかについての解説をするとともに、非課税所得となるものには例えばどのようなものがあるのかを具体的に例を挙げて解説していきます。
非課税所得とは?
非課税所得とは、所得のうち、所得税が課税されない所得を言います。
所得税は、納税義務がある人のすべての所得に対して課税されることが原則ですが、所得の中には、さまざまな要因で所得税を課さない所得があります。これを非課税所得と言います。
非課税所得の主なものには以下のようなものがあります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務関連の法改正まとめ 2026年版
所得税などの実務と並行して確認しておきたいのが、今後の労働法制の動きです。特に議論が進む労働基準法の改正は、企業の労務管理を大きく変える可能性があります。
最新の法改正情報と実務対応をまとめた本資料で、いつ、何が変わるのかを今のうちに把握しておきましょう。
扶養人数別の所得税早見表
所得税額は給与額や扶養親族の人数によって細かく変動します。毎月の給与計算で、正しい税額を算出できているか不安になることはありませんか?
計算ミスは給与の修正対応など無駄な業務を生んでしまいます。給与額と扶養人数を照らし合わせるだけで税額がわかる本資料を、計算時の確認用としてお使いください。
賞与の所得税計算早見表
年数回しかない賞与計算は、毎月の給与計算に比べて手続きを間違いやすい業務です。特に所得税は前月の給与額を基準にするなど特殊な算出が必要なため、計算ミスが起こりかねません。
複雑な計算や表の確認作業を効率化できる本資料で、ミスのない正確な賞与計算を行いましょう。検算用としても便利です。
非課税世帯とは?
住民税の非課税世帯とは、住民税が非課税になる世帯のことを言います。
住民税には「均等割」と「所得割」がありますが、この両方が非課税にならないと非課税世帯にはなりません。
所得税が非課税になるケース
非課税所得は、所得税法や租税特別措置法、その他の法律で規定しています。
非課税所得については、たとえ損失が生じたとしても、その損失分はなかったものとされます。
以下に所得税が非課税となる主な場合を紹介します。
給与に関して
通常の給与の他にもらえる手当、費用などで実費弁償的なものは非課税になります。
サラリーマンの出張費
出張費は、役員や従業員が出張に行く場合に、通常の範囲内で必要だと認められる費用について非課税になります。一方、個人事業主が出張に行く際の費用は課税対象となるので注意が必要です。
通勤手当(公共交通機関を利用)
常識的な通勤手段で最も経済的な方法を取る場合の通勤にかかる費用は、月10万円まで非課税です(10万円を超えた場合は給与所得として、課税対象)。また、この通勤手当には、新幹線も含めることができますが、グリーン車料金は入りません。
通勤手当(自動車、自転車などを利用)
自動車や自転車で通勤する場合には、片道の通勤距離ごとに非課税の対象となる上限が決まっています。平成26年4月以降適用分から、その上限が引き上げられました。例えば、2km未満は全て課税、2km以上から10km未満の場合は4,200円まで、最大55km以上で31,600円の通勤手当が非課税になります。
職務上必要と定められたものの現物支給
ユニフォームや食事などは、費用の種類や従業員の負担割合によって課税されるものと課税されないものがあります。ただ、現物で支給する必要があり、食事手当として現金を渡す場合は課税対象となります。
利子に関して
利子は、貯蓄を奨励する目的や障がい者の税負担を少なくする目的で、非課税になるものがあります。
合計が550万円以下の勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)の利子
財形住宅貯蓄とは住宅を購入するために使われる貯蓄のことで、勤労者が家を購入することを促進するために作られました。55歳未満の勤務者が勤務先に届け出をすることで、元本550万円まで(財形年金貯蓄との合計)非課税になります。
財形年金貯蓄とは、老後の生活に備えて蓄えるもので、60歳以降の年金受給開始まで引き出さないことと、5年以上定期に給料天引きで積み立てることを条件に元本550万円まで(財形住宅貯蓄との合計)非課税になります。
350万円以下の障がい者等の少額預金の利子(マル優)、障がい者等の少額公債の利子
障がい者で収入を得ることに難がある方への税金配慮として、元本の合計が350万円以下であれば、預貯金や有価証券などの利子が非課税になります。また、この制度はマル優とよばれています。
少額公債(国債、地方債)も同様に、元本合計が350万円以下であれば非課税です。なお、この制度は特別マル優とよばれています。
当座預金の利子
当座預金では、年利1%を超えない部分は非課税となっています。
譲渡に関して
社会政策に対する配慮から、譲渡に関して非課税になるものがあります。
生活用動産の譲渡所得
家具や衣服、電化製品など日常生活に使うものは原則として非課税です。ただ、宝石、書画などで1品あたり30万円を超えるものは課税対象になりますので、注意が必要です。
その他に関して
その他にも、2重課税防止のためや、公益的目的のために非課税になるものがあります。
相続や遺贈、個人から受け取る贈与
相続税や贈与税の対象にはなりますが、所得税は課税対象外です。
文化功労者年金、学術奨励賞など
文化功労者年金等や、財務大臣が定める学術奨励金等は非課税です。
所得税法以外の法律で定められる非課税
所得税法にはないものでも、非課税となるものがあります。
保険給付金
健康保険、介護保険等の保険給付などに関しては、健康保険法や介護保険法に定められており非課税です。出産一時金、傷病手当金などが含まれます。
宝くじの当選金、toto (スポーツ振興投票券)の払戻金
宝くじの当選金は当せん金付証票法で、totoの払戻金はスポーツ振興投票の実施等に関する法律で非課税と定められています。ただし、海外の宝くじ当選金は、課税対象になります。
非課税所得について再確認しましょう
今回は、所得には「課税所得」と「非課税所得」があること、非課税所得と非課税世帯の概要について説明しました。
また、非課税所得について、所得税が非課税になるケースとして、いくつかのケースに分けて例を挙げたのでぜひ参考にしてください。
このように所得の全てが課税所得だけではなく、非課税所得もあるということに注意して、所得について再度確認しておきましょう。
よくある質問
非課税所得とは何ですか?
所得税は、納税する義務がある人のすべての所得に対して課税されることが原則になります。所得の中には、利子・配当所得にかかるものや給与所得にかかるものなど、さまざまな要因で所得税を課さない所得があります。詳しくはこちらをご覧ください。
所得税が非課税になるケースについて解説してください
利子・配当にかかるもの、通常の給与の他に支給される出張旅費や通勤手当(上限あり)、現物支給などの手当、費用などで実費弁償的なもの、通常必要な動産の譲渡による所得などは非課税になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
小田原市の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
小田原市は歴史と自然が調和する観光都市として知られ、多くの企業が地域経済を支えています。そんな小田原市で事業を運営する企業にとって、給与計算は欠かせない業務ですが、その正確性と効率…
詳しくみる経費精算を担当する部署は?労務それとも経理?
働き方改革に伴い、経費精算の簡素化が求められています。特に、事業活動の際に従業員が一時的に立て替えた「立替経費」は払い戻すための手続きに手間や時間がかかり、大きな負担となっているの…
詳しくみる定額減税で毎月いくら入る?税額と手取りについて解説!
2024年に実施される定額減税の額は1人4万円です。内訳として、所得税3万円、住民税1万円が控除されます。配偶者または扶養親族がいる場合には、その人数分控除されるため、単身者では4…
詳しくみる秋田県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
秋田県は農業や林業、漁業が盛んで、特に米や日本酒の生産が有名です。また、観光業も成長しており、多様なビジネスが展開されています。こうした地域特有の業種では、給与計算の正確さと効率化…
詳しくみる給与計算の流れと業務を自動化するメリット
給与計算の一連の流れは、RPAや給与計算ソフトを用いることで、自動化できます。人の感覚的なチェックができない、イレギュラーに対応できないといった難しい課題があるものの、給与計算を自…
詳しくみる所得税で認められる寄付金控除の範囲とは?
納税者である個人が、国や地方公共団体などに対して寄付をした場合、つまり特定寄付金を支出した場合は、所得税の所得控除(寄付金控除)を受けることができます。 また指定寄付金のうち、政治…
詳しくみる