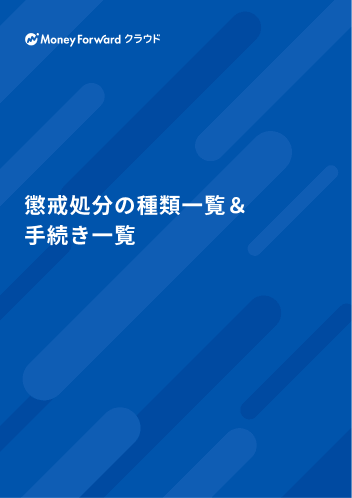- 更新日 : 2025年8月20日
懲戒処分の種類とは?会社員・公務員の処分のレベルや受けるとどうなるのかを解説
懲戒処分は、軽い規律違反から重大な不正行為まで多岐にわたり、その種類やレベルによってキャリアへの影響も大きく異なります。万が一、ご自身や同僚が懲戒処分の当事者となってしまった場合、その後の会社での立場や転職活動に深刻な影響を及ぼす可能性も否定できません。
この記事では、民間企業における懲戒処分の種類と、それぞれどのようなケースで科されるのかを具体例を交えて分かりやすく解説します。
目次
そもそも懲戒処分とは
懲戒処分とは、従業員が会社の規律や秩序を乱す行為(非違行為)を行った際に、会社が使用者としての権限に基づき科す制裁罰のことです。
懲戒処分の目的は、単に違反行為をした従業員を罰することだけではありません。むしろ、企業秩序を回復し、他の従業員への戒めとすることで、将来的な規律違反の再発を防ぐことに重きが置かれています。したがって、懲戒処分を実施するためには、就業規則にあらかじめその種類や理由が定められていなければなりません。
民間企業の懲戒処分の種類
会社が従業員に対して科す懲戒処分は、法律で定められているわけではなく、各企業の就業規則に基づいて決定されます。一般的に、処分の重さは7つのレベルに分けられます。
レベル1. 戒告(かいこく)・譴責(けんせき)
戒告や譴責は、懲戒処分の中で最も軽い処分です。従業員の規律違反に対して厳重注意を行い、将来を戒めることを目的とします。多くの場合、始末書の提出を求められますが、提出を強制されるのが譴責、口頭での注意に留まるのが戒告と区別されることもあります。
- 遅刻や無断欠勤の常習(頻度が比較的少ない場合)
- 業務上の軽微な指示・命令への違反
- 社内風紀をわずかに乱す言動
給与や役職に直接的な影響はありませんが、人事評価でマイナスに働く可能性があり、公式な処分記録として残る点を理解しておく必要があります。
レベル2. 減給
減給は、従業員が受け取るべき給与から一定額を差し引く処分です。これは従業員の経済面に直接的な影響を与えるため、労働基準法第91条によって上限が定められています。
- 1回の違反に対する減給額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
- 複数回の違反があっても、減給総額は一賃金支払期(月給制なら月)の総額の10分の1を超えてはならない。
- 正当な理由のない複数回の業務命令違反
- 部下への軽度なパワハラや、同僚への暴言
- 無許可での残業や休日出勤の繰り返し
レベル3. 出勤停止
出勤停止は、一定期間、従業員の就労を禁止する処分です。期間中は自宅謹慎などを命じられ、その間の給与は支払われないのが通例です。期間は企業の就業規則によって異なりますが、一般的には7日から1ヶ月程度が目安とされています。
この処分は、従業員を職場から隔離することで、職場の秩序を回復し、本人に反省を促す目的があります。
- 度重なる業務命令違反や、職務放棄
- 職場内での暴行・脅迫、重大なハラスメント行為
- 私生活上の飲酒運転(事故を起こした場合など)
レベル4. 降格
降格には、「懲戒処分としての降格」と「人事権に基づく降格(降職)」の2種類があります。懲戒処分としての降格は、役職や職位を引き下げる制裁です。これにより、役職手当などが減額され、実質的な賃金の引き下げにつながることがあります。
懲戒権の濫用と判断されないよう、処分の根拠と妥当性が厳しく問われる処分でもあります。
- 管理職による悪質なパワハラが認定された場合
- 重大な業務上のミスを犯し、会社に大きな損害を与えた責任者
- 職権を乱用し、不正な利益を得ようとした場合
レベル5. 諭旨解雇(ゆしかいこ)
諭旨解雇は、本来であれば懲戒解雇に相当するほど重大な規律違反があった場合に、会社が一方的に解雇するのではなく、従業員に退職を勧告し、合意による退職を促す処分です。
従業員が自主的に退職届を提出すれば、解雇ではなく自己都合退職に近い形で処理されるため、懲戒解雇に比べると温情的な措置と言えます。多くの場合、退職金が全額ではないにせよ、一部支払われることがあります。しかし、従業員が退職届の提出を拒否した場合は、懲戒解雇に移行するのが一般的です。
- 懲戒解雇に相当する行為だが、長年の功績が考慮されたり、深く反省していたりする場合
レベル6. 懲戒解雇
懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分であり、従業員との労働契約を一方的に即時解消するものです。
原則として、30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いはなく、退職金も全額または大半が不支給となります。これは従業員のキャリアに致命的な影響を与えるため、その適用は極めて悪質な規律違反に限られ、客観的で合理的な理由と社会的な相当性が厳格に求められます。
- 会社の金銭の横領、業務上の地位を悪用した着服・背任
- 重要な営業秘密や顧客情報の漏洩
- 理由のない長期間の無断欠勤で、出勤の督促にも応じない場合
- 会社内で刑法犯に該当する行為(窃盗、傷害など)を行った場合
公務員の懲戒処分の種類
公務員の懲戒処分は、国家公務員であれば国家公務員法第82条、地方公務員であれば地方公務員法第29条にその根拠が置かれています。これらの法律には、懲戒処分の事由や種類が明記されており、民間企業のように各組織の裁量で内容を自由に変更することはできません。
公務員の懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類に限定されています。
- 免職
職員の意に反してその職を失わせる、最も重い処分です。民間企業の懲戒解雇に相当します。 - 停職
一定期間、職務に従事させず、その間の給与は支給されない処分です。民間企業の出勤停止に近いです。 - 減給
一定期間、職員の給与を減額する処分です。 - 戒告
職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分です。始末書の提出を伴う場合もあります。
公務員の場合、人事院が具体的な処分量定の指針を公表しており、飲酒運転や情報漏洩、ハラスメントなど、事案ごとにおおよその処分レベルが示されているため、全国で統一的な基準に基づいた処分が行われやすい点が特徴です。
懲戒処分を受けるとどうなるのか
懲戒処分を受けると、現在の職場だけでなく、その後のキャリア全体に影響が及ぶ可能性があります。
昇進・昇給への影響
懲戒処分を受けると、その記録は人事評価に直接影響します。戒告や譴責といった比較的軽い処分であっても、賞与(ボーナス)の査定でマイナス評価を受けたり、将来の昇進・昇給が遅れたりする可能性は高いでしょう。
特に管理職への昇進などを目指す場合、過去の懲戒処分の履歴が大きな障壁となることは少なくありません。企業は、規律を守り、組織の模範となる人材を重要なポジションに就けたいと考えるためです。
退職金への影響
退職金が支払われるかどうかは、処分の重さと企業の退職金規程によって決まります。戒告、減給、出勤停止などの場合、退職金は規程通りに支払われることが多いですが、減額される可能性もあります。
一方、諭旨解雇の場合は一部支給、懲戒解雇の場合は全額不支給となるのが一般的です。退職金は功労報奨的な性格を持つため、会社に大きな損害を与えた従業員に対しては支払われない、という考え方が根底にあります。
転職活動への影響
懲戒処分を受けると、転職活動は非常に厳しくなるのが現実です。特に懲戒解雇の場合、その事実を隠して転職活動をすると、経歴詐称と見なされる可能性があります。法的に履歴書への明記義務はありませんが、後に発覚した場合には再び解雇などの重大なトラブルになるリスクがあります。
懲戒処分を科す場合のルール
企業が従業員に懲戒処分を科す際には、一方的な判断で行うことはできません。労働契約法第15条などに基づき、処分の客観的な合理性や社会的相当性が必要であるなど、法律に基づいた厳格なルールを守る必要があります。
就業規則への明記が必須
企業が懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則に懲戒処分の種類と、どのような場合にどの処分が科されるのかという事由を具体的に定めておく必要があります。就業規則に記載のない処分を科したり、記載のない理由で処分したりすることは原則として認められません。
これは、従業員にどのような行為が処分対象となるかを事前に知らせ、予測可能性を担保するための重要なルールです。
懲戒権の濫用に注意
懲戒処分は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合には、権利の濫用とみなされ無効となります(労働契約法第15条)。これは、懲戒権の濫用と呼ばれます。
具体的には、従業員の行為の性質や態様、会社に与えた損害の程度などを考慮し、それに対して処分が重すぎないか、というバランスが問われます。
例えば、一度の軽微なミスでいきなり懲戒解雇にすることは、社会通念上相当性を欠き、無効と判断される可能性が高いです。
一つの事案に対する二重処分の禁止
一事不再理の原則に基づき、一度懲戒処分を下した事案に対して、再び同じ理由で懲戒処分を科すことはできません。例えば、ある規律違反に対してすでに出勤停止処分を下したにもかかわらず、後から同じ理由で降格処分を追加することは許されません。
ただし、処分後に新たな規律違反が発覚した場合は、その新しい事実に基づいて別途処分を検討することは可能です。この原則は、従業員を不当に二重の不利益から守るためのものです。
懲戒解雇について正しく理解しましょう
本記事では、民間企業と公務員における懲戒処分の種類、それぞれのレベル、そして処分がキャリアに与える影響について詳しく解説しました。懲戒処分は、軽い戒告から最も重い懲戒解雇まで多岐にわたり、その内容は就業規則や法律によって定められています。
処分を受けると昇進や退職金、転職活動に大きな影響が及ぶ可能性があります。特に懲戒解雇の経歴は、その後のキャリア形成において深刻な足かせとなり得ます。一方で、企業側が処分を科す際にも、懲戒権の濫用とならないよう厳格なルールが課されています。懲戒処分に関する正しい知識は、労働者と企業双方にとって、公正な職場環境を維持するために不可欠なものです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
介護事故報告書とは?書き方やポイントを解説【無料テンプレートつき】
介護事故報告書は、介護サービスの提供に伴う事故が発生した場合に市町村などの行政機関に報告するものです。介護保険法や各自治体が定める指針では、介護事業者は事故の状況および事故に際してとった処置について記録することを義務付けています。 本記事で…
詳しくみる育休は何ヶ月取れる?制度ごとに何日取得できるかを解説
育児休業は、子育てと仕事の両立を支援し、労働者が安心して育児に取り組めるようにするための重要な制度です。 この記事では、「育休は何ヶ月取れるのか」という基本的な疑問から、育児休業の期間、延長条件、関連する給付金、社会保険料の扱い、そして20…
詳しくみる紛失届とは?テンプレートを基に必要項目や書き方、会社の対応を解説
企業が社員に貸与した物品や機器を紛失した場合、当然のことながら適切な対応が求められます。紛失届は、そのための大切な書類です。この記事では、紛失届の概要から、必要項目の記載例、会社の対応手順など、知っておくべき実務的な情報をわかりやすく解説し…
詳しくみる退職勧奨した場合でも離職票を発行する?発行の流れや離職証明書の書き方も紹介
退職勧奨により従業員が会社を辞める場合でも、本人が離職票の発行を求めた場合は対応する必要があります。 ただ、離職票の発行手続きを行おうとしている人の中には「退職理由に何を選べば良い?」「退職勧奨した場合の離職証明書の書き方は?」と悩んでいる…
詳しくみる日本で外国人労働者が多い職種は何?割合や受け入れ可能な業種を紹介
日本で外国人労働者が多い職種は「製造業」「サービス業」「卸売業・小売業」「宿泊業・飲食サービス業」「建設業」の5つが中心です。 とくに人手不足の業界では、技能実習生や特定技能外国人の受け入れが積極的に行われている傾向にあります。本記事では、…
詳しくみる外国人労働者の受け入れに必要な教育とは?日本語教育の現状や7つの解決策を紹介
外国人労働者を雇用するにあたり、大きな課題となるのが教育です。低い日本語レベルによって伝達ミスが起きてしまったり、安全教育の不足によって労働災害が起きてしまったりするリスクが想定されます。 そこで本記事では、外国人労働者への教育について、現…
詳しくみる