- 更新日 : 2025年8月18日
店長手当の相場はいくら?業種別の平均金額と決め方の注意点を解説
「店長にどれくらいの手当を支払えばよいのか」と悩んでいる経営者や人事担当者も少なくありません。店長は現場の最前線で業績に大きな影響を与える存在であり、その処遇次第でスタッフの士気や売上が変わることもあります。
とはいえ、店長手当の金額は業種や企業規模によってバラつきが大きく、相場に絞って基準を定めてしまうと不公平感やトラブルの原因にもなりかねません。
この記事では、「店長手当」の法的な位置づけや業種別の相場、手当の決め方、制度を設ける際の注意点まで、わかりやすく解説します。
目次
店長手当とは?
店長手当は、企業が独自に設ける「法定外手当」の一つで、法律上必須の手当ではありませんが、現場における役割や責任の重さを金銭的に評価するための報酬制度です。
一般社員と比べて業務量や責任が大きい店長に、一定の手当を支給することで、会社としての期待を明確に示し、意欲を高める狙いがあります。
制度としては「役職手当」の一種とされることが多く、時間外労働の割増賃金や労働保険料の算定にも含める必要がある点に注意が必要です。
また、最低賃金の判断にも影響するため、店長手当を含めて給与が法定基準を満たしているかを確認しなければなりません。さらに「店長=管理職」という誤解から、労働時間の制限が適用されないと考えがちですが、実態として裁量がなければ「名ばかり管理職」とされ、残業代の支払い義務が生じます。
制度を導入する際は、こうした法的ポイントを踏まえたうえで、トラブルのない設計と運用を行うことが重要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
従業員の賃上げに潜むリスクと、企業が打つべき対策
人手不足や物価上昇などを背景に、賃上げが企業経営の重要テーマとなっています。しかし、賃上げには様々なリスクを伴います。
本資料では、企業が賃上げを進める際に注意すべきリスクと対策について解説します。
住宅手当申請書(ワード)
住宅手当の申請にご利用いただけるテンプレートです。 Wordファイル形式のため、直接入力や編集が可能です。
ダウンロード後、必要事項をご記入の上、申請手続きにお役立てください。
休業手当の計算シート(エクセル)
休業手当の計算にご利用いただける、Excel形式の計算シートです。
Excelファイル形式のため、ダウンロード後自由にご使用いただけます。 業務での休業手当の計算を行う際にお役立てください。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
店長手当の相場や平均はいくら?
店長手当の相場や平均はいくらなのでしょうか。ここでは、2025年時点の最新統計に基づき、業種別の相場を解説します。
厚労省「賃金構造基本統計調査」のデータより
厚生労働省が公表した「賃金構造基本統計調査(令和6年)」では、「店長」という職種区分はありませんが、類似した役割を持つ「課長級」のデータが参考になります。
本調査によると、課長級の平均月額賃金は512,000円、年収換算ではおよそ614万円でした。役職別では、部長級が月額627,200円(年収約752万円)、係長級が385,900円(年収約463万円)となっています。
ただし、これらの数値は「課長級」全体の平均であり、実際の店長の給与や手当は、企業規模や店舗の収益性、地域によって異なる点に注意が必要です。
小売店長(スーパーの店長)の給与相場
job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))によると、スーパーの店長(小売店の店長)は、年収の全国平均は369.4万円、求人賃金は月額25.7万円です。
スーパーの店長は、商品の仕入れや販売計画、広告作成、従業員の労務管理や採用、育成、顧客対応や売上管理など、店舗運営に関わるすべての業務を担います。
参考:スーパー店長 job tag(職業情報提供サイト)|厚生労働省
飲食店店長(ハンバーガーショップ店長)の給与相場
同じくjob tagによるハンバーガーショップの店長は、年収の全国平均は358.4万円、求人賃金は月額27.7万円です。
主な仕事内容は、商品の味や品質、サービスの維持管理、販売促進、アルバイトの教育・管理など、店舗全体の管理です。店長は一経営者として、売上分析や食材発注などのデスクワークから、時には自ら調理や販売にも携わります。
参考:ハンバーガーショップ店長 job tag(職業情報提供サイト)|厚生労働省
店長手当を設定するメリットとは?
店長手当を活用することで、店長のモチベーションを高め、人材の安定確保や店舗の業績向上につながります。店長手当は人件費負担を伴いますが、それ以上に大きな経営効果をもたらすとされています。
店長のやる気を引き出す
店長という役割に対して、会社がきちんと報いる姿勢を示すことは、本人のやる気を高めるうえで非常に効果的です。「会社が自分に期待している」という意識が高まり、日々の業務にも前向きに取り組むようになるでしょう。
また、昇進を目指す一般社員にとっても、「店長になると月に3万円の手当がつく」といった明確な目標ができ、キャリアアップへの意識が高まります。
人材の確保と定着に効果がある
人手不足が深刻な中、他社と差別化できる待遇は、人材採用や定着において大きな武器になります。
実際に、手当の有無が応募者の志望動機や離職理由に影響するケースは少なくありません。
手当の金額は業種や会社規模によって異なりますが、仮に月額3万円の店長手当を支給した場合、年間で36万円の差が生まれます。このような待遇は、求職者にとっては魅力的なポイントになり、既存の店長が転職を思いとどまる理由の一つになります。
店舗の成果が上がる好循環を生む
適切な報酬を受け取ることで、店長は「店の売上は自分の成果」と捉えるようになります。売上管理、在庫最適化、クレーム対応、スタッフ教育など、あらゆる業務に対して主体的に動くようになるため、店舗全体のパフォーマンスも向上します。
その結果、店舗の売上や利益が改善し、企業全体の経営にもプラスとなる可能性が高まるでしょう。
店長手当の金額の決め方
店長手当の金額を決める際は、「他社がいくら出しているか」を参考にするだけでは不十分です。役割の重さや自社の経営状況も踏まえながら、納得感のある制度を設計することが大切です。
店長の役割や責任を明確にする
まずは、自社の店長に求めている業務や責任を洗い出すことから始めます。例えば、売上管理、在庫コントロール、スタッフの採用・教育・シフト管理、顧客対応、数値目標の達成など、どの業務をどこまで担っているのかを整理します。この内容が曖昧だと、手当の金額にも説得力を持たせることができません。
責任が重くなるほど、それに見合った手当が求められます。逆に、他店舗からの支援が多く、裁量が小さい場合は手当の水準も調整が必要です。
業界相場と自社の支払余力を照らし合わせる
次に、自社が市場でどの位置にあるのかを確認します。
ただ単に、相場に合わせるだけではなく、自社の財務状況や人件費比率も踏まえて、無理なく継続できる範囲で設定することが重要です。一時的に高めの水準に設定しても、のちに減額が必要になるようでは、信頼を損なう原因になります。
給与逆転が起きないように注意する
手当の設定での落とし穴の一つが、「部下のほうが給料が高くなる」という、いわゆる「給与逆転」の現象です。一般社員に多くの残業代が発生した場合、店長の基本給と手当を上回ってしまうケースは、労働契約法や労基法上の義務違反ではないものの、労務管理上の不満要因につながります。
このような逆転現象を避けるには、「店長の総支給額が、部下の想定残業代込みの金額を確実に上回る」ように、シミュレーションしたうえで金額を設計しましょう。そのときに重要なのが、責任の重さに見合った報酬であることです。
業績と連動したインセンティブを検討する
毎月固定で支給する手当に加えて、店舗の売上や利益率に応じて変動する「インセンティブ手当」を組み合わせるのも効果的です。月額3万円の店長手当を支給し、さらに目標を達成した場合に別途報奨金を支給するというスタイルです。
このように制度化することで、安定収入と成果への報酬を両立でき、店長のモチベーションを高めると同時に、企業としても費用対効果の高い報酬設計が可能になります。
制度決定後は就業規則や賃金規程も必ず見直す
店長手当の金額や支給条件を決定した後は、就業規則の賃金規程の内容を見直し、必要に応じて更新することが重要です。以下のような情報を明記し、従業員に説明・周知しておきましょう。
- 店長手当の支給対象(例:正社員のうち店舗責任者に任命された者)
- 手当の金額および支給タイミング(月額固定・変動の有無など)
- 固定残業代を含む場合は、その旨と内訳、該当時間数
- インセンティブの評価基準と算出方法(必要に応じて別規程化)
就業規則の変更は、作成時と同様、労働基準監督署への届出と従業員への周知が必要です。また、従業員に対して内容を説明し、文書で確認・同意を得ることも、トラブル防止の観点から重要です。
店長手当を設定する際の注意点
店長手当はモチベーション向上や人材定着に効果的ですが、設計や運用を誤ると法的リスクやトラブルにつながります。特に注意したいのは、「名ばかり管理職」「固定残業代の誤用」「不利益変更」の3点です。
「名ばかり管理職」とみなされないようにする
店長という肩書があっても、実態が伴っていない場合は、労働基準法41条2号の「管理監督者」として扱えません。裁量がなく、勤務時間が固定されており、権限も限定的な店長は、労働基準法上の管理職ではないため、残業代を支払う必要があります。
「店長だから残業代は不要」と決めつけるのは非常に危険です。過去の大手ハンバーガーチェーンの事件の判例でも、実態が重視されています。役職名だけで判断せず、労働時間の自由度、業務裁量、待遇面を含めた実態で判断することが必要です。
固定残業代として支給する場合のルールを守る
店長手当に残業代を含める「固定残業代制度」を導入する企業もありますが、要件を満たしていないと違法とされるおそれがあります。以下の3点が明確になっているか確認しましょう。
- 手当の中に何時間分の残業代を含むかを明記する
例:「店長手当50,000円には月30時間分の時間外労働手当を含む」など、明確な時間数の記載が必要です。 - 基本給と固定残業代を明確に区分して表示する
給与明細や雇用契約書において、「基本給250,000円/固定残業代50,000円(30時間分)」のように区別します。 - 超過分の残業代は別途支給する
実際の残業が30時間を超えた場合は、超えた分に対して法定の割増率(通常1.25倍)で追加支給する必要があります。
これらが曖昧だと、「すべて通常の役職手当とみなされ、残業代は別途支払いが必要」と判断される可能性があります。
減額・廃止する場合は「不利益変更」に該当する
一度支給していた店長手当を、業績不振などの理由で減額・廃止する場合、労働条件の不利益変更として厳しい制限を受けます。
原則として、社員本人の同意がなければ減額できません。就業規則を変更する場合も、合理性が求められ、従業員に与える不利益の程度が大きいと無効になる可能性もあります。制度変更時は、説明と同意の取得を丁寧に行うことが重要です。
店長手当に関するよくある質問(Q&A)
Q. 店長は残業代を請求できないのですか?
A. 店長という肩書きだけでは、残業代が不要になることはありません。労働基準法で「管理監督者」と認められる場合に限って、時間外・休日・深夜の割増賃金が免除されますが、その認定は非常に厳格です。
実際には、多くの店舗型ビジネスの店長は、シフト制で勤務時間が決まっており、会社の指示に基づいて業務をこなしているため、「労働基準法41条2号の管理監督者」とは認められません。そのため、原則として残業代の支払いが必要です。
Q. アルバイトやパートの店長にも手当を出す必要がありますか?
A. 法律上、パートやアルバイトの店長に必ず手当を支給しなければならないという決まりはありません。ただし、実際に正社員と同じような責任や業務を担っている場合は、手当の支給を検討すべきです。
パートタイム・有期雇用労働法で定める「同一労働同一賃金」の原則がある以上、同じ責任を負っている人に対し、雇用形態を理由に報酬を差別的に扱うと、労使トラブルの原因になります。責任の程度に応じた待遇が、公平な職場づくりには欠かせません。
Q. 手当の金額を途中で減らすことはできますか?
A. 原則として、従業員の同意がない限り、一方的に店長手当を減額することはできません。これは労働条件の「不利益変更」に該当し、慎重な対応が求められます。
どうしても制度変更が必要な場合は、まず変更の理由を丁寧に説明し、対象者から書面で同意を得ることが望ましいとされています。就業規則を変更して対応する方法もありますが、その際は「合理的な変更」と認められるだけの十分な根拠と手続きが必要です。
店長手当の相場を踏まえた制度設計で企業力を高める
店長手当は、企業と店舗の成長を支えるための重要な人事制度です。業種ごとの相場を考えたうえで、店長の責任や役割に応じた金額を設定します。
また、自社の経営状況や人件費比率を踏まえた「無理のない持続可能な制度設計」が必要です。給与逆転や不利益変更といったリスクを避けるためにも、法的な観点からのチェックや、就業規則・賃金規程の整備も欠かせません。
制度設計を丁寧に行うことで、店長のモチベーションは高まり、店舗のよりよい運営に注力するようになります。それが現場の生産性や顧客満足度を押し上げ、最終的には企業全体の競争力を高める結果につながります。
店長手当はコストではなく、組織への投資です。相場を正しく捉え、自社に合った制度として活用していきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
転勤したら住民税はどこに払う?国内転勤と海外転勤の違いを徹底解説
転勤が決まると気になるのは「住民税はどこに払うの?」という疑問です。 国内転勤と海外転勤では、住民税の納付先や手続きが大きく異なります。 転勤後に住民税について正しく手続きを行わな…
詳しくみる住民税をクレジットカードで払う方法と4つの注意点
日々、何気なく過ごしていても、私たちは様々な税金を支払いながら生活をしています。その中でも、特に多く人に関わりのあるのが「住民税」。あなたはこの住民税をどのように納めていますか? …
詳しくみる茅ヶ崎の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
茅ヶ崎は、湘南エリアに位置し、美しい海岸線と活気あるサーフカルチャーで知られるリゾート都市です。観光業や地元ビジネスが盛んなこの地域では、給与計算の正確性と迅速な対応が求められます…
詳しくみる賃金台帳と給与明細の違いは?代用できる?フォーマットや書き方も解説
賃金台帳と給与明細の違いについて理解できていますか?賃金台帳は、賃金の支払状況を記録するための書類で、給与明細は会社が従業員に給与額や控除額などを通知するために交付しなければならな…
詳しくみる社会保険料の計算方法は?シミュレーション・年収別早見表つき|2025年最新
毎月の給与明細を見ると、控除の欄に健康保険料や厚生年金保険料といった項目があります。これらが社会保険料です。社会保険は、私たちが病気やケガ、失業、老後といった人生のリスクに備えるた…
詳しくみる家族手当とは?金額の相場や支給条件の例、導入・廃止の手続きを解説【無料テンプレートつき】
家族手当とは、扶養家族がいる従業員の経済的な負担軽減を目的とした福利厚生の一種として支給される手当のことです。特に家族手当の一種である配偶者手当は、近年103万円や130万円などの…
詳しくみる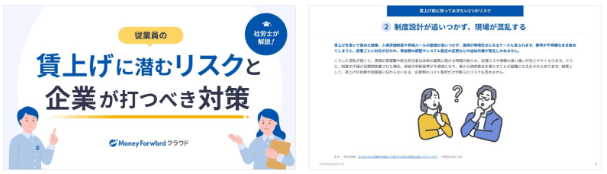
-e1763436002347.jpg)
-e1763436316712.jpg)
.png)