- 更新日 : 2025年11月19日
無給休暇は給料が減る?欠勤との違いや注意点を徹底解説
無給休暇を取得すると、休暇中は給料の支払い義務はありません。無給休暇と欠勤は給料が発生しない点では共通しますが、概念や労務管理上の扱いが異なります。
本記事では、無給休暇について徹底解説します。無給休暇と他の休暇との違いや種類、注意点について解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
労働基準法で定められた休暇と休日の違い
労働基準法では、休暇と休日についてそれぞれ異なる規定があります。休暇は、労働者が申請し、会社の承認を得て労働義務が免除される日を指します。
一方、休日は労働契約や就業規則で定められた労働義務のない日を指し、週に1回以上の割合で設定されることが一般的です。休暇と休日の違いを理解することは、労働環境を適切に管理するために重要です。
以下では、休暇と休日のそれぞれの特徴を解説します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
有給休暇管理の基本ルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
年次有給休暇管理帳(ワード)
従業員の年次有給休暇の管理は、適切に行えていますでしょうか。
本資料は、すぐにご利用いただけるWord形式の年次有給休暇管理帳です。ぜひダウンロードいただき、従業員の適切な休暇管理にご活用ください。
休日・休暇の基本ルール
休日・休暇の管理は労務管理の中でも重要な業務です。本資料では、法令に準拠した基本のルールをはじめ、よくあるトラブルと対処法について紹介します。
休日・休暇管理に関する就業規則のチェックリスト付き。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
休暇は労働義務が免除される日
労働基準法における休暇は、本来は労働者に労働義務があるものの使用者により労働義務が免除された日です。労働者が希望し、使用者が認めることで休暇を取得できます。
休暇は、一定の条件を満たした際に法律上付与する義務がある「法定休暇」と就業規則や労働協約に基づき、使用者が任意に付与する「特別休暇」の2種類あります。
法定休暇とは、法律で定められた休暇で、企業は従業員から請求されれば法定休暇を付与しなければいけません。たとえば、有給休暇は勤続年数や所定労働日数に応じて付与されるものであり、休んでいる日の賃金を保障しながら労働が免除されます。
一方、特別休暇は企業が定めた休暇であり、付与する義務はありません。そのため、多くの企業では福利厚生として導入しています。特別休暇は目的や取得条件、日数などを企業で自由に設定可能です。特別休暇の導入は、従業員のリフレッシュや仕事への意欲向上など企業においてもプラスに働くでしょう。
休日は労働義務がない日
休日は、労働契約上、労働者に労働義務がない日を指します。休暇は労使間の取り決めにより有給か無給かを決められますが、休日は原則として無給です。
休日は、法定休日と法定外休日の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
法定休日は、労働基準法に基づき、労働者に必ず付与しなければいけない休日です。労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通して4日以上の休日を付与しなければいけないと定められています。
法定休日は、特定の曜日に設定する必要はなく、土・日・祝日以外の日に設定しても法律上問題ありません。ただし、就業規則や労働契約書において、休日の設定方法や付与条件が定められている場合は、規定に従う必要があります。
さらに、労働基準法では「1日8時間、週40時間を超えた労働をしてはいけない」と定められています。1日8時間働く会社の場合、週の休日を2日に設定して調整していることがほとんどです。
法定外休日は、企業側が定める法定休日以外の休日です。年末年始休暇や夏季休暇などは法定外休日にあたります。
法定外休日に労働した場合、労働基準法において割増賃金の規定が設けられていないことにより、企業は法律上、休日労働として割増賃金を支払う必要はありません。しかし、法定外休日に労働したことにより、週40時間を超える場合には時間外の割増賃金の支払いが必要です。
無給休暇とは給料が発生しない休暇
無給休暇とは、賃金が発生しない休暇です。有給休暇を除く休暇では、賃金の支払いの有無を企業で決定できます。
法定休暇では、産前産後休業や育児休業、介護休業においては企業に賃金の支払い義務はありません。ただし、休業期間中、労働者は健康保険や雇用保険から給付金を受給可能です。
特別休暇である慶弔休暇(結婚や出産などの慶事や葬儀の弔事の際に取得できる休暇)は、法律上の定めはなく、企業が任意で設定します。そのため、無給とするか有給とするかは企業の裁量によります。
就業規則に「有給とする」旨が記載されている場合は、賃金の支払い義務があるため注意が必要です。
無給休暇は違法?
無給休暇を導入することは、違法ではありません。
労働基準法第24条では、労働者が働いていない場合は賃金を支払う義務がない「ノーワーク・ノーペイの原則」が定められています。
たとえば、法定休暇制度による産前産後休暇や育児休業などは、あくまでも休暇の取得が認められている制度で、原則として賃金の支払い義務はありません。
しかし、無給休暇の取得方法によっては違法性があるため注意が必要です。基本的に、休暇は労働者からの請求により付与するものであり、会社から一方的に無給休暇を強制することはできません。
もし、会社の都合で労働者に無給休暇を取得させた場合は休業に該当するため、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。ただし「外部の事情に起因し(外部起因性)、通常の経営者として最大限の注意を尽くしても避けられない」場合、休業手当の支払いは不要です。
たとえば、地震や台風、大雨、洪水などの自然災害により、事業が一時的に停止した場合は企業側の責任ではなく、事前に回避することが困難なため、休業手当の支払い義務が免除される場合があります。
無給休暇とその他の休暇の違い
無給休暇と他の休暇には、主に給与の支払い有無や取得条件が異なります。無給休暇は賃金支払いの義務がない一方、法定休暇や有給休暇は賃金の支払いが義務付けられていることが特徴です。以下では、無給休暇と他の休暇の違いについて解説します。
無給休暇と欠勤の違い
無給休暇と欠勤は、労働義務があるかどうかが異なります。
欠勤は、労働義務があるにもかかわらず休むことです。法定休暇や特別休暇に設定されている日以外で休む場合、基本的に欠勤として扱われます。
無断欠勤やバックレ(無断で逃げ出す、辞めること)に対して、企業が損害賠償を請求することは可能ですが、実際に認められるケースは稀です。また、労働基準法第16条では、使用者が労働契約の不履行に対して違約金を定めることを禁止しているため、違約金の請求は認められません。
一方、無給休暇は、労働者と使用者の合意に基づき、労働義務が免除されるため、賃金の支払い義務がありません。
無給休暇と欠勤は、どちらも労働日に休んで賃金が支払われない点は共通していますが、労働義務の有無が異なります。
無給休暇と有給休暇の違い
無給休暇と有給休暇では、賃金の支払いの有無が異なるポイントです。
有給休暇は労働基準法第39条に定められた休暇で、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障することを目的としています。入社から6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員であれば、雇用形態に関係なく有給休暇の取得権利があります。
勤続年数に応じた有給休暇の付与日数は以下のとおりです。
| 雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10労働日 |
| 1年6ヶ月 | 11労働日 |
| 2年6ヶ月 | 12労働日 |
| 3年6ヶ月 | 14労働日 |
| 4年6ヶ月 | 16労働日 |
| 5年6ヶ月 | 18労働日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20労働日 |
参考:「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省」
無給休暇は、労働基準法第24条に基づく「ノーワーク・ノーペイの原則」により、労働義務と賃金の支払いがありません。一方、有給休暇は労働する義務がないにもかかわらず、賃金の支払いがある点が大きな違いです。
無給休暇と特別休暇の違い
特別休暇は、企業が独自に定めた休暇です。法律で付与が定められていないため、付与する義務はありません。特別休暇の例は、慶弔休暇や病気休暇、ボランティア休暇、夏季・冬季休暇などです。
特別休暇は必ずしも無給とは限らず、給与の有無は労使間の合意で決定します。また、場合により無給休暇が特別休暇として位置付けられることがあります。
企業が定める特別休暇のなかで、労使間の合意により給与が発生しない休暇が「無給休暇」です。
無給休暇と休職の違い
無給休暇と休職の主な違いは、取得の目的や適用される状況です。
休職は、従業員が会社との雇用関係を維持したまま、一定期間業務から離れることです。主に、従業員の傷病や留学など、本人の事情により労働が困難な場合に適用されます。
休職期間中は労働義務が免除され、賃金の支払いもありません。賃金の支払いがない点は無給休暇と同様ですが、休職期間が満了しても復職できない場合、就業規則の規定によって退職扱いとなる場合があるため注意が必要です。
無給休暇は、従業員が個人的な理由で休暇を取得する場合、給与が発生しない休暇です。企業が特別休暇の一環で無給休暇を設けている場合もあり、従業員の申請に基づき取得されます。
【5種類の無給休暇】制度と特徴
無給休暇には、法定休暇や特別休暇など、さまざまな種類があります。以下では、代表的な5種類の無給休暇について、制度と特徴について詳しく解説します。
1. 産前産後休業
産前産後休業は、労働基準法第65条により付与が義務付けられています。具体的には、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を申請した場合、使用者は申請者を休業させる義務があります。
また、使用者は産後8週間を経過しない女性を労働させることはできません。ただし、産後6週間を経過した女性が労働をしたいと申し出て、医師が問題ないと判断した場合は労働させることが可能です。
産前産後休業は原則として無給ですが、企業が有給としていない限り、賃金の支払い義務はありません。ただし、社会保険に加入している場合は出産手当金を受給できます。
社会保険加入により受給できる出産手当金については、以下の記事をご覧ください。
2. 生理休暇
生理休暇は、労働基準法で定められた無給休暇です。労働基準法第68条で「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した際、申請者を生理日に就業させてはいけない」と定められています。
労働基準法に記載されている生理日の就業が著しく困難な女性は「生理日に下腹痛や腰痛、頭痛などにより就業が困難な女性」を指します。
生理期間、また期間中の苦痛の程度、就労できるかどうかは個人差があるため、就労規則で一律に日数を制限することは適切でありません。ただし、企業の就業規則において生理休暇を有給とする場合に、有給の生理休暇の日数に上限を設け、上限を超える生理休暇を無給とすることは可能です。
生理休暇は、有給でも無給でも問題ありませんが、多くの場合は無給とされます。
3. 育児休業
育児休業は、育児・介護休業法第2条に基づく労働者の権利です。育児休業は、あらかじめ会社の規定に定められるべきですが、会社に規定がない場合でも労働者が申し出た場合は法律に基づいて取得させる義務があります。
産前・産後休業と同様に、育児休業中は賃金の支払いはありません。給与は労働の対価であるため、労働義務がない休業は給与が支払われないことが一般的です。
ただし、雇用保険に加入していれば育児休業中に育児休業給付金を受給できます。
育児休業中の育児休業給付金については、以下の記事をご覧ください。
4. 子の看護休暇
育児・介護休業法第16条第2項では、子の看護休暇について定められています。子の看護休暇とは、負傷または病気の子どもの看病のために必要な休暇で、労働基準法第39条の規定による有給休暇とは別に付与する必要があります。
名前のとおり、看護する場合や予防接種や検診などの事由でも休暇を取得可能です。ただし、子の看護休暇は無給であることが一般的です。
5. 介護休業
介護休業は、育児・介護休業法第11条により、要介護状態にある家族の介護が必要な際に付与する休暇です。要介護状態とは、負傷や疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態を指します。
介護休業も基本的に無給であり、給与の支払い義務はありません。しかし、雇用保険に加入していれば、介護休業給付金の受給が可能です。
無給休暇を付与する際の4つの注意点
無給休暇を導入・運用する際は、トラブルを避けるためにも注意点を理解しておくことが重要です。注意点を理解し、適切に導入すると、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、労働環境の向上につなげられます。
以下では、無給休暇を付与する際の注意点をそれぞれ解説します。
1. 無給休暇の取得を従業員に強制してはいけない
企業は、従業員に対して無給休暇の取得を強制してはいけません。
無給休暇は、従業員の請求に応じて取得させる必要があります。もし、会社都合で無給休暇を取得してもらう場合、労働基準法第26条により従業員に対して休業手当を支払う義務があります。
ただし、自然災害や疫病など、会社が細心の注意を払っていても避けられない休業の場合、従業員に無給休暇を付与することが可能です。
2. 有給休暇を無給休暇に変更すると違法となる
従業員から申請された有給休暇を無給休暇に変更するのは、法律違反です。
有給休暇は、労働義務が免除され、賃金の支払いが求められます。有給休暇は労働者の権利で、労働基準法でも有給休暇の付与が義務付けられています。
もし、企業が有給休暇を無給休暇に変更した場合、労働基準法第119条により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。
3. 無給休暇でも従業員の希望で自由に休めない
無給休暇でも、従業員の希望により自由に休めないため注意が必要です。
無給休暇は給与が発生しないことにより企業にとって負担がないと解釈する従業員もおり、自由に取得できると勘違いされることがあります。
会社と従業員との間で雇用契約を締結している以上、会社には業務上の命令を出す権利があり、従業員は命令に従う義務があります。
そのため、無給休暇の申請をしても必ず受理されるわけでなく、有給休暇と同様に時期の調節をする必要があることを周知しておきましょう。
4. 欠勤扱いしてはいけない
無給休暇は、欠勤扱いしてはいけません。
無給休暇は、法律や会社の規定に基づき、労働者が正当な手続きを経て取得する休暇であり、取得による懲戒処分や評価への悪影響はありません。また、無給休暇でも、勤怠処理上は休暇取得として記録する必要があります。
一方、欠勤は労働義務がある日に労働者の都合で無断または正当な理由なしに休むことです。無断欠勤が続く場合、懲戒処分の対象となることがあります。
したがって、無給休暇を欠勤することは認められません。
無給休暇を付与する際は勤怠管理を徹底しよう
無給休暇を従業員に付与する際は、法律を遵守し、勤怠管理を徹底することが重要です。
無給休暇中に勤怠管理システムを導入しておくことで、トラブルや従業員間の不公平感も防げます。企業は、無給休暇をコスト削減策として考えるのではなく、従業員の柔軟な働き方を支援する方法として位置付けておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
月45時間を超える残業は年6回まで?36協定の残業上限について解説
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間までと定められています。しかし、業務の都合でこれを超える残業や休日労働をさせる場合には、労使間で「36協定」を締結し、所轄…
詳しくみる【社労士監修】障害者雇用納付金・調整金とは?金額や対象企業、計算方法、手続きまとめ
常用雇用労働者数100人を超える民間企業には、「障害者雇用納付金」の申告・納付が義務付けられています。民間企業の障害者法定雇用率は2.5%で、未達成の場合には不足障害者1人につき1…
詳しくみるテンプレート付き – 休日出勤届について解説!
休日出勤届とは、法令で定められた法定休日に休日出勤する際に必要となる申請書です。使用者は労働者に一定の休日を付与しなければならず、休日労働させた場合は割増賃金を支払わなければなりま…
詳しくみる36協定の特別条項について、上限時間や注意点を解説
従業員の時間外労働は労働基準法で厳格に制限されています。時間外労働を課す場合はいわゆる36協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。上限時間は労働基準法に規定されてお…
詳しくみる副業・兼業してる人必見!…社労士がその留意点を解説
副業・兼業の現状 実態はいかに? 副業・兼業(以下「副業等」)を希望する人は年々増加傾向にあります。副業等を行う理由は、自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、資格の活用、十分…
詳しくみる休日出勤の代休は必ず取得すべき?ルールや賃金計算、振替時の注意点
「代休」とは、休日出勤によって休むことができなかった日の代わりにとして、出勤日に休日として仕事を休むことです。振替休日は休日が前もって振替えられるのに対し、代休はあとから変更されま…
詳しくみる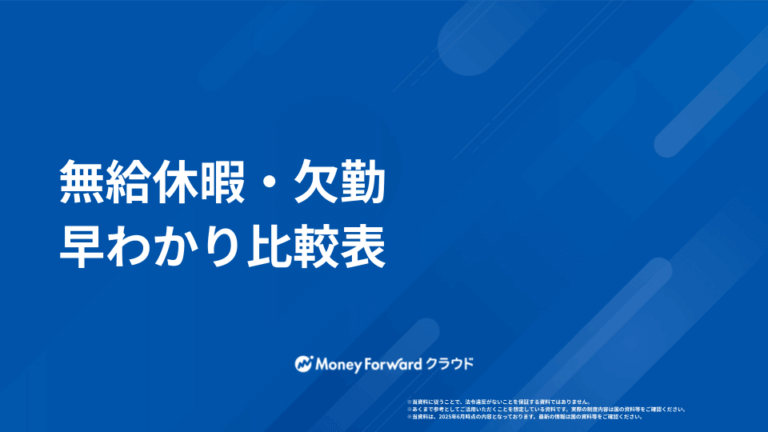


-e1761054979433.png)

