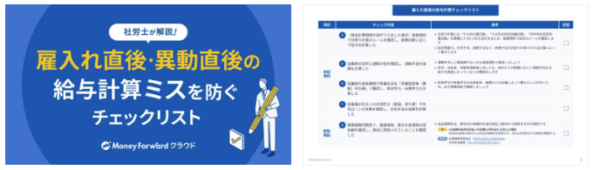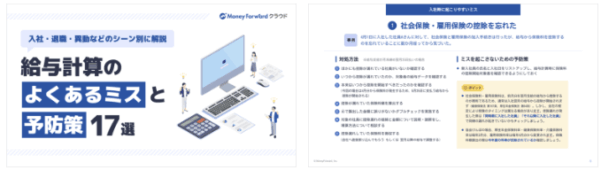- 更新日 : 2025年12月24日
新人だけど部署異動したい!希望の伝え方や異動できない場合の対処法を解説
新人として入社すると、最初は期待や希望に満ち溢れているものです。しかし実際に配属されると、「このまま今の部署で働き続けて大丈夫なのか」「自分に合わないかもしれない」といった不安やストレスを抱えるケースも少なくありません。この記事では、新人が部署異動するための具体的な方法や、部署異動できない場合の対処法などをわかりやすく解説します。
目次
新人が部署異動したいと感じる理由
そもそも、なぜ新人が部署異動したいと感じるのでしょうか。
人間関係のストレス
新人が部署異動したいと感じる大きな要因として、人間関係のストレスが挙げられます。特に入社半年や1年目のうちは職場のルールや雰囲気をつかむ余裕がなく、周囲とのコミュニケーションが思うようにいかないことも多いでしょう。特に、上司や先輩との価値観の違いや他部署への憧れがあると、ミスマッチが起こりがちです。
業務内容が合わない
新人のうちは、仕事の内容について十分に理解できていないまま配属先が決まることがよくあります。そのため、実際に業務をこなしてみて「想像と違う」「自分の得意分野ではない」と感じる新入社員が出てくるのです。例えば、理系出身なのに営業部に配属された、あるいはデスクワークが得意なのに外回りの仕事が多いなど、自分の強みが活かせない場合に異動したいと感じるようになります。
使えないと言われるプレッシャー
新入社員の中には、自分の部署内で「使えない」と評価されているのではないかと不安に思う人もいます。実際にそう言われていなくても、周囲の目が気になりプレッシャーを感じやすいです。自分は頑張っているつもりでも、周囲からのフィードバックが追いつかず「もっとやれるのでは?」と言われてしまうケースもあります。
キャリアの方向性が不透明
数年先のキャリアを考えたときに、今の部署では自分の理想とするスキルが身につかないと感じる場合もあります。特に入社2年目〜3年目になると、周囲の先輩を見て「このままでいいのか」と疑問を持つようになり、はやめに異動したいと思う新人も少なくありません。キャリアアップを目指す上で、社内での部署異動が認められないと、転職を検討するきっかけにもなります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
新人が部署異動の希望を出すか検討すべきポイント
部署異動を考え始めた新人は「どのタイミングで異動の希望を出すべきか」「自分の判断は正しいのか」と迷うことが多いでしょう。何も考えずに行動すると社内での評価を下げる可能性があるため、慎重に検討することが大切です。ここでは、新人が部署異動の希望を出す前にチェックしておきたいポイントを紹介します。
ストレスが一時的なものかを見極める
配属当初は覚えることも多く、慣れない環境でストレスを感じやすい時期です。新人にとっては「自分に合わないかもしれない」という悩みが強く出るタイミングでもあります。しかし、そのストレスが一時的なものなのか、長期的に続く可能性があるものなのかを冷静に判断することが重要です。
キャリアプランとの整合性を考える
部署異動したいと思う理由が、将来のキャリアプランとつながっているかどうかも大切な視点です。自分が成長したい方向と、異動先の業務内容が合致していなければ、部署を変わっても期待通りの成果を得られない可能性があります。まずは、5年後、10年後にどうなっていたいかという中長期的な目標を整理してみましょう。
わがままだと思われる可能性がある
新人が部署異動を希望すると、上司や同僚から「まだ早いのでは?」「わがままではないか」と思われる可能性があります。こうした不安がある場合は、周囲に与える影響を事前にシミュレーションしておくと安心です。また、人事担当や先輩社員に、異動に関する社内の仕組みや制度を確認してみるのもよいでしょう。
新人が部署異動するための具体的な方法
部署異動を希望する理由や必要性をしっかりと検討したあとは、実際に行動に移すステップへと進みましょう。ここでは、新人が部署異動を実現するための具体的な方法を解説します。
異動先の部署や業務内容を明確にする
異動を成功させるためには、「なぜその部署なのか」「どんな業務をやりたいのか」をはっきりさせることが大切です。ただ漠然と「今の部署が合わない」という理由だけでは、会社側を納得させるのが難しくなります。異動を希望する部署の情報を収集し、具体的な仕事のイメージを掴んでおきましょう。異動後に得られるスキルや経験が、自分のキャリアプランにどう役立つかも明確する必要があります。
実績やアピールポイントを整理する
新人はまだ実績が少ないものの、配属後に取り組んだプロジェクトや業務で学んだことは必ずあるはずです。こうした実績やアピールポイントを整理し、異動のアピール材料にしましょう。例えば、担当業務の成果をリスト化し、数値目標を達成した事例や、改善提案が採用された事例などを具体的に書き出すと、自分の強みを認識しやすくなります。また、業務を通じて習得したスキル・知識を棚卸しすると、異動後にどう活かせるかイメージしやすくなります。
上司や先輩、人事担当に相談する
異動の可否は会社の方針やタイミングにも左右されるため、独断で進めるのではなく周囲に相談することが大切です。例えば、配属先の上司に相談することで、現状の評価や可能性についてフィードバックが得られます。異動後の業務に備えるためにも、足りないスキルや知識を教えてもらいましょう。人事担当者からは、異動申請の手続きや部署の空き状況など、具体的な情報を得られます。制度やルールを把握しながら進めるのがポイントです。
会社のキャリア支援制度を活用する
多くの企業では、新人を含む社員のキャリア形成をサポートする制度が用意されています。部署異動を目指す新人は、こうした制度を積極的に活用して自分の成長をアピールしましょう。例えば、社内研修・勉強会に参加し、希望する部署に必要なスキルを学べば、配属後の即戦力として評価されやすくなります。また、資格手当や補助金が出る場合は、積極的に利用することで専門性を高めつつ会社に貢献できます。
新人が部署異動できない場合の対処法
部署異動を希望していても、会社の都合やタイミングにより、すぐに異動が認められない場合があります。ここでは、そのような状況に直面した新人がどのように対処すればいいのかを具体的に解説します。
異動できない原因を客観的に把握する
まずは、なぜ部署異動ができないのかを明確にすることが大切です。例えば、多くの企業では部署異動のタイミングが決まっているため、希望が通るのは年1回や半年に1回などに限定される場合があります。また、企業として新人に一定期間は現部署で経験を積んでほしいなど、組織的な理由で異動を制限している可能性があります。
まずは現部署でスキルアップを目指す
今の段階では異動が難しいとしても、現部署でスキルアップを目指せば、次のチャンスにつながる可能性があります。同じ部署内でも新しいプロジェクトに参加させてもらうなど、担当業務の幅を広げてみるとよいでしょう。また、将来的に異動を成功させるため、今の部署でどんなスキルを身につけるべきなのかという目標を明確に設定しながら行動するのもおすすめです。
相談を継続して次の異動のチャンスを狙う
一度異動を断られたからといって、今後ずっと異動できないわけではありません。重要なのは、周囲と良好な関係を保ちつつ、適切なタイミングを待つことです。例えば、半年に一度など、定期的に上司とキャリアについて話し合う場を設けることで、自分の希望がぶれないことをアピールできます。また、人事担当への相談を継続し、会社全体の異動状況や新たな空きポジションなどの情報を共有してもらうと、次のチャンスを逃さずに済みます。
新人の部署異動について職場が配慮すべきポイント
新人が部署異動を希望する場合、職場としても配慮が求められます。ここでは、新人が部署異動をスムーズに検討・実現できるよう、企業や上司が配慮すべき具体的なポイントを紹介します。
新人のメンタル面に配慮する
新人はまだ仕事に慣れていないため、些細なトラブルでも大きなストレスとなる可能性があります。特に、部署異動を検討するほどの悩みを抱えている場合は、心身の健康管理に十分配慮する必要があります。そのため、産業医やカウンセラーへの相談窓口を設置し、早期にフォローできる体制を整えておくと安心です。また、普段から上司や同僚と気軽に話し合える雰囲気づくりをすることがストレスの軽減につながります。
本人の希望や適性を踏まえた配属を行う
新人は、自分の得意分野や将来のキャリアがまだはっきりしていないことも多いでしょう。とはいえ、本人の適性を無視した配属が続くと、パフォーマンスの低下や早期離職につながりかねません。そのため、新入社員研修などの実績をもとに、どの部署で活躍できそうかを客観的に判断しましょう。本人の希望を一方的に聞くだけでなく、キャリア形成をサポートする視点で適切にアドバイスする姿勢が重要です。
チーム全体でフォローする体制を整える
新人が部署異動を考える背景には、上司や先輩に相談しづらい環境も影響することがあります。一人の上司だけでなく、チーム全体で新入社員をフォローできる仕組みがあれば、不安や悩みをフォローしやすくなります。例えば、先輩社員がメンターとして新人をサポートするメンター制度の導入によって、日々の悩みを気軽に相談しやすくなります。また、同期や他部署の新人との情報交換の場を設けると、「自分だけが悩んでいるわけではない」という安心感を得られます。
新人の部署異動はわがままではない
この記事では、新人が部署異動するための具体的な方法や、部署異動できない場合の対処法などを解説しました。部署異動を検討するなかで「わがままではないか」と悩む新人は少なくありませんが、適性やキャリアプランにマッチした仕事を選ぶことは、本人だけでなく会社にとってもプラスの効果があります。周囲の目を気にしすぎず、まずは自分にとってベストな選択を見極めるための情報収集と行動を心がけてみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
アルバイトでも産休・育休は取得可能!正しい申請方法や給料・扶養について
アルバイトでも産休・育休の取得は可能です。 しかし、取得の際には制度の概要を理解し、申請に関する注意点などを知っておく必要があります。 また、育休については、取得に際しての条件があ…
詳しくみる【テンプレート付き】通達とは?意味や通知との違い、社内通達・人事通達の基本事項を解説
会社などの組織運営では、情報や指示を伝えるコミュニケーション手段が非常に重要です。その一つに「通達」と呼ばれるものがあります。 しかし、通知や通告など、これに類似した用語は複数あり…
詳しくみる配置転換と転勤の違いを解説!目的や無効となるケースも紹介
配置転換と転勤は、社員の人事異動において意味合いが大きく異なります。本記事では、根本的な違いからそれぞれの目的や無効となるケース、人事異動を成功させるためのポイントまで詳しくご紹介…
詳しくみる離職票が届かない場合はどうすべき?届くまでの通常日数や届かない原因も解説
離職票は失業保険を申請するときに必ず提出しなければならない書類です。通常であれば退職してから10日~2週間ほどで届きます。 ただ失業手当を受給しようと考えている人の中には「なかなか…
詳しくみるジョブコーチ(職場適応援助者)とは?支援内容や種類、助成金制度など解説!
障害のある従業員を雇用する際、企業は適切な支援体制を整備することが重要です。そこで注目されているのが、ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援です。ジョブコーチは、障害者の職場適応…
詳しくみる雇用期間満了通知書とは?目的や書き方を解説!無料テンプレートつき
有期労働契約の締結時や満了時に生じやすいトラブルを未然に防止するため、厚生労働大臣は、労働基準法第14条第2項の規定に基づき「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」を定め…
詳しくみる