- 更新日 : 2026年1月14日
2026年最新!給与計算におすすめの本13選【初心者・資格勉強にも】無料の給料計算テンプレつき
給与計算はミスが許されない重要な業務です。そのため、業務の内容や知識に不安を感じている初心者の方も多いでしょう。給与計算に関する知識や実務を習得するには、本を読むのがおすすめです。本記事では初心者向けや資格取得など、給与計算に関するおすすめの本を13冊ご紹介します。
目次
まずはこの3冊!給与計算に関する無料のガイド
給与計算におすすめの本を探している方に役立つガイドをピックアップしていますので、ぜひご自由にダウンロードしてご活用ください。
給与計算の内製化を実現するための8ステップ
「給与計算は、何をやればいいかわからない」「システム運用コストや業務負荷は最小限に抑えたい」、そんな悩みを抱える人事労務担当の方に向け、給与計算の内製化実現に向けて取り組みたい8つのステップを解説します。
社労士が解説!給与計算ミスを防ぐ60のチェックリスト<完全版>
給与計算ミスの発生を防ぐため、雇入れ直後・異動直後などのシーン別に確認すべきポイントをチェックリストとしてまとめました。起こりやすいミスの傾向についても解説していますので、ぜひ業務にお役立てください。
給与計算のExcel作業、どこまで減らせる?
「給与計算ソフトを導入したけれど、Excelによる手作業が多い…」そんな悩みを抱えている方に向けて、Excel作業の削減ポイントを解説します。手作業を最小限にする仕組み作りのヒントとしてご活用ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
給与計算初心者にもわかりやすい本
初めて給与計算をする方にも、わかりやすいおすすめの本は以下の4冊です。
- 2024年版 まるわかり給与計算の手続きと基本
- 図解即戦力 給与計算の手続きがこれ1冊でしっかりわかる本
- この1冊でスラスラ! 給与計算大全
- 6年版 初心者にもよくわかる 給与計算マニュアル
以下で、それぞれの内容を解説します。
2024年版 まるわかり給与計算の手続きと基本
「2024年版 まるわかり給与計算の手続きと基本」は特定社会保険労務士が執筆しているため、実務に沿った1冊です。
本書では第1章で賃金の仕組みや所得税の仕組み、社会保険についてわかりやすく紹介しています。その後、第2章で給与計算のすすめ方を説明しているため、初心者でも仕組みを理解しやすいでしょう。フローチャートや図解が豊富にあるため、間違えやすい箇所などについてわかりやすく整理できます。
2024年版 まるわかり給与計算の手続きと基本の詳細はこちら
図解即戦力 給与計算の手続きがこれ1冊でしっかりわかる本
「図解即戦力 給与計算の手続きがこれ1冊でしっかりわかる本」の監修者は、社会保険労務士だけでなく、事業法人での実務や労務コンサルティングも経験しています。そのため解説がわかりやすく、新人や兼任担当者でも適切なスケジュールで給与処理する知識の習得が可能です。
オールカラーなので見やすく、重要な箇所にはマーカーが引いてあります。全9章からなり、実務や手続きごとに細かく段落わけしているため、知りたいことをすぐに調べられる点も特徴といえるでしょう。さらに、実務に役立つ書式シートのダウンロードサービスが付帯している点も、メリットの一つです。
図解即戦力 給与計算の手続きがこれ1冊でしっかりわかる本の詳細はこちら
この1冊でスラスラ! 給与計算大全
「この1冊でスラスラ! 給与計算大全」では冒頭で、給与担当者の年間スケジュールおよび月間スケジュールを紹介しています。これから経理業務を行う方にとっては、具体的な働き方がイメージしやすくなるでしょう。
また混同しがちな言葉の言い回しも、丁寧に表でまとめています。わかりにくい言い回しなども解説しているため、初心者の方でも抵抗を感じることなく読みすすめられるでしょう。
6年版 初心者にもよくわかる 給与計算マニュアル
続いてのおすすめの本が「6年版 初心者にもよくわかる 給与計算マニュアル」です。本書は30年以上続くロングセラー商品であり、多くの給与計算担当者が利用してきたマニュアルといえます。
ロングセラーではありますが、毎年最新の税制や実務について詳しく紹介しているため、お世話になっている経理担当者も多いでしょう。各種様式の記載方法や具体的な計算事例などを示しているため、初心者でもわかりやすい内容となっています。令和6年版では所得税・住民税の定額減税についても、詳しく解説しています。
給与計算のエクセルフォーマット(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
・給与計算のエクセルフォーマット(賃金台帳、給与計算表)のテンプレート
給与計算と社会保険・年末調整手続きを学べる本
給与計算に加えて、社会保険や年末調整手続きも学べる本は以下の4冊です。
- 令和6年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと
- 小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本 ’24~’25年版
- 基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険 24-25年版
- 増補改訂 給与計算・年末調整の手続きがぜんぶ自分でできる本【令和6年の定額減税に対応】
以下で、それぞれの内容を確認しておきましょう。
令和6年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと
この本の特徴は、タイトルにある通り給与計算と社会保険の事務を関連づけて説明している点です。本書を読みすすめるうちに月ごとの仕事の流れが、おのずと身につくでしょう。
毎年の改正点を丁寧に説明しているためベテラン担当者にも役立つほか、冒頭では実務知識を問う設問があるなど初心者にもおすすめです。図表や段落構成なども見やすく工夫されているため、ストレスを感じずに読める点も魅力といえます。
令和6年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごとの詳細はこちら
小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本 ’24~’25年版
この本は給与計算だけでなく、社会保険に関する事務手続きが詳しく記載されている点が特徴です。わかりやすく年間のタイムスケジュール別にまとめてあるため、初心者でも安心して事務に取り組めます。
たとえば、4月であれば入社に関する事務、6月は住民税、7月は賞与や労働保険の更新など、月ごとに調べたい事務手続きがまとめてあります。さらに入社時のチェックリスト、年末調整のチェックリストなど実務に役立つ各種チェックリストもあるため、手続きミスの防止に役立つでしょう。
小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本 ’24~’25年版の詳細はこちら
基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険 24-25年版
「基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険 24-25年版」は社会保険労務士と税理士が監修しているため、基礎的な知識から実務まで詳しく丁寧に解説している点が特徴です。
全7章の構成となっており、1~3章で基本的な知識と年間スケジュール、4~7章ではそれぞれの実務について解説しています。全体を通じて表や図解などが多く、基礎的な知識のない方でもわかりやすい内容です。また、巻末には出勤簿や給与規定、賃金台帳なども添付されているため、自社にフォーマットがない場合でも困りません。
基本と実務がよくわかる 小さな会社の給与計算と社会保険 24-25年版の詳細はこちら
増補改訂 給与計算・年末調整の手続きがぜんぶ自分でできる本【令和6年の定額減税に対応】
「増補改訂 給与計算・年末調整の手続きがぜんぶ自分でできる本【令和6年の定額減税に対応】」は、初心者の方向けに給与計算をはじめとした手続きのやり方を詳しく解説しています。
オールカラーで図や表も多く使っているため、非常にわかりやすくまとまっています。要所要所でキャラクターが重要ポイントを補足しているなど、堅苦しくなく初心者でもサクサク読みすすめられるでしょう。
増補改訂 給与計算・年末調整の手続きがぜんぶ自分でできる本【令和6年の定額減税に対応】の詳細はこちら
給与計算担当者が困ったときに参考になる本
ここからは、給与計算などをしていて困ったとき参考になる本を、3冊ご紹介します。
- 最新 知りたいことがパッとわかる 給与計算の事務手続き・届け出ができる本
- こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30
- こんなときどうする!?PART2 社会保険・給与計算“困った”に備える見直し・確認の具体例20
それぞれの内容を解説します。
最新 知りたいことがパッとわかる 給与計算の事務手続き・届け出ができる本
「最新 知りたいことがパッとわかる 給与計算の事務手続き・届け出ができる本」の特徴はタイトルにもあるとおり、わからないことがすぐに確認できる点です。月次の業務や年間のスケジュールなどが業務ごとに章分けされているため、わからないことも簡単に調べられます。
また、この本では知識に不安のある方でも、体系的に給与計算ができるようにまとめられています。必要書類の書き方をサンプルでまとめているため、すぐに実務にも活かせます。
最新 知りたいことがパッとわかる 給与計算の事務手続き・届け出ができる本の詳細はこちら
こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30
「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」は、ミスが発生してしまった際のリカバリー方法を中心に解説している本です。
普段からミスには気をつけていても、どうしてもミスは起こってしまいます。困ったときこの本を見れば、解決方法だけでなく、今後のミス防止対策までわかります。「実際にミスが起こった際に、この本で解決できた」という口コミも多く、経理担当者であれば持っておきたい一冊といえるでしょう。
こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30の詳細はこちら
こんなときどうする!?PART2 社会保険・給与計算“困った”に備える見直し・確認の具体例20
「こんなときどうする!?PART2 社会保険・給与計算“困った”に備える見直し・確認の具体例20」は、さまざまな事例ごとに対応策をまとめた本です。たとえば従業員が介護休暇をとったり、短期のアルバイトを採用したりするなど、ケースごとの実務を紹介しています。
目次で各ケースを紹介しているため、知りたいページがすぐにわかり問題解決ができるでしょう。また本書の購入特典として、業務に使えるチェックリストや申請書などの社内ファイルのダウンロードが可能です。ミスの事前防止など、実際の業務に役立てられるでしょう。
こんなときどうする!?PART2 社会保険・給与計算“困った”に備える見直し・確認の具体例20の詳細はこちら
給与計算の資格勉強におすすめの本
給与計算の知識や実務能力を測定する試験が、給与計算実務能力検定です。この資格には1級と2級があり、それぞれの資格取得におすすめの本を紹介します。
2024年度版 給与計算実務能力検定®1級公式テキスト
1級の資格取得におすすめなのが「2024年度版 給与計算実務能力検定®1級公式テキスト」です。給与計算実務能力検定1級は、基本的な給与計算ができるだけでなくイレギュラーなものへの対応も問われます。
給与計算だけでなく社会保険や年末調整・税務など、給与に関するすべての知識に精通していなくてはなりません。この本は1級の公式テキストであり、2024年度の最新の試験にも対応しています。本文解説と試験対策の問題を収録しており、資格取得を目指す方だけでなく業務に携わっている管理者にもおすすめです。
2024年度版 給与計算実務能力検定®1級公式テキストの詳細はこちら
2024年度版 給与計算実務能力検定®2級公式テキスト
2級の資格取得を目指す場合は「2024年度版 給与計算実務能力検定®2級公式テキスト」がおすすめです。給与計算実務能力検定の2級では、基本的な給与計算ができて明細をつくれるレベルが必要です。
年末調整など複雑な業務は範囲に含まれないため、初心者でも目指しやすい資格といえるでしょう。この本は2級試験の公式テキストであり、2024年に対応した最新版です。2級の資格取得を目指すのであれば、必携の一冊です。
2024年度版 給与計算実務能力検定®2級公式テキストの詳細はこちら
給与計算の習得には本の活用がおすすめ
給与計算は正確さが求められる業務であるため、初心者や資格取得を目指す方にとって本選びは重要です。本記事では、給与計算初心者向けの入門書から資格取得に役立つ公式テキスト、困ったときに参考になる実務書まで、2024年最新のおすすめの本を13冊厳選してご紹介しました。それぞれの本の特徴や活用方法を詳しく解説し、初心者から経験者まで幅広いニーズに応える内容です。給与計算スキルの向上や、資格試験対策に最適な1冊を探してみてはいかがでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
国家公務員の扶養手当とは?支給要件や配偶者手当廃止の影響を解説
国家公務員の扶養手当について、支給額や対象要件、特に注目される配偶者手当の廃止時期など、最新の情報を知りたい担当者も多いでしょう。国家公務員の手当制度は民間の給与体系とは異なり、子…
詳しくみる給料手当とは?手当の種類や仕訳方法、課税対象について解説
企業で働く従業員には、労働の対償として賃金が支払われます。賃金には、給与や給料、手当など様々な呼び方や種類がありますが、それぞれにどのような違いがあるのでしょうか。 当記事では、給…
詳しくみる懲戒処分の減給に上限ルールはある?計算方法や要件を解説
従業員の企業秩序違反に対する制裁である懲戒処分としての「減給」には、労働基準法で定められた厳格な上限ルールがあります。そのため、企業がペナルティとして自由に給料を減額できるわけでは…
詳しくみる頑張った手当とは?特別手当の一種!ボーナスとの違いや相場、ユニークな名称の事例も
「従業員の頑張りを正当に評価し、組織の活性化につなげたい。」そう考える経営者や人事担当者の皆様にとって、「頑張った手当」は非常に魅力的な選択肢の一つです。 この記事では、頑張った手…
詳しくみる1分単位で給与計算しないと違法?計算方法や端数処理できる例外も解説【無料テンプレートつき】
労働時間は1分単位で計算しなければなりません。例外として、月単位で30分未満や30分を超えた場合は、切り捨て、切り上げができるケースもあります。会社独自で15分単位、30分単位の切…
詳しくみるコロナの影響で住民税納税が難しい人向け 徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響で事業に支障が出ている個人事業者の方、中小企業の経営者の方もおられるでしょう。政府のコロナ対策としては、中小企業者や個人事業者向けの持続化給付金、フリーラン…
詳しくみる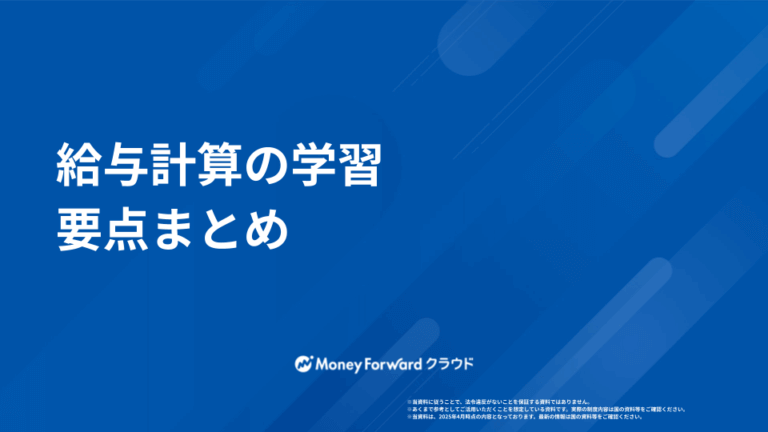




-e1762740828456.png)

