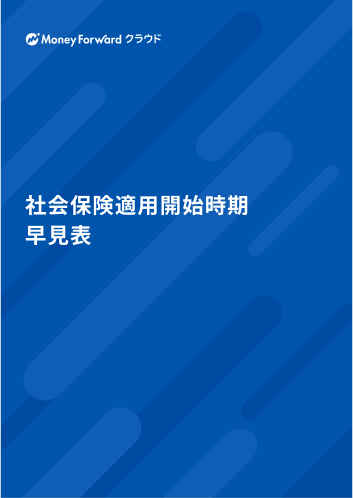- 更新日 : 2025年11月5日
社会保険は勤務期間の2ヵ月後から適用?令和4年10月の変更点
有期契約社員は、正社員とは社会保険の加入条件が異なります。旧制度では、契約期間が2ヵ月未満の方はその間の加入は不要でした。令和4年10月以降は更新の可能性がある場合、2ヵ月後からではなく契約時から加入が必須となります。3ヵ月目からの加入は違法なので注意が必要です。当記事では、社会保険の勤務期間要件について解説します。
目次
社会保険の適用開始は勤務期間のいつから?
正社員の場合、社会保険の適用開始、すなわち加入日は入社日です。一方、パート・アルバイト・有期契約社員の場合、社会保険の加入条件が正社員とは異なります。そもそも社会保険は、社会保険適用事業所に所属している方は必ず加入しなければならない強制保険です。適用要件には勤務期間も含まれており、令和4年10月から取り扱いが変更されています。
なお、当記事における社会保険は厚生年金保険と健康保険からなる「狭義の社会保険」を意味します。場合によっては雇用保険と労働者災害補償保険、いわゆる労災保険も含めて「広義の社会保険」と呼ばれることもありますが、雇用保険と労災保険からなる労働保険は適用条件が異なるため注意しましょう。
| 広義の社会保険 | 狭義の社会保険 | 厚生年金保険 |
| 健康保険 | ||
| 労働保険 | 雇用保険 | |
| 労災保険 |
ここでは、旧制度と令和4年10月以降における「狭義の社会保険」の適応要件を紹介します。
令和4年度10月以前は1年間勤務
まず、旧制度における社会保険の適用要件を紹介します。冒頭でもお伝えした通り、社会保険は適用事業所に所属するすべての方が原則加入しなければならない強制保険です。要件を満たした方は、その方の意思に関わらず必ず加入しなければならないため気をつけましょう。雇用形態は問わないため、正社員だけでなくパートやアルバイト、有期契約社員にも適用されます。令和4年10月以前の適用要件は下記の通りです。
- フルタイムで働く方
- 週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方
パート・アルバイトなどの短時間労働者については下記の要件が適用されます。
- 従業員数501人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 1年を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
旧制度では、雇用期間が1年を超える見込みがある方のみ社会保険への加入が必要でした。一方、厚生年金保険法第12条および健康保険法第3条第1項第2号には適用除外として「二月以内の期間を定めて使用される者」と定められています。そのため、契約期間が2ヵ月以内の有期契約社員は社会保険に加入する必要はありません。契約が更新される場合は、3ヵ月目から適用となります。

参考:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
令和4年度10月以後は2ヵ月勤務
社会保険の適用範囲拡大を目的に法律改正が行われ、雇用期間が2ヵ月に短縮されました。令和4年10月以降の適用要件は下記の通りです。
- フルタイムで働く方
- 週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方
有期契約社員やパート・アルバイトなどの短時間労働者については下記の要件が適用されます。
- 従業員数101人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同等)
- 学生でない
法律改正によって、令和4年10月以降2ヵ月を超えて雇用の見込みがある方は社会保険への加入が必要です。あわせて適用除外要件も変更され、厚生年金保険法第12条および健康保険法第3条第1項第2号は「二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」と改められました。すなわち、契約期間が2ヵ月以内であっても、雇用契約書等に契約が更新される旨が明示されている場合は、社会保険に加入しなければなりません。

参考:厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。|日本年金機構
参考:厚生年金保険法(第十二条) | e-Gov法令検索
参考:健康保険法(第三条) | e-Gov法令検索
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
勤務期間2ヵ月未満の場合でも社会保険が適用されるケースはある?
雇用期間に定めのない正社員の場合は、入社日が社会保険の加入日となります。有期契約社員の場合は前章で解説した通り、雇用契約書等に契約更新条項が明示され2ヵ月を超えて雇用される場合は、契約当初より社会保険に加入しなければなりません。旧制度では契約更新までの2ヵ月間は適用除外期間でしたが、下記に該当する場合は契約期間が2ヵ月以内であっても社会保険が適用されるため気をつけましょう。
- 就業規則や雇用契約書等に、契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
- 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により雇用契約期間を超えて雇用された実績がある場合
上記に該当する場合であっても、2ヵ月以内の契約期間を超えて雇用しない旨の労使間合意がある場合は、適用除外として取り扱われます。労使間合意は、メールを含む書面にて執り行う必要があるため注意しましょう。
なお、雇用期間の算定は入社日から退職日までとなります。例えば5月15日に入社し7月14日に退職した場合、在籍期間は5月・6月・7月の3ヵ月間に及びますが、雇用期間は61日間の2ヵ月です。ただし、保険料については日割り計算されずに月の途中で入社しても1ヶ月分納付しなければならないため気をつけましょう。
(※なお、月途中の退職の場合は、その月の保険料は発生しないものの、入社月(取得月)と喪失月が同じ場合は月途中であっても保険料が発生します)
3ヵ月目に社会保険の適用開始をしないと違法?
前述の通り、有期契約社員の方は契約更新条項が明示されている場合、令和4年10月以降は契約当初から社会保険に加入しなければなりません。旧制度においても、3ヵ月目からは加入が必須です。加入要件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入させないと、事業所は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるため気をつけましょう。
一方、2ヵ月を超える雇用の見込みがない有期契約社員の場合は、社会保険に加入する必要はありません。ただし、雇用契約の更新予定が無い場合でも、状況等の変化によって契約更新が見込まれる場合は、社会保険に加入する必要があります。その際の適用日は、契約の更新が見込まれるに至った日です。同様に、2ヵ月以内の契約期間を超えて雇用しない旨の労使間合意を取り交わしている場合、その後の状況変化等で合意を撤回し契約期間を超えて雇用される見込みとなった際には、社会保険に加入しなければなりません。適用日は、合意が撤回され契約の更新が見込まれるに至った日です。なお、「契約の更新が見込まれるに至った日」とは、メールを含む書面等によって労使間の合意に至った日となります。
契約時は社会保険の適用除外であっても、状況等の変化によって適用となるケースも十分あり得るでしょう。適用要件を満たした時点で速やかに社会保険に加入させないと、事業所に罰則が科せられるため注意しましょう。
参考:「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)」に伴う事務の取扱いに関するQ&A集|日本年金機構
適用条件を把握し正しく社会保険に加入しよう
社会保険の適用要件について解説しました。正社員は、入社と同時に社会保険に加入することになります。有期契約社員の方で2ヵ月以上継続した雇用が見込める場合は、正社員と同様入社と同時に社会保険に加入しなければなりません。旧制度では入社後2ヵ月間は適用除外期間でしたが、令和4年10月以降は雇用契約書等に契約更新条項が明示されている場合は契約当初から適用となります。
さらに、パートやアルバイトなどの短時間労働者は、以前は1年を超える雇用の見込みがある場合のみ社会保険の適用となっていましたが、法律改正にあわせて2ヵ月に短縮されました。適用要件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入させないと、事業所は罰則を科せられるため注意が必要です。令和4年10月に変更となった適用条件を把握し、正しく社会保険に加入しましょう。
よくある質問
社会保険の適用開始は、勤務期間のいつからですか?
正社員は入社日が適用開始日です。令和4年10月以降は、2ヵ月を超える雇用期間が見込める有期契約社員の場合も、入社と同時に社会保険が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
3ヵ月目以降に従業員に対して社会保険の適用を行わなかった場合、違法になりますか?
加入要件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入させないことは違法です。事業所は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるため気をつけましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
引越ししたら、どうする? 住所変更時の社会保険手続き
社会保険の適用事業所に勤める従業員が結婚、転居、自宅の新築などで住所が変更になったときには、住所の変更状況を国が把握しなければなりません。 住所変更先が国内か国外かによって把握する…
詳しくみる給料と労災給付は同時にもらえる?支給の条件を解説!
労災で働けないため休職すると、労災保険から休業補償給付を受けることができます。支給額は、休業1日について給料の約60%で、治癒するまで打ち切りはありません。賃金が支払われないことが…
詳しくみる厚生年金の資格期間が10年未満の場合 – 受給できるのかを解説
日本の年金制度では、国民年金、厚生年金への加入期間が10年以上でなければ受給資格がないとされています。では、これらの年金に加入していた期間が10年未満の場合には、もう受給する方法は…
詳しくみる社会保険の扶養とは?年収の壁についても解説
配偶者の収入で生活している専業主婦などは、自分では社会保険に加入しなくてもよい場合があります。社会保険被保険者である配偶者の扶養に入ることで、自分自身は社会保険料を納付しなくても健…
詳しくみる労働災害(労災)とは?種類や対策について解説!
企業の人事担当者にとって、労働災害の発生は避けられない課題の一つです。予期せぬ事故はいつでも発生する可能性があり、その際には迅速かつ適切な対応が求められます。本記事では、労働災害に…
詳しくみる標準報酬月額とは?決め方や計算方法、間違えた場合をわかりやすく解説!
毎月の給料から、標準報酬月額をもとにした社会保険料が控除されています。この標準報酬月額は、1年に1度の定時決定や、報酬額が大きく変わった場合に行われる随時改定などで決定されます。こ…
詳しくみる