- 更新日 : 2025年11月11日
厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?申請方法や結婚後の年金について解説!
厚生年金保険に結婚を対象とする給付はありませんが、企業による厚生年金基金には被保険者が結婚した際に支給する祝い金制度が設けられていることがあり、定められた方法で申請すると給付を受けられます。厚生年金被保険者が結婚後も働き続ける場合は、そのまま加入が継続されます。退職して扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者になります。
目次
厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?
厚生年金保険は、老齢・障害・死亡に対して給付を行う制度です。結婚を支給事由とする給付はないため、被保険者や被保険者であった者が結婚したとしても結婚祝い金は支給されません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
厚生年金加入者の結婚祝い金の申請方法は?
厚生年金保険に結婚祝い金制度はありませんが、厚生年金基金には加入者が結婚すると祝い金を支給するものがあります。厚生年金基金は手厚い保障を行うために、大企業が独自に設立・運営する企業年金です。厚生年金では行わない結婚に対する給付を制度として設けている厚生年金基金もあります。
申請方法も厚生年金基金によって異なるため、手続きを行う際は会社に確認しなければなりません。また、受給には加入期間の条件が設定されているものもあるため、手続き方法と併せて確認しておきましょう。
厚生年金加入者が結婚すると年金の取り扱いが変わる?
結婚祝い金が受け取れるか受け取れないかに関わらず、厚生年金加入者が結婚すると年金の取り扱いが変わることがあります。取り扱いが変更になるケースや必要な手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。2つの場合に分けて解説します。
結婚後に退職して扶養に入る場合
結婚を機に勤めをやめると、厚生年金の加入者でなくなります。別の勤め先で働いたり、自営業を始めたりしない場合は配偶者の扶養に入ることができ、国民年金では第2号被保険者から第3号被保険者へ変わります。第2号被保険者の勤務先が「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を提出することによって、第3号被保険者になる手続きが行われます。
- 第1号被保険者に扶養される場合
扶養に入って国民年金第3号被保険者となることができるのは、配偶者が国民年金第2号被保険者である場合、つまり厚生年金に加入している場合です。配偶者が国民年金第1号被保険者(自営業者や農業者など)である場合は、扶養に入って第3号被保険者になることはできません。配偶者と同じ第1号被保険者になるための手続きを、自分で行う必要があります。
結婚後も仕事を続ける場合
結婚しても勤めをやめない場合、厚生年金への加入は継続します。厚生年金被保険者資格の喪失や国民年金被保険者種別の変更はないため、手続きは不要です。ただし、住所や氏名が変わる場合は届出が必要です。仕事上では旧姓を使用する場合も、年金では氏名変更の届出をしなければなりません。
- 届出が不要な場合
マイナンバーと基礎年金番号の紐づけができている場合は、住所変更や氏名変更の届出は不要です。紐づけができているかどうかは、ねんきんネットで確認するか、近くの年金事務所へ問い合わせることで調べられます。ただし、マイナンバーとの紐づけによって年金で住所変更や氏名変更が不要の場合でも、健康保険で届出が必要になる場合があります。
厚生年金加入者の結婚時は必要な届出を忘れないようにしよう
厚生年金保険は老齢・障害・死亡に対して年金や一時金を支給するもので、結婚を支給事由とする給付はありません。そのため、加入者は厚生年金から結婚祝い金を受け取ることはできませんが、厚生年金基金には加入者の結婚に対して祝い金制度を設けているものもあるため、必要な手続き方法と併せて確認しておきましょう。
結婚した厚生年金加入者は、住所や氏名の変更届を提出する必要があります。勤めをやめた場合は、国民年金の手続きが必要になることもあります。行わなければならない手続きや届出を確認し、忘れずに行いましょう。
よくある質問
厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?
厚生年金保険には結婚を支給事由とする給付はありませんが、厚生年金基金から結婚祝い金をもらえる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金加入者の結婚祝い金の申請方法は?
結婚祝い金制度の有無も含めて厚生年金基金によって異なるため、確認が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金の事業所番号とは?わからない時の確認方法は?
従業員を雇用すると、事業主は健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関するさまざまな手続きを行う必要があります。 所定の書類を年金事務所などに提出することになりますが、その際は事業所…
詳しくみる育児休業給付金(育休手当)とは?給付の条件や申請方法を解説
育児休業給付金とは、育児休業を取得したときに国から支給されるお金のことです。休業中の収入が確保されることで、従業員は安心して育児に専念できます。パートや契約社員など、有期雇用社員も…
詳しくみる高額療養費(高額医療費支給制度)とは?社会保険の観点から仕組みを解説!
「高額療養費制度」とは、高額な医療費負担を軽減するための制度で、医療機関で支払った自己負担額のうち限度額を超えた額が手続きによって還付されたり、事前申請によって支払わずに済んだりし…
詳しくみる労働保険の年度更新はどうやる?やり方と注意点を解説
従業員を雇用している事業所が年に1回必ず行わなければならないのが、労働保険の年度更新です。年度更新の際には、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければなりません。期限の…
詳しくみる労災隠しとは?会社に罰則があるか事例なども紹介
労災隠しは違法であり、企業には罰則が科せられる可能性があります。 事故が発生した際に適切に報告しなければ法的リスクや経済的損失を招き、労災隠しによる罰則や企業の信頼喪失、従業員の安…
詳しくみる【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?人事・経営者が備えるべきコスト増と労務対策
Point年金3号廃止とは? 年金3号廃止とは、扶養配偶者の保険料免除制度見直しの議論です。 2026年に106万円要件撤廃 2027年以降、企業規模要件縮小 企業負担と実務対応が…
詳しくみる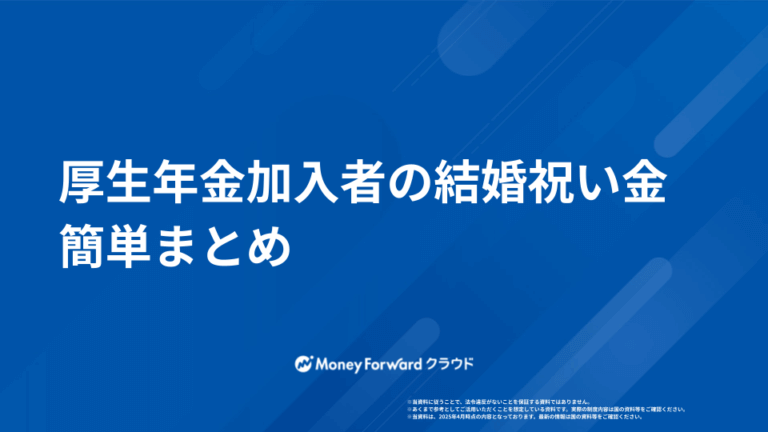

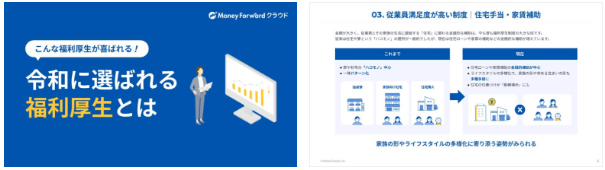
.jpg)
