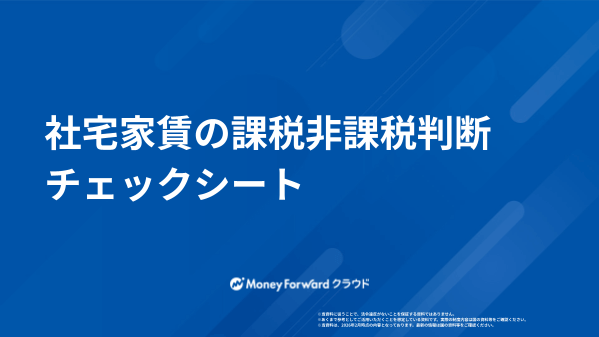- 更新日 : 2026年2月24日
社宅家賃の消費税は課税?非課税?税務上のルールや仕訳処理を解説
社宅家賃の消費税は居住用であれば非課税です。ただし、社宅を維持するために必要なその他の費用は、内容により課税対象のものもあります。
正しい経理処理を行うには、社宅に関する費用の消費税の扱いについて理解しておくことが大切です。
本記事では、非課税対象の費用と課税対象の費用、仕訳処理について解説します。
目次
住宅の家賃は消費税がかからない
住宅の家賃には消費税がかかりません。これは、住宅の賃貸が非課税取引に分類されているためです。
消費税がかかる取引は「課税取引」と呼ばれ、商品販売やサービス提供など事業者が対価を得る取引が該当します。一方、住宅の貸付けや土地の売買、医療費などは非課税です。
たとえば、店舗やオフィスの賃貸には消費税がかかりますが、住居としての賃貸住宅は非課税となります。社宅も住宅用の賃貸物件に含まれるため、企業が支払う家賃には消費税が発生しません。
住宅の賃貸は消費税の対象外となるため、家賃を支払う際に消費税の上乗せは不要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
福利厚生新制度 借り上げ社宅の費用対効果とは
本資料では、近年人気が出ている福利厚生制度である”借り上げ社宅”について解説をしております。
借り上げ社宅と社有社宅・住宅手当との違いや、なぜ企業が借り上げ社宅を採用しているのかを整理し新たな福利厚生制度”借り上げ社宅”を検討している皆様には必見の内容となっております。
借り上げ社宅 かんたん導入ガイド
企業の福利厚生や人材確保の施策として、借り上げ社宅制度の導入が検討されています。
本資料は、「借り上げ社宅制度」についての簡単な導入ガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社での制度導入の検討にご活用ください。
住宅手当 vs 社宅 メリット比較表
企業の福利厚生として、「住宅手当」と「社宅」は代表的な制度です。
本資料は、「住宅手当」と「社宅」それぞれのメリットをまとめた比較表です。 ぜひダウンロードいただき、貴社の福利厚生制度の検討・見直しにご活用ください。
社宅で消費税が非課税になる費用
企業が社宅を借りる際、一部の費用には消費税がかかりません。
本章では、賃貸物件に関わる費用のうち、非課税となるものを解説します。
借上社宅の家賃・更新料
住宅用の賃貸物件は消費税の対象外となるため、企業が不動産会社や家主と契約し社宅として従業員に提供する場合にも、家賃には消費税がかかりません。また、社宅の更新料は、契約を更新する際の費用であり、家賃と同様に扱われるため非課税です。
ただし、事業用として使用する場合や、一時的な宿泊施設(ホテル・短期賃貸マンション)の場合は課税対象となります。
関連記事
敷金・礼金
社宅を契約する際に支払う敷金や礼金のうち、返還されない部分は非課税となります。これらの費用は、家賃と同じく住居用の賃貸契約に必要な費用のためです。礼金は入居時に支払うもので、退去時に返還されないため非課税となります。
敷金は退去時に原則として返還される費用です。しかし、退去時に修繕費や未払いの家賃に充てられる場合があります。その場合、修繕にかかった費用には消費税がかかる点に注意しましょう。たとえば、企業が借りた社宅の敷金が10万円で、退去時に5万円が修繕費として差し引かれた場合、修繕費部分の5万円には消費税が発生します。
従業員から徴収した社宅家賃
企業が借り上げた社宅を従業員に貸し出して家賃を徴収する場合、その家賃には消費税がかかりません。借上社宅の家賃を企業が支払うのと同様に、従業員が支払う費用も住居用の家賃として扱われるためです。
また、会社が給与から天引きする家賃も消費税の対象にはなりません。ただし、社宅の提供が給与の一部とみなされる場合、税務上の取り扱いが変わることがあります。たとえば、企業が家賃の一部を負担し、従業員が通常より安い賃料で住める場合、給与所得の収入金額とされる可能性があります。社宅の賃料設定や契約内容については、事前に税理士などの専門家に相談しておくと安心です。
共益費・管理費
社宅の共益費や管理費は家賃の一部とみなされるため、消費税がかかりません。入居者が共同で負担するものであり、住宅の利用に必要な費用だと考えられるためです。共益費や管理費には、エントランスや廊下、エレベーターの電気代、浄化槽の保守点検費用なども含まれます。
関連記事
社宅で消費税が課税対象となる費用
社宅を利用する際に発生する費用の中には、消費税がかかるものがあります。本章では、課税対象となる費用について解説します。
不動産会社への仲介手数料
社宅を借りる際、不動産会社を通して契約すると仲介手数料が発生します。この仲介手数料には消費税がかかります。不動産会社が提供するサービスに対する対価であり、課税取引に該当するためです。
宅地建物取引業法では、借主の負担額は家賃の1ヶ月分が上限と定められています。たとえば、社宅の家賃が10万円で、仲介手数料が1ヶ月分の場合、消費税(10%)を加えて11万円の支払いが発生します。
駐車場代
社宅に付随する駐車場の使用料は、基本的に消費税の課税対象です。しかし、駐車場代が家賃や共益費に含まれている場合は非課税となります。
たとえば、建物の敷地内にある駐車場の料金が家賃と一括で設定されている場合、家賃の一部とみなされ消費税はかかりません。一方で、駐車場代を別途支払う契約の場合は、消費税が発生します。
さらに、社宅とは別の場所にある駐車場を契約する場合は、賃貸駐車場と同じ扱いとなり、消費税が課税されます。
清掃費・修繕費
社宅の清掃や修繕にかかる費用も、消費税の課税対象になります。清掃や修繕が「サービスの提供」に該当し、家賃とは異なる費用として扱われるためです。ただし、管理費として毎月一定額を支払い、その中から清掃費や修繕費がまかなわれる場合は、消費税がかからないこともあります。
たとえば、建物の共用部分の清掃費や軽微な修繕費が管理費に含まれている場合は、管理費が家賃と同じ扱いになり、非課税となります。
契約時に、清掃費や修繕費の負担について不動産会社に確認しておくことが大切です。
水道光熱費
社宅で使用する水道代や電気代は、原則として消費税の課税対象です。水道光熱費は生活費として扱われ、家賃とは別に請求されるためです。
ただし、社宅が共用設備を持ち、企業が一律で水道光熱費を負担する場合は、非課税になることがあります。水道や電気・ガスなどを企業が一括で契約しているケースでは、一人ひとりの使用額が明確でなかったり、職務遂行上やむを得ない理由で居住していたりするためです。
社宅にかかる消費税の仕訳処理
企業が従業員向けに社宅を用意する際には、家賃や関連費用の消費税の取り扱いを正しく理解し、適切に仕訳処理を行うことが重要です。社宅の家賃自体は非課税となる一方で、敷金・礼金、仲介手数料、共益費などの付随する費用には消費税がかかるケースがあります。
本章では、社宅に関連する費用の消費税の仕訳方法を解説します。
社宅家賃を会社が全額負担する場合の仕訳
企業が社宅の家賃を全額負担する場合、地代家賃として計上し非課税となります。社宅の家賃は、住宅用の賃貸借契約に基づく家賃が消費税の課税対象外であるためです。
仕訳を行う際には、税区分を「非課税仕入」として処理します。
たとえば、企業が毎月8万円の家賃を支払う場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 地代家賃 | 勘定科目 | 現金 |
| 金額 | 80,000円 | 金額 | 80,000円 |
| 税区分 | 非課税仕入 | ||
社宅家賃を従業員の給与から天引きする場合の仕訳
企業が社宅の家賃を支払った後、従業員の給与から一部を控除する場合、その金額は「受取家賃」として処理します。
従業員から徴収する社宅家賃も、住宅用賃貸に該当するため「非課税売上」として計上しましょう。
たとえば、従業員負担分3万円を給与から控除する場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 普通預金 | 勘定科目 | 受取家賃 |
| 金額 | 30,000円 | 金額 | 30,000円 |
| 税区分 | 非課税売上 | ||
従業員負担分を給与から差し引くことで、企業の負担額を抑えられます。また、従業員にとっても、家賃負担が少ないことがメリットです。ただし、企業負担分が大きすぎると、税務上「給与」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
敷金・礼金の仕訳
敷金と礼金は、支払う目的が異なるため、仕訳方法も異なります。敷金は契約終了後に返還されるため「不課税取引」として処理します。一方、礼金は返還されず「地代家賃」または「支払手数料」として計上するのが一般的です。
敷金10万円を支払う場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 敷金(または差入保証金) | 勘定科目 | 現金 |
| 金額 | 100,000円 | 金額 | 100,000円 |
| 税区分 | 不課税取引 | ||
敷金は基本的には非課税ですが、原状回復費用に充当される場合、その部分に消費税が発生することがあります。退去時の精算時に修繕費の内訳を確認しておきましょう。
礼金20万円を支払う場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 地代家賃 (20万円以上の場合は長期前払費用) | 勘定科目 | 現金 |
| 金額 | 200,000円 | 金額 | 200,000円 |
| 税区分 | 非課税仕入 | ||
仲介手数料の仕訳
社宅を契約する際、不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で家賃1ヶ月分と定められており、通常は0.5ヶ月分~1ヶ月分が相場です。この金額に10%の消費税を加算して支払います。
仲介手数料5万円(税抜)を支払う場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | |||
|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 支払手数料 | 仮払消費税 | 勘定科目 | 現金 |
| 金額 | 50,000円 | 5,000円 | 金額 | 55,000円 |
| 税区分 | 課税仕入 | |||
住宅手当を給与で支給している場合の課税
住宅手当は、家賃を支払う際の補助として支給されるため、給与所得とみなされ、所得税や住民税、社会保険料の算定基準の対象になります。
そのため、支給された住宅手当の全額をそのまま家賃の支払いに充てられるわけではありません。税金や社会保険料が差し引かれた後の金額が実際の手取り額となります。また、企業側も住宅手当分を含めた給与総額に対して社会保険料を負担するため、コストが増える点に注意が必要です。
一方で、社宅制度を利用すれば、一定の条件を満たすことで住宅手当よりも税負担を軽減できる可能性があります。企業としては、住宅手当と社宅制度のどちらが従業員と会社双方にとって有利になるかを検討することが重要です。
社宅家賃の消費税処理でよくある質問
社宅の家賃に関する消費税の取り扱いについて、よくある質問に回答します。
インボイス制度で社宅の契約はどう変わる?
社宅の家賃はもともと消費税がかからない非課税取引です。そのため、インボイス制度による影響はほとんどありません。
ただし、管理費や共益費などの費用は課税対象となる場合があります。そのため、これらの費用を支払う際は、適格請求書(インボイス)の発行が求められることがあります。管理会社や不動産会社から発行される請求書の内容を確認し、課税対象となる費用と非課税の費用を区別することが重要です。
従業員負担分が社宅家賃の一部の場合の消費税は?
社宅の家賃は住居用のため、消費税がかかりません。企業が家賃を支払い、その一部を従業員から回収する場合、従業員負担分も非課税売上として処理されます。
ただし、従業員負担額が賃貸料相当額の50%未満の場合、受け取っている家賃と賃貸料相当額の差額が給与課税されてしまいます。これは、企業が従業員へ家賃補助を行っていると判断されるためです。
たとえば、社宅の家賃が10万円、賃貸料相当額も10万円の場合、以下のように負担額を設定したとしましょう。
- 従業員負担が3万円
- 企業負担が7万円
この場合、従業員負担が50%未満になっているため、企業負担分の7万円が給与とみなされ、所得税や社会保険の支払いが増える可能性があります。
社宅家賃は消費税がかからない
社宅の家賃は消費税がかからないため、企業が支払う家賃や更新料、従業員から徴収する家賃も非課税です。ただし、仲介手数料や駐車場代、水道光熱費などは課税対象となるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
消費税の取り扱いを正しく理解することで、社宅の経理処理がスムーズになるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
パート社員の雇用契約書とは?記載事項や正社員との違いを解説
パート社員の雇用契約書は、会社とパート社員の間で雇用条件や業務内容、勤務期間、雇用契約期間などを記載した書面です。パート社員を雇用する際は、事前に書面で契約を交わしておかなければ、…
詳しくみる【社労士監修】労務とは?人事との違いや仕事内容、向いている人の特徴を解説
企業において労務と人事の領域は、組織の健全な運営に不可欠な要素ですが、多くの人にとっては混同されがちです。 この二つの領域が連携し合うことで、企業は労働者と良好な関係を築き、法令を…
詳しくみる労使協定方式の締結方法とは?派遣先均等・均衡方式の違いとあわせて解説
派遣労働者の同一労働同一賃金に対応するため、労使協定方式の導入を検討している人もいるでしょう。 しかし労使協定を締結する際に必要な情報を把握していなければ、派遣労働者に対して適切な…
詳しくみる退職証明書の発行ルールやもらい方、離職票との違い【テンプレ付】
退職証明書は、その会社を退職したことを証明するための書類で、法律にもとづいて請求できる書類です。転職先への提出や、国民健康保険への切り替え手続きなどで必要になります。しかし、「離職…
詳しくみる再雇用の契約途中に退職できる?手続きの流れや失業保険・年金への影響まとめ
再雇用制度は、定年後も経験豊富な人材を活用できる仕組みとして、多くの企業で導入されています。しかし、契約途中で再雇用社員が退職を申し出るケースも少なくありません。退職の扱い方を誤る…
詳しくみる定年後再雇用されない人とは?特徴や通知方法、リストラとの違いを解説
定年後、再雇用を希望しても、会社の判断で見送られることがあります。再雇用されない理由やその通知方法、リストラとの違いを理解することで、今後の対応策を見つけることができます。 この記…
詳しくみる