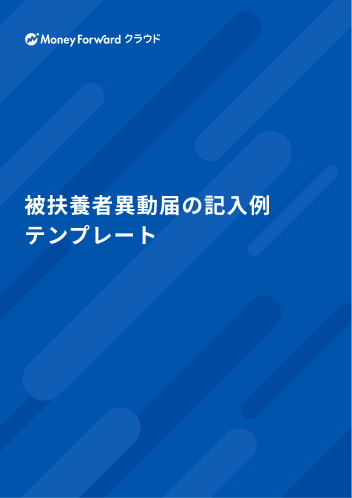- 更新日 : 2026年1月8日
被扶養者異動届の書き方は?家族が加入・外れる場合の記入例を解説【テンプレート付き】
被扶養者異動届は、健康保険や厚生年金保険の被保険者である従業員に対して、被扶養者を追加するときや削除するとき、氏名が変更になったときなどに必要な書類です。勤務先を経由して年金事務所などに提出します。どのような基準を満たすときに必要か、また、書き方や併せて提出する書類、作成時の注意するポイントをわかりやすく解説します。
目次
被扶養者異動届とは
被扶養者異動届とは、従業員の被扶養者を追加・削除する、あるいは被扶養者の氏名が変更になったときなどに提出する書類です。なお、提出方法には、窓口に直接持っていく方法や郵送、電子申請などがあります。
被扶養者の範囲や収入基準
被扶養者とは、被保険者により主に生計を維持されている人で、原則として日本国内に住民票を有していなくてはいけません。また、次の収入基準と同居基準の両方を満たしていることも必要です。
- 被扶養者に認定される年の年間見込み収入が130万円未満(60歳以上もしくは障害者の場合は180万円未満)
- 同居している場合は扶養者の収入の半分未満
- 別居している場合は扶養者からの仕送り額未満
- 扶養者の配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属は、扶養者と同居する必要はない
- 上記以外の3親等内の親族や内縁関係の配偶者の父母・子については、扶養者と同居している必要あり
夫婦ともに収入がある場合は、年間収入が多いほうを扶養者、少ないほうを被扶養者とします。ただし、育児休業などの期間中、一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合においては、被扶養者の異動手続きは不要です。
被扶養者異動届が必要なケース
上記の基準を満たした被扶養者を追加するとき、あるいは、被扶養者が上記の基準を満たさなくなったときに提出が必要です。たとえば、被扶養者が次のいずれかに該当するケースでは、被扶養者の削除をしなくてはいけません。
- 後期高齢者医療制度の被保険者になった
- 年間収入が130万円以上(60歳以上もしくは障害者は180万円以上)見込まれる
- 同居している場合、年間収入が扶養者の収入の半分以上になった
- 別居している場合、年間収入が扶養者の仕送り額を超えた
- 他の被保険者に扶養されることになった
- 同居基準を満たす必要があるのに対して別居した
- 日本国外に住民票がなくなった(海外特例要件を満たさない場合)
また、被扶養者の氏名・性別を訂正するときや変更するとき、生年月日を訂正するときにも提出します。
被扶養者異動届の提出先や期限
事実が発生してから5日以内に提出します。提出先は年金事務所や健康保険組合の事務センターですが、勤務先を経由するため、被保険者自身が当該事務所に出向く必要はありません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
被扶養者異動届の届出に必要な書類
被扶養者異動届を提出するときには、異動届だけでなく記載した内容を証明する書類もあわせて提出する必要があります。必ず提出する書類には次のものが挙げられます。
- 続柄確認のための書類
- 収入要件確認のための書類
それぞれの書類について見ていきましょう。
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届とは、被扶養者異動届の正式名称です。被扶養者の資格を取得・喪失したときや、被扶養者の氏名などに変更や間違いがあったときだけでなく、被扶養者の国民年金の資格に変更があったときもあわせて申請できます。
続柄確認のための書類
被扶養者異動届を提出するときは、続柄を確認できる書類もあわせて提出しなくてはいけません。次のいずれかを添付してください。
- 被扶養者の戸籍謄(抄)本
- 被保険者が世帯主かつ被扶養者と同一世帯のときは住民票の写し
ただし、被扶養者異動届に被保険者・被扶養者の個人番号がいずれも記載されており、なおかつ事業主が続柄が異動届の記載と相違ないことを確認しているときは、続柄を示すための書類提出を省けます。
収入要件確認のための書類
収入要件に合致していることを示すために、以下の書類もあわせて提出しなくてはいけません。ただし、被保険者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、事業主の証明があれば添付書類は不要です。
なお、被保険者の合計所得金額が1,000万円を超えるときは、所得税控除の対象配偶者の適用は受けられません。そのため、事業所の証明の有無にかかわらず、収入を示す書類の提出が求められます。
その他の書類
被扶養者が被保険者と別居している場合は、仕送りをしている事実と金額を示す証拠書類が必要です。ただし、被扶養者の年齢が16歳未満、もしくは被扶養者が16歳以上の学生であるときは提出する必要はありません。
内縁関係にある被扶養者に関しては、内縁関係を示せる戸籍謄(抄)本もしくは被保険者の世帯全員の住民票が必要です。どのような書類が必要かわからないときは、管轄の年金事務所にも相談してみてください。被扶養者との関係性によっては書類が変わることもあります。
なお、仕送りや内縁関係のない被扶養者に関しては、続柄・収入を示す書類以外は添付の必要はありません。速やかに準備して勤務先に提出してください。
被扶養者異動届の書き方
被扶養者異動届の最上部の欄は、事業所側で記載します。被保険者はその下にあるA(被保険者欄)から記載し始めましょう。氏名・生年月日・性別・個人番号・住所・収入を記載してください。なお、個人番号を記載した場合は、住所の記入を省略可能です。

引用:被扶養者( 異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届|日本年金機構
被扶養者異動届の書き方:扶養から外れる場合
被扶養者が扶養から外れるときは、A(被保険者欄)に加え、B(配偶者である被扶養者欄)もしくはC(その他の被扶養者欄)を記載します。それぞれについて解説します。
配偶者の場合の記入例
配偶者が被扶養者から外れるときは、A(被保険者欄)に加え、B(配偶者である被扶養者欄)を記載します。被扶養者の氏名・生年月日・性別・個人番号・住所・電話番号も記載してください。
次に上から4行目の欄の左端にある「2.非該当」を〇で囲みます。被扶養者から外れた年月日と理由の欄も記載してください。

引用:被扶養者( 異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届|日本年金機構
子の場合の記入例
子が被扶養者から外れるときは、A(被保険者欄)に加え、C(その他の被扶養者欄)を記載します。被扶養者の氏名・生年月日・性別・続柄・個人番号・住所を記載してください。
次に上から4行目の欄の左端にある「2.非該当」を〇で囲みます。被扶養者から外れた年月日と理由の欄も記載してください。

引用:被扶養者( 異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届|日本年金機構
被扶養者異動届の書き方:扶養に入れる場合
配偶者や子を扶養に入れるときも、A(被保険者欄)に加え、B(配偶者である被扶養者欄)もしくはC(その他の被扶養者欄)を記載します。それぞれについて解説します。
配偶者の場合の記入例
配偶者を扶養に入れるときは、A(被保険者欄)に加え、B(配偶者である被扶養者欄)を記載します。配偶者が扶養から外れるときと同様、まずは1・2行目の被扶養者の氏名・生年月日・性別・個人番号・住所・電話番号も記載してください。
次に上から3行目の欄の左端にある「1.該当」を〇で囲みます。被扶養者となった年月日と理由、職業、収入の欄も記載してください。

引用:被扶養者( 異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届|日本年金機構
子の場合の記入例
子を扶養に入れるときは、A(被保険者欄)に加え、C(その他の被扶養者欄)を記載します。
子が扶養から外れるときと同様、被扶養者の氏名・生年月日・性別・続柄・個人番号・住所を記載してください。
次に上から3行目の欄の左端にある「1.該当」を〇で囲みます。被扶養者となった年月日と職業、収入、理由の欄も記載してください。

引用:被扶養者( 異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届|日本年金機構
被扶養者(異動)届の書き方の注意点
被扶養者異動届は、以下の点に注意をして作成してください。
- 被保険者が記載する
- 生年月日や漢字、ふりがなに注意する
被扶養者異動届は被保険者が提出する書類です。被扶養者ではなく被保険者が記入しましょう。また、生年月日や漢字、ふりがなに間違いがないか確認してください。情報は後日訂正できますが、再度、被扶養者異動届を作成して提出しなくてはいけません。二度手間を省くためにも、間違いがないように確認することが大切です。
被扶養者の該当・非該当・変更手続きは早めに実施しよう
被扶養者異動届は、被扶養者が扶養に入るときや扶養から外れるとき、氏名や性別などに修正・変更があるときに作成・提出する書類です。変更する事由が生じてから5日以内に提出する必要があるため、速やかな対応が必要です。紹介した内容も参考に、早めに手続きを実施してください。
また、正確に手続きすることも大切です。訂正はできますが、再度被扶養者異動届を提出することになるため注意してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
育児休業給付受給資格確認票の被保険者番号とは?調べ方や書き方を解説
従業員が育児休業を取得する際、「育児休業給付受給資格確認票」の「被保険者番号」の欄で手が止まってしまった経験はないでしょうか。 この被保険者番号は、雇用保険の被保険者番号のことで、…
詳しくみる労災は使わない方がいい?メリット・デメリットを徹底比較
仕事中や通勤途中にケガや病気をしたとき、労災保険を使うかどうか悩む方は非常に多くいます。「会社に迷惑をかけるのではないか」「申請手続きが面倒そう」など、不安や疑問は尽きないものです…
詳しくみる労災保険給付の金額はいくら? 計算方法などを詳しく解説
業務上または通勤中の事故によって負ったケガや病気などに対して、保険給付される制度を「労災保険制度」といいます。 本記事では、労災認定される条件や種類、給付額の計算方法について解説し…
詳しくみる【テンプレ付】労災事故報告書とは?提出義務がある事故や記入例を解説
労災事故報告書は、一定の労災事故があったことを届け出る際に用いる書類です。事業場内で火災などが発生した場合は、労働安全衛生規則第96条の規定により、様式第22号を用いて報告しなけれ…
詳しくみる【社保⇔国保】転職・退職時の切り替え手続きガイド!金額や期限を解説
会社を退職後、再就職までに1日でも空白期間ができる場合は、原則として社会保険の切り替えが必要です。 その際の選択肢としては、「国民健康保険への切り替え」「健康保険の任意継続」「配偶…
詳しくみる従業員が退職したら何をすべき?社会保険手続きや必要書類の書き方まとめ
従業員の退職が決まったら、人事がするべき手続きが数多くあります。なかでも健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険は、手続きの期限が決まっているため、迅速に必要書類を提出しなけ…
詳しくみる