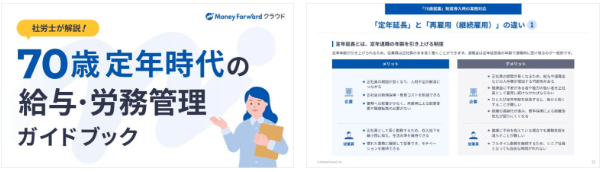- 更新日 : 2025年11月12日
定年後再雇用と退職金、いつ払う?再雇用後の支給有無の取り決めも解説
再雇用制度は、多くの企業で定年後の働き方を支える仕組みとして定着しています。しかし、定年退職時の退職金の取り扱いや、再雇用後の給与体系、そして将来の退職金に不安を感じる方は少なくありません。本記事では、2025年5月現在の最新情報に基づき、再雇用制度と退職金に関する疑問を解消し、安心して定年後のキャリアを築くための具体的な情報を提供します。
目次
定年後に再雇用する場合、退職金の支給タイミングは?
多くの企業では、定年を迎えたタイミングで退職金を支払います。これは雇用契約が一度終了し、勤続年数に基づいて退職金が確定するためです。再雇用後は新たな契約となり、定年前の勤続とは切り離されます。
再雇用終了時に支払う企業もある
企業によっては、再雇用期間を含めた全勤務期間に対して、再雇用終了時に退職金を支払う制度を採用しています。例えば、再雇用が65歳で終了する場合、60歳までと再雇用期間の勤続年数を合算して退職金を計算します。この場合、退職金の受給額が増えることもありますが、給与が下がると退職金も少なくなる傾向があるため、会社の規定を確認することが大切です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
定年延長による退職金の支払い時期はいつ?
定年延長制度を採用している企業では、退職金は延長後の新たな定年年齢に達した時点で支払われます。例えば、定年を60歳から65歳に変更した場合、退職金は65歳での退職時に一括支給されるケースが見られます。
雇用契約が継続するため途中支給は行わない
定年延長では、従業員との雇用契約が継続するため、60歳の時点では退職金は発生しません。延長後の定年までの勤続年数も退職金の計算に含まれるため、最終的な受給額は増える傾向にあります。
賃金水準の変化が退職金に影響することも
延長後の賃金が定年前より下がる場合、退職金の算出基準である最終給与が低くなり、結果として退職金が減ることがあります。従業員の不安を防ぐためにも、企業は制度内容や計算方法を就業規則に明記し、周知徹底することが必要です。
退職金を再雇用前に払う場合の税務上の扱い
再雇用前の退職金は税制上のメリットが大きい
定年退職時に退職金を支給することで、「退職所得」として扱われます。これにより、退職所得控除が適用され、課税対象額は控除後の金額の1/2です。例えば勤続30年の場合、1,500万円まで退職所得控除が適用されるため課税対象額が大幅に減少し、手取りが大きくなります。
再雇用契約と明確に切り分けることが必要
税務上の優遇を受けるためには、退職金の支給時点で雇用契約が終了していることが必要です。たとえ再雇用が予定されていても、一度契約を終了し、新たな契約として再雇用することが重要です。この手続きが曖昧だと、「給与」とみなされて課税される可能性があります。
社会保険料はかからないが再雇用後は注意
退職金は一時金のため、健康保険料や厚生年金保険料の対象にはなりません。ただし、再雇用後の給与は通常どおり保険料が発生します。定年後は健康保険の任意継続や国保への切り替えなどの対応が必要で、選択肢によって負担額が大きく異なります。
支給時期によって税負担が変わる
退職金の受け取り方には「定年時に一括」「再雇用終了時に一括」「2回に分ける」などの方法が挙げられます。退職所得控除はそれぞれの支給時に適用されるため、2回に分けて受け取ると合計の控除額が増え、税負担が抑えられる場合もあります。
企業側は損金処理のタイミングに注意
退職金を支払った年度に企業はその金額を損金として計上できます。これは、支給日ベースで処理されるため、退職金をいつ支払うかが法人税に影響します。制度設計にあたっては、退職金規程に「定年退職時に支給する」など明確な文言を記載し、税務調査で説明できるよう準備しておくことが大切です。
再雇用後に新たに退職金は支払うべき?
原則として支給しない企業が多い
定年退職時に退職金を精算し、再雇用契約を新たな雇用として取り扱う企業では、再雇用後の退職金は支給しないのが一般的です。例えば、60歳で定年退職し、同じ会社で65歳まで再雇用された場合、60歳以降の5年間は退職金計算の対象外とするケースが多く見られます。企業側は、再雇用者の賃金を抑える代わりに退職金支給の対象から除外することで、コスト管理を行っています。
再雇用者にも退職金を支給する企業もある
再雇用期間に対しても退職金を支給する企業もあります。方法としては、(1)定年時と再雇用終了時の2回に分けて支給する方式、(2)定年退職時に支給せず、再雇用終了時に全期間をまとめて支給する方式があります。
支給する場合は、対象者の範囲、勤続年数のカウント方法、最終給与水準の反映など、詳細な取り決めを退職金規程に定めることが必要です。
就業規則で明確にすべき退職金と再雇用のルール
退職金の支給条件を文書で明記する
退職金の支給時期や対象者の範囲は、就業規則や退職金規程に明確に定めておくことが必要です。例えば「定年退職時に退職金を支給し、再雇用後は支給しない」または「再雇用期間にも別途退職金を支給する」など、条文として残しておくとトラブル防止につながります。
再雇用制度の取り扱いも規則化する
再雇用制度の内容、適用年齢、雇用形態(嘱託・契約社員など)、給与体系、勤務時間なども就業規則に具体的に記載することが求められます。「原則65歳まで再雇用可能」「勤務条件は個別に契約書で定める」など、曖昧さを避けた表現を用いることが重要です。
制度変更時は周知と同意が不可欠
退職金制度や再雇用規程に変更がある場合は、労働者代表や労働組合との協議を行い、全従業員への周知を徹底する必要があります。周知に関しては書面、説明会、イントラネット掲示など複数の手段で行い、従業員が制度内容を正しく理解できるようにしましょう。
再雇用後の退職金に関するよくある疑問
Q1:再雇用で給与が下がると退職金も減る?
再雇用後の給与が退職金計算に反映される場合、支給額が減る可能性があります。企業の規程と計算方法を確認し、必要に応じて試算を依頼しましょう。
Q2:再雇用制度は断れる?デメリットは?
再雇用の利用は任意ですが、断ると収入や社会保険の継続に影響します。他の収入源や生活設計と合わせて判断が必要です。
Q3:再雇用中の退職金にも税金はかかる?
再雇用後に支払われる退職金も退職所得として課税対象ですが、退職所得控除があるため税負担は軽減されます。事前に税額を確認しましょう。
Q4:再雇用後に退職金を受け取る際の注意点は?
支給条件の確認と「退職所得の申告書」の提出が必要です。他の所得と合算されると税額に影響するため、受け取り方と時期の選択にも注意しましょう。
退職金と再雇用の適切な制度設計に向けて
退職金の支給時期や再雇用後の取り扱いは、企業の規程内容によって異なります。不明確な制度は、従業員の不安や税務リスクにつながります。就業規則や退職金規程を明文化し、支給条件や再雇用の扱いを明確にすることが、円滑な雇用継続と信頼構築につながります。企業は最新の法令や税制に沿って制度を見直し、従業員にとっても納得のいく運用を目指すことが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
福利厚生費とは?計上可能な経費の条件や節税メリットを分かりやすく解説
Point福利厚生費とは、従業員の福祉向上を目的に会社が支出する経費です。 福利厚生費は、一定要件を満たせば経費計上でき、節税と従業員満足を同時に実現します。 法定福利費と法定外福…
詳しくみるつわりによる休職に診断書は必要?期間や手当金を解説
妊娠のサインでもあるつわりは、吐き気やおう吐などの症状のことです。就業中の妊婦さんの中には、つわりによる体調の変化によって不安になる方もいることでしょう。つわりには個人差があります…
詳しくみる男性も育休1年間以上とれる?最大限利用する方法やメリット・デメリットを解説
育児休業は、女性だけではなく、男性も1年間取得することができます。しかし、実際に長期間の育休を取るとなると、職場の理解や収入面への影響を心配する声も少なくありません。 近年の法改正…
詳しくみる外国人労働者を受け入れた際に起こりうる5つの問題|原因・解決策・事例も紹介
外国人労働者を受け入れると、主に5つの問題やトラブルが発生する可能性があります。 「どのような問題が実際に起こっているの?」「トラブルが発生したときの解決策はある?」など気になって…
詳しくみる事故発生状況報告書の書き方は?記載例・無料テンプレートつき
事故発生状況報告書は、交通事故の詳細を保険会社や関係機関に正確に伝えるための重要な文書です。適切な記載方法を知ることで、円滑な保険金請求や事故処理が可能になります。本記事では、事故…
詳しくみる会社は福利厚生で保険を導入すべき?社会保険との違いや種類、メリット、導入方法を解説
企業が福利厚生として導入する保険制度は、従業員の満足度や安心感を高め、企業にとっても人材の定着率向上や優秀な人材確保に効果的な制度です。しかし、「どのような保険を導入すればよいか」…
詳しくみる