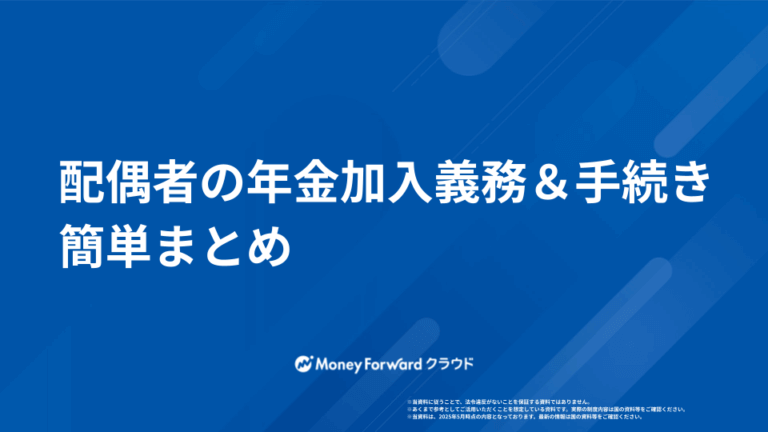- 更新日 : 2025年11月13日
厚生年金加入者の配偶者でも国民年金への加入は必要?
会社員や公務員などは、厚生年金に加入するのが一般的です。厚生年金には扶養制度があるため、専業主婦など条件を満たした被扶養配偶者は扶養加入することができます。しかし、収入が一定以上ある場合や、年齢が60歳以上の場合は条件から外れるため注意が必要です。この記事では、厚生年金の被保険者と配偶者の年金について紹介します。
目次
厚生年金加入者の配偶者でも国民年金への加入は必要?
会社員や公務員が加入する厚生年金には「扶養制度」があるため、厚生年金に加入している被保険者に扶養されている配偶者は「扶養加入」することが可能です。収入や年齢などの条件を満たせば扶養として年金制度に加入することができるため、別途国民年金に加入する必要はありません。
なお、日本の年金制度は2階建て構造となっており、厚生年金加入者は同時に国民年金の「第2号被保険者」でもあります。一方、第2号被保険者に扶養されている配偶者は「国民年金第3号被保険者」です。個人事業主や自営業者、学生や無職の人は、一般的に「国民年金第1号被保険者」として国民年金に加入します。
|
|
| |
第3号被保険者となる要件は「20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている人」と定められています。被扶養者として認定されるための扶養要件については下記のとおりです。
年間収入が130万円未満、または障害者の場合は180万円未満かつ
- 同居の場合は、収入が扶養者である被保険者の収入の半額未満
- 別居の場合は、収入が扶養者である被保険者からの仕送り額未満
ただし、扶養者である第2号被保険者が65歳に到達し、老齢基礎年金の受給資格を満たした場合は、第2号被保険者の資格喪失とあわせて第3号被保険者の資格も喪失するため注意が必要です。例えば、7歳差夫婦の扶養者が65歳で第2号被保険者の資格を喪失した場合、配偶者は58歳でも第3号被保険者の資格を喪失するため気をつけましょう。
また、厚生年金と合わせて社会保険に分類される健康保険は、条件を満たした親族も扶養加入することが可能です。しかし、国民年金第3号被保険者となれるのは配偶者のみとなっています。なお、社会保険における配偶者には婚姻関係の無い、いわゆる「内縁関係者」も含まれます。同居要件もないため、配偶者は必ずしも扶養者である第2号被保険者と同居している必要はありません。ただし、前述のとおり別居している場合でも収入要件は満たす必要があります。年金制度に扶養加入する場合は収入要件等に十分注意しましょう。
さらに、第3号被保険者として年金制度に加入した場合、保険料を別途納付する必要はありません。扶養者である第2号被保険者の加入する厚生年金が、一括で保険料を負担するためです。一方、収入の増加や離婚などで扶養から外れた場合は、個別に保険料を負担しなければならないため気をつけましょう。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
配偶者が国民年金に入っている場合、厚生年金加入者は保険料を払わなくてよい?
前章でも紹介したとおり、第3号被保険者として年金制度に加入している場合、第2号被保険者の加入する厚生年金が一括で保険料を負担するため、別途保険料を納付する必要はありません。しかし、収入増加・離婚などで扶養から外れた場合、被扶養配偶者は国民年金か厚生年金に加入して、別途保険料を負担しなければなりません。扶養から外れる要因は下記のとおりです。
- 被扶養配偶者の収入が増加し収入要件を満たさなくなった場合
- 被扶養配偶者が就職した場合
- 被扶養配偶者が60歳になった場合
- 扶養者である第2号被保険者と離婚した場合
- 独立、退職、死亡などにより扶養者が第2号被保険者の資格を喪失した場合
- 扶養者の第2号被保険者が65歳以上となり老齢基礎年金の受給資格を満たした場合
海外に移住し海外特例に該当しない場合
など
日本は全国民が年金制度に加入する「国民皆年金制度」を採用しているため、第3号被保険者の資格を喪失した場合、ただちに何らかの年金制度に加入しなければなりません。例えば、収入が増加し収入要件を満たさなくなった場合や就職した場合は、自身が勤めている会社で別途厚生年金に加入する必要があります。扶養者が独立し個人事業主や自営業者になった場合は、個別に国民年金へ加入しなければなりません。なお、第2号被保険者の要件は「65歳未満および65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人」と定められています。そのため、被扶養配偶者が60歳未満であっても、扶養者が第2号被保険者の要件を満たさなくなった時点で第3号被保険者の資格を喪失するため気をつけましょう。第3号被保険者の資格を喪失した場合は、別途国民年金もしくは厚生年金に加入しなければなりません。なお、被扶養配偶者が60歳に到達し第3号被保険者の資格を喪失した場合、65歳の老齢基礎年金受給開始まで国民年金に「任意加入」することが可能です。
参考:3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き|日本年金機構
配偶者が第3号被保険者になった場合の手続き
結婚などにより配偶者が第3号被保険者となった場合、第2被保険者が勤めている会社を通して「国民年金第3号被保険者関係届」を日本年金機構に提出しなければなりません。

国民年金第3号被保険者関係届は、日本年金機構のWebサイトからダウンロードすることができます。「第3号被保険者欄」の「該当」に丸を付け、所管の年金事務所に郵送もしくは持参しましょう。郵送ならびに窓口持参が難しい場合は、電子政府の総合窓口である「e-Gov」か、日本年金機構が無償で提供している「届書作成プログラム」を利用し電子申請することも可能です。
参考:国民年金に加入するための手続き(第3号被保険者)|日本年金機構
引用:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
参考:電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)|日本年金機構
配偶者が第3号被保険者でなくなった場合の手続き
配偶者が第3号被保険者でなくなった場合は、国民年金第1号被保険者か第2号被保険者への切り替え手続きが必要です。
まず、国民年金に加入し第1号被保険者となる場合は、扶養者である第2号被保険者が勤めている会社を経由し、日本年金機構に国民年金第3号被保険者関係届を提出しましょう。その際、必ず「第3号被保険者欄」の「非該当(変更)」に丸を付け、会社を管轄している年金事務所に提出してください。加えて、配偶者は居住地の市区町村年金窓口に「国民年金種別変更届」を提出しましょう。その際、年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかる書類、厚生年金の被保険者資格喪失通知書など扶養から外れた日を確認できる書類、本人確認書類、印鑑を必ず携行してください。
なお、国民皆年金制度を敷いている日本では何らかの年金制度に必ず加入しなければならないため、資格喪失後14日以内に種別変更の届け出を行わなければなりません。14日を過ぎてもただちに罰則を科せられるわけではありませんが、未納期間が生じて将来の年金受給額が減ってしまう恐れがあるため気をつけましょう。2年以内であれば追納することもできますが、2年を過ぎてしまうと時効となって納付することができなくなってしまいます。
一方、就職などで自ら厚生年金に加入する場合は、自身が勤める会社に「被保険者資格取得届」を提出しましょう。被保険者資格取得届を受領した日本年金機構が種別変更手続きを行うため、扶養者の勤務先に別途国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要はありません。

参考:国民年金に加入するための手続き(第1号被保険者)|日本年金機構
引用:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構
厚生年金加入者の配偶者は扶養加入可能
厚生年金の被保険者と配偶者の年金について紹介しました。会社員や公務員が加入する厚生年金には扶養制度があるため、配偶者は別途国民年金に加入することなく年金制度に扶養加入することが可能です。保険料については厚生年金が一括で負担するため、個別に負担する必要はありません。ただし、配偶者の収入増加や厚生年金加入者と離婚し、扶養から外れた場合は国民年金もしくは厚生年金に加入して保険料を負担しなければなりません。厚生年金加入者の配偶者は当記事を参考に要件等を確認し、年金制度に扶養加入しましょう。
よくある質問
厚生年金加入者の配偶者でも国民年金への加入は必要ですか?
厚生年金には扶養制度があるため、配偶者は別途国民年金に加入することなく年金制度に扶養加入することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者が国民年金に入っている場合、配偶者分の厚生年金保険料は支払わなくて大丈夫ですか?
配偶者が扶養に入り国民年金第3号被保険者の場合は保険料の負担は不要です。個別に国民年金に加入している国民年金第1号被保険者の場合は保険料を支払わなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
国民健康保険に扶養はある?加入手続きの注意点も解説
日本は国民皆保険制度を採っているため、全国民に健康保険への加入を義務付けています。退職によって社会保険の資格を喪失した際や、フリーター・アルバイトで親の扶養から外れた場合、自営業の…
詳しくみる退職に伴う社会保険手続きガイド|従業員本人と会社がやるべきことをそれぞれ解説
退職は人生の大きな転機ですが、同時に健康保険や年金、雇用保険など、これまで会社任せだった社会保険の手続きを自分で行う必要があります。手続きにはそれぞれ期限が定められており、もし遅れ…
詳しくみる社会保険の加入要件
社会保険は、国や地方公共団体などによって運営がなされており、国民皆保険体制のもと、一定要件を満たした会社や個人は加入する義務があります。 社会保険の加入要件には、例外的なものまで含…
詳しくみる建設業で外国人雇用するには?手続きや注意点を徹底解説
建設業で外国人を雇用するには、適切な在留資格の確認と必要な手続きを正しく行うことが重要です。 特定技能や技能実習などの業務内容に応じた在留資格があるか確認し、労働環境を整えることで…
詳しくみる企業年金は3種類!厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の違いと特徴を解説
退職時または60歳以降に受け取ることができる給付に企業年金があります。企業年金は、3階建ての年金の3階部分(1階部分の「基礎年金」、2階部分の「被用者年金」)を担っている年金制度で…
詳しくみる厚生年金における加給年金とは?もらえる条件や振替加算についても解説!
厚生年金保険加入者が年金を受給できることになったときに、条件により年金額が加算されることを知っていますか?年金に加算される額のことを「加給年金」「振替加算」といいます。これらは家族…
詳しくみる