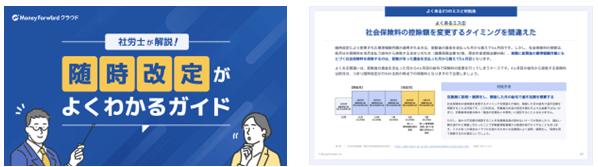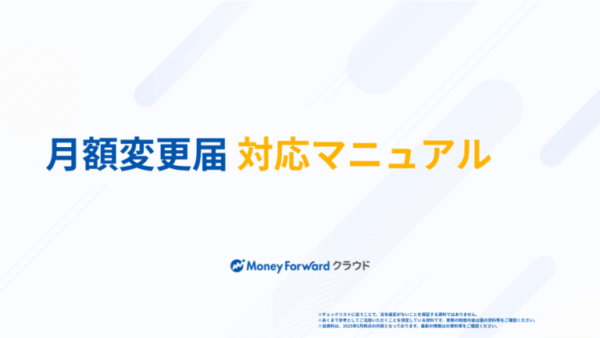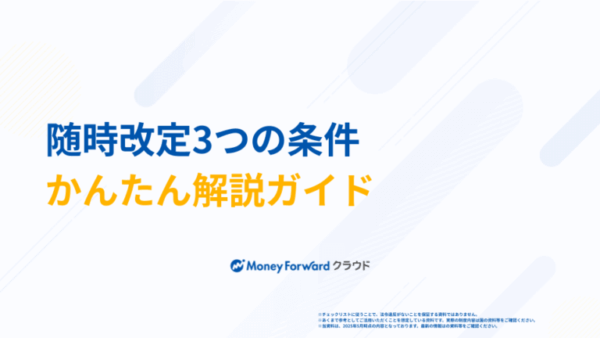- 更新日 : 2025年11月14日
月額変更届(随時改定)は1等級差の場合は提出が必要?提出基準や手続き方法を解説
給与が変動した際に、月額変更届(随時改定)は1等級差でも提出しなければならないのかと疑問に思う方は多いでしょう。社会保険の標準報酬月額は、給与の変化に応じて見直されますが、すべてのケースで手続きが求められるわけではありません。
本記事では、月額変更届の概要や提出基準、手続き方法について解説します。正しく手続きを進めたい方は、参考にしてください。
目次
月額変更届とは?
月額変更届(随時改定)は、給与が大きく変動した際に、社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を変更するための手続きです。
正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」です。この届出を行うことで、社会保険料の適正な負担が確保されます。
また、社会保険料は、標準報酬月額の等級ごとに決定されるため、給与の増減に応じて適宜見直しが必要です。標準報酬月額が2等級以上変動し、かつ一定の要件を満たす場合は、月額変更届を提出する必要があります。
関連記事
定時決定との違い
標準報酬月額は、「定時決定」と「随時改定(月額変更届)」の2つの方法で見直されます。
定時決定は、毎年4〜6月の給与に支給された給与の平均額を基準として、9月から翌年8月までの社会保険料を決定する制度です。企業は、7月10日までに「算定基礎届」を提出する必要があります。
対象となるのは、7月1日時点で雇用されているすべての被保険者および70歳以上の被用者です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの従業員も含まれます。
一方、随時改定(月額変更届)は、給与に大きな増減があった際に、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更する仕組みです。
定時決定と随時改定の時期が重なった場合は、随時改定が優先され、最新の給与状況に応じた社会保険料が適用されます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
1等級差の場合、原則として月額変更届は提出不要
通常、標準報酬月額が1等級のみ変動した場合は、月額変更届の提出は必要ありません。これは、月額変更届の提出基準が「2等級以上の変動があった場合」と定められているためです。
1等級差で提出不要とされる理由は、下記のとおりです。
- 社会保険料の負担に大きな影響を与えないため
- 頻繁に届出が発生すると、企業の事務負担が増えるため
- 社会保険制度の運用をスムーズにするため
たとえば、標準報酬月額が22等級から23等級へ変動しても、保険料の増減幅は小さいため、手続きの必要はありません。
月額変更届の提出基準
月額変更届(随時改定)は、標準報酬月額が一定の基準を超えて変動した場合に提出が求められます。しかし、単に給与が変動しただけでは届出の対象とはなりません。
個々では、3つの条件について詳しく解説します。
関連記事
1.従業員の固定的賃金に変動がある
給与の変更があった場合でも、すべてが随時改定の対象となるわけではありません。月額変更届が必要となるのは、「固定的賃金」に変動があった場合です。
固定的賃金とは、毎月一定額または一定の割合で支給される給与や手当のことを指します。具体的には、下記のようなケースです。
- 基本給の増額・減額
- 役職手当、扶養手当、通勤費補助の変更や支給停止
- 日給制・時給制の賃金単価見直し
- 歩合給・請負報酬の支給額や計算基準の変更
- 時間外労働の割増率や時間単価の修正による残業手当の変動
これらの項目が変更された場合、随時改定の対象となる可能性があります。ただし、残業代やインセンティブなどの「非固定的賃金」の変動は、要件に含まれません。
労働時間や成果によって変動する給与は、随時改定の対象外となるため、間違えないようにしましょう。
2.3ヶ月間とも支払基礎日数が17日以上ある
賃金の変動があった場合でも、その後3か月間にわたり、支払基礎日数が一定の基準を満たしていることが必要です。
賃金の変動があった月とは、給与額が変更され、その影響を受けた給与が実際に支給された月を指します。
たとえば、給与の支払いが月末締翌月末払いの場合、1月の昇給分が含まれる給与が支払われるのは2月28日です。この場合は、2~4月の3ヶ月間の支払基礎日数で、随時改定の要件を満たしているか確認しましょう。
給与形態別の支払基礎日数の計算は、下記のとおりです。
- 月給制・週給制:総暦日数(欠勤がある場合は欠勤控除方法に沿った暦日)
- 日給制・時間給制:実際の出勤日数(有給休暇を含む)
また、パート・アルバイトなどの短時間労働者が「特定適用事業所」に勤務している場合は、支払基礎日数が11日以上で要件を満たします。
3.標準報酬月額に2等級以上の差が生じている
給与の変動額が小さい場合は標準報酬月額が変わりません。標準報酬月額に2等級以上の差が発生した場合のみ、月額変更届の提出が必要です。
標準報酬月額は、社会保険料を計算するための基準となる金額のことです。全国健康保険協会の「保険料額表」に記載されている等級にもとづいて社会保険料が決定されます。
【昇給のケース】
| 変更前の等級 | 変更後の等級 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 20等級:260,000円 | 22等級:300,000円 | 随時改定が必要 |
【降給のケース】
| 変更前の等級 | 変更後の等級 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 18等級:220,000円 | 15等級:180,000円 | 随時改定が必要 |
標準報酬月額を適切に管理するために、必要な手続きを行いましょう。
1等級の場合でも月額変更届の提出が必要なケース
通常、標準報酬月額の変動が1等級以内であれば、月額変更届の提出は不要とされています。しかし、特定の条件に該当する場合は、例外的に随時改定が必要です。
その条件のひとつが、標準報酬月額の上限または下限に該当するケースです。標準報酬月額には、健康保険・厚生年金保険ともに「最高等級」と「最低等級」が設定されています。
これらの基準に近い方は、給与が増減しても通常は1等級分しか変動しない仕組みです。ただし、給与の変動幅が大きい場合でも1等級の範囲内にとどまってしまうため、実質的には2等級以上の変動と同等の影響を受けます。例外として随時改定の対象となり、月額変更届の提出が必要になります。
具体例は、下記のとおりです。
【厚生年金保険の場合】
| ケース | 従前の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 昇給の場合 | 31等級:620,000円 | 665,000円以上 | 32等級:650,000円 |
| 1等級:88,000円で 報酬月額83,000円未満 | 93,000円以上 | 2等級:98,000円 | |
| 降給の場合 | 32等級:650,000円で 報酬月額665,000円以上 | 635,000円未満 | 31等級:620,000円 |
| 2等級:98,000円 | 83,000円未満 | 1等級:88,000千円 |
【健康保険の場合】
| ケース | 従前の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 昇給の場合 | 49等級:1,330,000円 | 1,415,000円以上 | 50等級:1,390,000円 |
| 1等級:58,000円で 報酬月額53,000円以上 | 63,000円以上 | 2等級:68,000円 | |
| 降給の場合 | 50等級:1,390,000円で 報酬月額1,415,000円以上 | 1,355,000円以上 | 49等級:1,330,000円 |
| 2等級:68,000円 | 53,000円以上 | 1等級:58,000円 |
このようなケースでは、1等級の変動であっても実質的な給与変動の影響を考慮し、適切な手続きを行う必要があります。
標準報酬月額の等級について
標準報酬月額は、社会保険料を決定するための基準であり、健康保険や厚生年金保険の適用において重要な役割を担います。
標準報酬月額に含まれるものは、下記のような給与・手当が該当します。
- 基本給
- 役付手当
- 勤務地手当
- 扶養手当(家族手当)
- 通勤手当(一定額まで)
- 住宅手当
- 時間外手当(残業手当)
ここでは、標準報酬月額の等級について、解説します。
関連記事
健康保険の等級数
健康保険における標準報酬月額は、健康保険法および船員保険法にもとづき、50等級に区分されています。
【健康保険の標準報酬月額の最高等級・最低等級】
| 等級 | 標準報酬月額 |
|---|---|
| 1等級 | 58,000円 |
| 50等級 | 1,390,000円 |
参考:全国健康保険協会|令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
健康保険の保険料率は、毎年改定され、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合から最新の料率表が提供されます。これにもとづき、各従業員の社会保険料が決定される仕組みです。
厚生年金保険の等級数
厚生年金保険の標準報酬月額は、健康保険とは異なり、32等級に設定されています。
【厚生年金の標準報酬月額の最高等級・最低等級】
| 等級 | 標準報酬月額 |
|---|---|
| 1等級 | 88,000円 |
| 32等級 | 650,000円 |
標準報酬月額に上限が設けられているのは、高額所得者や事業主の保険料負担を抑えるためです。また、年金給付額の格差が大きくなりすぎないようにするという目的もあります。
1等級の変動幅
1等級の変動幅とは、給与が変動した際に標準報酬月額の等級がひとつ上下する範囲のことです。各等級には、一定の給与範囲が設定されており、その範囲内の変動であれば等級は変わりません。
【健康保険の場合】
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 |
|---|---|---|
| 21等級 | 280,000円 | 270,000円~290,000円 |
| 22等級 | 300,000円 | 290,000円~310,000円 |
【厚生年金の場合】
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 |
|---|---|---|
| 18等級 | 280,000円 | 270,000円~290,000円 |
参考:保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
給与が増減しても、同じ等級内の範囲に収まる場合、標準報酬月額は変わりません。ただし、1等級を超えて変動すると、随時改定の対象となる可能性があります。
2等級以上変動する場合
標準報酬月額が2等級以上変動した場合、月額変更届の提出が必要です。これは、社会保険料の適正な負担を確保するために定められています。
具体例は、下記のとおりです。
| 変更前の等級 | 変更後の等級 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 18等級:220,000円 | 21等級:280,000円 | 随時改定が必要 |
固定的賃金の変動があり、3ヶ月間の平均給与で2等級以上の変動が確認された場合は、月額変更届を提出しましょう。
月額変更の手続き方法
随時改定を行う際には、月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)を提出する必要があります。届出用紙は、年金事務所の窓口で取得するほか、日本年金機構の公式サイトからダウンロードすることも可能です。
年間平均算定を行う場合は追加書類として、申立書や被保険者の同意書が必要となります。以下で、月額変更届の記入方法や月額変更届の提出方法を詳しく解説します。
月額変更届の記入方法
月額変更届には、下記の情報を正確に記入する必要があります。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 被保険者情報 | 整理番号・氏名・生年月日 |
| 改定年月 | 給与変動後4ヶ月目を記入 |
| 従前の標準報酬月額 | 変更前の金額を記入 |
| 昇(降)給の内容 | 変更のあった月・増減の区分を記載 |
| 給与支給月 | 給与変動後の3ヶ月間を記載 |
| 給与計算の基礎日数 | 17日以上の支払いがあったことを証明 |
| 個人番号(基礎年金番号) | 70歳以上被用者に該当する場合は、個人番号 または基礎年金番号を記入 |
参考:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(記入例)
4月に昇給し、5月の給与で反映された場合、8月が改定年月となります。正確な情報を記入し、誤りのないようにしましょう。
月額変更届の提出方法・提出先
月額変更届は、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。また、健康保険が協会けんぽ以外の組合健保・共済組合の場合は、それぞれの組合にも提出が必要です。
提出方法は、下記のとおりです。
- 窓口
- 郵送
- 電子申請※一部法人では義務化
資本金1億円超の法人や投資法人は電子申請が義務化されているため、該当企業はオンライン手続きを行う必要があります。
月額変更届を提出する際の注意点
月額変更届を提出する際には、事前に注意すべき点を理解しておく必要があります。
ここでは、月額変更届の提出によって発生するデメリット・随時改定の手続きをしなかった場合のリスクを解説します。
月額変更届の提出によって発生するデメリット
月額変更届を提出することによって発生するデメリットと対策方法は下記のとおりです。
| デメリット | 対策 |
|---|---|
| 社会保険料が増え、手取り額が減る | 事前に従業員へ説明し、負担増を理解してもらう |
| 企業側の社会保険料負担が増える | 事前に財務計画を立て、影響を最小限に抑える |
| 短期的な給与変動では手続きが不要な場合がある | 一時的な手当や残業増による変動なら手続き不要となる |
このように、適切な手続きを行うことで、デメリットを最小限に抑えることが可能です。
随時改定の手続きをしなかった場合のリスク
随時改定の条件に該当しているにもかかわらず、手続きをしなかった場合、企業と従業員にリスクが生じます。具体的なリスクと対策方法は、下記のとおりです。
| リスク | 対策 |
|---|---|
| 社会保険料の誤徴収が発生する | 定期的に給与と標準報酬月額を照合する |
| 傷病手当金・出産手当金に影響が出る | 給付額を正しく計算するため、適切な届出を行う |
| 監査や指摘により過去分の修正を求められる | 社会保険手続きを正しく管理し、未提出を防ぐ |
| 企業の信頼や労務トラブルにつながる | 労務管理の適正化を図り、従業員の不安を解消する |
適切な手続きを行うことで、リスクを回避し、企業の信用を守りましょう。
1等級差の提出基準を理解し、適正に手続きを進めよう
月額変更届(随時改定)は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に提出が必要です。しかし、特定の条件下では1等級差でも例外的に届出が求められます。
一方で、短期的な変動や1等級のみの変動では、提出不要なケースもあります。本記事を参考に、社会保険のルールを正しく把握し、適切な管理を心がけましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職後の健康保険 – 国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較
国民皆保険制度を採用している日本では、会社を退職したら、なんらかの公的保険に加入しなければいけません。退職後は国民健康保険に加入することもできますが、会社の健康保険を継続する選択肢…
詳しくみる社会保険の入り方・加入手続きは?事業所・従業員の条件や必要書類も解説!
人事労務の担当者になったり、起業して人を雇用したりする場合は、社会保険の手続きが必要です。 しかし、社会保険にはさまざまな種類があり、手続きは煩雑で管轄も1つではありません。 本稿…
詳しくみる社会保険の休業補償とは?金額や手続きについて解説
休業補償給付とは、業務災害にあった従業員の生活の保護を目的とする社会保険(労働保険)の1つ、労災保険の制度です。企業として労働災害は軽視できない問題であり、労災事故を発生させない仕…
詳しくみる雇用保険における特例一時金とは
雇用の形態には職種や業態によってさまざまなものがあります。一年を通して平均して仕事がある会社と雇用契約を結んで勤め続けるのが一般的ですが、一定の期間のみ仕事があってその都度雇用をす…
詳しくみる子供を扶養に入れるメリット・デメリットは?ポイントや手続き方法も解説
子供がアルバイトを始めたり、就職活動を控えたりする時期になると、「子供を扶養に入れる」ことについて検討する方は少なくありません。親にとっては税金の控除や保険料の免除といったメリット…
詳しくみる労働保険番号とは?わからないときの調べ方を解説!
労働保険(労災保険、雇用保険)では、適用事業所に労働保険番号が割り振られています。労災事故が発生した場合の保険給付支給請求書に記載が必要になりますが、わからない場合はどうすればよい…
詳しくみる