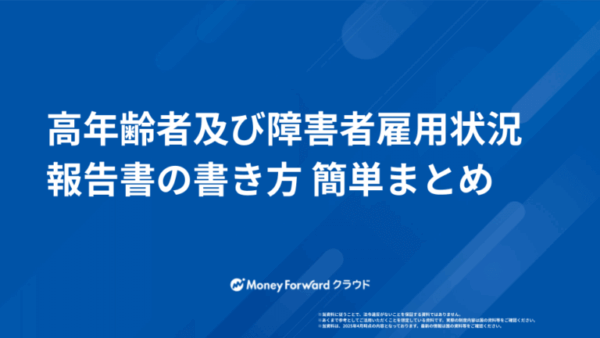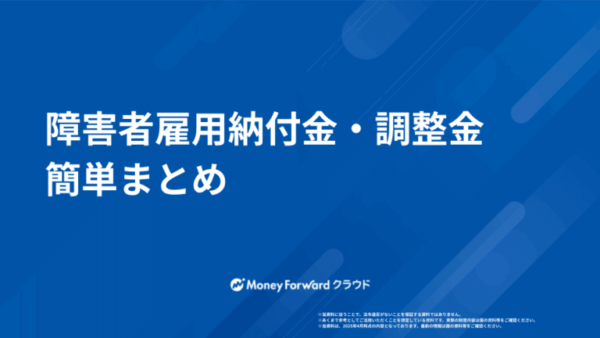- 更新日 : 2025年11月19日
精神障害3級の手帳を取得して障害者雇用枠で就職するメリットは?
精神障害があると診断された人が障害者雇用枠で就職するには、精神障害3級以上の手帳が必要です。
ただ、「障害者雇用枠で就職するメリットは?」「障害者雇用枠で働くデメリットは?」などと疑問に思っている人もいるでしょう。そこで本記事では、精神障害3級の手帳を取得して障害者雇用枠で就職するメリット・デメリットを中心に解説します。
目次
精神障害の手帳における3つの等級
精神障害の手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得する対象となるのは、統合失調症・うつ病・発達障害などの精神障害を持つ人です。
精神障害の手帳には3つの等級があり、厚生労働省がそれぞれの等級の判定基準を以下のように定めています。
- 1級:日常生活を1人で送ることが、ほぼできない
- 2級:周囲のサポートが必要不可欠というわけではないが、日常生活を1人で送ることが困難である
- 3級:日常生活や社会生活に一定の制限がある
どのような精神障害があるか、日常生活や社会生活にどのような支障があるかなどが、等級の判断材料です。
等級は、3級→2級→1級の順に症状が重いと判定されます。精神障害3級は最も症状が軽いと判定された人に交付される手帳です。
参考:厚生省保健医療局長「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
精神障害3級の手帳の取得によって受けられるサポートやサービス
精神障害3級の手帳を取得すると、主に以下のようなサポートやサービスを受けられます。
上記は一例です。地域によってサポートやサービス内容は異なりますが、公共交通機関の乗車賃の割引や税金の障害者控除は、多くの地域に共通しています。
また、等級によって適用されるサポートやサービスが異なる場合があります。より詳しく知りたい人は、お住まいの地域の障がい者に関するページをご確認ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の書き方 簡単まとめ
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の作成準備で、お困りごとはございませんか?
本資料は、報告書の書き方を分かりやすくまとめた資料です。ぜひダウンロードいただき、報告書作成にご活用ください。
障害者雇用納付金・調整金 簡単まとめ
障害者雇用納付金・調整金の申告準備はお済みでしょうか?
本資料は、障害者雇用納付金・調整金の制度について分かりやすくまとめた資料です。ぜひダウンロードいただき、制度の理解や実務にお役立てください。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
精神障害3級の手帳を取得して障害者雇用枠で就職する3つのメリット
精神障害3級の手帳を取得し、障害者雇用枠で就職する主なメリットを3つ紹介します。
1. 精神障害に対して企業から配慮してもらえる
障害者雇用枠として入社すると、精神障害に対して以下のような配慮をしてもらえることがあります。
- 面接したときや入社したときに、症状について相談できる
- 通院の状況や体調に応じて、出退勤の時間や休憩時間などを調整してもらえる
- 時短勤務に応じてもらえる
一般雇用枠で入社した場合よりも、同僚や上司など周囲の人に症状について理解してもらいやすいでしょう。
また、障害者雇用促進法によって「合理的配慮」の提供が会社に義務付けられています。合理的配慮とは、障害者が職場で不利益を被らないよう、働きやすい環境を整える措置のことです。
合理的配慮によって、一般雇用枠で就職するよりも働きやすい環境が提供されることが期待できます。
参考:雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮|厚生労働省
2. 就職の際に支援してもらえる
障がい者の就職活動に関して、市区町村の障がい者就労支援センターや民間の障がい者就労を支援する事業者などがサポートしてくれます。主なサポート内容は以下の通りです。
- 自身に適した仕事の紹介やカウンセリング
- 応募書類の作成援助や添削
- 面接対策や面接同行
- 面接日や入社日の調整
上記のように、仕事の紹介から入社まで手厚く支援してもらえます。入社後も、職場に定着できているか確認してくれたり、休職した際や復職する際にフォローしてもらえたりします。
また、採用担当者にも面接時に体調や症状について相談可能です。面接の際に相談することで、不安や疑問を解消したうえで入社できます。
3. 一般雇用よりも定着しやすい可能性がある
障害者雇用枠で入社すると、一般雇用枠で入社したときよりも定着しやすい可能性があります。
障害者職業総合センターが障害者求人と一般求人の定着率を調査し、以下の結果を発表しています。
| 就職からの 経過期間 | 障害者求人 | 一般求人 障害開示 | 一般求人 障害非開示 |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 86.9% | 69.3% | 52.2% |
| 1年 | 70.4% | 49.9% | 30.8% |
一般求人よりも障害者求人の方が、3ヶ月後も1年後も定着率が高い傾向です。
障害者求人に応募した人の3ヶ月後の定着率は9割近くあります。反対に、一般求人に応募した人の3ヶ月後の定着率が5割~7割であることから、約3割~5割の人が短期間で離職していることになります。
また、一般求人の1年後の定着率は5割もありません。対して障害者求人の定着率は、7割以上を保っています。
よって、一般雇用枠で就職するよりも障害者雇用枠で就職した方が、長期的に働ける可能性が高いです。
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」
障害者雇用枠で就職する2つのデメリット
精神障害の手帳を入手し、障害者雇用枠で就職する主なデメリットを2つ紹介します。
1. 希望の業種や職種の求人がない可能性がある
障害者雇用枠を設けている企業が少ないため、希望する業種や職種の求人がない可能性があります。
障がい者を雇う義務があるのは、従業員が40人以上の会社です。経済産業省の調査によれば、日本全国で40人以上の従業員がいる会社は全体で6.5%ほどしかありません。つまり、障害者雇用枠を設けているのも全国の企業のうち多くても6.5%というわけです。
入社したい会社を見つけても、希望の業種や職種の採用を行っていない可能性があるため、条件の幅を広げて就職活動をするのが良いでしょう。
なお、厚生労働省が産業別や職業別に、障がい者の雇用数の割合を発表しています。
| 産業別 | 職業別 | |
|---|---|---|
| 1 | 卸売業・小売業 (25.8%) | 事務的職業 (29.2%) |
| 2 | 製造業 (15.4%) | 専門的、技術的職業 (15.6%) |
| 3 | サービス業 (14.2%) | サービスの職業 (14.2%) |
精神障がい者の4人に1人が、卸売業や小売業の仕事に就くようです。また、職業別に見ると3人に1人が事務職に就くことが分かります。
業種や職種に迷った人は、上記の表も参考にしてみてください。
参考:経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 産業横断的集計」、厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
2. 全国平均に比べて平均給与が低めである
全国の平均給与と比較すると、障がい者の平均給与は低めです。令和5年における、精神障がい者の平均給与と全国の平均給与を以下の表で比較してみます。
| 精神障がい者の平均給与 | 全国の平均給与 | |
|---|---|---|
| 年間 | 約178.8万円 | 約459.5万円 |
| 1ヶ月 | 約14.9万円 | 約38.3万円 |
年間の平均給与・1ヶ月の平均給与のいずれも、2倍以上の差があることが分かります。
もともと一般雇用枠で働いていた人からすれば、障害者雇用枠で就職した場合の給料が非常に少なく感じるでしょう。一般雇用のときと同様の生活水準を保つのは難しい可能性があります。
参考:厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」、国税庁 長官官房 企画課「民間給与実態統計調査」
障害者雇用枠で働くうえでの注意点
障害者雇用枠で就職し働くうえでの注意点を紹介します。
入社後も企業の担当者とコミュニケーションを取る
面接の際に症状や配慮して欲しいことなどを相談すると思いますが、入社後も人事担当者や上司とコミュニケーションを取り続けましょう。
直近の体調、業務への適正、通院の状況を報告したり、追加で対応してもらいたいことがあれば相談したりするのがおすすめです。
面接時から症状が変化していることもあり得ます。精神的にも負担なく働き続けられるよう、気になったことがあれば小さなことでも相談してください。相談できずにストレスが溜まって負荷がかかったり、仕事に影響が出たりする方が好ましくありません。
2年に1度、手帳を更新する
精神障害の手帳は、2年に1度の頻度で更新してください。更新しないと手帳を失効することになります。
更新する際は、精神障害の手帳・診断書・個人番号を確認できる書類などが必要です。地域の障がい者手帳の公式ページも併せてご確認ください。
更新の審査結果によっては、等級が変化したり手帳が交付されなかったりします。いずれの場合も必ず会社に報告しましょう。
なお更新は、有効期限の3ヶ月前から手続きできます。更新の申請から完了まで約2ヶ月ほどかかるため、余裕を持って申請するのがおすすめです。
精神障害の手帳を申請する手順
精神障害の手帳は以下の手順で申請できます。
- 医師に診察を依頼し、診断書を書いてもらう
- 市区町村の窓口にて手帳取得の申請書類をもらう
- 診断書や申請書などの必要書類を窓口へ提出する
- 審査によって等級が決定され、手帳が交付される
申請してから審査の結果が分かるまで、約1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。また、診断書は初診日から6ヶ月を経過した時点で作成されたものでなければなりません。もし今から通院を始めると、手帳を取得して障害者雇用枠で就職するまで、約1年弱はかかることを理解しておいてください。
また、申請をすれば誰でも手帳が交付されるわけではありません。審査によっては承認されず、「不承認通知書」が届くこともあります。
精神障害の手帳を申請する際に必要な書類
精神障害の手帳を申請する際は、以下の書類を持参してください。
- 診断書
- 申請書類
- マイナンバーカード
- 縦4cm×横3cmの顔写真
申請書類に個人番号を記載したり本人確認をしたりするため、マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードを持っていない人は、個人番号が載っている住民票の写し・住民票記載事項証明書・通知カードのいずれかでも代用できます。ただ、代用する場合は、運転免許証やパスポートなどの公的書類も必須です。
地域によって必要な書類や物が異なる場合があります。お住まいの地域の障がい者手帳に関する公式ページも併せてご確認ください。
精神障害の手帳の取得と障害者雇用枠での就職を検討しましょう
障害者雇用枠での就職には、さまざまなメリットやデメリットが存在します。
障がい者として入社すると、周囲からの理解を得やすいです。また、一般雇用枠で就職するよりも仕事を長期的に継続しやすいでしょう。
ただ、障害者雇用枠を設けている企業が少ないため、希望の業種・職種には就けないという懸念もあります。
メリット・デメリットも踏まえて、障害者雇用枠で就職するのか慎重に検討してください。安易に決めると、職場の環境や働き方が合わずに就職活動をやり直すことになる可能性があります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【テンプレ付】在職証明書(勤労証明書・在籍証明書)とは?書き方や注意点、手続きをご紹介
在職証明書とは、会社に在籍していることや、在籍していたことを証明するための書類のことです。勤労証明書や就業証明書、雇用証明書など、さまざまな名称で呼ばれています。本記事では、在職証…
詳しくみるパワハラは安全配慮義務違反?判例や防止策を解説
職場でのパワハラは、労働者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても「安全配慮義務違反」として法的責任を問われる可能性があります。 本記事では、パワハラが安全配慮義務違反…
詳しくみるパワハラ上司の特徴は?処分の注意点やパワハラ防止策を解説
パワハラ上司による問題行動は、職場全体の生産性を低下させる深刻な問題です。日常的に無化に対し、パワハラをする上司には、いくつかの特徴があります。 本記事では、パワハラ上司の特徴や行…
詳しくみる退職勧奨の解決金相場はいくら?なしと言われた時の対処法や上乗せ交渉のポイントを解説
退職勧奨を受けて「提示された解決金は妥当なのか」と不安を感じる人もいるでしょう。 本記事では、退職勧奨と解決金の一般的な相場目安、解決金の支払いがないと言われた場合の対応策、上乗せ…
詳しくみる定年後再雇用されない人とは?特徴や通知方法、リストラとの違いを解説
定年後、再雇用を希望しても、会社の判断で見送られることがあります。再雇用されない理由やその通知方法、リストラとの違いを理解することで、今後の対応策を見つけることができます。 この記…
詳しくみる転勤とは?異動との違いや離職・退職を防ぐコツを解説【テンプレート付き】
転勤は企業の成長と従業員のキャリア形成にとって重要な要素であり、多くの企業で実施されています。しかし、その実施方法や意図が不明確であると、従業員の離職や退職を招く可能性があります。…
詳しくみる