- 更新日 : 2026年1月13日
給与の締め日・支払い日を変更する方法は?従業員へのお知らせの書き方も【無料テンプレ付き】
「給与締日変更のお知らせ」は、従業員の生活設計に大きく関わる重要な通知です。本記事では、給与の締め日や支払い日の変更方法や、従業員へのお知らせの書き方や注意点について解説します。適切な手続きを踏むことで、スムーズな給与日程の移行を図りましょう。
目次
給与の締め日・支払い日は変更できる?
給与の締め日や支払い日を変更することは可能ですが、労働基準法第24条が定める「賃金支払の5原則」を守る必要があります。この原則には「毎月払い」と「一定期日払い」が含まれ、それぞれに留意が必要です。
まず、「毎月払い」では、月に最低1回の給与支払いが求められるため、変更月のスケジュールを適切に調整しなければなりません。また、「一定期日払い」では、支払い日が特定されて定期的に到来する必要があり、不定期な支払いは原則認められません。
さらに、締め日や支払い日を変更する場合は、事前に就業規則を改定し、労働基準法で定められた手続きに従って労働者に周知することが必要です。
加えて、従業員が金銭的な不利益を被る場合、会社への信頼低下やモチベーションの低下につながる可能性があります。そのため、変更時には十分な説明を行い、従業員の理解を得ることが重要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
給与の締め日・支払い日を変更する方法
給与制度変更は、従業員の生活に直接影響するため、慎重な計画と周知が不可欠です。特に締め日や支払い日の変更は、初月の給与に影響が及ぶため、従業員の理解と協力を得ることが欠かせません。
ここでは、締め日・支払い日変更のケース別に、具体的な方法と注意点を確認していきましょう。
給与の締め日のみ変更する場合
給与の締め日を変更する際には、対象期間が変わることで、変更による初月の給与額が減少する場合もあります。従業員の生活に支障が出る可能性もあるため、事前の配慮が必要です。
【変更例】
例えば、20日締めの当月25日支払いのケースで、事務処理期間が5日では短いため、15日締めに変更したいと検討している場合を考えてみます。15日締めを10月の給料から適用した場合は、以下のとおりです。
| 給料支給日 | 対象勤務期間 | 日数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 9月25日 | 8月21日〜9月20日 | 満額 | 変更前 |
| 10月25日 | 9月21日〜10月15日 | 25日分 | 変更後初回(5日分減少) |
| 11月25日 | 10月16日〜11月15日 | 満額 | 通常運用 |
【注意点】
変更後初回の支給である10月25日の給与額は、対象となる勤務期間が短縮されるため、通常よりも5日分減少します。11月25日以降は通常サイクルに戻るものの、この初月の減額は従業員にとって負担となる場合があります。
給与の支払い日のみ変更する場合
給与支払い日のみを変更する際は、賃金支払いの5原則の一つである「毎月1回以上払い」の遵守を大前提とした手続きが求められます。
また、従業員の生活に与える影響を考慮し、住宅ローンやクレジットカード決済など各種支払いの引き落とし時期への配慮が必要です。十分な説明会の開催と、就業規則変更までの余裕のある日程設定を行いましょう。
支払い日の変更に際しては、賞与支払い月に合わせた変更時期の調整や無利子貸付による生活支援、賃金の一部前倒し支給、数ヶ月かけた段階的な支払い日への移行などの対応策を検討する必要があります。
変更月に給与未払い期間が発生しないよう、慎重な計画立案と従業員からの同意の取得を心がけましょう。
給与の締め日と支払い日を両方変更する場合
給与の締め日と支払い日を両方変更する場合として、以下の例を考えてみます。
【変更例】
例えば、20日締めの当月25日支払いのケースで、どちらも5日ずらして25日締めの当月末支払いとした場合を考えてみます。この変更を10月の給料から適用した場合は、以下のとおりです。
| 給料支給日 | 対象勤務期間 | 日数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 9月25日 | 8月21日〜9月20日 | 満額 | 変更前 |
| 9月30日 | 9月21日〜9月25日 | 5日分 | 変更後初回(5日分の給料) |
| 10月31日 | 9月26日〜10月25日 | 満額 | 通常運用 |
【注意点】
締め日と支払い日を同時に変更した場合、9月で給与計算や支給が2回発生します。そのため、従業員へ事前に十分な説明を行い、勤務期間の一部を翌月分に含めるなどの対応を検討する必要があります。
給与の締め日・支払い日を変更するまでの流れ
給与の締め日や支払い日を変更するには、従業員への影響を最小限に抑えつつ、スムーズに移行するための準備が必要です。次に、給与の締め日・支払い日を変更するまでの具体的な流れを解説します。
従業員に変更を通知する
給与の締め日や支払い日を変更する際は、従業員への迅速かつ明確な通知が不可欠です。生活に直結する給与スケジュールの変更は、住宅ローンやクレジットカード決済への影響を伴う場合があります。
変更が決定した時点で速やかに説明し、予告期間を十分に確保することが重要です。説明会や個別面談など、従業員規模に応じた方法を選び、不安を解消できる緩和措置もあわせて提示することで、従業員が新たなスケジュールに備えられるよう配慮します。
従業員の同意を得る
給与の締め日や支払い日を変更する際には、従業員の同意を得ることが必要です。不安の声がある場合には個別面談を通じて生活への影響を確認し、賞与の一部先払いや変更時期の調整、無利子貸付といった補填策を提示し、従業員の理解と納得を得ることが求められます。
さらに、過半数代表者の意見を聴取し、変更の理由やメリットを丁寧に説明することで、新しい給与の支払い体制を受け入れやすくなるための環境を整えることが重要です。
就業規則の変更・届出を行う
給与の締め日や支払い日を変更する場合、就業規則の改定が必要です。改定時には、過半数代表者から意見を聴き、その意見書を添付して労働基準監督署へ届出します。
改定内容を従業員に事前周知したうえで、運用を開始しましょう。新制度での給与計算を実施するとともに、新規入社者には改定後の条件を反映した「雇用契約書」を交付します。
給与の締め日・支払い日の変更のお知らせの書き方
給与の締め日変更を例にしたお知らせ文は、以下のとおりです。

まず、従業員に感謝の気持ちを最初に伝えることが大切です。例えば、「日々の業務における皆さんのご協力に、心よりお礼申し上げます」といった表現で、日々の業務に対する感謝の意を示します。
次に、変更の理由を「業務量の増加」や「正確な事務処理の維持」のためとして説明し、従業員が納得できるように具体的に背景を述べましょう。
変更内容については、日程や金額を表形式で具体的に記載し、従業員が理解しやすいよう配慮します。
また、影響が心配な従業員には、経理部で個別に対応することを伝え、サポートの姿勢を示します。
給与締日変更のお知らせのテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
在宅勤務中のルール周知文(ワード)のテンプレート
給与の締め日・支払い日を変更するときの注意点
給与の締め日や支払い日を変更する際には、従業員に与える影響を最小限に抑える配慮が必要です。事前に適切なサポート策を整え、従業員が困難を感じないようにすることが重要です。ここでは、従業員への配慮と事務負担の観点から、変更時の注意点を解説します。
従業員の損失を補填する必要がある
給与の締め日・支払い日を変更する際は、従業員の生活への影響を考慮し、事前の説明と理解を得ることが重要です。
特に、支払い日を先に延ばす場合、住宅ローンやクレジットカードの引き落とし時期とのずれにより、従業員の資金繰りに支障が生じる可能性もあります。
そのような事態に備え、給与の前払いや無利息の社内貸付制度といった支援策を整備し、従業員の資金繰りをサポートする体制の整備が必要です。
社会保険の手続きが煩雑になる
給与の締め日や支払い日を4〜6月に変更すると、社会保険の保険料算定が複雑化します。これは、4〜6月の給与をもとに保険料を計算するためです。
算定基礎届の記入時などに、通常より煩雑な算定作業が発生するおそれもあります。従業員数が多い場合、さらに負担が増大するでしょう。したがって、締め日・支払い日の変更は4〜6月をさけて実施するのが賢明です。
変更による影響を最小限に抑え、計画的な給与日程の移行を心がけよう
給与の締め日や支払い日の変更は、従業員の生活に大きく影響する重要な事項です。法令を遵守するだけでなく、従業員への配慮と十分な準備が求められます。
変更前には、従業員に向けて早めに通知し、丁寧に説明することで理解を得ることが重要です。また、必要に応じて支援策を用意し、不安や負担を軽減する工夫も欠かせません。計画的かつ段階的に進めることで、スムーズな移行を目指しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
エクセル(Excel)で時給の給与計算が上手くいかない!正しく計算する方法を解説【無料テンプレ付き】
エクセル(Excel)で時給の給与計算をする際は、そのまま「時給」×「時間」の計算をすると上手く計算できないため、注意が必要です。残業の際の割増賃金も、注意して計算しなければなりま…
詳しくみる青森県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
青森県はリンゴをはじめとする農業、豊かな海の資源を活かした漁業、そして製造業が主要な産業です。また、観光業も盛んで、多様なビジネスが展開されています。こうした地域特有の業種では、給…
詳しくみる住民税を特別徴収しなくていい会社とは?普通徴収に切り替える方法も紹介
住民税の特別徴収は会社の義務ですが、一部例外があり普通徴収に切り替えられるケースもあります。 「特別徴収の対象外となるのは、どのような会社?」「普通徴収に切り替える方法は?」などと…
詳しくみる休職中のボーナス・賞与は?1~3カ月休職したときの目安は?
賞与を支給する場合には就業規則にあらかじめ定めておく必要があります。休職中の賞与の支給は、賞与査定対象期間中の勤務実績及び支給日の在職の有無によって決定され、ノーワーク・ノーペイの…
詳しくみる最低賃金とは?勤め先が違反していた場合の対応について
街中で求人広告を見かけることがあります。パート、アルバイトの場合、労働条件のうち、賃金は時給で提示されるのが普通ですが、意外と最低賃金法に違反しているケースが少なくありません。確認…
詳しくみるボーナスの手取りについて計算方法を解説!
年に数回支給されるボーナスは、額面全てが貰えるわけではありません。毎月の給与と同様、所得税や社会保険料、労働保険料が天引きされます。一方、月々の給与から源泉徴収されている全ての税金…
詳しくみる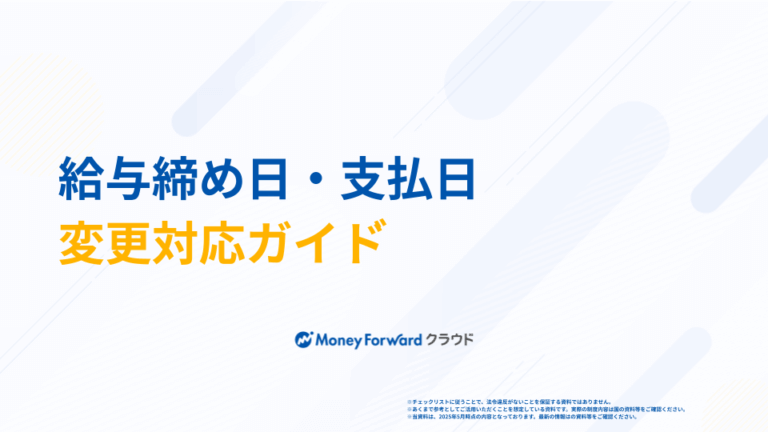

-e1762740828456.png)

