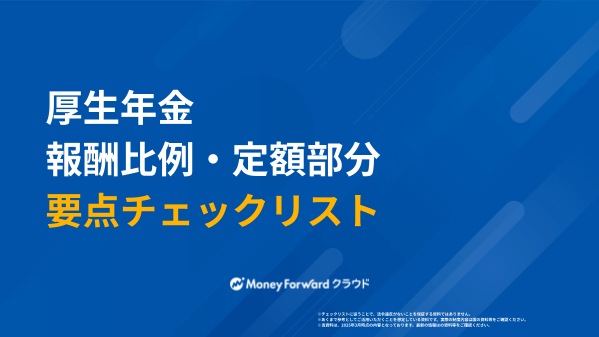- 更新日 : 2025年11月6日
厚生年金の報酬比例部分とは?定額部分との違いや計算方法、支給開始年齢を解説
公的年金制度には厚生年金と国民年金がありますが、その仕組みは複雑です。
支給開始年齢が65歳であることは知っていても、年金を構成する報酬比例部分や定額部分がどのようなものなのか、理解している人は少ないのではないでしょうか。
本稿では年金制度の概要、会社員が受け取る厚生年金の報酬比例部分と定額部分の違い、計算方法、支給開始年齢などについて詳しく解説します。
目次
厚生年金の報酬比例部分とは?
公的年金制度では、老齢年金は原則として65歳から支給されます。その仕組みは2階建て構造になっており、1階部分はすべての国民が加入する定額の国民年金(基礎年金)、2階部分は会社員や公務員が加入する、在職中の報酬に比例する厚生年金です。
この仕組みは1985年4月に改正された、年金一元化に向けた新年金制度と呼ばれるものです。
それまで自営業は国民年金、会社員は厚生年金、公務員は共済年金という縦割りの仕組みでした(公務員の共済年金が厚生年金に統合されたのは2015年10月)。
厚生年金はもともと2階建て構造であり、1階部分は定額部分、2階部分が報酬比例部分であったため、改正によって1階部分が国民年金に置き換わったことになります。
つまり会社員や公務員は、65歳から1階部分の国民年金から老齢基礎年金(定額部分)が、2階部分から老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。
この2階部分が、厚生年金の報酬比例部分です。現役時代の報酬に応じて算出されるため、報酬比例部分と呼ばれます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
厚生年金の定額部分との違いは?
前述のとおり、厚生年金はもともと2階建て構造でしたが、改正によって1階部分が国民年金の老齢基礎年金に置き換わりました。
本来であれば老齢厚生年金に定額部分はなく、老齢厚生年金は2階部分の報酬比例部分だけです。
改正前の旧制度では、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳であったのに対し、国民年金は65歳でした。
新制度では、国民年金に合わせて支給開始年齢を原則65歳としましたが、期待権を保護するため、暫定的に60歳から65歳になるまでの間は、特別支給の老齢厚生年金という形で残しました。
この特別支給の老齢厚生年金は旧制度の老齢厚生年金であり、2階部分は報酬比例部分、1階部分は定額部分となっています。
定額部分は在職中の報酬ではなく、厚生年金に加入して保険料を納付していた被保険者期間の月数に応じて算出されます。
3種類の厚生年金の計算方法は?
老齢年金を中心に、新旧年金制度の概要を見てきました。公的年金である1階部分の国民年金(基礎年金)と2階部分の厚生年金(報酬比例部分)はいずれも、保険支給の原因となる保険事故は老齢、障害、死亡の3つです。
それぞれに対応する年金として、1階部分には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があり、2階部分には老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。
ここからは2階部分の老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の計算方法について見ていきます。
老齢厚生年金
新制度の老齢厚生年金には原則の老齢厚生年金と、例外となる特別支給の老齢厚生年金があります。
原則の老齢厚生年金
前述のとおり、原則の老齢厚生年金は65歳から支給される2階部分の報酬比例部分だけです。
支給額は、以下の①と②を合算して算出します。
なお、①で用いる給付乗率は生年月日に応じて1,000分の9.5~1,000分の7.125であり、②で用いる給付乗率は生年月日に応じて1,000分の7.308~1,000分の5.481となっています。
計算式を①と②に分けているのは、賞与を算入するか否かが異なるからです。平成15年4月以後は厚生年金保険料を賞与からも徴収する総報酬制となり、その分が将来の年金にも反映されるようになりました。
そのため、①の平均標準報酬月額は厚生年金保険の「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った平均額であり、賞与は含まれませんが、②の平均標準報酬額は「被保険者であった期間の標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計を「被保険者であった期間の月数」で割った平均額となります。
特別支給の老齢厚生年金
これに対し、60歳から65歳になるまで支給される特別支給の老齢厚生年金は旧制度の老齢厚生年金であり、上記の報酬比例部分とは別に、1階部分に定額部分があります。
定額部分の計算方法は以下のとおりです。
給付乗率は、生年月日に応じて1.875~1.000となっています。2階部分の報酬比例部分の計算方法は、原則の老齢厚生年金と同じです。
障害厚生年金
障害厚生年金は2階部分の報酬比例部分として、1階部分の国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。支給額は、障害等級によって異なります。
障害厚生年金には年金と一時金があり、年金は障害の程度に応じて1級、2級、3級の障害厚生年金、一時金は障害手当金が支給されます。
支給額は以下のとおりです。
〇1級
〇2級
〇3級
〇障害手当金
報酬比例部分の計算方法は、原則の老齢厚生年金と同じです。1階部分の国民年金の障害基礎年金は1級と2級しかないため、3級と障害手当金は報酬比例部分のみとなります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金も2階部分の報酬比例部分として、1階部分の国民年金の遺族基礎年金に上乗せする形で支給されます。
支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分に4分の3を乗じて算出します。厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月と見なして計算します。
厚生年金の支給開始年齢は?
新制度では原則の支給開始年齢は65歳ですが、例外として特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給されます。ただし、これは暫定措置という位置付けです。
60歳からの特別支給は段階的に廃止
当初は、65歳になるまでは定額部分と報酬比例部分の両方が支給されることになっていましたが、生年月日に応じて段階的に廃止されます。
まずは1階部分の定額部分を生年月日に応じて支給開始年齢を段階的に60歳から引き上げて廃止し、65歳からの国民年金(定額部分の老齢基礎年金)につなげます(1994年の法改正)。
その後、2階部分の報酬比例部分も生年月日に応じて段階的に60歳から引き上げて廃止し、最終的には65歳からの新年金制度(1階部分は国民年金、2階部分は厚生年金)へ完全に移行します(2000年の法改正)。
1994年の改正によって、定額部分の廃止による国民年金(老齢基礎年金)への移行は2013年度に完了しています(女性は5年遅れ)。

※参考:「第4回社会保障審議会年金部会」資料から引用
厚生年金の繰り上げ・繰り下げ受給はできる?
原則の老齢厚生年金は、65歳の支給開始を繰り上げる、あるいは繰り下げることができるのでしょうか。
繰り上げ受給
受給権者が希望すれば、原則の老齢厚生年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。
ただし、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、減額率は一生変わりません。
減額される年金額は、原則の老齢厚生年金の額に以下の減額率を乗じて算出します。
原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求を行う必要があり、上記の減額率を老齢基礎年金の額にも乗じることになります。
繰り下げ受給
原則の老齢厚生年金は65歳からではなく、66歳から75歳までの間で繰り下げて受給することもできます。
繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げて受給することもできます。
増額率は、老齢厚生年金および老齢基礎年金の額に以下の増額率を乗じて算出します。
なお、特別支給の老齢厚生年金には繰り下げ受給の制度はありません。
特例で定額部分の年金が受給できる?
厚生年金保険には、44年特例という優遇措置があります。
特別支給の老齢厚生年金の2階部分の報酬比例部分を受けている人が、国民年金(老齢基礎年金)が支給される65歳になる前に退職などで被保険者でなくなったとき、暫定措置の廃止によって1階部分の特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できないケースがあります。
44年特例は長期間厚生年金に加入しているなど一定の要件を満たした場合、本来であれば受けられない1階部分の定額部分も合わせて支給するという優遇措置です。
44年特例の対象となるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 報酬比例部分を受給できること
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
- 厚生年金の被保険者でないこと
将来受け取れる年金額がいくらかシュミレーションしておきましょう
公的年金制度の概要、厚生年金の報酬比例部分と定額部分の違い、計算方法、支給開始年齢などについて解説しました。
年金制度は、これまで大きな改正が何度か行われています。新制度に完全移行するまでの暫定措置を正しく理解した上で、将来受給する年金をシミュレーションしておくことが大切です。
よくある質問
厚生年金の報酬比例部分とは?
1階の定額部分に上乗せされる2階部分の年金のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金の支給開始年齢は?
原則は65歳ですが繰り上げ、または繰り下げて受給することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
高年齢雇用継続給付支給申請書の書き方は?初回や2回目の手続きを解説
初回の高年齢雇用継続給付 申請時の必要書類について|公共職業安定所 高年齢雇用継続給付支給申請書は、60歳以降も継続して働く従業員の賃金が一定額未満に低下した場合、その低下分の一部…
詳しくみる65歳以上の従業員の社会保険手続き
昨今の高年齢者の増加に伴い、60歳を過ぎた方々が就業を続けるケースが増えてきました。 これは、社会保険の「高年齢者雇用安定法の改正」や「厚生年金の受給開始年齢の65歳への段階的引上…
詳しくみる月額変更届の手続きを効率化する方法は?システム導入や電子申請のポイントを解説
月額変更届の手続きは、毎月の対象者確認や書類作成が人事労務担当者の大きな負担となる業務です。 本記事では、月額変更届の業務をシステム導入や電子申請で効率化する手順を、注意点とともに…
詳しくみる厚生年金保険料が2ヶ月分引かれた!社会保険料の徴収ルールを解説
厚生年金の保険料は毎月の給与から天引きされ、会社が日本年金機構に納付しています。給与から控除される保険料は、原則前月分に相当する1ヶ月分です。しかし、退職のタイミングによっては、2…
詳しくみる労災の遺族年金とは?受給条件・金額・手続きをわかりやすく解説
勤務中の事故や通勤途中の災害によって、突然大切な家族を失ってしまうことは誰にとっても想像したくない出来事です。しかし、そんなときに遺されたご遺族の生活を支える仕組みとして、「労災保…
詳しくみる高年齢雇用継続給付とは?制度の変更点と計算方法を紹介
従業員が60歳で定年を迎えても、企業は65歳まで継続して雇用する義務があります。企業は非正規雇用に切り替え、給与を減額するのが一般的です。これを補填するのが雇用保険から支給される …
詳しくみる