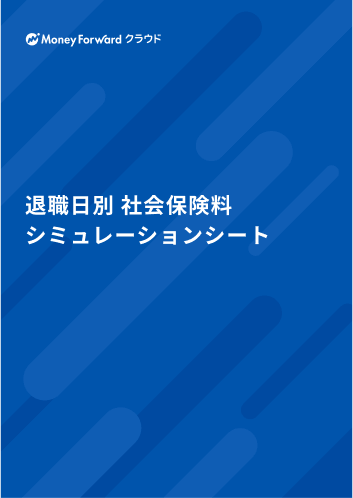- 更新日 : 2025年11月6日
退職月の社会保険料はいくら?月末退職と月途中退職の違いは?2か月分徴収の理由も解説
会社を退職する際、「退職月の社会保険料はいつまで支払うのか」「なぜ最後の給与から2か月分引かれるのか」といった疑問は尽きません。実は、退職日を月末にするか月の途中にするかで、社会保険料の負担が大きく変わります。
この記事では、退職日と社会保険料の関連性や、退職後に発生する手続きについて、具体的なケースを交えながら分かりやすく解説します。
目次
退職月の社会保険料はどのように決まる?
社会保険料(健康保険・厚生年金)がいつまで発生するかは、資格喪失日を基準に決まります。資格喪失日とは、健康保険や厚生年金の資格を失う日のことで、退職日の翌日と定められています。
そして、会社経由で支払う社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までです。このルールがあるため、退職日が1日違うだけで、支払う社会保険料が変わってくるのです。
退職月の社会保険料はいくら?
それでは、具体的な日付を挙げて、給与から天引きされる社会保険料がどうなるのかを確認してみましょう。無料でダウンロードできるシミュレーションシートもご用意しましたので、ぜひあわせてご覧ください。
| 月末退職 | 月の途中で退職 | |
|---|---|---|
| 退職日 | 7月31日 | 7月30日 |
| 資格喪失日 | 8月1日 | 7月31日 |
| 会社で払う保険料 | 7月分まで | 6月分まで |
| 退職月の保険料 | 最後の給与から天引きされる | 自身で国民健康保険・国民年金に加入し、7月分を支払う |
| メリット |
| – |
| デメリット | – |
|
月末退職の場合
月末である7月31日に退職すると、資格喪失日は翌月の8月1日です。この場合、資格喪失日(8月1日)が属する月の前月である7月分までの社会保険料が、会社での支払い対象となります。
したがって、最後の給与から7月分の社会保険料が天引きされます。退職後にご自身で7月分の国民健康保険料などを支払う必要はありません。
月の途中で退職する場合
月の途中である7月30日に退職した場合、資格喪失日は翌日の7月31日です。この場合、資格喪失日(7月31日)が属する月の前月である6月分までの社会保険料が、会社での支払い対象です。
したがって、最後の給与から7月分の社会保険料は天引きされません。その代わり、自身で国民健康保険などに加入し、7月分の保険料を納付する必要があります。
退職後の社会保険料はいくら?
退職後の社会保険料は、どの制度に加入するかで金額が変わります。
国民健康保険に加入する場合
多くの人が選択するのが、市区町村が運営する国民健康保険です。保険料は、前年の所得や世帯の加入者数などに基づいて計算されます。会社負担がなくなるため、在職中の本人負担分に比べて高くなる傾向があります。自治体によって計算方法や料率が異なるため、具体的な金額は住所地の役所の窓口で確認が必要です。
任意継続被保険者制度を利用する場合
退職日までに継続して2か月以上被保険者期間があれば、退職後も最大2年間、それまで加入していた健康保険を継続できます。これを任意継続と呼びます。保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて算出されますが、会社負担分がなくなるため、原則として在職中の保険料の2倍になります。ただし、上限額が設定されているため、詳しくは加入していた健康保険の運営団体に問い合わせましょう。
家族の扶養に入る場合
配偶者や親族が加入している健康保険の被扶養者になる選択肢もあります。被扶養者として認定されるには、自身の年間収入が130万円未満であることなどの条件を満たす必要があります。退職後に配偶者などの健康保険の被扶養者となれば、本人が保険料を支払う必要はありません。
退職後に社会保険料を請求された場合の対応は?
退職後に社会保険料を請求された場合、まずはその請求内容を確認しましょう。
月末退職の場合、最後の月の給与で控除しきれなかった保険料である可能性が高いです。また、住民税の最終徴収分であるケースも考えられます。不明な点があれば、まずは退職した会社の給与・人事担当者に連絡し、請求の内訳を明確にしてもらうことが重要です。
退職月の社会保険料についてよくある質問
ここでは、退職月の社会保険料についてよくある質問とその回答をまとめました。
月末退職で社会保険料が2か月分引かれるのはなぜ?
月末退職で社会保険料が2か月分引かれるのは、給与の締め日と支払日の関係から生じます。
例えば、6月30日に退職した場合を考えてみましょう。「月末締め・翌月20日払い」の会社では、翌月の7月20日に最後の給与を支払います。この場合、6月分の社会保険料は7月20日支給の給与から控除すれば問題ありません。
一方、「月末締め・当月25日払い」の会社では、退職月である6月が最後の給与支給月となるため、6月25日支給の給与から6月と5月分の社会保険料をまとめて控除する必要があります。このように締め日と支払日の関係によっては、社会保険料が2か月分引かれることがあります。
月の途中で退職すると社会保険料が二重に引かれる?
月の途中で退職した場合、任意継続や国保加入まで一時的に社会保険料が二重に感じられることがありますが、制度上の二重負担ではありません。会社の給与天引きと退職後に自身で加入する国民健康保険の納付タイミングが近くなることで、負担が重なったように感じられるだけです。
退職月の社会保険料を考慮して退職日を設定しましょう
社会保険料の観点から見ると、退職日は月末に設定するのが最もシンプルで、経済的な負担感を軽減できる方法です。月末退職であれば、退職月の社会保険料は給与から天引きされ、退職後に国民健康保険料をすぐに支払う必要がありません。一方、月の途中で退職すると、自身で国民健康保険に加入し、その月の保険料を支払う義務が生じます。ご自身の状況や転職先の入社日などを考慮し、最適な退職日を設定してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職者は算定基礎届が必要?対象者・書き方・記入例を紹介
退職者は基本的に算定基礎届の提出は必要ありません。ただし、退職日によっては届出の対象になる場合があり、誤った対応をすると年金事務所から指摘を受ける可能性があります。 本記事では、退職者の算定基礎届について解説します。基本的な記入例や対象者別…
詳しくみる社会保険の保険者番号について – わからない場合の調べ方
社会保険の保険者番号とは、国民健康保険や企業が加入する健康保険の保険者である「運営者ごと」に割り振られた番号です。6桁または8桁で構成されています。保険証を見れば確認できますが、数字の項目が多いためどれが保険者番号かわからないと思うケースも…
詳しくみる外国人雇用の際に社会保険加入は必要?条件や手続きの流れを解説
外国人労働者を雇用する際、日本人と同じように社会保険への加入が必要になる場合があります。適切な手続きを行わず未加入のままだと、企業には追徴金や罰則が科されることがあるため、注意が必要です。 本記事では、外国人雇用時の社会保険の適用条件や加入…
詳しくみるパート・アルバイトの社会保険
一定の要件を満たせば、パート・アルバイトであっても、社会保険に加入することはできます。しかし、会社によって対応はまちまちで、なかには正社員でなければ社会保険の手続きをしてもらえない会社もあるようです。 このような事態は、社会保険の適用事業所…
詳しくみる労災保険に加入していないとどうなる?未加入のリスクや責任
労災保険は、常勤やパート・アルバイトなど、労働者の業務上あるいは通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行い、保険料は会社が負担します。 会社が労災保険の加入手続きを行わなかった場合、罰則はあるのか?また、会社が労災保険に加入していなかった…
詳しくみる障害者雇用とは?制度の概要や一般雇用との違い
障害者雇用とは、障害者雇用促進法に定められた障害者の安定就労を目的とした制度です。この制度により、会社は一定割合以上の障害者を雇用する義務があります。本記事では、障害者雇用制度の概要、障害者雇用率や企業側の義務などに加え、障害者雇用枠で働く…
詳しくみる