- 更新日 : 2025年7月11日
就業規則における健康管理の記載例|雛形をもとに義務や罰則、費用負担についても解説
従業員の健康は、企業の持続的な成長を支える最も重要な経営資源です。従業員の健康を維持・増進するために、常時使用する従業員への健康診断の実施が法律で義務付けられています。健康診断の実施とそのルールを定めた就業規則の整備は、企業の危機管理に不可欠と言ってよいでしょう。
本記事では、健康診断に関する規定の重要性から、実務で判断に迷う論点、関連規定までをわかりやすく解説します。すぐに使える就業規則の雛形(テンプレート)もご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
就業規則への健康診断の記載は企業の義務
結論から言うと、事業者による従業員への健康診断の実施は、労働安全衛生法第66条で定められた法律上の義務です。これに違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、この法的な義務を会社のルールとして具体的に落とし込み、全従業員に周知するために、就業規則への記載が必要となります。
就業規則に実施時期、費用負担、受診義務などを明記することで、労使間の不要なトラブルを防ぎ、円滑な制度運用が可能になります。 規定が曖昧な場合、「受診は任意か」「費用は自己負担か」「健康診断の受診時間は労働時間になるのか」といった疑問が従業員に生じ、混乱や紛争を招きかねません。
就業規則で従業員の健康管理について明確な方針を示すことは、従業員が安心して働ける環境を整備し、企業の安全配慮義務を果たす上で不可欠です。
実施が義務付けられている健康診断の種類と対象者
一口に健康診断といっても、法律で義務付けられているものにはいくつかの種類があります。どのような従業員に、どの健康診断を実施する必要があるのかを正しく理解し、自社の就業規則に反映させましょう。就業規則の健康診断に関する規定の雛形・記載例では、これらの法定健康診断を網羅的に記載しています。
- 雇入時の健康診断:常時使用する労働者を雇い入れる際に実施します。
- 定期健康診断:常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施します。
- 特定業務従事者の健康診断:深夜業などの特定業務に従事する労働者に対し、配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回実施します。
- 特殊健康診断:法で定められた特定の有害な業務に従事する労働者を対象に行われる特別な健康診断です。
そのほかにも、従業員を6ヶ月以上海外派遣させる際や6ヶ月以上海外派遣した従業員が帰国して国内業務に従事する際に実施する「海外派遣労働者の健康診断」、給食業務に従事する従業員の雇入れの際や配置替えの際に実施する「給食従業員の検便」、塩酸、硝酸、硫酸などを発散する場所で業務を行う従業員に実施する「歯科医師の健康診断」などがあります。
「常時使用する労働者」には、パートタイマーやアルバイトも条件に該当すると対象になりますので注意しましょう。以下の要件をいずれも満たす場合は、パートタイマーやアルバイトも健康診断を実施する必要があります。
- 契約期間の定めがない契約の従業員
※有期雇用契約で、契約期間が1年以上の従業員や契約を更新して1年以上の雇用が見込まれる従業員、契約更新により1年以上雇用されている従業員も含みます(有害業務などの特定業務に従事する場合はいずれも6ヶ月以上) - 週の所定労働時間がフルタイムで働く正社員などの4分の3以上の従業員
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
就業規則の作成・変更マニュアル
就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。
本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。
労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。
本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。
就業規則(ワード)
こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
就業規則変更届 記入例
こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。
実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。
就業規則の健康診断に関する規定のポイント
健康診断に関する規程を設ける際、特にトラブルになりやすい「費用」と「受診時間中の賃金」については、ルールを明確に定めておくことが重要です。
健康診断の費用負担
労働安全衛生法に基づく健康診断(法定健診)の費用は、事業者に実施義務があるため、事業者が負担しなければなりません。
就業規則にも、法定健診の費用は会社が全額負担することを明記しましょう。
ただし、以下のようなケースについては、従業員の自己負担と定めることが可能です。
- 従業員が任意で追加する検査項目(人間ドックのオプションなど)
- 自己都合で会社が指定した医療機関以外で受診を希望した場合の差額や交通費
再検査(二次検査)の費用負担
定期健康診断などで「要再検査」と診断された場合の費用については、法律上の定めはなく、会社に負担義務はありません。しかし、従業員の健康確保は企業の安全配慮義務の観点からも重要です。労使トラブルを避け、円滑な受診を促すためにも、会社が費用を負担するか一部補助するのが望ましいでしょう。
人間ドックの補助は福利厚生として有効
法定健診を超える人間ドックの費用補助は、必須ではありませんが、従業員の健康をサポートするのに有効な福利厚生です。就業規則に「会社は、従業員の健康増進のため、人間ドックの受診勧奨や費用補助を行うことがある」といった規定を設けることで、従業員の健康意識を高め、より手厚いサポート体制をアピールできます。
健康診断の受診時間中の賃金
健康診断の受診時間に対する賃金の支払いについても、法律に明確な定めはありません。しかし、従業員の受診をスムーズに進めるためには、所定労働時間内に受診できるよう配慮し、その時間は有給とするのが望ましいとされています。
特殊健康診断は、業務に関連して従業員の健康確保のため当然に実施しなければなならない健康診断です。そのため、特殊健康診断の受診時間は労働時間となりますので、有給扱いにする必要があります。
就業規則の健康診断に関する規定の雛形・記載例でも、受診時間は労働したものとみなし、賃金を支払う旨を原則として定めています。
就業規則の健康診断に関する規定の雛形・記載例
「まずは具体的な規定例が見たい」「自社の就業規則をすぐに整備したい」という方のために、健康診断はもちろん、安全衛生や労災補償、各種手当まで網羅した就業規則の雛形をご用意しました。
健康診断の条文だけでなく、関連する社内規定を整備する際のベースとしてもご活用いただけます。下記よりダウンロードし、自社の実情に合わせてカスタマイズしてください。
健康診断の結果の取り扱いと企業の義務
従業員の健康診断結果は、極めて機微な個人情報です。その取り扱いには、個人情報保護の観点から細心の注意を払わなければなりません。
- 結果の保管と管理:事業者は健康診断の結果を記録した個人票を法令に基づき所定の期間保存する義務があります。
- 産業医の意見聴取と就業上の措置:異常の所見があった従業員については、医師の意見を聴き、必要に応じて作業転換や労働時間の短縮といった措置を講じます。
- 秘密の保持:健康診断に関する個人情報は、法令等に基づき適正に管理し、その秘密を保持することを明記する必要があります。
就業規則の健康管理に関連する規定
従業員の健康と安全を守るためには、健康診断だけでなく、より広い視野で就業規則を整備することが重要です。
- 安全衛生
事業者は、従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成する義務があります。保護具の着用や整理整頓など、従業員が遵守すべき事項を具体的に定めます。 - 労災(災害補償)
従業員が業務中や通勤中に怪我などをした場合(労働災害)の補償について、「労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う」と明記し、万が一の際の対応を明確にします。 - ストレスチェック制度
50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施も義務付けられています。健康診断と同様に、就業規則に実施に関する規程を盛り込むようにしましょう。 - 資格手当
安全管理者や衛生管理者といった、企業の安全衛生管理に関連する資格の取得を奨励するため、「資格手当」を設けることも有効です。
自社に合った規定で従業員の健康と会社を守る
就業規則における健康診断の規定は、単なる義務の履行ではありません。従業員の健康と安全を守り、安心して働ける職場環境を構築するという、企業の重要な責務の現れです。
今回ご提供した雛形を参考に、自社の業種や規模、働き方の実態に合わせて最適な規程を作成してください。健康診断、安全衛生、労災、そして従業員のウェルビーイング全般に配慮した就業規則は、労使双方の信頼関係を深め、企業の持続的な発展に不可欠な基盤となるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
定年後再雇用のボーナスはいくら?相場やボーナスなしの違法性、交渉のポイントも
「定年後、再雇用で働き続けたいけど、ボーナス(賞与)はどうなるんだろう?」「現役時代より大幅に減らされる、もしかしたらゼロになるって本当?」 人生100年時代を迎え、60歳の定年後…
詳しくみるHRM(人的資源管理)とは?5つの機能をもとに具体的な事例を紹介
HRM(Human Resource Management)とは「人的資源管理」を意味します。具体的には、従業員を人的資源と捉えて有効活用するための採用、教育、人事評価、人材配置な…
詳しくみる【テンプレート付】口座振込労使協定とは?作成方法を解説!
かつて、給与は現金の手渡しで支給されていました。給料日には1カ月間の働きに対する報酬を封筒で受取り、その有り難みを感じていました。 今は、給与は銀行口座への振込が当たり前になってい…
詳しくみる高年齢雇用継続基本給付金が廃止されるのはいつ?企業への影響や対策も解説
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳未満の被保険者を対象に、賃金が下がった場合にその一部を補填する目的で支給されている制度です。しかし、この制度は近年の高年齢者雇用政策の変…
詳しくみる就業規則の変更に同意しないとどうなる?不利益変更に同意できない場合の対応も解説
会社から就業規則の変更を告げられた際、その内容に納得がいかない、あるいは明らかに自分にとって不利益だと感じることがあるかもしれません。そんなとき、「本当に同意しなければならないか?…
詳しくみる就業規則への福利厚生の記載例|厚生労働省のモデルに準拠したテンプレートを無料配布
従業員のエンゲージメントを高め、魅力的な職場を築くために欠かせないのが「福利厚生」です。しかし、慶弔見舞金や住宅手当といった制度を導入する際「就業規則にどこまで書けばいいのか?」「…
詳しくみる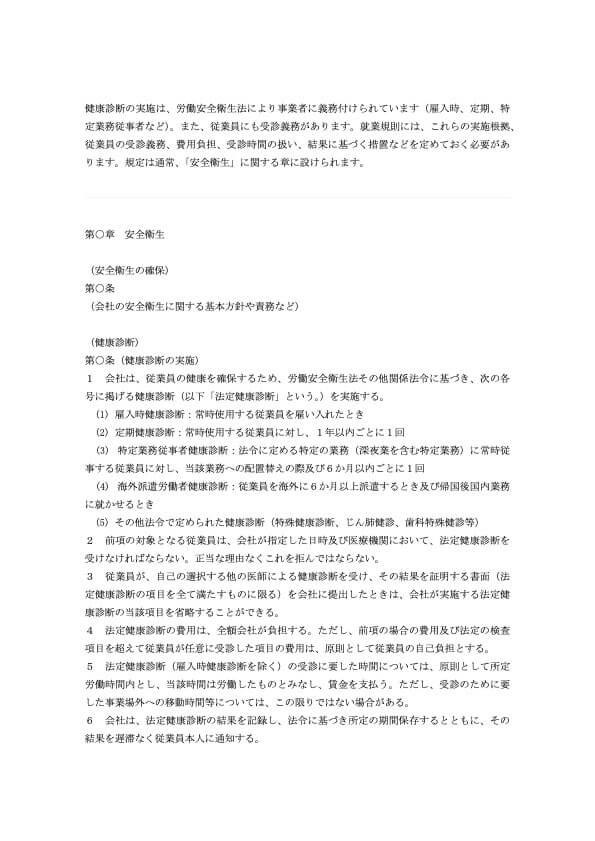


-e1762754602937.png)
