- 更新日 : 2025年11月16日
うつ病になった従業員を部署異動させるのは義務?配置転換のポイントもあわせて解説
業務が原因でうつ病になった従業員は、部署異動させなければならないのでしょうか?配置転換を禁止する法律もないため、企業の適切な判断が求められます。
本記事では、うつ病になった従業員への対応や部署異動させるメリットと注意点について解説します。あわせて、部署異動などの配置転換で従業員がうつ病になった場合の対応方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
業務が原因でうつ病になった従業員は、部署異動させたほうがよい?
うつ病になった従業員の配置転換を禁止する法律はありません。だからといって、配置転換をしないといけないというわけでもありません。
配置転換自体は、企業の裁量に委ねられます。配置転換を命じるかは、業務上支障を来すおそれがあるか、無理をさせることで再発しないかなど、さまざまな事情を考慮する必要があります。
うつ病は再発することが多い病気でもあるため、部署異動のほか、軽易な職種に変更するなどの検討もするとよいでしょう。休職後に復職した従業員が無理をして働いた結果、うつ病を再発させてしまうと安全配慮義務違反を問われるおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
部署異動以外の対応
部署異動以外の対応としては、次の3つが挙げられます。
- 最適な解決策を探す
- 産業医に相談する
- 休職や復職に対するサポートを行う
最適な解決策を探す
従業員に対して最適な解決策を模索することが重要です。従業員の相談を受け、一緒に最適な解決策を考えましょう。問題に対してみんなで取り組むことで、うつ病の進行を防げる可能性もあるでしょう。
その際、本人と一緒になって解決策を探ることが重要です。決して会社の都合だけで解決策を決めないようにしましょう。
たとえば、次のような解決策が挙げられます。
- 業務量が多い場合 → 業務量を減らす
- 人間関係のトラブルに巻き込まれている → 部署異動を考える
- 体調不良が続いている → 休職を考える
産業医に相談する
産業医と連携して対応することも有効な手段です。精神疾患はデリケートな病気のため、専門家の力を借りることで早期解決につながる場合があります。
休職や復職に対するサポートを行う
医師と連携したうえで、休職や復職のサポートをすることも重要です。
医師から休職の指示が出た場合は、速やかに休職させる必要があります。また、体調が回復したら、復職に向けてのサポートも行いましょう。
復職後、半年から1年間は再発のリスクが高いため、業務調整が必要です。無理のない業務を与えるようにしましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
うつ病の従業員が復職した場合、部署異動させなかったら安全配慮義務違反になる?
前述したように、部署異動の義務はありません。また、うつ病で休職していた従業員が復職の際に配置転換を希望しても、会社は必ずしもそれに応じる必要はありません。
なぜなら、配置転換は会社の人事権に基づくもので、従業員から配転の申し出があった場合においても、応じる義務がないためです。
ただし、精神疾患を罹患している従業員に対する扱いには注意しなくてはなりません。以下は、精神疾患に罹患した従業員が転勤命令を受け、退職の意思を表示した事案です。
裁判では、従業員に対する転勤命令が無効であることを前提として、企業に従業員に対して行った配転命令等が安全配慮義務違反に当たるとして、企業に慰謝料の支払いを求めました。
判決のポイントは、配転命令の有効性と安全配慮義務違反の2点です。
【配転命令の有効性】
- 転勤に関して、業務上の必要性が認められないか、あったとしても非常に弱いものであった
- 通勤時間の大幅な長時間化(片道1時間→片道2時間半へ)や環境変化により、従業員の心身や疾患に悪影響を与えるおそれも否定できない
以上より、従業員の転勤による負担や不利益が大きいと判断されました。
【安全配慮義務違反】
- 転勤を命ずる使用者としては、労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意すべき
- 企業は、精神疾患による欠勤ないし休職から復帰した労働者を転勤させるにあたって、当該従業員の意向、主治医等の専門医の意見も踏まえて検討し、従業員の生命および身体等を危険から保護するように配慮すべき義務を負う
- にもかかわらず、配転命令の決定にあたっては診断書のみ依拠し、主治医等の専門医の意見や従業員の意向等も聴取していない
以上より、企業は安全配慮義務違反と判断されました。
前述したように、部署異動させなかったら安全配慮義務違反になるわけではありません。しかし、異動の有効性を判断するにあたって従業員が精神的疾患者である場合は、従業員と十分協議したうえで、より慎重な判断が要求されます。
うつ病の従業員を部署異動させるメリットと注意点
うつ病の従業員を部署異動させるメリットと注意点について解説します。
メリット
メリットは、部署異動することで異動前の仕事や人間関係から離れられることです。異動前の仕事内容や職場環境が原因でうつ病を発症していたのであれば、環境を変えることでうつ病の改善に効果があるかもしれません。また、リスタートを図れるため、従業員にとってもモチベーションになるでしょう。
注意点
一方で注意点も存在します。新たな部署での作業や人間関係に対してストレスを覚える従業員もいることは理解しておきましょう。
環境の変化はもちろん未経験の業務内容であった場合、肉体的または精神的に大きな負荷がかかります。また、人間関係を再構築しなければならないこともストレスになりかねません。
異動すればうつ病が落ち着くとは限りません。異動を安易に行ってしまったことでうつ病が再発した事例も多く存在します。部署異動をさせる場合には、本人の希望を聞いたうえで慎重に対応しましょう。
部署異動などの配置転換で従業員がうつ病になった場合の対応方法
部署異動や昇格・降格・出向などの配置転換によってうつ病になることは考えられます。その場合には、適切な対応が必要です。
うつ病になった場合に企業ができることは、専門家への相談や職場環境の改善などです。カウンセラーや心理士に相談することで、問題を解決する手助けが得られるでしょう。
また、休職制度や企業の提供するメンタルヘルスプログラム、相談窓口の活用もおすすめです。
部下がうつ病になってしまったら、上司や管理職は責任を問われる可能性があります。メンタルヘルス対策となる体制づくりや、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐ職場環境づくりに取り組みましょう。
従業員にストレスを与えずに配置転換を行うポイント
従業員にストレスを与えずに配置転換を行うポイントを紹介します。主なポイントは次の3つです。
- 従業員の話を聞く
- 異動先を正しく選ぶ
- 異動で生じる負担をサポートする
ポイントを押さえてストレスのない配置転換を実現しましょう。
従業員の話を聞く
まずは、従業員の話を聞くことが大切です。従業員の悩みや異動希望の理由に耳を傾けましょう。
その際は、話しやすい雰囲気を作ることや相談内容がほかの従業員に漏れないような対策が必要です。
異動先を正しく選ぶ
異動先を正しく選ぶことも重要です。異動先は、従業員がストレスなく働けるかどうかに大きく影響を及ぼします。異動先の雰囲気や人間関係、業務量などについてあらかじめ把握しておき、従業員にとってストレスの原因となるものが少ない異動先を選びましょう。
異動で生じる負担をサポートする
異動で生じる従業員の負担をサポートすることも大切です。ストレスが配置転換の理由の場合は、定期的なフォローアップや相談窓口の設置などで、従業員のメンタルサポートに取り組みましょう。
うつ病の場合には慎重な対応が必要
従業員がうつ病で異動希望が出されても対応する義務もありません。しかし、部署異動によってうつ病が改善される可能性がある場合、検討は必要です。
その際には、従業員の状況や希望などをしっかりとヒアリングしたうえで慎重な対応が求められます。本記事で紹介した判例を参考にしながら、適切に対応できるようにあらかじめ対策を検討しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社宅と寮の違いとは?メリットやデメリット、選ぶ際のポイントを解説
企業の福利厚生として、社宅や寮の導入を検討する際「どちらがより自社に適しているのか?」と悩む人事・総務担当者は少なくありません。 本記事では、社宅と寮の基本的な違いやメリット・デメ…
詳しくみる配置転換と転勤の違いを解説!目的や無効となるケースも紹介
配置転換と転勤は、社員の人事異動において意味合いが大きく異なります。本記事では、根本的な違いからそれぞれの目的や無効となるケース、人事異動を成功させるためのポイントまで詳しくご紹介…
詳しくみる就業規則への管理監督者の記載例|適用範囲や賃金、名ばかり管理職を防ぐ方法も解説
企業の成長と労務管理の適正な運用を実現するうえで、管理監督者の役割は非常に重要です。しかし、管理監督者の定義や就業規則における取り扱いは複雑で、誤った運用は「名ばかり管理職」問題な…
詳しくみる【テンプレ&記入例あり】キャリアデザインシートとは?書き方やメリットを解説
キャリアデザインシートとは、仕事を中心に希望する将来像やそれを実現するための方法を考えて、図や表にまとめたもののことです。キャリアデザインシートを作成すると希望や夢が明確になるため…
詳しくみるパート社員の雇用契約書とは?記載事項や正社員との違いを解説
パート社員の雇用契約書は、会社とパート社員の間で雇用条件や業務内容、勤務期間、雇用契約期間などを記載した書面です。パート社員を雇用する際は、事前に書面で契約を交わしておかなければ、…
詳しくみるその社宅管理、本当に最適?フローの見直し方法を理解してコストと手間を削減しよう
「うちの社宅管理、もっと効率化できないかな?」「コストや手間がかかりすぎている気がする…」と感じていませんか。社宅管理の業務フローは一度決めたまま見直さず、非効率な状態になっている…
詳しくみる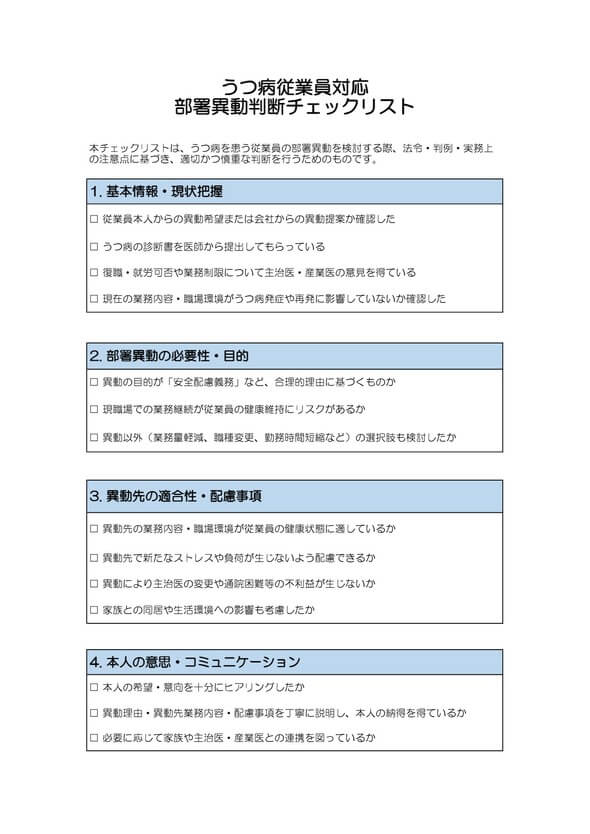


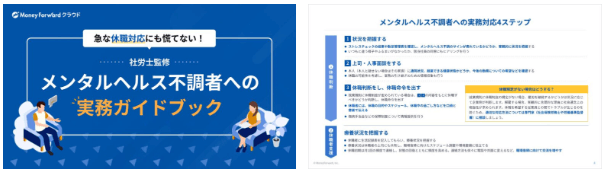
-e1763463724121.jpg)