- 更新日 : 2025年11月11日
衛生管理者とは?仕事内容や資格取得について解説!
衛生管理者は、労働安全衛生法によって定められた国家資格です。就労中の労働災害や、労働者の健康障害を防止する役割を担います。本記事では、衛生管理者の役割や仕事内容、資格取得によって得られるメリットなどをお伝えします。衛生管理者試験の難易度や合格率なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
衛生管理者とは?
衛生管理者とは衛生管理の専門家であり、労働安全衛生法という法律によって定められた国家資格です。衛生管理者が担う主な役割は、就労中の労働災害や労働者の健康障害の防止です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則、その事業場専属の衛生管理者の専任が求められます。なお、衛生管理者になるためには「第一種衛生管理者」か「第二種衛生管理者」の資格を取得しなければなりません。第一種衛生管理者と第二種衛生管理者のそれぞれの特徴、衛生管理者の仕事内容を解説します。
第一種の特徴
第一種衛生管理者は、有害業務に携わる業務も含め、すべての業種において衛生管理者として働くことが可能です。第一種と第二種の違いは、専任できる業種の範囲です。「農林畜産業」や「鉱業」、「建設業」をはじめとするいくつかの業種については、第二種衛生管理者では対応できません。
そのため、業種によっては第一種衛生管理者試験を受ける必要があるでしょう。ただし、基本的な業務内容については、第一種と第二種では、大きな違いはありません。
第二種の特徴
第二種衛生管理者は、基本的に有害業務の業務には携わりません。そのため、一般的なオフィスや店舗での業務に限定されることが特徴です。
詳しくは後述しますが、第二種衛生管理者試験の合格率のほうが第一種衛生管理者試験よりも高いため、挑戦しやすいといえます。勤務先で第一種衛生管理者が必要とされなければ、第二種衛生管理者のみの取得でも十分でしょう。
衛生管理者の仕事内容
衛生管理者の主な役割は、職場の労働者の健康を守ることです。そのため、職場の安全対策を講じたり、労働者に対して安全や衛生に関する教育を行ったりします。主な仕事内容は、以下をご参照ください。
- 原則週1回以上の職場巡視
- メンタル不調を含む、体調不良の労働者の発見と処置
- 労働者の健康診断の管理
- 労働者に対する衛生教育
- 救急用品などのチェックや管理
特に重要な仕事は、週1回以上の職場巡視です。定期的にチェックを行うことで、職場の問題点を早期に発見し、対策を講じられます。そのほか、衛生委員会の運営や健康診断の受診率向上に向けた取り組みなども、衛生管理者の仕事です。なお、衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進の取り組みなどの重要事項について、労使で調査審議を行う場です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
衛生管理者が職場の安全対策において果たす役割
衛生管理者は、労働者の健康を守るだけでなく、安全な作業環境を維持するためにも重要な役割を担っています。事故や疾病を未然に防ぐために、現場の安全対策に積極的に関与することが求められます。
職場環境の巡視によるリスクの早期発見
衛生管理者の基本的な業務の一つが、職場の巡視による衛生状況の把握です。作業場を定期的に見回ることで、換気状況や照明、作業姿勢、騒音・粉塵などのリスク要因を早期に発見することができます。たとえば、滑りやすい床、化学物質の保管状況、労働者の疲労蓄積の兆候など、事故につながる要素を見逃さず、関係部署に改善を提言することが重要です。
衛生委員会への参加による改善提案
常時50人以上の労働者を抱える事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。衛生管理者はその構成員として委員会に参加し、現場の衛生課題や事故防止策について意見を述べる責任があります。実際の労働環境に即した改善提案を通じて、管理職や他部門との協力体制を築き、全社的な安全文化の醸成に貢献することが求められます。
衛生管理者が労働者の健康増進について果たす役割
衛生管理者は労働者の疾病予防や健康増進の面でも重要な役割を担っています。単に法令を守るだけでなく、従業員が心身ともに健康に働ける環境づくりをリードすることが求められます。
健康診断の実施とフォローアップ
衛生管理者は、定期健康診断やストレスチェックの実施を管理し、その結果に基づいたフォローアップの推進に関与します。健診結果に異常があった場合には、産業医との連携を図り、再検査や保健指導の対象者を特定・支援します。
また、従業員に対して健診結果の説明や生活習慣改善のアドバイスを行うなど、健康リスクの「気づき」につながる対応を行うことも衛生管理者の役割です。
健康教育や衛生活動を通じて意識を高める
職場での健康意識を高めるためには、定期的な衛生講話や健康教育、キャンペーン活動の実施が有効です。衛生管理者は、たとえば「感染症対策セミナー」「生活習慣病予防週間」などを企画・運営し、従業員が自発的に健康行動をとれる環境づくりを支援します。
さらに、長時間労働や睡眠不足、栄養バランスの偏りといったリスクにも目を向け、現場での声をもとに改善提案を行うことが期待されます。
衛生管理者が職場の巡視で気をつけるべきポイント
衛生管理者の重要な職務のひとつが、職場環境の巡視です。現場の実態を把握し、リスクを未然に防止するためには、「見回り」にとどまらず、観察の視点や改善の着眼点を持つことが求められます。
作業環境の物理的リスクに注目する
巡視の際には、作業場の温度・湿度、照明、換気、騒音、粉塵・有害物質の管理状態など、労働環境の物理的側面に注視することが重要です。換気が不十分な場所や、化学物質を取り扱うエリアでは、作業者の体調に影響を及ぼす恐れがあるため、設備の適正な使用と保守状態も確認します。
また、床面の滑りやすさ、機械の可動範囲内での障害物の有無など、労働災害につながりやすい状況にも敏感になる必要があります。
作業者の行動と作業姿勢を観察する
巡視は、作業者の健康状態や作業姿勢を確認する絶好の機会です。不自然な姿勢、過度な力を使う作業、同一動作の繰り返しなどが見られれば、腰痛や筋骨格系障害のリスクがあると判断できます。
また、個人用保護具(マスク、手袋、ヘルメットなど)が適切に着用されているかも確認するべきポイントです。従業員が不安や不調を訴えていないかをさりげなく聞き取る姿勢も大切です。
衛生管理者の選任義務と罰則規定
労働者の健康と安全を守るため、一定規模以上の事業場では衛生管理者の選任が法律で義務付けられています。選任義務の対象や違反時の罰則を正しく理解し、確実な対応が求められます。
衛生管理者の選任が義務付けられる事業場
労働安全衛生法第12条により、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、衛生管理者を1名以上選任しなければなりません。業種を問わず、労働者数が基準を超えた時点で義務が発生します。
また、労働者の数が増えるに従って選任人数も増加します(例:労働者数200人を超えると2人、500人を超えると3人以上が必要)。衛生管理者は、原則として「有資格者」でなければならず、第一種または第二種衛生管理者免許を取得していることや、医師・歯科医師、労働衛生コンサルタントなどであることが条件です。
違反した場合の罰則と企業が受ける影響
衛生管理者の選任義務に違反した場合、労働安全衛生法第120条に基づき、「50万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、労働基準監督署からの是正勧告や監査対象となり、企業の法令遵守姿勢が問われる事態にもつながります。
また、労働災害が発生した際に衛生管理体制の不備が認定されると、企業責任が重く評価される場合があるため、リスク管理の観点からも早期の選任と適切な届出が不可欠です。
衛生管理者と産業医・安全管理者との連携
職場の健康と安全を確保するためには、衛生管理者、産業医、安全管理者がそれぞれの専門性を活かしながら連携し、統一的な安全衛生活動を行うことが不可欠です。
連携が重要な理由
衛生管理者、産業医、安全管理者はいずれも労働安全衛生法に基づき設置される法定職種であり、職場のリスクを低減し、労働者の健康と命を守るという共通の目標を持っています。しかし、それぞれの役割には違いがあります。衛生管理者は日々の職場巡視や衛生面の管理、健康診断の実施管理などを担当し、産業医は医学的専門知識をもとに個別対応や職場環境の助言を行い、安全管理者は機械や作業環境の安全性確保を主に担当します。
これらの役割が孤立してしまうと、重大なリスクを見逃す恐れがあります。たとえば、衛生管理者が現場で異変に気づいても、産業医と情報共有できていなければ、医学的支援や就業措置に結びつかないことがあります。連携の目的は、こうした情報と対策を一体化し、「現場」「健康」「安全」の視点を統合した取り組みを可能にすることにあります。
相互の職責を理解し役割分担を整理する
まずは三者がそれぞれの業務範囲を正しく理解し、連携の必要性を共通認識として持つことが重要です。役割が重複する部分や、責任の境界が曖昧な場面を整理し、誰が主導するべきかを明確にすることで、業務効率が向上し、責任の所在も明確になります。
また、現場での課題を衛生管理者が拾い上げ、産業医が医療的観点から助言、安全管理者が業務改善を提案する、といった流れを確立すれば、部門横断型のリスクマネジメント体制を築くことができます。
情報共有と定期的な連携会議で一体感を持たせる
三者が実際に連携する場として最も重要なのが「安全衛生委員会」です。この場で、健康診断の結果傾向、巡視での気づき、作業リスクの報告などを共有し、課題に対して多角的な解決策を検討します。
また、重大な労災や体調不良者発生時には、産業医・衛生管理者・安全管理者が迅速に連携し、原因究明や再発防止策の策定を共同で行う体制が求められます。定期的な非公式ミーティングや、情報共有ツールを活用した連携強化も有効です。
衛生管理者の合格率
ここからは、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者、それぞれの合格率を解説します。
第一種の合格率
安全衛生技術試験協会によると、2024年の第一種衛生管理者試験の合格率は、46.3%でした。受験者数は64,911人で、そのうち合格者数は30,081人です。過去5年間の合格率は、以下のように推移しています。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格率 | 43.8% | 42.7% | 45.8% | 46.0% | 46.3% |
| 受験者数 | 43,157名 | 68,210名 | 68,066名 | 67,572名 | 64,911名 |
| 合格者数 | 18,916名 | 29,113名 | 31,207名 | 31,108名 | 30,081名 |
第二種の合格率
第二種衛生管理者試験の合格率は49.8%で過半数近くが合格しており、第一種衛生管理者試験の合格率を3%以上、上回っていることがわかります。なお、受験者数は39,262人、合格者数は19,546人でした。第二種衛生管理者試験の過去5年間の合格率の推移は、以下をご参照ください。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格率 | 52.8% | 49.7% | 51.4% | 49.6% | 49.8% |
| 受験者数 | 22,220名 | 36,057名 | 35,199名 | 37,061名 | 39,262名 |
| 合格者数 | 11,729名 | 17,922名 | 18,089名 | 18,374名 | 19,546名 |
参考:労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく試験|安全衛生技術試験協会
衛生管理者の試験難易度
衛生管理者の試験難易度は、他の国家資格と比べると決して高いわけではありません。合格率も、第一種衛生管理者は45%程度、第二種衛生管理者は50%程度であり、しっかり勉強をすれば誰でも合格は可能です。ただし、一定以上の勉強時間を確保しなければ、合格は難しいでしょう。知識を丸暗記するのではなく、その理由や背景まで理解する必要があります。
衛生管理者の試験内容
第一種衛生管理者の試験では、関係法令2科目と労働衛生2科目、労働生理1科目の計5科目が問われます。試験の形式は5つの選択肢から正解を選ぶ選択問題であり、44問を3時間で解答しなければなりません。合格基準は、それぞれの試験科目ごとの得点が40%以上、かつ全科目の合計点が満点の60%以上必要です。
第二種衛生管理者の試験範囲は、関係法令と労働衛生労働生理の計3科目です。第一種衛生管理者の試験と同様に五肢択一式で、30問を3時間で解答する必要があります。合格基準は、第一種衛生管理者試験と同じです。
衛生管理者に合格するための勉強方法
衛生管理者試験に合格するためには、独学で勉強する方法と、資格取得の講座に通う方法があります。衛生管理者試験に合格するための勉強方法と、必要とされる勉強時間をご紹介します。
独学で勉強する
独学でも十分に合格できる可能性があるのが、衛生管理者の試験です。過去の試験問題はインターネットなどでもダウンロードでき、参考書も販売されています。
ただし、独学では試験のポイントがわからなかったり、勉強を続けるモチベーションを保てなかったりする場合もあるでしょう。そのような場合は、講習会やセミナーを活用するのも選択肢の1つです。労働基準協会やコンサルタント会社、資格スクールなどさまざまな団体で開催されています。
セミナーや講習会は、1~2日間で開催されるものがほとんどで、仕事をしながらでも受講が可能です。費用相場は、1万5,000円~3万円です。
資格取得の講座に通う
独学や単発のセミナーのみでは不安な場合は、民間の資格取得の講座に通ったり、通信講座を受講したりする方法もあります。わからない箇所は質問できるコースも用意されているため、独学では学習に不安がある場合は、民間の講座を検討してもよいでしょう。
必要な勉強時間
衛生管理者の試験に合格するために必要な勉強時間は、第一種衛生管理者が100時間、第二種衛生管理者が60時間といわれています。 第一種衛生管理者試験の合格までの勉強期間は、4~6ヶ月程度を見込んでおきましょう。
ただし、上記の時間はあくまでも目安です。労働安全衛生法などの勉強経験があればさらに少なくて済む可能性があります。人によって予備知識や経験は異なるため、参考程度に捉えてください。
衛生管理者を取得するメリット
衛生管理者は、難易度はそれほど高くないことに対し、常時50人以上の労働者が働く事業場では1人以上の衛生管理者の選任が必須であるため、一定の需要がある資格です。衛生管理者を取得する主なメリットは、主に以下の2つです。
転職に有利になる
衛生管理者の資格を取得していると、転職に有利になります。常時50人以上の労働者が働く事業場では、1人以上の衛生管理者を専任しなければなりません。そのため、多くの企業が衛生管理者の求人を出しており、資格を取得していることが、転職に有利に働く可能性があります。
キャリアアップに繋がる
特に人事・総務系の仕事においては、衛生管理者の資格取得がキャリアアップに繋がる場合があります。管理職昇進の条件に、衛生管理者の資格取得を掲げている企業も珍しくありません。実際、昇進に有利に働くかどうかは職種によるものの、少なからずチャンスは増えるでしょう。
衛生管理者の仕事や資格取得について理解を深めよう
衛生管理者は、労働安全衛生法という法律によって定められた国家資格です。就労中の労働災害や、労働者の健康障害を防止する役割を担います。
衛生管理者には、「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」があり、専任できる業種の範囲が異なります。資格取得によって転職に有利になるほか、特に人事・総務系の仕事において、キャリアアップに繋がる可能性があるでしょう。衛生管理者の仕事や資格取得に関する、理解を深めておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
OJTとは?意味やOFF-JTとの違い、研修のやり方や成功のコツを解説
従業員を育成するための代表的な教育手法の一つにOJTがあります。今回は、このOJTについて見ていくとともに、OJTと似たような言葉である「OFF-JT」との違いは何か、OJT研修の…
詳しくみるムーンショットの意味とは?日本政府が掲げる10目標をわかりやすく解説
ムーンショットの意味を理解し、自社の事業やイノベーション推進に活かしたいと考えていませんか? 本記事では、ムーンショットの意味や、ムーンショット目標に対して企業ができること、ビジネ…
詳しくみるインターンシップとは?意味や企業での実施方法について【報告書テンプレつき】
インターンシップとは、大学生などが在学中に企業で就業を体験することを指します。大学に求められることや就職市場が変化したことから広く実施されるようになりました。学生にとっては就活の一…
詳しくみる内定辞退のやり方 – メールだけで大丈夫?各種マナーも解説
会社から採用の内定通知をもらったのに、他社内定と重複してしまい内定辞退する場合があります。しかし、内定を断る際に、辞退する会社にどのように伝えたらよいのか、連絡方法は電話かメールか…
詳しくみる研修とは?意味や目的・種類を紹介!
企業が行う研修は、業務で必要な知識やスキルの習得を目的に、勉強会や講座などで学ぶもので、インソースで行う社内研修とアウトソースで実施する社外研修があります。本記事では研修を行う意味…
詳しくみるGABテストとは?人事が知るべき適性検査の特徴と導入メリットを解説
採用の現場で、「応募者を客観的に評価したい」「GABを導入すべきか判断材料が足りない」という悩みを抱える採用担当者は少なくありません。 適性検査を適切に理解せずに導入すると、採用の…
詳しくみる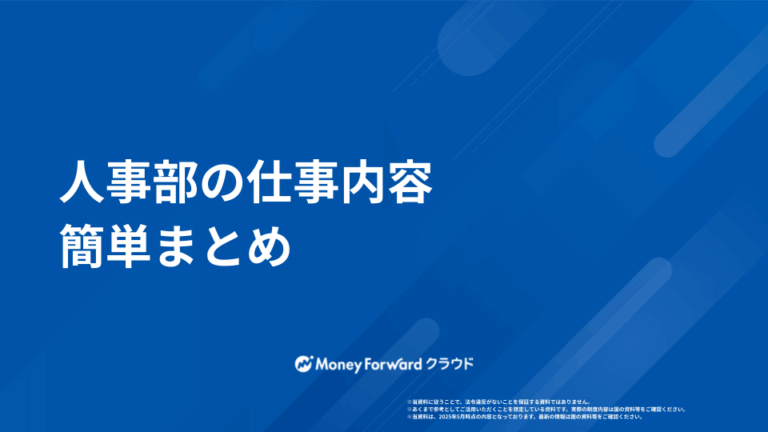


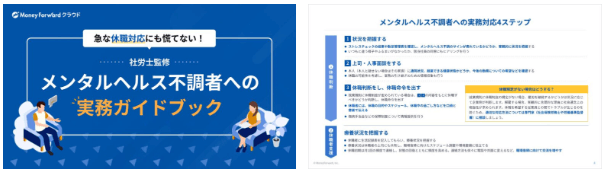
-e1763463724121.jpg)