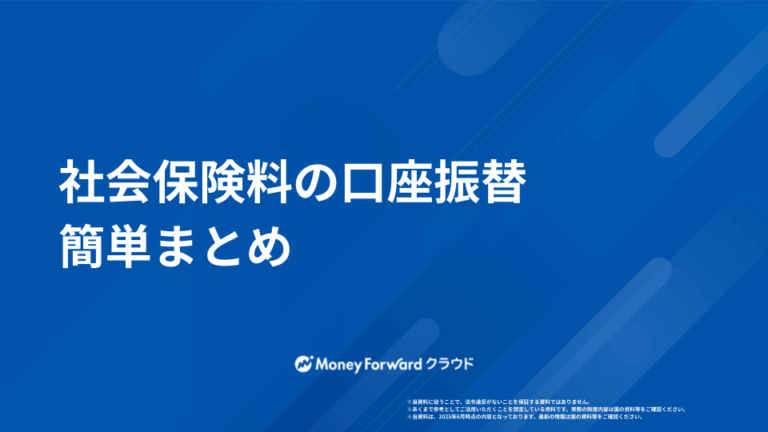- 更新日 : 2025年12月8日
社会保険は口座振替できる?手続きや提出方法を解説!
社会保険料は会社が国に保険料を納付する義務のある保険料です。皆さんの会社では、社会保険料を納付する際にどのような手続きをされているでしょうか。
今回は、社会保険料の納付の手続きについて、支払方法にはどのような種類があるか、口座振替はできるのか、口座振替ができる場合にはどのような手続きが必要かなどについて見ていきます。
目次
社会保険は口座振替できる?
社会保険の支払いにはどんな方法があるか知っていますか?支払方法として口座振替が利用できるのか、あるいは、金融機関の窓口で納付しないといけないのかなど、ここでは支払方法の手段について見ていきます。
社会保険の支払方法にはどういった手段がある?
社会保険料は以下のような方法での支払いが可能です。
口座振替で納付する
会社が取り引きしている金融機関の預金口座から社会保険料を自動的に振替して納付することができます。
金融機関の窓口で納付する
日本年金機構から毎月送られる「保険料納入告知書」に記載された社会保険料に「保険料納入告知書」を添えて納付期限までに金融機関で納付することができます。
パソコンやスマートフォンを利用したインターネットバンキング等で納付する
日本年金機構から毎月送付される「保険料納入告知書」に記載されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」の情報を使用して納付することができます。
口座振替をするメリット
社会保険料の支払方法の一つとして「口座振替で納付する」を紹介しましたが、口座振替には以下のようなメリットがあります。
- 社会保険料を納付するために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や金融機関での待ち時間がなくなる
- 納付忘れや納付遅れがなくなるため安心である
- 手数料がかからない
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
社会保険の口座振替についての手続き方法
社会保険の口座振替の手続きは、事業主が社会保険の口座振替を希望するとき、又は、現在口座振替を行っている口座を他の口座に変更したいときに事業主が申請するための手続きです。
手続きに必要な「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申込書」の記入方法などについて説明します。
申込書の入手方法について
「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申込書」は、日本年金機構のホームページあるいはお近くの年金事務所に出向いて入手してください。
参考:ケース3:健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき|日本年金機構
申出書の記入方法について
申出書の記入方法は、次の通りです。
提出者記入欄
事業主の情報を記入します。
- 事業主整理番号
- 事業所番号
上記は、新規適用時は決まっていませんので空欄のままにします。
振替事由欄
「新規」(振替口座の新規申出)の手続きか、「変更」(振替口座の変更)の手続きかを選択します。
指定預金口座欄
口座名義は年金事務所に届け出済みの所在地、名称、事業主氏名と同じものを記入します。
対象になる保険料は?
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金になります。
申込書の提出先はどこか?
記入を終えた申込書は口座振替を希望する金融機関に提出してください。金融機関が口座の照合を行った後に、日本年金機構(年金事務所)に書類が送付されます。
口座振替日はいつか?
保険料の納付期限は翌月末日です。その日が休日にあたる日は、その翌日以降の最初の営業日になります。
口座振替が可能な金融機関はどこか?
日本銀行の一般代理店、歳入代理店での口座振替手続きが可能です。
ただし、インターネット専業の銀行など、一部利用できない金融機関があります。
口座振替の手続きが終わった後の流れ
日本年金機構から会社宛に「保険料納入告知書」が届きます。
これは、下記の順番で綴られたものが送付されます。
- 領収済通知書
- 領収書控
- 納入告知書(納付書)・領収証書(領収書)
社会保険料の納付は口座振替がメリット大です
社会保険の支払方法には、口座振替を含めいろいろな方法があることを見てきました。
なかでも、口座振替を行うことによって社会保険料納付のために金融機関の窓口に行く手間や、納付忘れの防止、手数料がかからないなど、メリットが多いことも理解できたのではないでしょうか。
社会保険料の口座振替の手続きを行って、社会保険料を正確に納付していきましょう。
よくある質問
社会保険の口座振替はできますか?
社会保険料は、事業主が日本年金機構に必要な書類を提出して申請することによって、口座振替によって納付することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険の口座振替について、概要を教えてください。
社会保険の口座振替は、事業主が日本年金機構に口座振替申出書で申請することによって、会社が取り引きを行っている金融機関の預金口座から自動的に社会保険料を口座振替して納付することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
企業年金は3種類!厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の違いと特徴を解説
退職時または60歳以降に受け取ることができる給付に企業年金があります。企業年金は、3階建ての年金の3階部分(1階部分の「基礎年金」、2階部分の「被用者年金」)を担っている年金制度で…
詳しくみる厚生年金の受給に必要な加入期間 – 10年未満の場合はどうなる?
日本の公的年金制度は2段階です。会社勤めで厚生年金保険に加入していた方は、国民年金の制度で受け取れる老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金が上乗せされます。 国民年金の支給額が年間約78…
詳しくみる月末時点で育休なら社会保険料が免除?賞与の場合はどうなる?
月末が育休期間に含まれている場合、基本的には当月の社会保険料は免除になります。ただし、育休の開始日と終了日が同月にある場合は、休業期間が14日未満だと社会保険料が免除されないため注…
詳しくみる傷病手当金における申請書のもらい方 – 申請方法や条件も解説
労働者が病気やケガで働けなくなったときの生活を保障してくれる社会保障制度の一つに「傷病手当金」があります。会社から賃金を支給されなくなった場合も一定期間所得が保障されるため、安心し…
詳しくみる建設業における労災保険の特徴は?単独有期と一括有期の違いなど
事業主は、労働者を雇用すれば原則として労働保険(労災保険、雇用保険)の適用事業所として加入義務が生じ、所定の手続きを行う必要があります。 一般的な業種の手続きは共通していますが、建…
詳しくみる【図解】厚生年金とは?受給額の早見表や計算方法をわかりやすく解説
厚生年金(厚生年金保険)は、会社などに勤務している人が加入する年金です。日本の公的年金には2種類あり、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、「厚生年…
詳しくみる