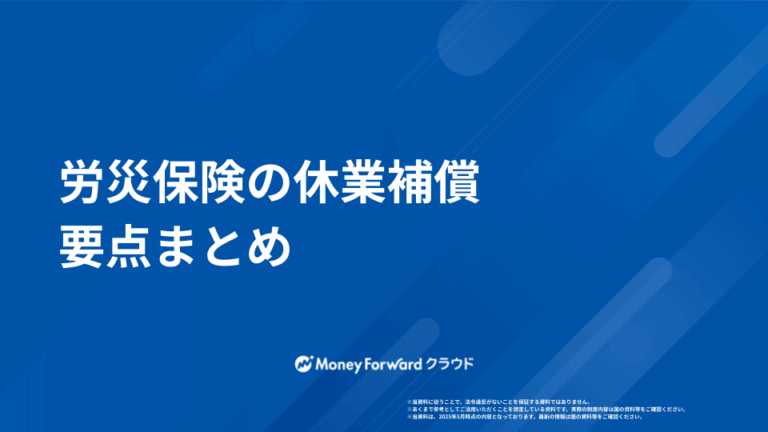- 更新日 : 2025年6月23日
労災保険の休業補償とは?金額や手続きについて解説
労災は企業にとって軽視できない問題です。企業としては職場環境の改善などで労災の発生を抑制するだけでなく、労災発生後にも適切な対応が求められます。従業員の収入を保護するためにも、労災保険の休業補償について正しく理解しなくてはなりません。そこでこの記事では、労災保険の休業補償について分かりやすく解説しました。労災保険や休業補償の概要、休業補償給付金の計算方法、申請手続きなどについてまとめたので、ぜひ参考にしてください。
目次
労災保険の休業補償とは?
労災保険の休業補償は、業務や通勤を原因とする負傷・疾病で休業が生じた場合に、所得を補償するための給付です。労働災害による負傷などの療養で4日以上休業が発生した場合、該当期間の休業補償給付および休業特別支給金を受け取れます。有給休暇を使用せずに欠勤しても給付金を受け取れるので、休業補償を活用すれば労働者は休業期間も安心して治療に専念できます。
労災保険とは
労災保険とは、業務や通勤を理由とする労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して、労働者や遺族に必要な保険給付を行う制度です。解説した休業補償による給付のほかにも療養給付や傷病年金などがあり、状況に応じてさまざまな労災保険給付が用意されています。
労災保険の費用は、原則として企業が負担する保険料でまかなわれています。原則として 一人でも労働者を使用する企業は、業種の規模を問わずに労災保険に加入しなければなりません。なお、労災保険における労働者の定義は、職業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者です。 労働者であればアルバイトやパートタイマーなどの雇用形態は関係ありません。外国人でも日本国内で働いている限り、労災保険が適用されるのです。
なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険ではなく企業が労働者に対して休業補償を行うことになっています。
参考:労災保険とは|東京労働局
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
休業補償給付の要件
休業補償を給付するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 労働者が業務上の事由による負傷または疾病によって療養していること
- 療養のために労働できないこと
- 労働できないために、賃金を受けていないこと
なお、療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病年金が支給されます。
休業補償の支給金額
それでは、休業補償の支給金額はいくらになるのでしょうか。休業補償は「休業補償給付」と「休業特別支援金」が支払われます。具体的な計算方法について見ていきましょう。
休業特別支援金
休業特別支援金は休業4日日から1日につき、給付基礎日額の20%に相当する額が支給されます。給付基礎日額は、原則として平均賃金に相当する額です。平均賃金は給付基礎日額を算定すべき事由が生じた日の前の3ヶ月間を算定期間と考えます。該当の労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の休日などを含めた総日数で割ると給付基礎日額を求められます。ただし、結婚手当など臨時の賃金やボーナスなどは算定賃金の対象外なので注意しましょう。
参考:休業(補償)等給付傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省
休業補償給付金の計算方法
休業補償給付金は、休業4日日から1日につき給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。つまり、休業補償の支給金額は休業補償給付と休業特別支給を合計したものになるため、給付基礎日額の80%が受け取れるのです。
例題として、月25万円の賃金で11月に事故が発生して怪我を負い、30日間休業したケースを考えてみましょう。まず、給付基礎日額は次の数式で求められます。
25万円×3ヶ月÷92日[8月(31日)+9月(30日)+10月(31日)]≒ 8,153円
給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。1日あたり支給される休業補償給付金と休業特別支援金もそれぞれ求めてみましょう。
休業補償給付金:8,153×60%=4,891円8銭
休業特別支援金:8,153×20%=1,630円6銭
なお、1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てて考えます。端数をそれぞれ切り捨てた金額を合算すると、休業補償の1日当たりの支給金額を以下のように求められます。
4,891円+1,630円=6,521円
続いて、30日間の休業に対する休業補償の合計支給金額は以下の式で求められます。
6,521円 ×(30日-3日)= 176,067円
休業開始後最初の3日間は待機期間のため休業補償が支給されないため注意しましょう。
休業補償を請求する申請手続き
続いて、休業補償を請求する申請手続きについて見ていきましょう。申請手続きの流れと請求書について解説します。
申請手続きの流れ
労災保険の休業補償の申請手続きの流れは以下のとおりです。
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が調査する
- 労働基準監督署から決定通知が届く
- 厚生労働省より休業補償給付金が振り込まれる
労働基準監督署から決定通知が届くまでの時期は、大体1ヶ月程度とされています。ただし、申請内容によって期間が長引く場合があるので注意しましょう。例えば、うつ病などの精神疾患のケースでは労災認定が長引く傾向があります。
参考:休業(補償)等給付傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省
請求書について
休業補償の給付には、請求書の提出が必要だとお伝えしました。請求書は業務災害と通勤災害で用紙が異なります。さらに、休業補償の請求書には別紙1・別紙2・別紙3があり、必要に応じてそれぞれ作成しなくてはなりません。それぞれの請求書の概要について見ていきましょう。
- 休業補償給付支給請求書
労災が業務中に起きた場合に提出が必要な請求書です。表面と裏面があり、労働者や負傷についての情報をまとめます。災害発生状況については、できるだけ詳細に記入しましょう。文章を読んだ方が実際の光景が浮かぶように、なるべく具体的に記載することがポイントです。 - 通休業給付支給請求書
労災が通勤中に起きた場合に提出が必要な請求書です。記載内容は前述した休業補償給付支給請求書とほとんど変わりません。請求書の裏面に、通常の通勤経路・怪我をした場所・所要時間などを、経路図や地図などを用いて分かりやすく記入しましょう。 - 別紙1
休業給付の支給額の計算に必要な、平均賃金の確認で提出が求められる書類です。 - 別紙2
所定労働時間の一部のみ休業した日がある場合にのみ、提出が求められる書面です。 - 別紙3
被災した労働者が複数の企業に雇用されている場合に限り提出する必要があります。
参考:休業(補償)等給付傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省
損害賠償は請求できる?
労災保険の休業補償によって一定の補償を受け取れます。しかし、労働者の損害のすべてが労災保険の休業補償で補償されるわけではありません。そうした不足分については、企業に対して損害賠償を求める手段も考えられます。
ただし、すべてのケースで企業に損害賠償請求できるわけではありません。企業に対して損害賠償を請求するためには、企業側に安全配慮義務違反などの賠償責任の根拠が必要なのです。安全配慮義務とは労働契約法の第5条にも定められている、企業が労働者の健康と安全に配慮する義務を指します。企業側に明らかな非がある場合に限り、損害賠償も検討してみましょう。
労災保険の休業補償はすべての労働者を守る制度
労災保険の休業補償は企業で働くすべての労働者を守る制度です。業務上の理由による病気などで働けなくなってしまった場合、休業補償を受けられます。1人でも労働者を雇っている企業は、必ず労災保険に加入しなければなりません。最近では、長時間労働などによる強いストレスで精神疾患や過労死などが労災認定されるケースも増加しています。労災の発生を削減する取り組みは重要ですが、企業は労働者の万が一の事態にも備えなければなりません。労働者の安全を守るだけでなく、怪我や病気で働けなくなった際には迅速にサポートできる体制づくりが大切です。労災保険の休業補償について正しく理解して、労働者が安心して働ける職場環境を整えましょう。
よくある質問
休業補償は誰が支給されるの?
業務上の理由による負傷や疾病による療養のため働けず賃金の支払いを受けていない労働者が対象です。アルバイトやパートタイマーなどの雇用形態は関係なく、外国人でも日本で働いていれば適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。
休業補償はいくら支給されるの?
1日あたりの平均賃金に相当する額を算出し、80%の金額が支給されます。合計の休業日数から待機期間の3日間を除外した日数に対して支払われます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
労災保険の関連記事
新着記事
働きがいのある職場とは?・特徴・メリット・つくり方を解説
Point働きがいのある職場とは? 働きがいのある職場とは、社員が仕事に誇りと成長を実感し、自律的に貢献できる環境です。 信頼・尊重・公正が職場文化に根づく 意見しやすく成長を支え…
詳しくみる就業規則を会社が守らないときはどこに相談すべき?相談先と対処法を解説
Point会社が就業規則を守らないとき、どこに相談すればいい? 就業規則を会社が守らない場合、違反内容に応じて相談先を使い分けることが最短での解決につながります。 違法性が明確なら…
詳しくみる運送業の就業規則とは?記載必須事項や業界特有の注意点を解説
Point運送業の就業規則は何を定めるべき? 運送業の就業規則は、労働時間管理や安全運行ルールなどを明記する文書です。 改善基準告示と年960時間上限を反映する 36協定と運行・車…
詳しくみる飲食店の就業規則は必要?作成義務・メリット・記載内容と注意点を解説
Point飲食店に就業規則は必要? 就業規則は、飲食店の従業員が常時10人以上いる場合に作成・届け出が義務です。 労働基準法で記載項目が定められている 届け出には労働組合または従業…
詳しくみる給与計算は誰でもできる?業務の基本・必要スキル・効率化の方法を解説
Point給与計算は誰でもできる? 給与計算は資格がなくても可能ですが、正確性と法令対応が求められる専門性の高い業務です。 ソフトで自動化すれば初心者も対応可能 法改正への継続的な…
詳しくみる給与計算の代行には資格が必要?依頼できる業務内容や費用相場を解説
Point給与計算の代行に資格は必要? 給与計算は資格がなくても代行可能ですが、業務範囲により有資格者の関与が必要です。 給与計算自体は資格不要 税務は税理士、労務手続きは社労士 …
詳しくみる