- 更新日 : 2025年12月24日
個人事業主に給与明細は必要ない?作成場面や無料テンプレートを紹介
個人事業主に対して業務を発注した場合、給与明細は必要ありません。その代わり、報酬額を証明する書面を発行します。一方で個人事業主は、従業員を雇った場合など一定の条件に該当した場合に、給与明細を発行する義務を負います。
本記事では、個人事業主に対して給与明細の代わりに発行しなければならない書類や、個人事業主が給与明細を発行すべきケースなどを網羅的に解説します。
▼個人事業主向けの給与明細のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。
目次
個人事業主に給与明細は必要ない?
個人事業主に業務を発注した場合、個人事業主に対する給与明細の発行は不要です。これは個人事業主に対して支払う対価が給与ではなく報酬であるためです。
給与とは、雇用者(事業主)が被雇用者(従業員)に対して支払うものです。しかし個人事業主と発注者のあいだには、雇用関係がありません。雇用関係のない個人事業主へ支払われるのは給与ではないため、給与明細も必要ありません。
その代わり、個人事業主に対しては報酬額の証明となる書面として、支払明細書や納品書などを発行します。
個人事業主は自分の給料をどう計上する?
個人事業主は、自分の給料を経費計上できません。なぜなら、そもそも個人事業主は雇用されていないので、給料という概念自体がないためです。個人事業主は業務の対価として、給料ではなく報酬を受け取ります。
たとえ事業用口座から個人口座へ、毎月「給与」という名目で一定額を移動していたとしても、それはあくまで個人の収入管理の方法です。個人事業主である限り、振込の頻度や金額、名目に関わらず、給与として経費計上することはできません。
自分への給料を経費として計上できるのは、個人事業主ではなく、法人を設立した場合です。雇用する従業員がいなかったとしても、法人の代表者(自分)の収入は法人から支払われた給与という扱いになり、法人の経費として計上できます。
個人事業主の給与については、以下の記事をご参照ください。
個人事業主が給与明細の代わりとして使える書類
個人事業主が給与明細の代わりとして使える書類として、以下が挙げられます。
単に所得額を証明するだけなら、所得証明書で充分です。しかし各種控除や納税額は所得証明書には記載されていないので、これらの証明が必要な場合は課税証明書や確定申告控えを用意しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与明細電子化マニュアル
こちらは「給与明細電子化マニュアル」の資料です。給与明細の電子化をご検討中、または導入を進めている企業様向けの資料となります。
情報収集や実務の参考資料として、ぜひご活用ください。
給与明細(自動計算できる計算式入り)
こちらは「給与明細(自動計算できる計算式入り)」の資料です。給与計算を自動で行うための計算式が設定されています。
日々の給与計算業務の参考資料として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
個人事業主が給与明細を作成する場面
個人事業主でも、従業員を雇っている場合は給与明細を作成し、本人に交付しなければなりません。給与明細の発行と交付は給与を支払う人の義務として定められており、怠った場合は罰則も適用されます(所得税法第231条)。
また給与の支払対象が家族である場合、給与明細発行は必須ではありませんが、発行したほうがよいでしょう。
家族に給与を支払う場合
青色申告をしている個人事業主が家族に給与を支払う場合、給与明細の発行は義務ではありません。これは、自分の事業に従事させる家族に支払う給与が青色事業専従者給与に該当し、通常の労働者と異なる方法で所得税控除が行われるためです。
しかし事業主が青色専従者給与を経費控除する際の証明となるため、給与明細は発行したほうがよいでしょう。もし税務調査を受けた場合でも、給与明細を発行していれば経費計上額の証拠となります。
白色申告でも給与明細の発行は必須ではありませんが、発行しておくことをおすすめします。白色申告では給与の金額に関わらず、一定額の事業専従者控除が適用されます。しかし控除を受けるためには、給与を支払っていることの証明が必要です。給与明細は証明として利用できるため、確定申告の際の手間がありません。
青色事業専従者の給与明細については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
従業員やアルバイトを雇用する場合
個人事業主が従業員やアルバイトを雇用する場合は、給与明細の発行が必須です。もし発行しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(所得税法第242条7号)
業務委託を頼む場合は給与明細は必要?
個人事業主が業務委託として外部に業務を委託した場合、給与明細の発行は不要です。委託元である個人事業主は、業務委託先を雇用しているわけではありません。そのため業務委託先に対して支払うのは報酬であり給与ではないため、給与明細も不要です。
給与明細の発行は不要ですが、支払明細は発行したほうがよいでしょう。支払明細は支払った報酬額や消費税を記載した書面です。支払明細の発行は法律による義務はありませんが、支払った報酬を経費計上する際に金額の証拠となります。
支払明細は業務委託先が確定申告をする際の証跡にもなるので、委託先との信頼関係を継続するためにも、発行しておくことをおすすめします。
業務委託の給与明細の詳細は、以下の記事をご参照ください。
個人事業主向けの給与明細のひな形・テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、個人事業主が青色専従者向けに発行する給与明細のテンプレートを用意しています。WordやExcelで編集できるため、専門ソフトを用意しなくても利用可能です。
個人事業主の給与明細に必要な項目や作成方法
個人事業主が発行する給与明細の項目や作成方法は、法人が発行する場合とそれほど大きな違いはありません。
また記載項目について、法令で必ず記載するよう明示されているものはありません。しかし労働者の利便性や法令主旨により、以下の項目が記載されていることが一般的です。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払年月、支払日 | 給与の対象となる期間と支払が行われた日 |
| 支給項目 | 基本給、各種手当、総支給額など |
| 控除項目 | 所得税、住民税、社会保険料など |
| 差引支給額 | 支給項目合計から控除項目合計を差し引いた額 |
| 勤怠項目 | 出勤日数、有給休暇取得日数など |
| 振込先 | 金融機関名、口座番号など |
これらの項目について、それぞれ詳しく解説します。
支払年月と支払日
支払年月と支払日(支給日)は似ている項目ですが、意味が異なります。
| 支払年月 | 給与の対象となる月。「〇年〇月分」と記載する |
|---|---|
| 支払日 | 実際に給与が支払われる日 |
例えば「月末締め翌月20日払い」の会社が2025年4月分の給与を支払う場合、支払年月は「2025年4月分」、支払日は「2025年5月20日」と記載します。銀行営業日の関係で支払日がずれる場合は、実際に支払われる日を記載しましょう。
支給項目
支給項目で記載するのは、基本給のほか、役職手当、残業手当、通勤手当等の諸手当です。いわゆる額面と呼ばれる項目です。
固定残業代を支給している場合、就業規則や雇用契約書でその金額と時間数が明示され合意がとられていれば、必ずしも個別に固定残業代や残業時間数を記載する必要はありません。ただし固定残業代として含まれている時間数以上の残業が発生した場合や、それに対する残業代が発生した場合は、支払いの証拠として別途残業代としての記載が望ましいでしょう。
給与明細の見方については、以下の記事をご参照ください。
参考:フーリッシュ事件(令和1年(ワ)第10133号)|公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
控除項目
控除項目では健康保険料、厚生年金保険料等の社会保険料や、所得税等の源泉徴収額を記載します。労働組合の組合費や持ち株制度の拠出金など、いわゆる給与天引きされるものはすべて記載しましょう。
社会保険料や国税の源泉徴収は、健康保険法、厚生年金保険法など各法によって本人に控除額を知らせることが義務付けられています。必ずしも給与明細に記載しなければならないわけではありませんが、給与明細に記載したほうが差引支給額もわかりやすいでしょう。
差引支給額
差引支給額はいわゆる手取りと呼ばれる金額です。支給項目の合計金額から控除項目の合計額を差し引いて計算します。
勤怠項目
勤怠項目では、勤務日数や有給休暇の取得日数などを記載します。
記載項目の例
- 勤務日数、勤務時間数
- 欠勤日数
- 有給休暇取得日数
- 時間外労働時間 など
アルバイトやパートなど、時給制で給与を支払っている場合は勤務時間を記載するとよいでしょう。また時間外労働時間については、休日出勤や深夜労働時間、法定内残業など細かく分けて記載する場合もあります。
振込先
給与明細に振込先を記載しておくことで、従業員は正しく振り込みがされているかを確認しやすくなります。また支払う側も、金額が違うなどの問い合わせを受けた際に対応しやすいでしょう。
個人事業主の給与明細の作成、取り扱い時の注意点
給与明細は個人情報を含む書面であり、給与という労働者にとって重要な証明書でもあるため、作成や取り扱いには注意が必要です。個人事業主に限らず、すべての給与明細発行者が注意すべきポイントも踏まえて解説します。
給与明細は雇用形態を問わず交付する
給与明細発行の義務は従業員を雇う場合に生じますが、対象になるのは正社員だけではありません。パートやアルバイトなど、雇用形態を問わず、雇用契約を交わしたすべての従業員に対して給与明細を発行し、交付しなければなりません。
プライバシー保護に注意する
給与明細には氏名や収入など個人情報が記載されています。そのため誤って本人以外の従業員の目に触れたり、紛失してしまったりしないように注意しましょう。
給与明細からの情報漏洩を防止する方法の例
- 給与振込先は下4桁のみを表示する
- 住所や電話番号など不要な情報を記載しない
- 本人に手渡しする
- 専用システムを利用して本人以外が閲覧できないようにする
専用システムの利用はプライバシー保護だけでなく、従業員の利便性や給与明細交付にかかる業務の効率化にもつながります。過去のデータも保存されるため、紙での発行や過去のデータの確認が必要になった場合でもすぐに対応可能です。
ペーパーレスには同意が必要
プライバシー保護や業務効率化の観点から、給与明細の交付に労務管理システムやメールを利用するケースも増えています。しかし給与明細をペーパーレスで交付するためには、あらかじめ従業員の同意が必要です(所得税法第231条第2項)。
同意書の形態は特に決まっていません。専用システムで交付する場合は、システムログイン時に同意書を表示してペーパーレス発行への同意をとりつけることもできます。
なお、給与明細の電子化については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:所得税法|e-gov
給与明細は5年間保管する
給与明細を発行したら、5年間は発行側でも控えを保管しておきましょう。給与明細には、発行義務はあっても保管義務はありません。しかし以下のような理由により、発行後の保管が推奨されます。
給与明細の保管が推奨されている理由
- 従業員からの再発行依頼に対応しやすくするため
- 未払賃金の請求があったときに支払いの証拠とするため
発行元は給与明細の再発行依頼に応じる義務はありません。しかし再発行しないことで従業員の不便や不信につながるので、特段の事情がなければ再発行に応じたほうがよいでしょう。
また未払賃金の請求には、原則5年の期限が設けられています(労働基準法第115条)。そのため5年間保管しておけば、もし未払賃金を請求されたとしても給与明細を証拠として対応が可能です。
給与明細はデータで保管すると場所も取らず、検索や管理も効率的です。専用のシステムを利用すれば、データの紛失や漏洩防止にもつながります。
参考:未払賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
計算ミスや振り込みミスに注意する
計算ミスや振込ミスがあると再手続きが必要になり、組戻手数料など追加費用も発生します。なにより従業員からの不信感にもつながるため、チェック体制を強化するなどミスが起こらないよう十分に注意しましょう。
ミスの防止におすすめなのが、専用システムの導入です。人の手で計算するよりミスが少なく、また振込先を毎回手入力する必要もありません。金融機関へのオンライン入金に対応しているシステムであれば振込ミスも防止でき、業務効率化につながります。
給与明細の発行が遅れるとき
なんらかの事情で給与明細の発行が遅れる場合は、遅延が確定した時点で従業員に説明を行いましょう。同意や了承をとる必要はありません。
給与明細の発行のタイミングは、所得税法施行規則において「支払いの際」と定められています(所得税法施行規則第100条)。遅延しても罰則はありませんが、発行を怠ると所得税法により罰せられます(所得税法242条7号)
参考:所得税法|e-Gov 法令検索
参考:所得税法施行規則|e-Gov 法令検索
給与明細を手書きするとき
給与明細を手書きで発行しても、法的には問題ありません。手書きで作成する場合は、会社の控えと本人に渡すための2部を作成します。その際、転記ミスを防ぐために複写式の用紙を利用するか、本人へ渡すものを作成してコピーを取るとよいでしょう。
人の手作業は効率が悪く、ミスも起こりやすくなります。また従業員や担当者による数字の書き換えや偽造を防げないため、トラブルの温床にもなりかねません。従業員が少ない場合でも、電子化を検討することをおすすめします。
個人事業主の給与明細にミスがあったらどうする?
給与明細にミスが起こる場合、給与計算に誤りがあるのか、給与計算は合っているがその後の処理に問題があったのかで対応は異なります。
また原因や内容を問わず、給与明細に関するミスは従業員の不信感を招きます。素早く正確な修正対応を行うとともに、従業員に誠実に説明し再発防止策を徹底するようにしましょう。
給与計算に誤りがあった場合
給与計算に誤りがあった場合は、速やかに計算しなおして、正しい金額で明細を発行しなおします。総支給額や差引支給額だけでなく社会保険料や税金の控除額も変わる可能性があるので、すべての項目の見直しが必要です。
さらに誤った金額での振込が完了していた場合は、以下の手続きが必要です。
- (不足がある場合)差額分の支払い
- (過大に支払った場合)返金もしくは翌月給与との相殺
支払った額に不足があった場合は、すぐに差額分を支払いましょう。翌月の給与で振り込めばよいと考える人もいるかもしれませんが、労働基準法に規定されている給与の全額払いの原則に抵触する可能性があります(労働基準法第24条第1項)。
逆に本来の給与より過大な金額を支払っていた場合は、差額分を変換してもらわなければなりません。直接本人から返金してもらうよりも、翌月の給与を減額して支払う方法が一般的です。これを調整的相殺と言います。ただし調整的相殺は金額が少額であることなど一定の条件でのみ認められています。金額が大きい場合は分割で精算しましょう。
また社会保険料の徴収額にも変更があった場合は、差額納付や返金、相殺の手続きが必要です。
給与計算は合っているが記載内容にミスがあった
給与計算は合っているが給与明細に記載された金額が違っていた、など、給与明細の記載内容にミスがあった場合、すぐに修正したものを発行、交付します。給与明細の虚偽記載は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(所得税法242条7号)。
給与計算は合っていたが明細の記載と違う金額で振り込んでしまった
給与計算は合っていても振込額が間違っていたという場合は、正しい給与額に合わせて不足分を支払うか、従業員から過剰振込分を返金してもらいます。
もし過剰振込分を現金で返金してもらう場合は、差額分を仮払金として借方に仕訳をします。返金が完了したら、仮払金を消し込みましょう。
違う振込先に振り込んでしまった
振込先に誤りがあった場合は、組み戻し手続きを行います。組戻手続きは、振込元である会社が金融機関に依頼します。従業員に手続きをお願いすることはありませんが、正しい振込先への振り込みが遅れることを従業員に説明しましょう。
個人事業主の給与明細を効率よく作成する方法
個人事業主の給与明細を効率よく作成するには、会計ソフトが便利です。入力すべき項目がわかりやすくまとめられているので、入力もれや項目の間違いを防げます。残業代や控除額が自動で計算されるので、計算ミスの心配もありません。また過去の給与明細データも保管できるので、従業員から再発行依頼があったときにも手間なく対応できるでしょう。
会計ソフトを選ぶ際には、以下の点に注意して選びましょう。
- 社会保険料率や税制の改正の際に更新されるか
- 確定申告の帳票作成や電子申告に対応しているか
- 自分の使っているパソコンのOSやスマホに対応しているか
- クラウド型か
- カスタマーサポートの時間や受付方法は使いやすいか
社会保険料や税制の改正は頻繁に行われており、特に社会保険料率は原則として毎年更新されます。自動更新機能があれば、更新し忘れによる計算ミスを防ぎ、また入力の手間も省けます。
個人事業主の場合は、確定申告に対応しているかどうかも是非チェックしましょう。従業員への給与支払は経費として算入できます。確定申告機能の対応があれば、会計科目として別途入力する必要がなく、給与明細の作成と合わせて会計書類にも反映されます。
個人事業主に対する給与明細の発行は不要
個人事業主は雇用されているわけではなく給与の概念がないため、個人事業主へ業務を発注した場合でも給与明細の発行は不要です。いっぽうで、個人事業主でも従業員を雇った場合は、法律により給与明細の発行義務が生じます。同居の親族や、パート、アルバイトであっても発行しましょう。
給与明細を発行する際には、会計ソフトの利用がおすすめです。ミスのない発行手続きと管理の効率化につながるので、まずは無料試用期間のあるソフトで導入を検討してみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所得税が非課税になるケース – 非課税所得も解説
所得税は、納税義務のある人のすべての所得に対して課税されます。しかし、所得の中には、所得税を課さないとする「非課税所得」と定められているものもあります。 ここでは、非課税所得とはど…
詳しくみる退職月の給与計算ルールを分かりやすく解説!
退職月の給与計算は、通常の給与計算とは異なる点が多く、特に日割り計算や社会保険料・税金の控除が複雑になります。 退職月の給与計算は、代表的な要素としては以下で構成されます。 基本給…
詳しくみる現物給与とは?具体例や価額、課税の有無について分かりやすく解説!
現物給与にはどのようなものがあり、その価額がどのように決められているのかをご存知でしょうか。一般的には社員の給料は現金で支払いますが、食事、通勤定期券、住宅の提供など、現金以外のも…
詳しくみる所得税は扶養人数でいくら変わる?年齢による違いや給与計算の注意点
家族を扶養する従業員は、その人数に応じて源泉所得税が減額されます。そのため、給与計算においては、所得税と扶養人数の関係を理解することが欠かせません。当記事では、所得税と扶養人数の関…
詳しくみる【図解】住民税決定通知書とは?入手方法や見方、再発行について解説
地方税である住民税では、自治体から毎年5〜6月頃に「住民税決定通知書」が交付されます。普通徴収は納税者の自宅宛に、特別徴収は納税者が勤める会社宛に、納付書と合わせて送付されます。 …
詳しくみる熊本県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
熊本県内で事業を運営する企業にとって、給与計算は日々の業務の中でも特に重要な位置を占めます。しかし、正確な計算と法令遵守を維持するのは容易ではなく、特に中小企業では人的リソースの制…
詳しくみる
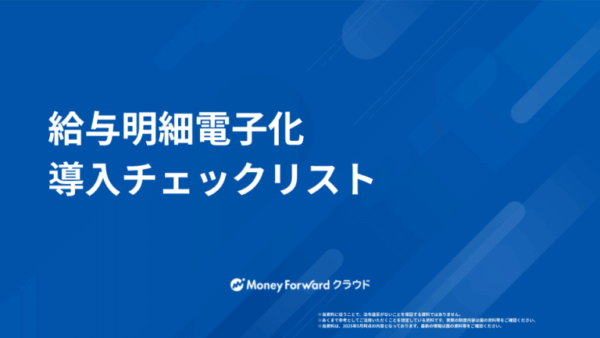
.png)

