- 更新日 : 2026年1月8日
特定退職金共済制度とは?中退共との違いやメリット・デメリットを徹底解説【退職金規定テンプレ付】
特定退職金共済制度(特退共)は、国の認可を受けた商工会議所などが運営する、信頼性の高い退職金制度です。事業主が毎月掛金を支払うことで、従業員の退職金を計画的に準備できます。
本記事では、特定退職金共済制度の仕組みやメリット・デメリット、混同されやすい類似制度との違いについて、わかりやすく解説します。退職金の計算方法や請求手続き、確定申告の要否まで詳しく説明しますので、 特定退職金共済制度の導入を検討している事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
特定退職金共済制度(特退共)とは
特定退職金共済制度(特退共)とは、事業主が掛金を負担し、従業員の退職金を計画的に準備できる国の認可を受けた制度です。所得税法施行令第73条で定められた「特定退職金共済団体」が運営しており、社外で積み立てるため、企業の経営状況に左右されずに退職金を確実に保全・管理できます。
制度の仕組み
特定退職金共済制度(特退共)は、事業主が毎月納付する掛金を原資とし、従業員の退職時に共済団体から直接退職金が支払われる、社外積立型の制度です。
具体的な流れは以下の通りです。
- 契約締結
事業主が商工会議所などの共済団体に申し込み、従業員の同意を得て退職金共済契約を締結します。 - 掛金の納付
契約後、事業主は毎月、口座振替で掛金を納付します。 - 運用
共済団体は、集めた掛金から事務経費を差し引いた額を、定期預金や証券投資信託などで運用します。 - 退職金の支払い
従業員が退職した際、事業主が団体へ必要書類を提出すると、団体から従業員の口座へ直接退職金が支払われます。
この仕組みにより、企業は退職金を計画的に準備でき、従業員は安定して退職金を受け取ることが可能です。
運営母体
特定退職金共済制度(特退共)の運営母体は、所得税法施行令第73条に基づき、税務署長の認可を受けた「特定退職金共済団体」です。 具体的には、以下のような退職金共済事業を主目的とする団体が挙げられます。
- 商工会議所
- 商工会
- 商工会連合会
- 都道府県中小企業団体中央会
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 市町村(特別区を含む)など
なお、制度の具体的な内容は運営する団体によって異なる場合があるため、加入前に確認が必要です。
契約できる事業主
特定退職金共済制度(特退共)の契約対象は、商工会議所の地区内に事業所を持つ事業主です。 従業員数や企業規模に関する制限はなく、中小企業から大企業まで幅広く利用できます。 事業主が従業員の同意を得て加入手続きを進めることで、従業員の退職金を計画的に準備できるため、労使双方にとって安心できる退職金制度といえるでしょう。
加入できる従業員
原則として、満15歳以上、満70歳未満の全従業員が加入対象です。
ただし、以下の従業員は加入対象となりません。
- 個人事業主および個人事業主と生計を同じくする親族
- 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
- 他の特定退職金共済団体の加入者
また、パートタイマーや休職者など、下記の従業員は必ずしも加入させる必要はありません。
- 特定の期間だけ雇われている人
- 使用期間中の人
- 休職期間中の人
- 季節的な仕事で雇われている人
- 非常勤の人
掛金
特定退職金共済制度(特退共)の掛金は、従業員1人あたり月額1,000円から30,000円の範囲で、事業主が任意に設定できます。掛金は1,000円単位(1口)で設定するのが一般的で、全額を事業主が負担します。
この掛金は、全額を損金または必要経費として計上できるため、課税対象所得を抑える高い節税効果が期待できます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
特定退職金共済制度の特徴
特定退職金共済制度は、企業と従業員の双方にメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
特定退職金共済制度のメリット
- 簡単な導入と管理
加入手続きは商工会議所などで簡単に行え、掛金の積立や運用は外部機関が代行してくれるため、管理負担が少ないのが大きなメリットです。 - 幅広い企業が対象
従業員数に制限がなく、商工会議所の地区内であれば中小企業から大企業まで規模を問わず契約が可能です。 - 掛金を上回る退職金の可能性
運用益や国の補助(※団体による)が加算される場合があり、特に長期間加入している従業員は、支払った掛金総額を上回る退職金を受け取れる可能性があります。 - 税制上の優遇
事業主が支払う掛金は、全額を損金または必要経費に算入できます。
特定退職金共済制度のデメリット
- 役員は加入不可
この制度は従業員を対象としているため、取締役や監査役といった会社法上の役員は加入できません。 - 掛金の減額が困難
一度設定した掛金を減額するには、全従業員の同意を得た上で、「事業継続が困難である」と共済団体に認められる必要があり、手続きが非常に複雑です。 - 元本割れのリスク
加入期間が短い従業員が早期に退職した場合、運用期間の短さから、受け取れる退職金が支払った掛金総額を下回る「元本割れ」が発生する可能性があります。
特定退職金共済制度がおすすめの企業
特退共は、特に以下のようなニーズを持つ企業におすすめです。
- 節税効果を求める企業
掛金が全額損金または必要経費として計上できるため、高い節税効果を求める企業に適しています。 - 長期雇用を促進したい企業
安定した退職金制度を設けることは、従業員の定着率向上につながります。 特に、年金形式での受け取りも可能なため、長期的なライフプランを支援できます。 - 従業員の退職金を確実に管理したい企業
社外積立型であるため、企業の経営状況に左右されずに退職金を確実に保全・管理したい企業に最適です。
特定退職金共済制度と似た制度の違い
特定退職金共済制度に類似した制度として、「中小企業退職金共済(中退共)」や「特定業種退職金共済(建退共など)」といった制度があり、違いを理解しておくことが重要です。
| 制度名 | 特定退職金共済制度(特退共) | 中小企業退職金共済(中退共) | 特定業種退職金共済(建退共など) |
|---|---|---|---|
| 運営母体 | 商工会議所など(国の認可を受けた団体) | 国(独立行政法人) | 厚生労働大臣が指定した業種ごとの団体 |
| 対象企業 | 業種・規模を問わず幅広い企業 | 中小企業基本法に定める中小企業 | 建設業、林業、清酒製造業など特定の業種 |
| 請求手続き | 事業主が団体へ請求 | 退職者本人が機構へ請求 | 事業主が団体へ請求 |
| 掛金の仕組み | 月額固定 | 月額固定 | 働いた日数に応じて納付 |
| 重複加入 | 中退共との重複は可能 | 特退共との重複は可能 | 他制度との関係は各共済による |
中小企業退職金共済制度(中退共)との違い
中小企業退職金共済制度(中退共)との最も大きな違いは、運営母体です。
特定退職金共済制度は、地域の商工会議所などが運営していますが 、中小企業退職金共済制度(中退共)は、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」という国の機関が直接運営しています。
中小企業退職金共済制度(中退共)では、企業が勤労者退職金共済機構と直接契約を結び、掛金を納付します。 従業員が退職した際は、事業主ではなく従業員本人が直接機構へ請求手続きを行い、退職金を受け取る点も異なります。
特定業種退職金共済(建退共など)との違い
特定業種退職金共済(建退共など)との最も大きな違いは、対象業種です。
特定退職金共済制度が、商工会議所の地区内であれば業種を問わず幅広い中小企業を対象としているのに対し 、特定業種退職金共済は、厚生労働大臣が指定した特定の業種(建設業、林業、清酒製造業)で働く従業員を対象としています。 代表的なものに建設業の「建設業退職金共済制度(建退共)」があります。
また、掛金の仕組みも異なり、特退共が月額固定の掛金を納付するのに対し、建退共などでは働いた日数に応じて掛金を納付し、その業界を離れる際に退職金が支給される仕組みです。
参考:特定業種退職金共済(特退共)制度について|厚生労働省、建設業退職金共済制度(建退共制度)|厚生労働省
特定退職金共済制度の退職金はいつもらえる?
退職金は、従業員の退職後、事業主による請求手続きが完了してから約1ヶ月程度で、共済団体から従業員の指定口座へ直接支払われます。
退職一時金の計算方法
退職一時金の額は、毎月の「掛金口数(月額)」と「加入期間」に応じて、各共済団体が定める支給額表に基づいて計算されます。そのため、勤続年数が長く、掛金月額が高いほど、受け取れる退職金額は多くなります。
退職金の受け取り方法
受け取り方法は、原則として「退職一時金」として一括で支払われます。ただし、共済団体の規約によっては、加入期間が10年以上などの一定の要件を満たす従業員が希望した場合、「年金形式」で10年間にわたり分割して受け取ることも可能です。
請求手続きの流れ
- 書類の請求
従業員の退職後、事業主が契約している共済団体(商工会議所など)に連絡し、退職金請求に必要な書類を取り寄せます。 - 書類の作成・提出
事業主と退職する従業員が「退職金(一時金)請求書」などの必要書類に記入・捺印し、共済団体へ提出します。 - 退職金の支払い
書類に不備がなければ、共済団体から退職者の指定口座へ退職金が振り込まれます。
必要書類と請求書の書き方
主な必要書類と請求書の書き方のポイントは以下の通りです。
請求書の書き方で不明な点があれば、契約している商工会議所などの共済団体に問い合わせることで、スムーズに手続きを進められます。
退職金規程の無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、退職金規程の無料テンプレートをご用意しております。
無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
特定退職金共済制度の退職金の確定申告は必要?
特退共から受け取る退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要です。
特退共から支払われる退職金は税法上「退職所得」として扱われ、給与所得など他の所得とは分けて課税されます。退職所得には勤続年数に応じた「退職所得控除」という大きな控除が適用されるため、税負担が大幅に軽減されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を事業主経由で共済団体に提出していれば、受け取る際に適切な所得税が源泉徴収されるため、原則として退職者本人が確定申告を行う必要はありません。ただし、この申告書を提出しなかった場合は、自身で確定申告を行い、納税または還付の手続きをする必要があります。
特定退職金共済制度に関するよくある質問
最後に、特定退職金共済制度に関するよくある質問とその回答をまとめました。
中小企業退職金共済(中退共)と重複して加入できますか?
はい、重複して加入できます。
特退共と中退共は別の制度であるため、重複加入が認められています。 これにより、従業員の役職や勤続年数に応じて制度を使い分けるなど、より手厚い福利厚生を設計することが可能です。 ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできないため注意が必要です。
中小企業が増資した場合、中退共から特退共に移行できますか?
はい、一定の要件を満たせば移行可能です。
増資・増員などにより企業規模が拡大し、中退共の加入資格(中小企業の範囲)を超えてしまった場合でも、特退共へ積立資産を引き継いで移行ができます。 移行手続きには、まず特退共の加入資格を確認し、従業員の同意を得る必要があります。 また、特退共への加入前に中退共を脱退する必要があるため、「中小企業者でなくなったことの届の提出などが求められます。
従業員が退職金を受け取る前に死亡した場合はどうなりますか?
ご遺族が「遺族一時金」として受け取れます。
従業員が在職中に死亡した場合は、ご遺族が死亡退職金(遺族一時金)を受け取ることが一般的です。請求手続きには、死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本など)が別途必要となります。詳細は加入している共済団体の規約をご確認ください。
必要に応じて特定退職金共済制度に加入しよう
特定退職金共済制度(特退共)は、商工会議所などが国の認可を受けて実施する、信頼性の高い退職金制度です。 事業主は、この制度と退職金共済契約を結び、毎月掛金を納めることで、従業員が退職する際に安定した退職給付金を準備できます。
導入が簡単で管理の手間が少なく、税制上のメリットも大きい一方で、役員が加入できない、掛金の減額が難しい、短期退職では元本割れの可能性があるなどの注意点もあります。
本記事で解説した制度の概要やメリット・デメリットを十分に理解した上で、自社の状況に合った退職金制度として活用を検討してみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【チェック付】2026年(令和8年)給与計算のやり方とは?変更点やポイントを解説
給与計算の流れは、【①総支給額を計算→②控除額を計算→③差引総支給額を計算】という3段階で進めます。 2026年(令和8年)1月より、税制改正に伴い、控除する税額の算出に使う表や、…
詳しくみる個人住民税の特別徴収とは?
個人住民税の徴収方法として、「普通徴収」と「特別徴収」があります。 このうち、特別徴収は納税者以外の者が納税者から税額を徴収し、納税義務者の代わりに納める、いわゆる「給与天引き」に…
詳しくみる就業規則の退職金規定のポイントは?支給条件から計算方法、トラブル対処法まで解説
退職金は、長年勤続した従業員にとって将来の生活を支える大切な資金であり、企業にとっては従業員のモチベーションや定着率に関わる重要な人事制度の一つです。しかし、「自分の退職金はどうな…
詳しくみる賃金締切日(給料の締め日)とは?支払日との違いや変更する際のポイントを解説
賃金締切日は、給料を計算する該当期間の最終日を指します。企業によって自由に決められますが、労働基準法によるルールも存在しており、日にちを変更したい場合はどのように設定するべきか迷う…
詳しくみるマイナンバー制度で「住民税のごまかし」が効かなくなる!
マイナンバー制度が導入されると住民税額を計算する際の行政上の手続きが一段とスマートになります。今回はそもそも住民税額はどのように決められているのかというところから、「住民税のごまか…
詳しくみる住民税非課税世帯とは? 対象世帯への臨時特別給付金も解説
住民税非課税世帯とは、所得が一定以下で住民税の「所得割」と「均等割」の両方が非課税となる世帯です。住民税非課税世帯に該当すると、優遇措置を受けられますが、事前に自分が非課税に当たる…
詳しくみる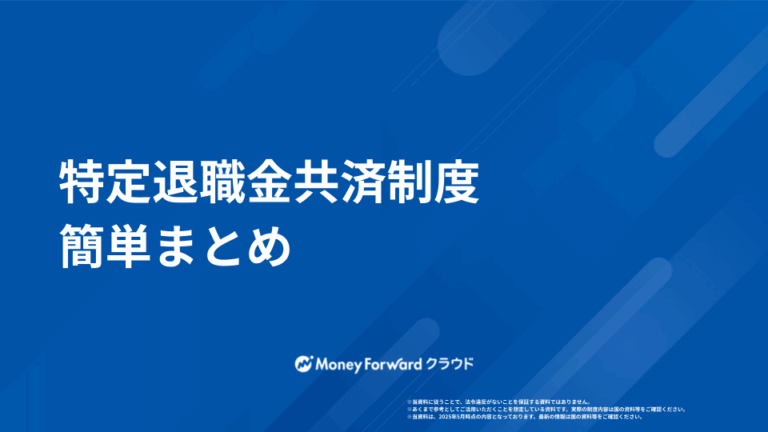

-e1762740828456.png)

