- 更新日 : 2025年11月19日
深夜業従事者向けの健康診断は年2回必要?実施基準や義務を解説
深夜業は生活リズムが乱れやすく、健康リスクが高まる恐れがあるため、年2回の健康診断が義務付けられています。本記事では、深夜業従事者に該当する人の基準や必要な検査項目について解説します。
目次
深夜業の健康診断は年2回が必要
深夜業は、一般的な勤務に比べて体への負担が大きいため、定期的な健康診断が必要です。労働安全衛生法では、事業者は深夜業従事者に対し、6ヶ月ごとに1回の健康診断を受けさせることを義務付けています。
本章では、年2回の健康診断を受ける必要がある従業員や、その理由について解説します。
対象となる「深夜業」の基準
深夜業とは、22時から翌朝5時までの時間帯に行われる労働を指します。この時間帯の勤務は生活リズムを崩しやすく、通常の勤務に比べて健康への影響が大きいため、健康管理に注意が必要です。短時間の労働であっても、この時間帯に勤務する場合は深夜業に該当します。
たとえば、22時30分までの勤務では深夜業の時間は30分間ですが、基準を満たしている場合、年2回の健康診断が必要な深夜業従事者となります。
参考:深夜労働とは?割増率や給与の計算方法、深夜労働が禁止される労働者について解説
深夜業が健康に与える影響
深夜業に従事すると体内リズムが乱れ、健康リスクが高まる恐れがあります。主な健康被害には以下のようなものがあります。
- 肥満
- 高血圧症
- 耐糖能障害
- 脂質異常
- メタボリックシンドローム
健康リスクを軽減するには、深夜業従事者は年2回の健康診断を受け、問題を早期に発見することが大切です。また、交替勤務を伴う場合は、さらに健康への影響が大きくなるため注意しましょう。
年2回実施が必要な従業員の判断基準
労働安全衛生法では、深夜業を含む業務に従事する人は、年2回の健康診断を受けることが必要とされています。深夜業を含む業務とは、「過去6ヶ月の平均で、月4回以上深夜業を行っている」場合を指します。
たとえば、23時まで残業をした場合、それが過去6ヶ月間で平均して月に4回以上行っている場合は年2回の健康診断が必要です。繁忙期のみ深夜業を行う場合も、基準を満たせば対象になります。
日々の勤務状況を記録し、該当者を正確に把握することが大切です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック
入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。
本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。
健康診断のご案内(ワード)
従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。
社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。
深夜業従事者の健康診断で実施される検査項目
本章では、深夜業従事者が健康診断で受けるべき検査項目について解説します。
深夜業従事者の健康診断で必須となる検査項目
深夜業従事者の健康診断で行う基本項目は一般定期健康診断と同様です。労働安全衛生法で定められた検査項目は次のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長※、体重、腹囲※、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査※及び喀痰(かくたん)検査※
- 血圧の測定
- 貧血検査※
- 肝機能検査※
- 血中脂質検査※
- 血糖検査※
- 尿検査
- 心電図検査※
なお「※」の付いた項目については、厚生労働大臣が定める基準該当者及び医師が不要であると判断した場合は、検査を省略できます。
深夜業従事者が追加で検査したほうがよい項目
深夜業は、生活リズムの乱れからさまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。法定の健康診断項目に加えて、自分の体調や気になる症状に合わせたオプション検査を受けましょう。
追加できる検査項目は医療機関によって異なりますが、主に以下のようなオプション検査があります。
- 脳検査
- 眼検査
- 循環器検査
- 動脈硬化検査
- 肺検査
- 腹部検査
- 大腸検査
- 骨密度検査
- 甲状腺検査
- 睡眠時無呼吸検査
- がん検査
定期的な健康チェックと早期発見・早期治療が、健康管理の基本となります。
健康診断実施における事業者の義務
事業者は、深夜に働く従業員の健康を守るため、法律に従い健康診断を実施する義務があります。
本章では、事業者が実施するべき業務を解説します。
深夜業従事者の健康診断にかかる料金の負担
健康診断にかかる費用は、事業者が負担することが法律で定められています。健康診断の実施は義務であり、従業員に費用を負担させることはできません。
ただし、法律で定められた診断項目以外のオプション検査については、従業員が自己負担で受けることも可能です。
結果を従業員に通知
健康診断の結果は、事業者が従業員に通知する義務があります。
健康診断の目的は、病気の早期発見や予防です。結果が適切に伝えられなければ、従業員が体調の変化に気づく機会を逃してしまう可能性があります。
異常がある場合でもない場合でも、速やかに従業員に通知しましょう。
健康診断個人票の作成・保管
事業者は「労働安全衛生法第66条の3」に基づき、健康診断の結果を記録した健康診断個人票を作成し、5年間保存する義務があります。
健康診断個人票には、検査結果のほかに「医師の意見聴取」が必要です。事業者が医師の意見を参考にし、必要な措置を実施することも健康診断実施の目的のひとつとなります。
健康診断個人票は、厚生労働省のホームページなどからダウンロード可能です。また、医療機関によっては、結果をそのまま個人票として使える場合もあります。
労働基準監督署への報告
事業所に常時50人以上の従業員がいる場合、健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出する義務があります。健康診断結果報告書には、診断を受けた従業員の健康状態や必要な措置について記載しなければなりません。
健康診断結果報告書の提出によって、労働基準監督署は職場の健康管理状況を把握し、必要に応じて改善指導を行います。多くの従業員に共通した健康リスクが見つかった際には、勤務体制の見直しや職場環境の改善が求められる場合もあります。
また、2025年1月からは、健康診断結果報告書の申請が原則として電子申請の義務化となりました。手続きは、厚生労働省の専用サイトで行えます。
参考:
働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
雇用・労働 | 労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください
健康診断で異常所見が認められた場合の対処法
健康診断で異常所見が認められた場合、事業者には従業員の健康を守るために適切な対応を行う義務があります。
本章では、従業員に異常所見が認められた場合の対処法について解説します。
産業医から意見聴取
異常所見がある場合、事業者はまず産業医から意見を聴取します。
健康診断の結果を基に、就業措置について検討しましょう。また、従業員の健康状態を評価し、必要に応じて追加の検査や生活習慣の改善を勧めることもあります。産業医の意見を参考にすることで、従業員の健康を守るための適切な対応を進められます。
従業員に再検査の受診を推奨
異常所見が認められた場合、事業者は従業員に再検査の受診を促します。
健康診断で異常が見つかっても、一度の検査だけでは正確な判断が難しいことがあります。重大な疾患の早期発見に再検査は欠かせません。
ただし、事業者には再検査を強制する権限がないため、従業員に対して丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。
従業員と面談
健康診断の結果を基に、就業措置について従業員と直接話し合う機会を設けます。検査結果を丁寧に伝え、不安を和らげることが大切です。
また、健康状態や業務に対する本人の希望を確認し、必要に応じて働き方を調整することも有効です。面談を通じて、従業員が安心して働ける職場環境を整えましょう。
産業医・保健師による保健指導を実施
健康診断の結果によっては、産業医や保健師による保健指導が必要になります。
保健指導は、生活習慣の改善や業務負担の軽減が目的です。食事の取り方や運動習慣、睡眠時間の確保などを提案し、従業員の健康管理をサポートしましょう。また、健康リスクが高いと判断された場合には、医療機関での治療を勧めることもあります。
就業措置を決定
健康状態によっては働き方を調整する必要があります。事業者は、健康診断の結果や産業医の意見を基に、従業員と相談して就業措置を決定しましょう。
就業措置には、業務の軽減や深夜業の回数減少、場合によっては一時的な休業などがあります。健康状態を考慮しながら、適切な就業措置を講じてください。
深夜業従事者に年2回の健康診断を実施しない場合の罰則
深夜業従事者に対して年2回の健康診断を実施しないことは、労働安全衛生法違反となります。違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。事業者の義務は従業員が健康診断を受けることを拒否した場合でも免除されません。事業者は従業員に健康診断の重要性を説明し、受診を促しましょう。
また、事業者には従業員が健康診断を受けやすい環境を整える責任があります。たとえば、勤務時間内での受診を可能にしたり、健康診断の日程を複数設定したりするなどの配慮が必要です。
深夜業従事者の健康を守るため、法律で定められた健康診断は必ず実施しましょう。
深夜業健康診断に関するよくある質問
深夜業に従事する人が受ける健康診断について、よくある質問とその回答を解説します。
夜勤時間が短くても健康診断は年2回必要?
深夜業にあたる時間の業務が1時間でも、条件を満たせば健康診断が必要です。
たとえば、残業で午後11時までの勤務になり、深夜時間帯に1時間だけ働いている場合、それが週1回以上または月4回以上行われるなら健康診断は年2回受ける義務があります。
勤務時間の長さは関係ないため、深夜業務に該当するか確認しましょう。
年の途中から深夜業を開始した場合は?
年の途中で深夜業務をはじめた場合でも、配置換えの際と6ヶ月以内ごとに1回健康診断を受ける必要があります。
たとえば、4月から深夜業務をはじめた従業員は、「配置換えの際」と「その年の10月まで」に健康診断が必要です。そのため、深夜業をはじめた時期によっては、次回の定期健診を待たずに受診しなければならない場合もあります。
深夜業事業者を雇用する際には、健康診断の時期を確認し、適切なタイミングで受診できるよう計画を立てましょう。
再検査が必要になった場合の対応方法は?
健康診断で異常所見が見つかった場合は、医療機関での再検査が推奨されます。
再検査は、より詳しく健康状態を確認するために行われます。事業者は従業員に再検査の必要性を説明し、受診を促すとともに、産業医の指示にしたがって適切な対応を取りましょう。
深夜業の健康診断は対象者や法定ルールの把握が重要
22時から翌朝5時までの時間帯に勤務する深夜業従事者は、一般の勤務に比べて健康リスクが高いため、年2回の健康診断が義務付けられています。適切な頻度で健康診断を受けることで、生活習慣病や過労による健康被害を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。事業者は、法令を遵守し、従業員が健康的に働けるよう配慮することが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
農地の無断転用で必要な始末書の書き方は?無料テンプレートつき
農地の無断転用が発覚した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。当記事では、農地の無断転用に対して必要となる始末書について、書き方や記載事項などを解説します。無断転用には、罰則も予定されており正しい知識が必要です。無料で使えるテ…
詳しくみる離職票の書き方・記入例|ハローワークへ提出する前に確認すべきポイントも解説
退職後、会社から離職票が届いたものの、どこに何を書けばいいのか分からず、手続きが進められないと悩んでいませんか? 離職票は、失業手当の受給手続きに欠かせない重要書類です。もし記入内容に不備があったり、会社が記載した内容をよく確認せずに提出し…
詳しくみる従業員名簿とは?テンプレートを基に必要項目や書き方、保存方法を解説
企業における人事管理の根幹ともいえる従業員名簿は、労働者の基本情報を記録し、適切な雇用管理を行うために不可欠の法定帳簿です。この記事では、従業員名簿の定義から、日常業務での活用方法、正確な記入方法、そして法令に基づいた保存方法まで、人事担当…
詳しくみるなぜ働き方改革にペーパーレス化が必要か?現状や進め方、成功事例を解説
政府は、多様な働き方の実現や不合理な格差の是正等を目指し、働き方改革を推進しています。国や地方公共団体だけでなく民間においても、その流れは波及しており、各社様々な施策を講じています。 当記事では、働き方改革の実現に不可欠なペーパーレス化につ…
詳しくみる社会人とはなにか?定義や学生・フリーターとの違いや社会人研修を解説
「社会人 としての自覚を持ちなさい」などと、言われたことはないでしょうか。「社会人」は、良く使われる言葉ですが、漠然としたイメージしか持っていない方が大半だと思います。 当記事では、社会人の定義や、学生との違い、フリーター・ニートなど関連す…
詳しくみるソーシャルキャピタルとは?重要性やメリット、企業での活用事例を解説!
ソーシャルキャピタルとは一般的に社会関係資本と呼ばれ、人と人とのつながりから生みだされる価値を指します。構成要素は信頼・規範・ネットワークです。組織運営の円滑化、離職率低下、スムーズな事業展開、企業イメージアップがメリット、フリーアドレス制…
詳しくみる

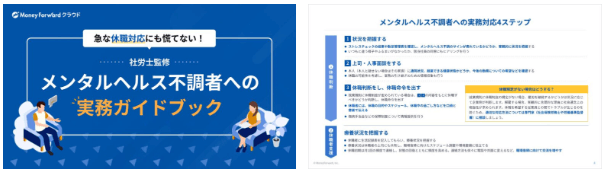
-e1763463724121.jpg)