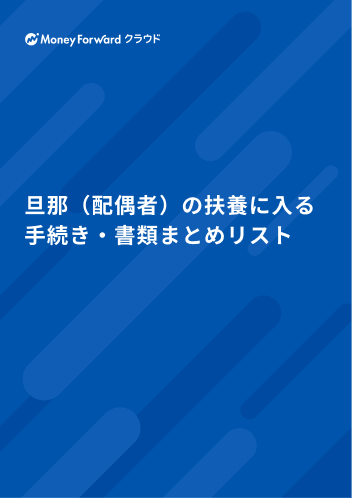- 更新日 : 2025年11月5日
配偶者や親族の扶養に入るためには?手続きや条件を解説!
夫婦で働いている人は、それぞれが社会保険に加入して働くか、それとも、夫か妻の扶養に入って働くかの選択によって、それぞれの働き方が違ってきます。被保険者の扶養に入ることで、保険料が免除になったりするようになります。
今回は、被扶養者について再確認し、扶養に入る手続き方法やメリット、デメリットについて解説していきます。
目次
被扶養者とは?
被扶養者とは、健康保険に加入している被保険者の三親等以内の親族のうち、健康保険の被扶養者の要件を満たす人のことを言います。被保険者に扶養されており、被保険者が受けられる保険給付を同じように受けることができます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
被扶養者の範囲について
被扶養者の範囲は、下図の三親等以内の親族図の中で一定の要件を満たした人になります。

被扶養者になることができる条件
被扶養者の範囲に含まれているというだけで、無条件に被扶養者になることができるわけではありません。被扶養者になるには、「被保険者によって生計を維持されていること」と「収入要件に該当していること」にあてはまる必要があります。
それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
被扶養者になることができる人の要件
被扶養者になることができる人の要件は、下記の要件にあてはまる人です。
【生計維持関係が必要な人】
- 被保険者の直系尊属である父母、祖父母
- 配偶者(内縁関係の人を含む)
- 子(養子を含む)
- 孫
- 兄弟姉妹
【生計維持関係ならびに同一世帯に属していることが必要な人】
- 上記以外の三親等以内の親族
- 被保険者の配偶者(内縁関係を含む)の父母、子
- 被保険者の配偶者(内縁関係を含む)が死亡した後におけるその父母、子
被扶養者になることができる人の収入要件
被扶養者になることができる人の収入要件は、下記の要件にあてはまる人です。
【同一の世帯に属している場合】
- 認定対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の収入の2分の1未満
- 認定対象者が60歳以上の場合、または、障害厚生年金を受けることができる程度の障害者の場合は180万円未満、かつ、被保険者の収入の2分の1未満
【同一の世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない
- 認定対象者が60歳以上の場合、または、障害厚生年金を受けることができる程度の障害者の場合は180万円未満、かつ、被保険からの仕送り額より少ない
扶養に入るための手続き
健康保険の扶養に入るためには、被保険者は「健康保険 被保険者(異動)届」に必要事項を記入し、会社を経由して必要な添付書類とともに年金事務所に提出します。ここでは、手続きを行う時期や提出方法について見ていきます。
手続きを行う時期
扶養に入る手続きは、扶養することになった事実が発生した日から5日以内に手続きを行う必要があります。
書類の提出先
作成した書類や添付書類(ある場合)の提出先は、以下になります。
- 全国健康保険協会の事業所・・・管轄の年金事務所または事務センター
- 組合健保の事業所・・・会社を管轄する健康保険組合
提出先を間違えないように、提出前に日本年金機構や健康保険組合のホームページなどで提出先を確認しておきましょう。
書類の提出方法
書類は、電子申請、郵送や管轄の年金事務所の窓口に持参する方法で提出してください。
扶養に入るために必要な書類
ここからは、健康保険の扶養に入るために必要な書類について見ていきます。
健康保険 被扶養者(異動)届
まず、「健康保険 被扶養者(異動)届」です。必要事項を記入して会社に提出し、会社が手続きを行うための書類です。

引用:健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)|日本年金機構
添付書類
続柄、収入、同居・別居、内縁関係などを証明する必要がある場合はその事実を確認する書類が必要です。ただし、事業主が確認し、証明すれば添付が不要になる書類もあります。
【続柄を確認するための書類】
戸籍謄本(または戸籍抄本)、住民票のいずれか(事業主の確認により添付不要)
【収入を確認するための書類】
年間収入が130万円(60歳以上などは180万円)未満であることを確認できる書類
【同居を確認するための書類】
原則は必要ありませんが、同居の確認が取れない場合、被保険者の世帯全員の住民票
【別居の確認のための書類】
- 仕送りの事実と仕送り額のわかる書類
- 預金通帳のコピー
- 現金書留の控えのコピー など
【内縁関係を確認するための書類】
- 内縁関係にある両人の戸籍謄本(または戸籍抄本)
- 被保険者の世帯全員の住民票
必要な書類を早めに準備してもらうようにしましょう。
扶養に入るメリット・デメリット
健康保険の扶養に入る場合のメリット・デメリットについてまとめました。
扶養に入るメリット
扶養に入ると、社会保険料や税金の面でメリットがあります。
- 配偶者が扶養に入った場合、配偶者が本来払うべき国民健康保険料や国民年金を納める負担がなくなります。
- 被扶養者になった配偶者が配偶者控除を受けることができると、被保険者の所得税や住民税の負担を減らすことができます。
- 扶養に入っても出産育児一時金を受け取ることができます。
扶養に入るデメリット
では、扶養に入った場合のデメリットについても見ておきましょう。
- 収入要件があるため、働き方や得られる収入に制限が出てしまい、場合によっては働きづらくなることが考えられます。
- 配偶者の場合、自分で社会保険に加入している時と比較すると、将来受給できる年金額が下がる可能性があります。
扶養に入るための条件を再確認しておきましょう
扶養に入るための要件には生計維持や収入要件などいろいろな項目があります。従業員から手続きの依頼があった際に正しい説明ができるように、扶養に入るための条件について再確認しておきましょう。
よくある質問
被扶養者とはなんですか?
被扶養者とは、健康保険に加入している被保険者の三親等以内の親族のうち、被扶養者の要件を満たす人のことです。 被保険者に扶養されており、被保険者が受けられる保険給付を同じように受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
扶養に入るための手続き方法について教えてください
健康保険の扶養に入るためには、被保険者は「健康保険 被保険者(異動)届」に必要事項を記入し、会社を経由して年金事務所に必要な添付書類とともに提出する手続きが必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
国保と社保は何が違う?対象者や保険料・扶養・給付内容を徹底比較
国民健康保険(国保)と社会保険(社保)の主な違いは、加入対象者や保険料の負担方法、扶養制度の有無、給付内容にあります。社保は主に会社員が対象で保険料は会社と折半、扶養制度がある一方…
詳しくみるカスハラの労災認定基準は?事例や精神疾患の認定率、企業側の対策などを解説
近年、日本社会において顧客からのハラスメント、いわゆるカスハラの問題が深刻化しており、社会的な関心が高まっています。特に、2023年に労災認定基準が改正され、カスハラによる心理的負…
詳しくみる厚生年金加入者の配偶者でも国民年金への加入は必要?
会社員や公務員などは、厚生年金に加入するのが一般的です。厚生年金には扶養制度があるため、専業主婦など条件を満たした被扶養配偶者は扶養加入することができます。しかし、収入が一定以上あ…
詳しくみる確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表とは?記入例を解説
労働保険の年度更新の時期(毎年6月1日~7月10日) になると、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(様式第6号)の作成が必要になります。しかし、その申告書に正しい金額を記…
詳しくみる厚生年金基金の8つのメリット
厚生年金基金とは、企業年金の一種であり、厚生年金保険料の一部を「代行部分」として運用し、その運用益による「プラスアルファ部分」を公的年金に上乗せ支給する制度です。厚生年金基金の仕組…
詳しくみる雇用保険を会社都合退職で受給する場合
会社を退職する理由としては、さまざまな理由が想定されます。自らの都合で会社を退職する場合もありますが、時には会社の都合により会社を退職するケースもあります。 会社側からの解雇通告に…
詳しくみる