- 更新日 : 2025年6月23日
個人番号関係事務とは?利用事務との違いを解説
個人番号関係事務と聞いても、何のことだかわからないというのが一般的な反応ではないでしょうか。また、類似する用語として個人番号利用事務というものもあります。個人番号とは、マイナンバーのことですが、これらの事務はマイナンバーを扱う立場にいる方は十分に理解しておく必要があるでしょう。今回は、個人番号関係事務について、定義のほか、個人番号利用事務との違いについて解説していきます。
個人番号関係事務とは?
2015年10月、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
マイナンバーとは個人番号のことであり、同年以降、市町村から住民票を有するすべての人に個人が特定されないように住所地や生年月日などと関係のない12桁の番号が通知されています。
政府がマイナンバーカードの普及を推進していることもあり、一般的には個人番号という呼称よりも、マイナンバーのほうが馴染みがあると思います。
日本は個人情報については、EU諸国などに比べて十分なレベルの保護がなされていない後進国だったこともあり、当初、2013年5月に番号法として公布されたものが、施行前の2015年9月に改正されて利用の開始が2016年1月からになるなど、この法律の施行に至るには紆余曲折があります。
また国民一人ひとりに振られた番号としては、マイナンバー導入の前に住基ネットで活用されている住民票コードがあります。
しかし、もっぱら行政機関等に対する本人確認情報の提供と市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理が目的とされていたため、個人情報の保護が十分でなく、プライバシー権の侵害として訴訟が相次いで起こったという経緯がありました。
マイナンバーの用途は、住基ネットのような行政の効率化、国民の利便性の向上だけでなく、公平・公正な社会の実現を目指すために個人の所得を把握することにまで広げています。
そこで、住基ネットでの住民票コードを元にしながら、マイナンバーという新たな番号を生成し、個人情報の保護をより厳格にしました。マイナンバーを扱う立場の人についても、「関係事務」と「利用事務」に明確に分けています。
個人番号利用事務との違い
マイナンバー法において「個人番号関係事務」とは、事業者が法令に基づき、個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいいます(法2条11項)。
具体的には、事業者が従業員等のマイナンバーを給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等および健康保険組合等に提出する事務のことを指します。
個人番号関係事務を処理する者を個人番号関係事務実施者(法2条13項)といいますが、従業員を雇用するすべての事業者が該当することになります。
事業者は、原則として、これらの事務の範囲の中から具体的な利用目的を特定しなければマイナンバーを利用することはできません。
本人の同意があっても、次の例外として認められる場合以外はマイナンバーを利用してはならないとされています。
- 【例外として認められるケース】
- 金融機関が激甚災害時等に金銭の支払いを行う場合、
および人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難である場合
また、事業者だけでなく、給与所得者である従業員が扶養親族のマイナンバーを扶養控除等申告書に記載し、勤務先の事業主に提出することも個人番号関係事務に該当します。
一方の「個人番号利用事務」は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度でマイナンバーを利用して処理する事務としています(法2条10項)。
例えば、国税の分野では、国税局や税務署等において国税の賦課または徴収に関する事務が該当します。これらの事務を処理する者を個人番号利用事務実施者といいます(法2条12項)。
マイナンバー法では、上記の個人番号関係事務実施者と個人番号利用事務実施者を併せて「個人番号利用事務等実施者」としています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
マイナンバー漏洩時 対応チェックシート
マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。
本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。
マイナンバー保管期間かんたん早見表
マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。
本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。
マイナンバー提出用紙(ワード)
従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。
本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。
個人番号関係事務と利用事務の違いを知っておこう!
マイナンバー法は、マイナンバーの用途を個人の所得の把握にまで広げており、情報の漏えいには厳格なルールを定めています。
事業者と行政機関について、マイナンバーに係る事務の名称を切り分けて規定しており、個人番号関係事務と利用事務の違いをよく把握しておくことが大切です。
よくある質問
個人番号関係事務とは何ですか?
事業者が、法令に基づき、個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
個人番号関係事務と利用事務の違いについて教えてください。
個人番号関係事務が事業者の事務であるのに対し、利用事務は行政機関が処理する事務を指します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マイナ保険証の住所変更は必要?手続き方法と注意点を解説
引越しや転職をしたとき、「マイナ保険証の住所変更って必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。マイナ保険証はマイナンバーカードと一体になっているため、従来の保険証と手続き方法が異な…
詳しくみるマイナンバーで職歴もわかってしまう!?過去のことはどこまで知られるのか
マイナンバー制度が平成28年1月より運用開始となりました。マイナンバー制度が導入されるとプライバシーに関わるような部分はどれくらい第三者や企業に開示可能になってしまうのか、皆さんは…
詳しくみるマイナンバー制度っていつから?マイナンバー制度のスケジュールとは
マイナンバー制度っていつから始まったか知っていますか? 平成27年10月から個人への通知が始まり、平成28年1月1日から本格運用が始まりました。 1.基本方針の策定 できる限りすぐ…
詳しくみるマイナンバーの民間利用はこれからどうなる?利用範囲拡大の現状と展望
現在認められているマイナンバーの利用範囲 マイナンバーの利用範囲は? 民間利用の動きが始まっているマイナンバーですが、現在認められているの利用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」の…
詳しくみる転職したらマイナ保険証はどうなる?反映されない理由・対処法など解説
転職を機に健康保険の変更があったとき、マイナ保険証は自動的に切り替わるのか不安になる方も多いでしょう。 2024年12月から健康保険証は原則としてマイナ保険証に一本化され、ますます…
詳しくみるマイナンバーに関連する3つのカードを徹底解説!
通知カード (出典:通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト) 「通知カード」とは何か? 「通知カード」とは平成27年(2015年)の10月から配布が開始されたマイナンバー…
詳しくみる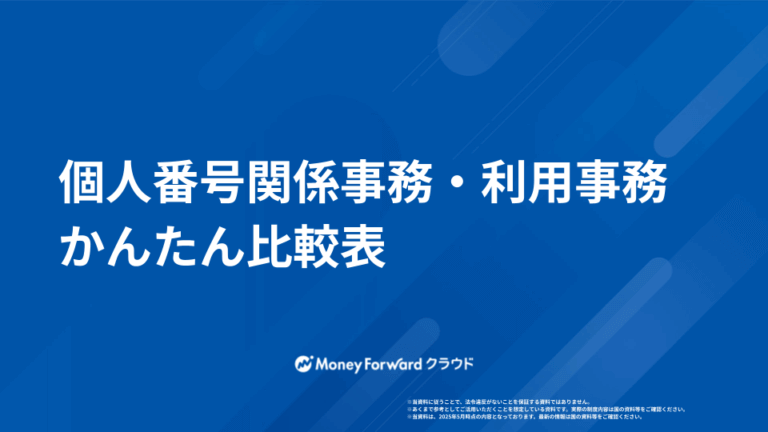



-e1761041825741.png)