- 更新日 : 2025年12月24日
在宅勤務手当(テレワーク手当)とは?相場・事例や導入のメリットも解説
在宅勤務手当(テレワーク手当)とは、在宅勤務中に発生した光熱費や通信費などを補填するために支給される手当のことです。
ただ、「在宅勤務手当の相場が知りたい」「手当を支給するメリットはある?」と悩んでいる方も多いでしょう。
そこで本記事では、在宅勤務手当の相場や導入事例、メリット・デメリットなどを解説します。
目次
在宅勤務手当とは?
在宅勤務手当とは、在宅勤務をするうえでかかる費用を補うために支払われる手当のことです。
在宅勤務をすると、会社に出勤したら発生しない電気代や通信費などがかかります。人によってはデスクや椅子などを購入する必要もあり、家計を圧迫してしまうことも考えられるでしょう。企業が在宅勤務手当として費用を補填すれば、従業員の負担を減らせます。
法的には、在宅勤務手当の支払い義務はありません。しかし導入すれば、従業員のモチベーション向上や経費削減を期待できます。
総務専門誌の『月刊総務』の調査によれば、在宅勤務を導入している企業のうち、在宅勤務手当を支給している企業は3割以上存在することが判明しました。毎月、一律の金額を支給している企業が多いことも分かっています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
従業員の賃上げに潜むリスクと、企業が打つべき対策
人手不足や物価上昇などを背景に、賃上げが企業経営の重要テーマとなっています。しかし、賃上げには様々なリスクを伴います。
本資料では、企業が賃上げを進める際に注意すべきリスクと対策について解説します。
住宅手当申請書(ワード)
住宅手当の申請にご利用いただけるテンプレートです。 Wordファイル形式のため、直接入力や編集が可能です。
ダウンロード後、必要事項をご記入の上、申請手続きにお役立てください。
休業手当の計算シート(エクセル)
休業手当の計算にご利用いただける、Excel形式の計算シートです。
Excelファイル形式のため、ダウンロード後自由にご使用いただけます。 業務での休業手当の計算を行う際にお役立てください。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
在宅勤務手当の相場
『エンワールド』の調査によれば、在宅勤務手当を毎月支給している企業のうち、3,000円以上~5,000円未満を支給している企業が最も多く約4割ほどです。
出勤よりも在宅での勤務を推奨している企業は、3,000円~5,000円が在宅勤務手当の相場と言えます。
出勤と在宅勤務が半々の企業や在宅勤務の割合があまり高くない企業は、一定の金額を在宅勤務を行った日数分だけ支給する場合もあります。日数分だけ払うなら、
※参考:『在宅勤務における企業の従業員サポート調査』エンワールド・ジャパン株式会社
在宅勤務をした際に発生する実際の費用
在宅勤務をした際に発生する実際の費用を求めてみましょう。在宅勤務で発生する費用としては、光熱・水道代、電気代、インターネット接続料が挙げられます。
| 光熱費・通信費 | 1ヶ月の費用 | 1日の費用 | 8時間の費用 |
|---|---|---|---|
| 光熱・水道 | 約13,045円 | 約435円 | 約145円 |
| 電気代 | 約6,726円 | 約224円 | 約75円 |
| インターネット 接続料 | 約2,451円 | 約88円 | 約29円 |
※「1日あたりの費用」は「1ヶ月あたりの費用」の30日分の平均で算出し、小数点第一位を四捨五入をしています。
「光熱・水道」「電気代」「インターネット接続料」の8時間の費用を合計すると、約249円となります。1ヶ月に15日~20日ほど在宅勤務をする場合、約3,735円~4,980円が実際にかかる費用です。
よって、毎月一律の金額を在宅勤務手当として支給するなら、3,000円~5,000円が適切でしょう。
※参考:『家計調査 家計収支編 単身世帯』(2023年)、『家計消費状況調査 平成29年改定 単身世帯』(2023年)
在宅勤務手当の主な支給方法
在宅勤務手当の主な支給方法は、現金支給と現物支給の2通りです。現金支給にするか、現物支給にするかは企業が自由に選択できます。
現金支給
現金支給とは、在宅勤務手当を給与に上乗せして支給することです。一定額の手当を毎月支給したり、在宅勤務をした日数だけ支給したりする方法があります。
企業側のメリットとしては、一定額を支給する方法であれば、業務の負担が増えにくいことです。また、従業員側も手当を比較的自由に使用でき、使いきれなくても返金する必要がありません。
一方、デメリットとしては、在宅勤務をした日数分を計算して支払う方法だと、管理がやや大変なことが挙げられます。従業員のモチベーション向上には繋がりやすいですが、企業側は費用対効果を感じにくいでしょう。
現物支給
現物支給とは、業務で使用する機材や備品を支給もしくは貸与することです。個人で調達するのが難しい機材を扱う場合は、現物支給の方が企業も従業員もやりやすいでしょう。
現物支給は在宅勤務手当の使い道を管理しやすい支給方法です。物品をそのまま渡せば、用途以外の方法で使用されることもありません。大型の機材や備品を購入する場合でも、従業員の負担にならない点もメリットです。
ただ、従業員が職場と同じ製品を自宅で使いたくても、価格や使用環境などが原因で支給できない可能性があります。また、企業側にもデメリットがあり、返品や故障の際の対応策が必要になったり、大勢の社員を雇用したときにコストが嵩んだりします。
在宅勤務手当が課税・非課税となる場合
在宅勤務手当を支給すると、課税となるケースと非課税となるケースがあります。支給方法によって変わるため、それぞれ詳しく解説します。
在宅勤務手当が課税となるケース
在宅勤務手当が課税対象となるのは、毎月一定額を支給する場合です。給与の一部となるため、所得税がかかります。
また、機材や物品などを支給する場合も基本的に課税対象です。機材や物品などの支給は「現物給与」に該当し、所得税を納める必要があります。
在宅勤務手当を一定額を支給する場合は、給与から源泉徴収します。また、従業員が在宅勤務中に実際に使用しなかった場合でも支給された手当を会社に返還する必要がないものを支給することがあります。これを「渡し切り」といい、従業員に対する給与として課税されます。
なお、在宅勤務手当は労働基準法上の「賃金」に該当するため、社会保険料や時間外・休日・深夜の割増賃金を計算する際の算定基礎に含まれるため注意は必要です。
※参考:国税庁
在宅勤務手当が非課税となるケース
在宅勤務手当が非課税となるのは、実費を支給する場合です。立て替えや仮払いに関わらず税金を納める必要がありません。
また、機材や物品などを貸与した場合も非課税です。支給だと所得税が課されますが、貸与は税金がかかりません。
実費として支給した手当を会計処理する際は、領収書や請求書などを従業員から受け取って、しっかり保管してください。機材を購入する際も領収書を発行してもらいましょう。
在宅勤務手当を支給するメリット・デメリット
在宅勤務手当の支給には、いくつかメリットやデメリットが存在します。それぞれ確認したうえで、手当を支給するか検討してください。
在宅勤務手当を支給するメリット
在宅勤務手当を支給する主なメリットは、以下の3つです。
- 従業員のモチベーションが向上する
- 経費削減に繋がる
- 人材が集まりやすくなる
一つ目のメリットは、従業員のモチベーションが上がることです。在宅勤務手当が支給されれば、実質的に光熱費や備品代などを負担する必要なくなります。業務の環境を整えられるため、仕事にも良い影響があるでしょう。
二つ目のメリットは、経費削減に繋がることです。具体的には、在宅勤務の導入に伴い定期代の支払いを廃止すれば、経費を抑えられます。
| 1ヶ月の定期代 | 約10,000円~20,000円 |
|---|---|
| 1ヶ月の在宅勤務手当 | 約3,000円~10,000円 |
| 差額 | 約7,000円~10,000円 |
在宅勤務手当を支給することで、1人あたり約7,000円~10,000円も経費を削減できます。
三つ目のメリットは、人材が集まりやすくなることです。単に在宅勤務のみをアピールするよりも手当をもらえることも併記する方が、求職者が集まりやすくなるでしょう。より会社に合った人材を確保しやすくなります。
在宅勤務手当を支給するデメリット
在宅勤務手当を支給する主なデメリットは、以下の2つです。
- 業務の負担が増える
- 従業員は源泉徴収額が増える可能性がある
一つ目のデメリットは、業務の負担が増えることです。在宅勤務手当にかかる税金の計算、支給ルールの設定、交通費の処理など追加で発生する業務は多くあります。在宅勤務手当の支給を始める前に、ルールの整備や交通費の管理方法などを決めておきましょう。
二つ目のデメリットは、従業員の源泉徴収額が増える可能性があることです。在宅勤務手当を毎月一律で支給する方法や業務に必要な物品を支給する方法は、課税対象であるため納める税金が増えます。定期代の支払いを廃止すると、さらに手取りが減ることもあり得ます。
在宅勤務手当の導入事例
在宅勤務手当を実際に導入している企業の事例を見ていきましょう。支給額や支給方法などを参考にしてください。
| 企業 | 支給額 | 交通費の対応 |
|---|---|---|
| LINEヤフー株式会社 | 11,000円/月 | 実費支給 (上限150,000円/月) |
| 富士通株式会社 | 5,000円/月 | 通勤定期代の支給を廃止 |
| note株式会社 | 最大120,000円/年 | 実費支給 (上限150,000円/月) |
| 株式会社SmartHR | 5,000円/月 | 実費支給 (上限30,000円/月) |
※参考:LINEヤフー株式会社、富士通株式会社、note株式会社、株式会社SmartHR
上記4社の場合、1ヶ月あたりの支給額を一律で設定している企業がほとんどです。在宅勤務手当の支給条件については多くの企業が記載していませんでしたが、株式会社SmartHRのみ「オフィスへの出社日数に関わらず」と明記しています。
また、定期券代を支給している企業はなく、上限を設けて実費を支払う体制にしている企業が大半であることも分かりました。note株式会社や株式会社SmartHRはフルリモートを許可しており、交通費自体あまり発生しない可能性もあります。
在宅勤務手当に関する注意点
在宅勤務手当を支給する際に、ルールの整備や税金など注意すべきことを解説します。
あらかじめ支給ルールを決めておく
在宅勤務手当の支給ルールを事前に決めておくことが大切です。特に以下の項目だけでもルール化しましょう。
- いくら手当として支給するのか
- どのような方法で支給するのか
- 何日以上、在宅勤務をしたら支給するのか
- 手当を実費支給する場合、半日出社をどう扱うか
- 定期代の支給を継続するか、廃止するか
ルールが定まったら、就業規則にも追記してください。賃金に関する内容は、「絶対的必要記載事項」として記載することが義務付けられています。
在宅勤務手当のルールを設けて従業員にも周知すれば、トラブルも未然に防げるでしょう。
在宅勤務手当の課税に関して周知する
在宅勤務手当の支給ルールと併せて、課税に関する内容も従業員に周知しましょう。支給方法によって課税・非課税が変わること、課税されると手取り額が減る可能性があることは、必ず共有するべきです。
支給方法について従業員にアンケートを取ってみるのも良いでしょう。課税対象の支給方法・非課税対象の支給方法を説明したうえで、支給額や徴収される税金なども例示すると親切です。
支給を開始する前に税金について理解してもらうことで、従業員の不満も溜まりにくくなります。
在宅勤務手当を導入する場合は相場や税金の把握を
在宅勤務手当は、テレワークをする従業員の経済的負担を軽減できる手当です。従業員のモチベーションが向上したり、人材を確保しやすくなったりします。
実際に在宅勤務手当を支給するのか検討する際は、相場や他社の導入事例などを確認しましょう。自社に必要か、従業員に良い影響があるか、しっかり考えることが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
処遇改善加算とは?新制度の変更点や算定要件、計算例など解説
介護・福祉業界の人材不足解消を目的とした「処遇改善加算」。2024年(令和6年)6月の大改正により、これまでの複雑な制度が一本化され、新たな「介護職員等処遇改善加算」としてスタート…
詳しくみる給与計算の時間短縮方法を解説!ツールの選び方も紹介
給与計算は、月末から月初にかけて勤怠集計や控除計算を短期間で正確に処理する必要があり、担当者に大きな負担がかかります。本記事では、そんな煩雑な業務を根本から見直し、時間を短縮する方…
詳しくみる産休中はボーナスの査定期間に入る?賞与が減る、もらえない原因も解説
産休期間もボーナス(賞与)の査定期間に含まれることが一般的です。しかし、査定期間中に産休を取得した場合、ボーナスの金額に影響が出る可能性はあります。この記事では、産休中のボーナスの…
詳しくみる所得税は扶養人数でいくら変わる?年齢による違いや給与計算の注意点
家族を扶養する従業員は、その人数に応じて源泉所得税が減額されます。そのため、給与計算においては、所得税と扶養人数の関係を理解することが欠かせません。当記事では、所得税と扶養人数の関…
詳しくみる手取りは「天引き後」の給与!どこから何が差し引かれているか知っておこう
「手取り」「年収」「額面」など、給与額を表現する言葉には様々なものがあります。しかし実はそれぞれの言葉がどんな数字を意味するのかを、よくわからない人も多いのではないでしょうか。 こ…
詳しくみる宝塚市の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
宝塚市は華やかな宝塚歌劇団を擁するエンターテインメントの街として有名で、多くの観光客や地元企業が活発に活動しています。こうした地域特有のビジネスニーズに対応するためには、給与計算の…
詳しくみる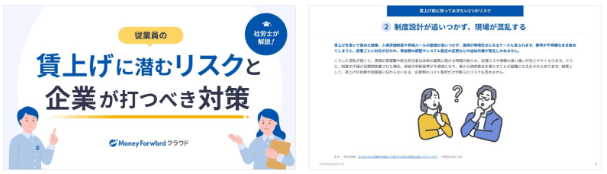
-e1763436002347.jpg)
-e1763436316712.jpg)
.png)